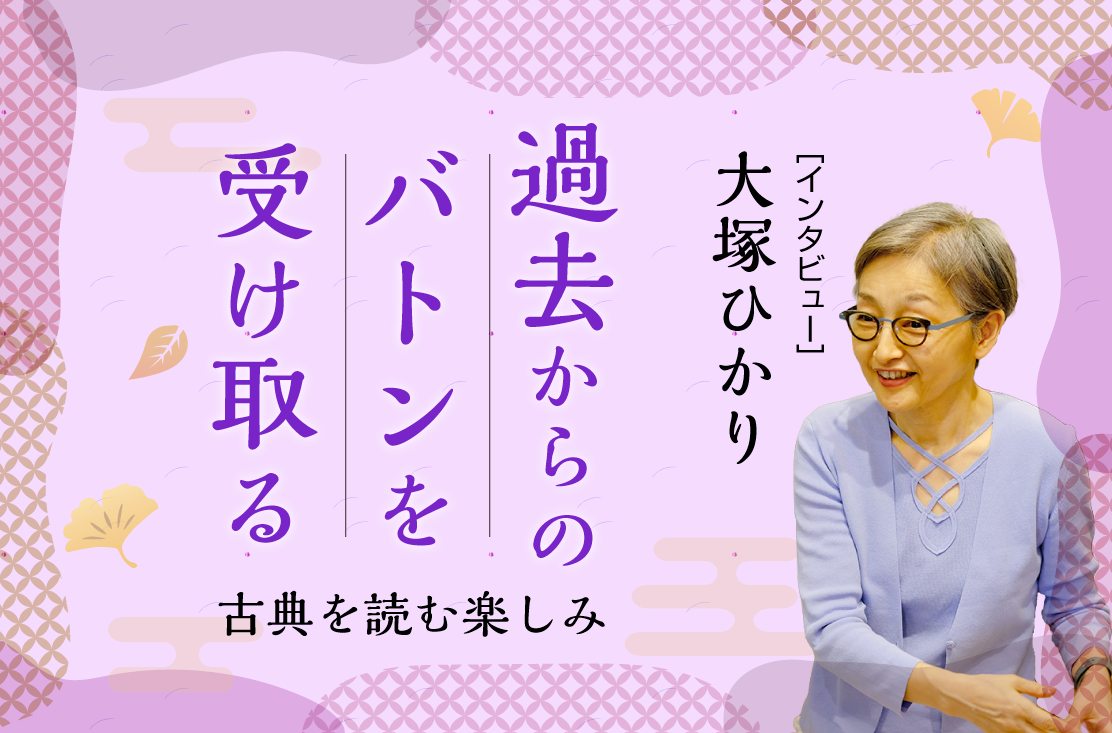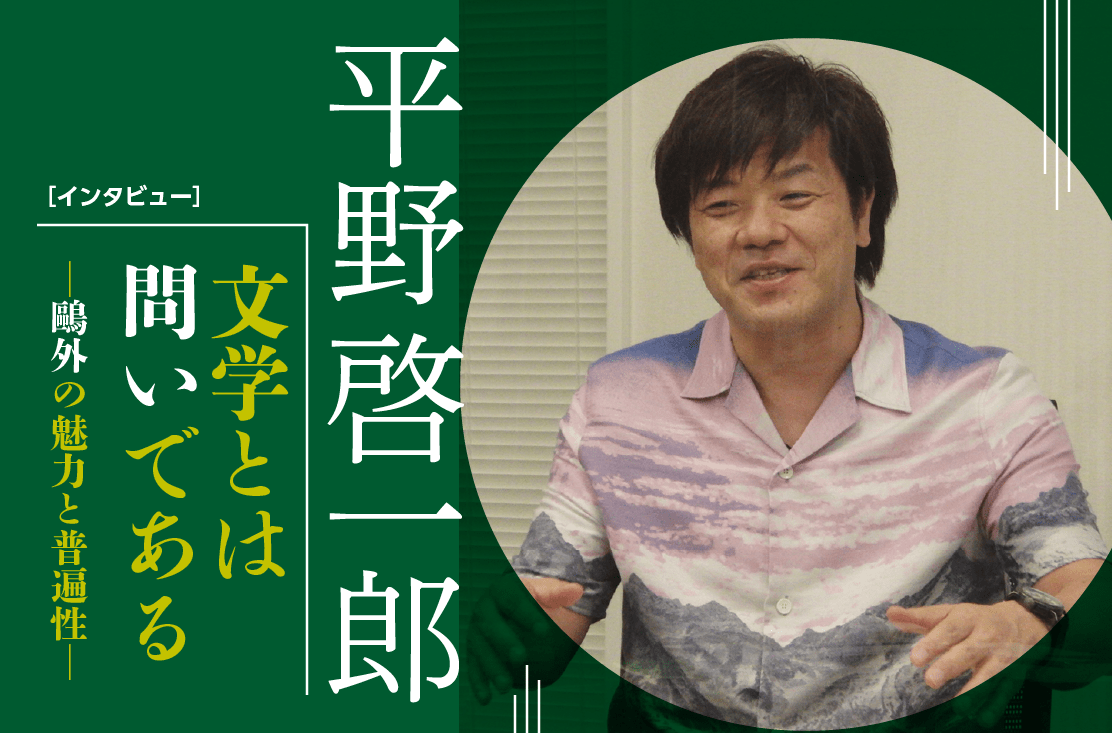〈インタビュー〉山崎正和 聞き手:山下 直
私の国語教育論
山崎正和
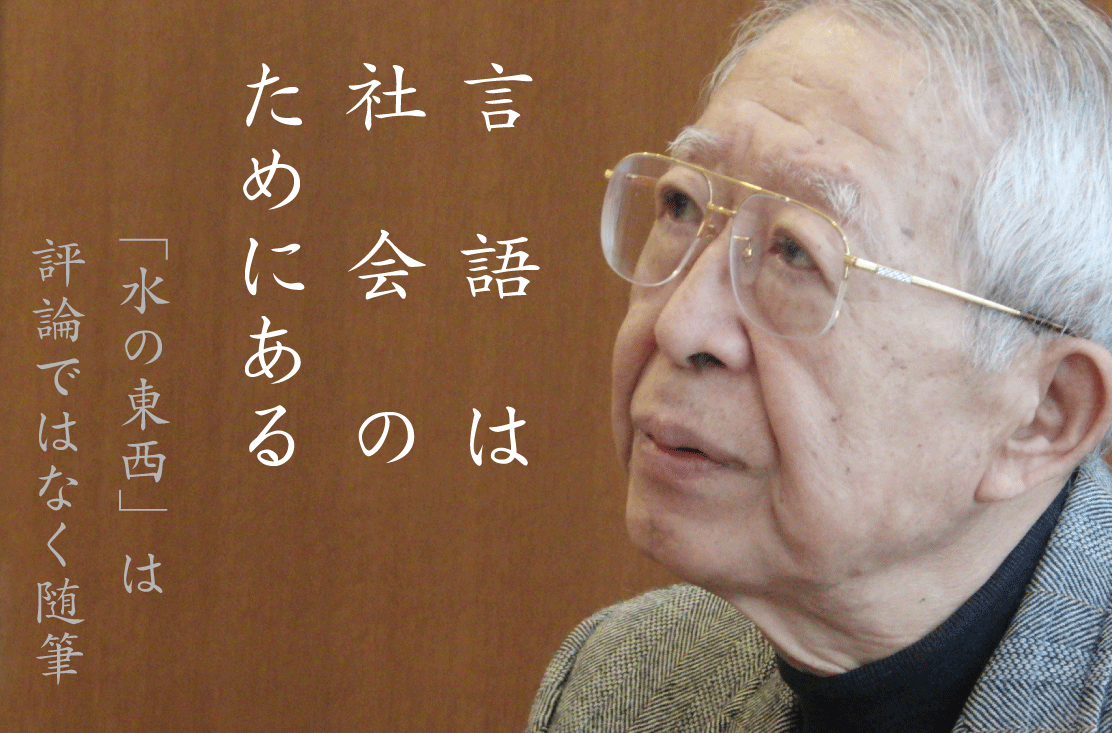

劇作家、評論家
山崎 正和(やまざき まさかず)
●聞き手・山下 直(文教大学准教授)
国語教育の根底にあるのは名文の暗誦である
――まず、印象深かった国語の授業についてお聞かせください。
私が小学校に入学したのは昭和一六年、第二次大戦が始まった年です。そのころはまだ小学校でした。二年生になると国民学校になって、卒業する六年生のころはまた小学校になった。そういう、日本の教育自体がいろいろ変動する時代に国語の授業を受けたわけですが、やはり、戦前の小学校教育、あるいは戦争直後の中学校教育が、私にとっては印象深いですね。じゃあ一体、どういう勉強をしたかというと、基本的には近代の立派な文章を読んで、暗誦しました。例えば、徳富蘆花とか国木田独歩とかの、主に風景を叙したような文章をよく暗誦しました。つまりは、文章とはどういうものか、あるいは言葉とはどういうものかというのを、先人の名文を通して、まずは頭ごなしに覚えたということですね。
この年になってもまだ印象に残っている名文の一部で、蘆花だか独歩だか忘れましたが、武蔵野の風景を描くなかで、「武蔵野の雨は馬背を分かつ」と書いてあるんです。武蔵野の雨というのは、どうも局地的に降って、ほんのわずかな距離でこっちは晴れていてこっちは雨が降っている。そういう風景を長々と説明するのではなくて、一頭の馬の背中を分かつという表現をしている。これは子ども心に非常に印象に残って、いまだに覚えています。事柄というものは、こういうふうに言葉を選んで組み合わせると、極めて簡潔に、しかも独創的に描けるものだということが、まだ一〇歳になるかならないかの子どもの心に染み込んだ。ですから、近代の名文の暗誦が、私の国語教育観の根底にあるわけです。
感情表現よりも物を描写させることが大切
福沢諭吉について語りつがれている話ですが、福沢は思ったこととか感じたことを書くよりは、物を描写しろと教えたそうです。彼が例に挙げたのは、当時、言ってみれば文明の最先端であった、人力車です。明治の初めですから、人力車を見たことのない人は、まだ日本人の中にいました。そういう時代に、学生に人力車をよく観察して、それを見たこともない人にもわかるように描写せよと教えた。私は、これも非常に立派な教えだと思うんです。
とかく戦後の国語教育は感じたことを書くとか、あるいは自分が思ったことを書く、表現するという方向に重点が置かれていると聞きます。私はどうも、それは順番が逆であるような気がします。なぜなら、自分の思い、あるいは考えを書くということは、言葉を自分のために使うということなんです。しかし、そもそも言葉というものは、自分のためにあるものではないと考えます。社会のため、あるいは相手のためにあるものだ。相手に自分をわかってもらう、あるいは、自分の考えや印象を他人と共有する、これが言葉というものの本質だと思うんです。
仮に、自分が満足するために音声を使ったらどうなるか。一番最初に出てくるのは、オノマトペです。例えば、「今日、私の気分はグニャッとしている」と言ったとしますね。愉快ではないな、元気ではないなと、何となくはわかりますよ。しかし、それ以上はわからないわけです。これでは、他者との、あるいは社会との気持ちの共有ということはあり得ない。現に若い人のいわゆる若者用語というのが、事柄をきちっと描写するのではなくて、思いを述べる方に流れている。それも、スマートフォンの一四〇字で言えるようなことに限られているうえ、変な記号を使って笑顔が描いてあったり、なんだか悲しそうな顔があったり。それでは、非常に荒っぽい気持ちしか表現できませんよね。
たくさん言葉を知っていれば、他人と正確に感情を共有できるわけです。その訓練をするためには、自分の気持ちではなくて、まずお互いに見たらわかる物を描写してみせる。そうすると、いやでも第三者にわかる言葉を習得できますよね。
文学ではなく豊かな国語を教えるべきである
第二に、これは本質論ですが、人間は感じたことを言葉にするのではないんです。言葉があって、言葉によって感じるんです。つまり、言葉がなければ、そもそも感じというものが浮かんでこない。例えば「夕暮れ」と「黄昏」とでは違うんですね。朝の早い時間、「朝まだき」と「かわたれ時」。これも違う。じゃあ、どう違うんだと言うと、概念では定義できない。名文の中でたくさんの用例を読んで、ああ、あの気分かと理解しなければ、言葉の理解にならない。逆に言えば感情の細分化というか、感情の厳密な分類、命名というものは、実は言葉が先にあってできるんです。ですから、最初は理解に苦しむかもしれないけれども、子どもたちにはたくさん名文を読ませて、教師がその意味を教えて、慣れさせることです。
語源というのは、案外面白いんですよ。子どもに教えたら、きっと喜ぶと思う。黄昏というのは、語源は「タソ、カレ」。あの人は誰だというんです。「誰ぞ、彼」ですね。それが「黄昏」になった。「彼は誰(かわたれ)」は同じことで「彼は誰」なんです。つまり、薄暗いからよく顔を見ても見えない。だから、あいつは誰だというのが、「彼は誰」という言葉になった。「黄昏」と同じです。もっと言うと、「黄昏」は夕方にしか使いませんが、「彼は誰時」は薄暗い夜も薄暗い朝も両方に使える。そういうことを教えたら、生徒はきっと喜ぶと思うんですよ。たとえすぐに理解できなくても、言葉がたくさんあって、いろいろな異なる事柄に対応しているんだと知ること。私は、これが国語教育というもののすべてだと言ってもいいかと思うんです。
もちろん、高等学校教育の後期になれば、国語の時間に文学を教えることも悪くはないと思います。しかし、文学、つまり文芸評論家が書くようなことを高校生に教えるのは、実はちょっと、時間の無駄だという気がします。というのは、今までお話ししたような例は、どんな将来を選ぶ子どもにとっても必要な国語教育です。しかし、文芸評論なんていうものは、それを専門にする人にだけ役に立つものです。だから、理科系に行くにしても、あるいは企業の事務職に就くにしても必要な国語というのは、文学じゃないんですよね。それ以前の国語がずいぶん豊かなんだから、それを十分に教えるべきだ。しかも、一般の国語の先生にとっても、実はそのほうが楽だと思う。文学の解釈、理解というようなことは、本当に千差万別で客観性がないんですから。
「水の東西」は評論ではなく随筆

私自身の文章が、国語の教科書によく載るんですね。それで、出版社からこれをこう教えていますという先生の手引き書を送っていただく。すると、中にはびっくりするような解説があるんですよ。例えば私の書くものには、私が満州育ちだということが強く影響していると書いてあるんだけど、そう考える理由の説明はないんですね。そんなことを子どもに教えてどうなるのか。さらに、もっと私が困っていることがあるんです。私の「水の東西」という文章がありまして。
――国語総合の教科書のほとんどに出ています。
ところがですね、どの教科書もあれを評論の部類に入れていらっしゃる。これは全く間違いです。あれは随筆なんです。評論というのはやはり結論が正確さを旨としていて論争可能な文章でなければならない。ということは、例えばある主張をする場合、筆者は自分で例外を見つけて、その例外がなぜ出てきたかということも説明して、あるいは予測される反論にもあらかじめ答える、これだけの準備をするのが評論なんですね。随筆はそうではない。思いつきの面白さ、その感想の面白さ。結論が仮に間違っていても面白ければそれでいい、これが随筆なんです。
「水の東西」という文章は、もし私があれを日本文明論、あるいは日本文化論として書こうとしたら、いっぱい隙があるんです。あれはもともと、「産経新聞」の夕刊の文化欄に連載したものの一つですから、いわば娯楽読み物なんですね。それはそれで子どもに教えていいと思いますが、しかし、これは随筆だよと言って教えないと、将来、子どもが間違えます。だけど、どの出版社にお願いしても直してくださらない。ある出版社に聞いたんですが、一冊の教科書に評論が何本、随筆が何本と、こういうバランスに配慮しているらしいですね。それで、私のを随筆部門に移すとそのバランスが崩れるから評論扱いのままにさせてほしいというんです。あれはどう考えても随筆なのに、困ったものです。
教材としての「水の東西」の意義
――大変耳の痛いご指摘です。やはり評論とは何かという目で見れば、「水の東西」が随筆だというのは、その通りだと思います。ただ、大体、高校に入った最初ぐらいに扱うんですが、論理的な展開とか思考とかというものを意識づけたいときに「水の東西」を読んでいくと、頭の中で読み手が追っていくのとほとんど同じ感じで文章が流れていって、論理というものが体感できるというか、非常にわかりやすい教材だと思っているんです。
それは本来、私が厳密な意味での評論書きから出発しているからだと思いますね。ですから仮に随筆を書いても、本当に柔らかい随筆にならないんですよね。それが結局、評論として受け取られる結果になっているのかと思うと、忸怩たるものがあります。
――随筆は着眼が面白ければという話がありましたが、その着眼が、なるほどと腑に落ちる。ちょっと面白いというよりもはるかにレベルの高いところでスッと入ってくるんです。だから、おっしゃるようなきちんとした結論というのはないのかもしれませんが、基本的にものを考えていくときの着眼とか切り口とかの見本として、「水の東西」はとても扱いやすい教材なのです。
そう言われると、少なくとも、大修館に関しては、区分を変えてくれとは言いにくくなってきたね(笑)。
それはさておき、文学教育というのは、もしやるなら随筆と評論の違いまで議論するような、そこまでやらなきゃいけないわけです。そんなことは高校の目的ではない、大学へ入ってからでいいんだ、というふうに割り切るならば、さっき申し上げたような正しい日本語というか、伝統的な日本語というものをしっかり教えておくことです。
――今、文科省でも国語教育をいろいろ模索していて、指導の例を作るんです。その中で、「水の東西」を読むのではなくて、書くことのお手本に使うことも紹介されています。
それは光栄ですね。「水の東西」のことはともかく、一般論として、書く力をつけるためには、名文を書き写すとか暗誦するとかいうことが意外に効果があるんです。でも今、これは一番嫌われているようです。なぜかというと、暗誦というのは頭ごなし、強制というイメージと結びつくから先生も嫌がる。生徒はもっと嫌がる。しかし実はそうではないんですね。英語を暗記するように、国語だってそういう段階があっていいんじゃないかと思うんです。
言葉は変わるからこそ国語教育は一貫性が必要

私は、国語教育というものについては保守主義者です。言葉は放っておくと、どんどん変わっていくものだ。そのことを否定はしないですよ。保守主義者といっても、変わること自体を否定はしません。例えば、「とても」というのは、本来は、私の小学校時代までは否定形にしか使ってはならないと言われていた。「とてもできない」「とても及ばない」というようにね。ところが今は、単なる強調の言葉に使われるようになって、「とても美しい」とか、「とても楽しい」とか言いますよね。言葉というのは、そうやって変わっていくものです。だから、逆に学校では、世代を超えた一貫性というか、変わらない国語、歴史的な伝統というものを教えておくべきです。極端なことを言えば、もしも伝統を完全に忘れてしまうと、日本人同士でも違う世代と意思疎通ができなくなる。
「情けは人のためならず」を、今の子の多くは逆に理解しているというんですよね。もとは、情けを人にかければ、やがてお返しが来るから、人のためならずだ、自分のためだという意味だった。ところが今は、人に情けをかけるとそいつが甘ったれになってためにならないから、人のためならずだと。だから、もっと相手に薄情にしなさいという言葉になったんですよね。これはおかしい。もはやそう使っても構わないけれども、昔はそうではなかったということは知っておかなきゃいけない。でないと、じいさんが「情けは人のためならず」と言うと、孫がいじめっ子になる可能性がある。
ですから、学校教育の国語というのは、基本的になるべく保守的でなければならない。だからと言って、小学生に古文を教えろとか、そんな極端なことは言いません。近代の名文でいいから、名文の中に表れている表現、用法、用例を教えていくべきです。
言語は社会のためにあるからこそ教育できる
私の言葉の哲学は先に申し上げたように、言語というものは自分のためにあるものではなくて、社会のためにあるものだということ。だから、国家が義務教育で教えることが許されるんですよね。
もっと言えば、一対一の相手とのコミュニケーションというのは、まだ言葉としては不十分なんです。一対一の関係というのは、言葉がなくても意思疎通ができるからです。例えば、腹が立った。黙って殴る。もう十分通じますよね。また、家族の間であれば、ほんのちょっとしたしぐさでも、ああ、今日は機嫌が悪いななどと通じるわけです。ですから、本当に言葉が必要なのは第三者が予想されるときです。このことを私は鼎話構造と言っています。
言葉というものの本質は第三者が立ち聞きできるメディアである。そういうふうに私は定義している。言語というのは、ある特別のコミュニケーションで、第三者を含む広い社会というものが前提にあるわけです。例えば私が手紙を書いて、それが相手に届くということは、本質的には第三者に読まれても構わないという態度で書いているわけです。実際には第三者に読まれちゃ困ることもありますが、言葉としては第三者に通じる言葉で書いている。その証拠に、作家の書簡集なんていうものが残っているわけです。
言語というのはそういう鼎話構造を持つのが本質だから、その訓練をしなきゃいけない。ちなみに、感性や情緒を育む教育について言えば、直接にはそんなものはありません。感性や情緒などというものは自ら開拓していくものであって、それを教育で教えられるものじゃない。しかし、人間は言葉で感じるもので、感じること自体の根底に言葉があるんだから、言葉とその用例、ニュアンスをしっかり教えておけば、感情は自ずから細やかになっていきます。
今、その点で非常に心配なのは、日常で単語の数が減り出していることです。なんでも「かわいい」でしょう。やはり、今の国語教育を全面的に変えろとは言わないけども、徐々に文学じゃなくて本当の国語教育に重点を移していくべきです。見知らぬ人にちゃんと伝わる言葉を身につけてほしい。それを学校で教えてほしいんです。
(2014年11月7日収録)
『国語教室』第101号(2015年5月)より転載
著者プロフィール

山崎 正和(やまざき まさかず)
1934(昭和9)―。劇作家、評論家。京都府生まれ。主な著書―『鷗外 闘う家長』『柔らかい個人主義の誕生』など。
●聞き手=山下 直(やました なおし)
文教大学准教授。大修館国語教科書編集委員。2000~2014年文部科学省教科書調査官。
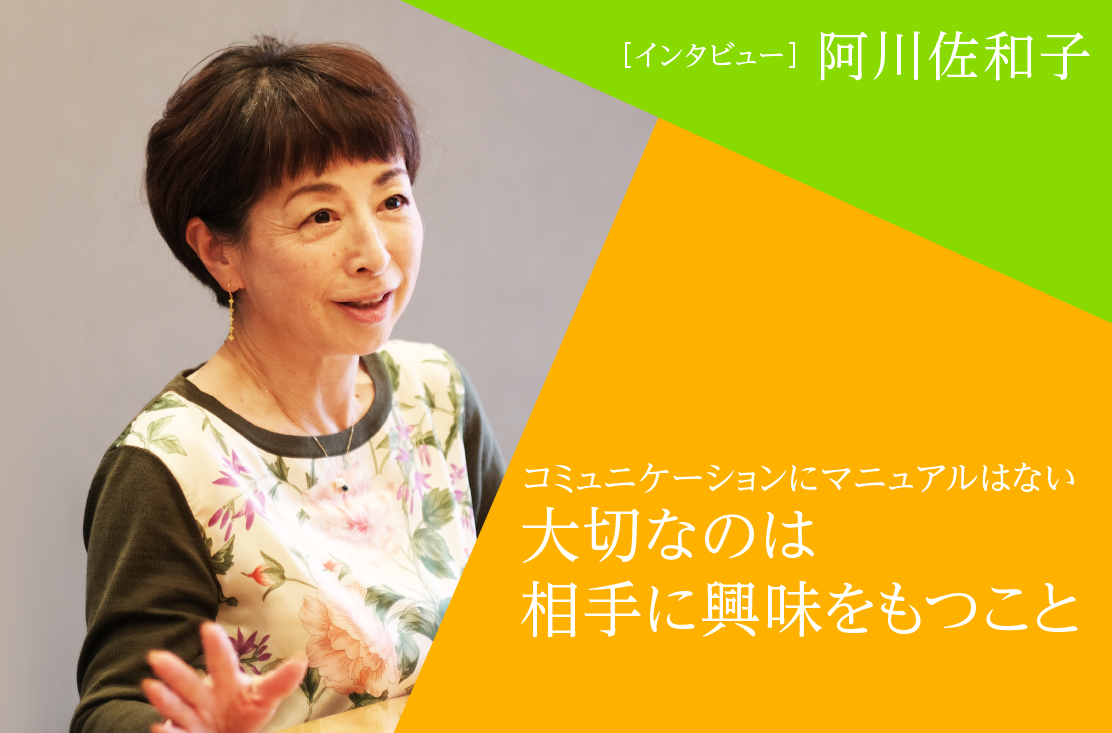
詳しくはこちら
一覧に戻る