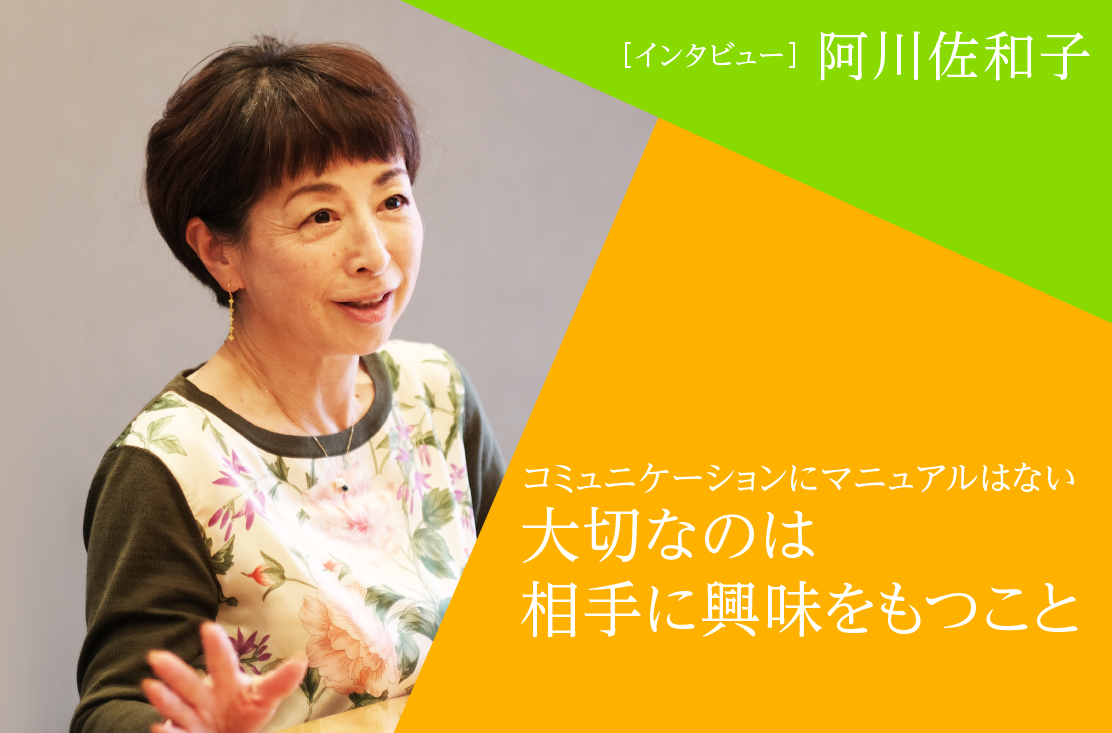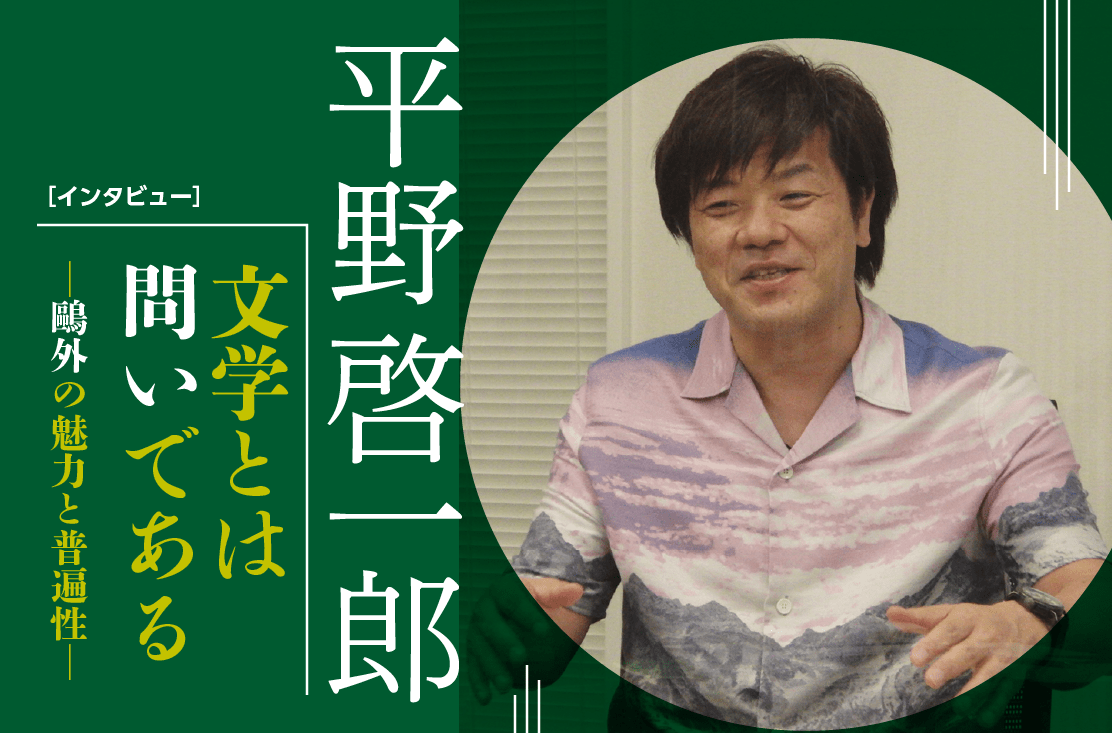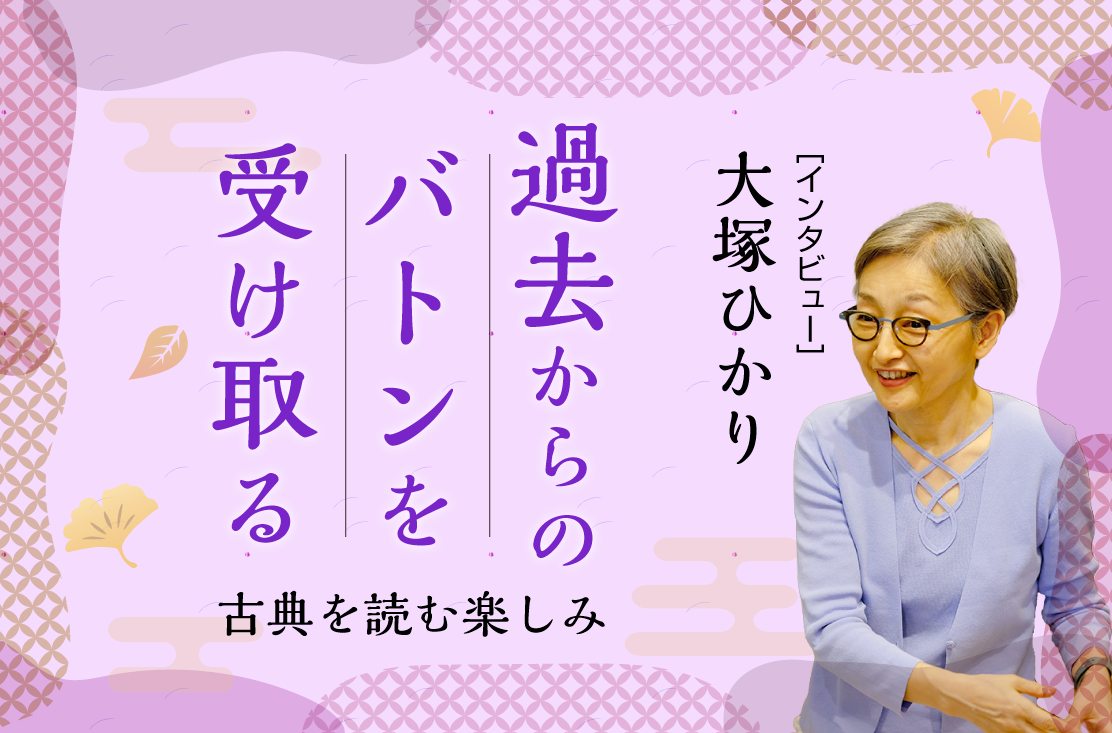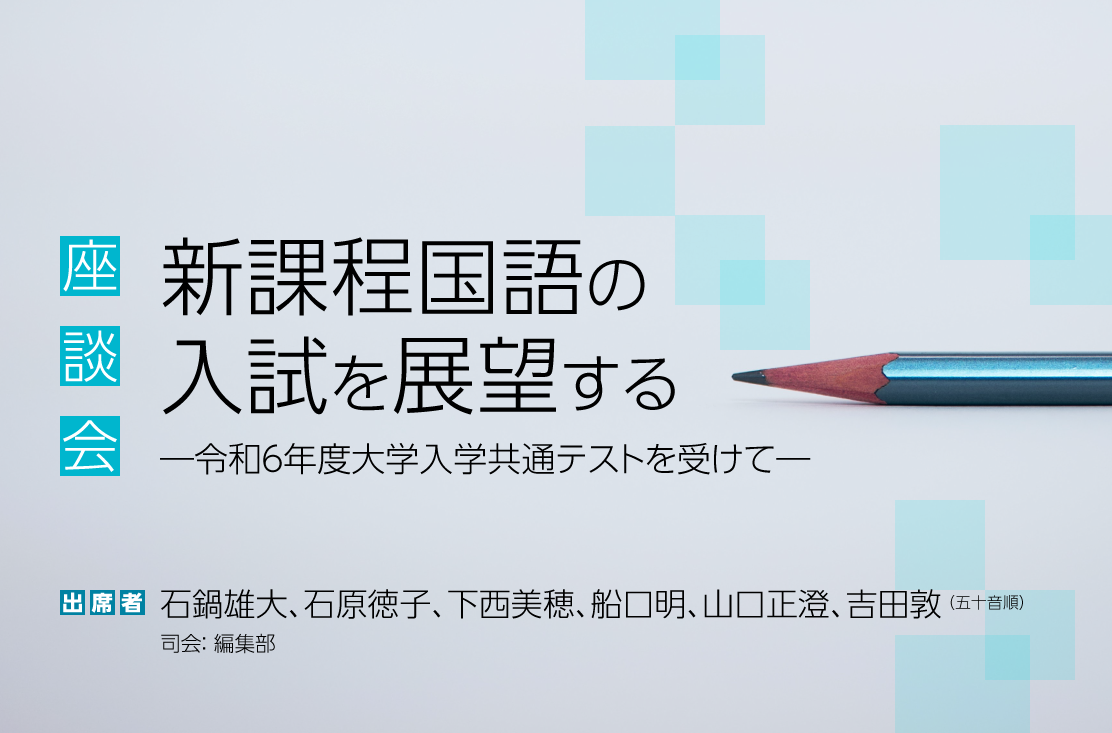〈インタビュー〉 中西進 聞き手:西一夫
今に生きる言語文化
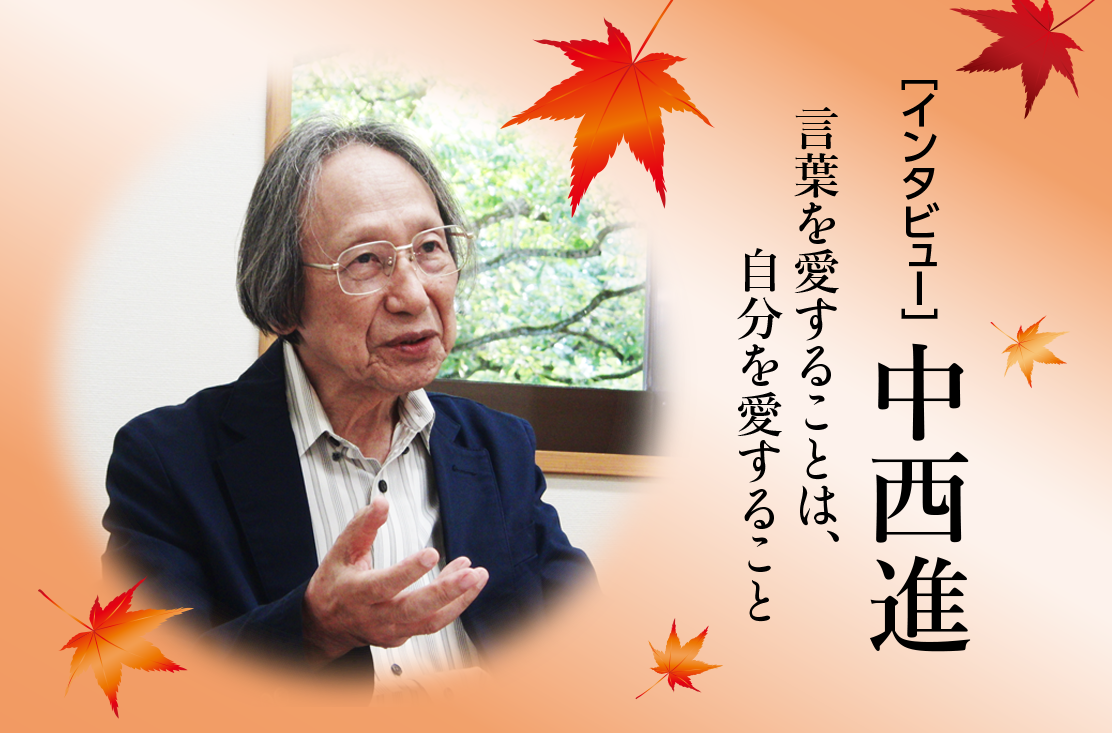
急速なグローバル化が進み、異なる国や文化に属する人々との関わりが、今後ますます重要となってくる現代。 このような新時代「令和」に生きる私たちが、今こそ見つめ直すべき「我が国の言語文化」とはどういったものなのでしょうか。 『万葉集』をはじめとする、日本の古典文学研究の第一人者・中西進先生に、じっくりとお話をうかがいました。
ことわざこそ、日本の聖典
―先生はしばしば日本語、つまり大和言葉の美しさや響きということをおっしゃっていると思いますが、まずはそういう点からお話しいただけないでしょうか。
現在の社会を見ていますと、非常に漢字偏重の傾向があると感じます。でも日本の伝統を考えますと、それはやっぱりあまり正しくない。
たとえば日本には、書物としてのバイブルってないでしょう。漢字を伝えてくれた中国には『論語』や『詩経』といった聖典がきちんとありますけれど。『古事記』や『源氏物語』も、やはり他国でいうところのバイブルとは違うと思います。じゃあ日本民族が伝統として伝えてきた聖典って果たして何なのかといいますと、わたしはことわざだと思います。ことわざというのは、漢字に代表される書き言葉ではなくて、あくまでも古代の人々の話し言葉がもとになっていますよね。日本人が書き言葉としてではなく、口承伝承として今に至るまでずっと伝えてきた大切な聖典。そういうものとしてわたしはことわざを位置づけています。
日本の聖典が文字として、つまり証拠になるものとしてほとんど残っていないというのは、ちょっと頼りないような気もするかもしれません。しかし逆に言うと、口から発せられた言葉が、わが国では証文と同じような働きをしてきたともいえます。そういう、書き言葉よりも話し言葉を大切にしてきたという言語的背景が日本にはあるから、われわれにとっては音声言語、くちびる言葉というものが、非常に大切になってくる。ですから、言葉が本来もっている響きとかイントネーションとか、そういう生きた感覚を教えるのが最も重要な言語教育だと思います。
 音読によって、言葉の響きを味わおう
音読によって、言葉の響きを味わおう
―今回の学習指導要領でも、全校種で「音読」や「暗唱」という言葉が出てきます。やはり一生懸命声に出すことで、頭ではなく体に落とし込んでいくということが重要なんですね。
以前映画のシナリオを見せてもらったことがあるんですよ。私、台本にはイントネーションとか間合いとか、細かい指示も全部書いてあるんだろうと思っていたんですが、実際に見てみるとあるのは台詞だけで、最低限の動きの指示しか書いていなかったので驚きました。つまり、私たちがテレビや映画で観る立体的な動きとか迫力とかは、俳優が台本から読み取った後に表現されているということです。それを見て、やはり書き言葉はただ視覚的に意味をもっているに過ぎないけれども、音声言語には細かいニュアンスとか呼吸とか声の響きとかがすべて含まれていて、無限の可能性があるということを感じました。
それは国語の教育でも同じで、教室で文章を黙読しているとき、人間の脳はごく限られた活動しかしていませんが、声に出して読むことで、脳の働きは劇的に変わりますね。少なくとも字を追っていたらいつの間にか寝ていた、なんていうことにはならない(笑)。だから黙読だけの学習というのは、本当に限られた生命活動でしかない。それが音読という活動を通すだけで、われわれの言葉に関する意識が100%に近い形で総動員されるという、この違いはそう簡単に見過ごしてはいけない問題です。そしてそれが、子どもたちの文章への解釈や理解にもつながっていくはずです。
―先生の「万葉みらい塾」に参加した小学生の感想を読んでいますと、万葉歌の音読を通して「細かいことはわからないけど、歌われているのはたぶんこんな風景だ」って答えた子が多いんですよね。それはやはり声に出すことによって子どもたちの中で言葉のイメージが広がって、歌の世界につながっていったんだろうと思います。
「万葉みらい塾」での主体的な授業
数学や物理などが典型的ですが、今の学校ではまずは定理や公理といった一般的なものから始まって、次に一つ一つのケースを考えていくという教え方が、重視されてきたんだろうと思うんです。もちろん、それでうまくいく学問もあるでしょうが、しかしこれは人間の本能的な、自然な発想とは全く逆行しているということもまた事実です。たとえば赤ちゃんは、近くにあるものを何でも触って、学習していく。生活全部がケーススタディですよね。触ったり泣いたりというケースを一つずつ重ねていく中で、徐々にトータルなものがわかっていくというのが、本来の人間の営みであるはずです。
私がこれを感じたのが、「万葉みらい塾」での授業です。この第一回目で、小学六年生の子供たちに和歌をテーマにした授業をしてくれと言われたんです。学校に行ったときに、校庭にチューリップの花が咲いているのが見えたので、私がまず「校庭に きれいに咲いた チューリップの花」と示して、上の二句を変えていってごらんといったら、みんなわいわい手を挙げましてね。中には「午後六時 つぼみにかえる チューリップの花」なんて言った子もいて、大変にびっくりしました。そしてこの二つの歌をつなげると、「校庭に きれいに咲いた 午後六時 つぼみにかえる チューリップの花」と、五七五七七の和歌が一つできますよね。和歌についての一般的な説明なんてしないで、チューリップという一つの事例をもとに授業をしたら、みんなおもしろがって和歌という全体を理解しちゃいました。

―今のお話をうかがっていると、今回の学習指導要領で言われている「主体的、対話的で深い学び」ということは、すでに先生のご授業で実現されているような気がします。
この「万葉みらい塾」は計六十六回やりましたが、最も成功したのは忘れもしない、ある学校でした。生徒たちが沸きに沸いて、大成功で終わったんですが、そのあとに校長先生と話していたら、「実はあのクラスは、二か月くらい前まで学級崩壊を起こしていて、誰も手がつけられなかったんですよ」とおっしゃったんです。それで驚いて、成功の理由は何だったのかなと考えたんですが、結局は生徒たちに主体性・自主性を与えた、ということなんでしょうね。今、「対話」とおっしゃいましたが、私はもともと教えることなんてできないと思っています。できるのは生徒との対話だけです。それも常に生徒のほうから話を引き出すように、必ずどんな質問にも向き合うようにしていました。
日本語の幅広さを感じる
―最初にことわざのお話がありましたが、今の生徒たちはことわざや故事成語などを、あまり日々の会話で使わなくなってきている気がします。その点はどのようにお考えになりますか。
ことわざについては、文字言語か音声言語かということで話をしましたけども、ことわざにはさらに「幅広さ」という特徴もあります。つまり、ひとつのことわざに対して、必ず反対の意味のことわざがある。例えば「渡る世間に鬼はない」といったら、「人を見たら泥棒と思え」、といった調子です。これは、ことわざがどんな場合にも役立つ言語体系なんだ、ということを示しています。こう言うと逆に、「ことわざには一つの思想がないということじゃないか」と言われることもありますけど、そうじゃなくて特定のイデオロギーやポリシーなんかを超えていく、力強い構造をもっていると言うべきです。その意味で、ことわざはあらゆる場合に、あらゆる人間に救いの手を差し伸べられるのですから、すごいことです。
こういう幅広さはことわざに限りません。先日録音の仕事をしていたら、業者の人が「優しい」という言葉が「恥ずかしい」という意味にもなることを初めて知りました、と言うんです。恥ずかしいと思う時には、自分がその瞬間とても優しくなっています。傲慢な人というのは、相手に対して自分が恥ずかしいと思わない人間のことですから。逆に恥ずかしいと思うからふるまいが優しくなるのです。そういうふうに、反対の意味を考えればわかることがよくあります。
同じことですが、みなさんは知らないうちに辞書に使われていませんか。辞書が挙げる①②③…の意味のうちのどれに当たるか、などと辞書を見るのではなくて、①②③…のすべてが、この言葉の意味だと考えるべきでしょう。それでこそ辞書を使っていることで、その反対では辞書に人間が使われているのです。
近頃、「令和」の「令」という字で、そういうことをよく言われましたよ。「令」の意味で、「②に『命令』と書いてあるから、これは悪い元号だ」と言うんです。「じゃああなたは命令されたら何でも言うこと聞くんですか」と言ったら、「いえ、いい命令は聞きますが悪い命令なら聞きません」と言う。じゃあ人を聞く気にさせるほどいい命令なんだから、「令」は本来いい意味ではないですか。これもやはり辞書に使われてしまっているんですね。そうではなく、「令」は善や、立派さや、「命令され、使役されるほどにいいこと」を指す。この言葉が使われてきた全部の、もっと幅広い意味合いや歴史を背負っているものです。そういうふうに辞書を使ってもらいたいですね。
古典が好きになったきっかけ
―では最後に、古典についてうかがいたいと思います。先ほど「万葉みらい塾」で和歌などを楽しんで学んだという子供たちのお話がありましたが、現代では古典嫌いの生徒たちがとても多いようです。生徒たちが古典を自分に身近なものに感じるには、どのようなことに心がければよいのでしょう。

それについては私は、生徒だけじゃなく教える側の先生にもお願いしたいことがあるんです。それは教えるときに、「自分で鎧を着ていませんか」ということです。
たとえば、私は「中西さんはいつ、万葉を志したんですか」と聞かれたら、いつも高校時代のある先生のことを思い出すんです。その先生が『万葉集』の授業をしていて、「なんか質問ないか」と言った。でも誰も質問せず黙っていたら、先生が「お前たちには学習意欲がない」と言って怒りだしてしまった。仕方がないから私が手を挙げて、「今の歌に赤人とか黒人とかって名前が出ましたが、先生、これはどういう意味なんですか」と聞いたんです。すると先生は、「それは俺もわからん」とおっしゃった。その瞬間に私、その先生への信頼感がぐーんと増しました。後から調べてみたら、その先生は俳諧の専門家だったんです。だから専門的に勉強されていて、自信もあったはずです。自信があったからこそ、「知らないことは知らない」ととても正直におっしゃれたんですね。そういう姿勢を示すことが最大の教育だと思います。だから私、その先生を今でも尊敬しています。その時の授業から私は、国語や古典が好きになったと言ってもいいくらいです。
ですから、今現場でがんばっておられる先生方も、「自分は先生なんだから何でも知っていなくちゃならない」と鎧を着ないでほしいですね。それでは逆に生徒にとって、古典への垣根が高く感じられてしまいますから。人間ですから、知らないことはなんでもないんです。「知らないことがいけないんじゃない、知ろうとしないことがいけないんだ」という精神でいていただきたいものです。
自分を愛するように古典と言葉を愛する
そして、子供たちがどうすれば古典を好きになるかというお話ですが、それにはとにかく古典を自分のものとして、愛することが大事だと伝えたい。
たとえば『源氏物語』を読むと、なんで光源氏はこんなにも苦しむんだろうと思う。他の人物にしても、みんな愛を求めながら、苦しんで生きています。そして六条御息所のような人になりますと、もう完全に我々の条理を超えた、不思議なものが人間にはあるんだなぁということがわかりますね。そういう愛に関することとか、昔からずっと続いてきた、わたしたち人間に共通で普遍的なことが、古典には描かれています。その意味で、古典は決してガラスケースの中だけに保存しておくものじゃなくて、自分のこととして考えるべき、普遍的な価値をもったものです。自分のものだと思えば、自然と古典を大事にします。
そして、古典を愛するためには、まずは言葉を愛さなくてはいけませんね。日本人は『万葉集』が編まれた時代から、大和言葉というものをずっと大事にしてきました。ギリシャ語やラテン語などとは事情が全く違い、万葉の時代と現代とで、約七から八割は共通の言葉を使っているという、本当に特殊な民族です。千年以上の時代を経て、大切に受け継がれてきた言葉の尊さを、しっかりと感じることがまず大切です。
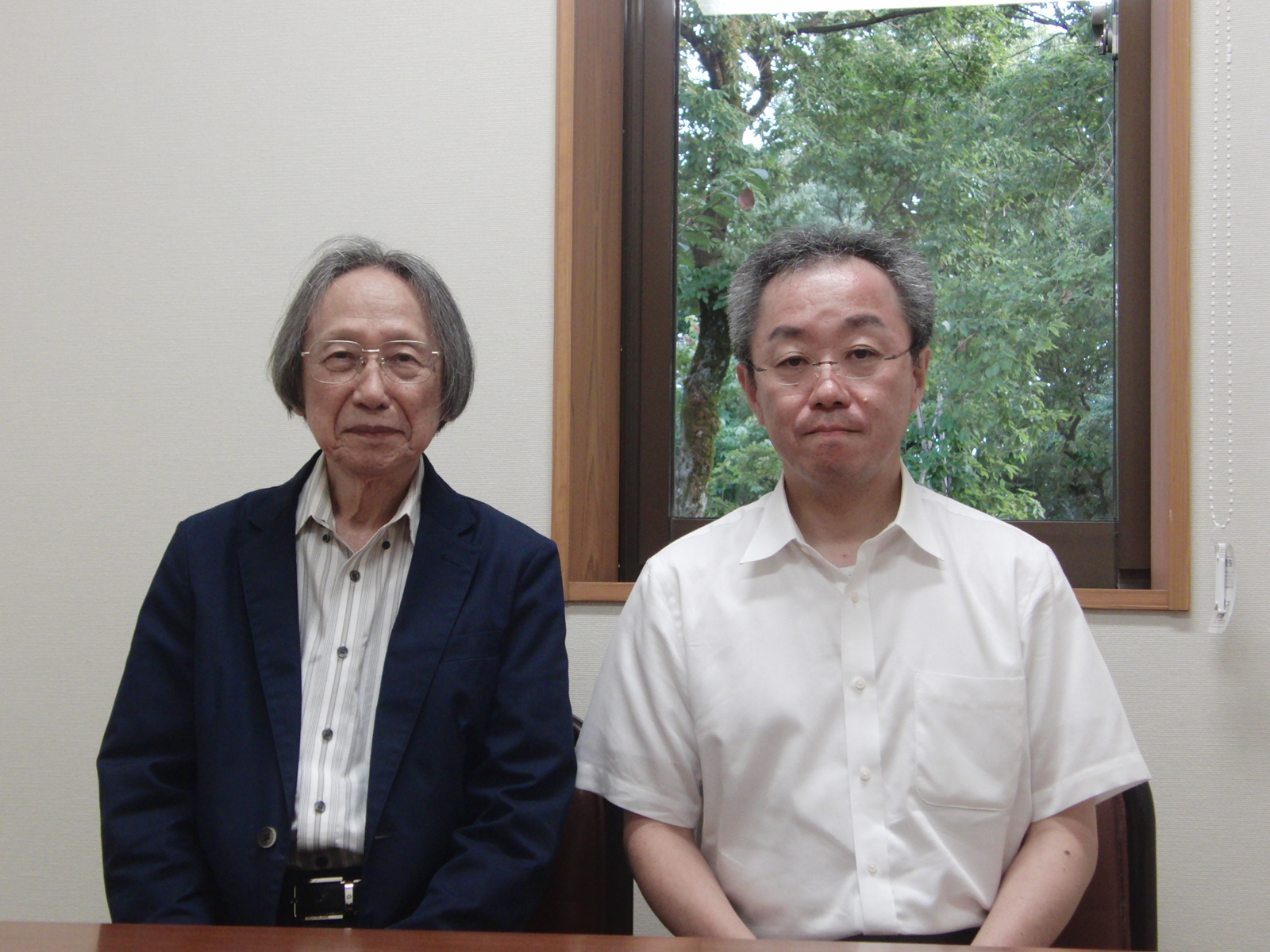
さらに言葉を愛するということをつきつめていくと、これは「自分を愛する」ということになる。言葉は人間が何かを認識するときの根本にあるのですから、それによって自分を見つめて、そこからその人の行動が発せられて、立派に生きたい、美しく生きたいというその人の生き方につながっていきます。ですから、まずは言葉を愛することによって自分を愛する、自分の命や人生をもっと大事に見つめる。これが古典に親しんだり、古典を愛したりするということの、根本の出発点になります。
―ありがとうございました。
(2019年8月11日。中西進先生が館長をなさっている高志の国文学館にて)
『国語教室』第111号より転載
著者プロフィール
中西 進(なかにし すすむ)

『万葉集』をはじめとする日本の古典文学研究のほか、小学生に古典の面白さを伝える授業「万葉みらい塾」などの活動で知られる。著書に『万葉の秀歌』、『ひらがなで読めばわかる日本語』など。
西 一夫(にし かずお)

専門は日本古代文学・古典文学・古典文学教育。大修館書店国語教科書編集委員。
一覧に戻る