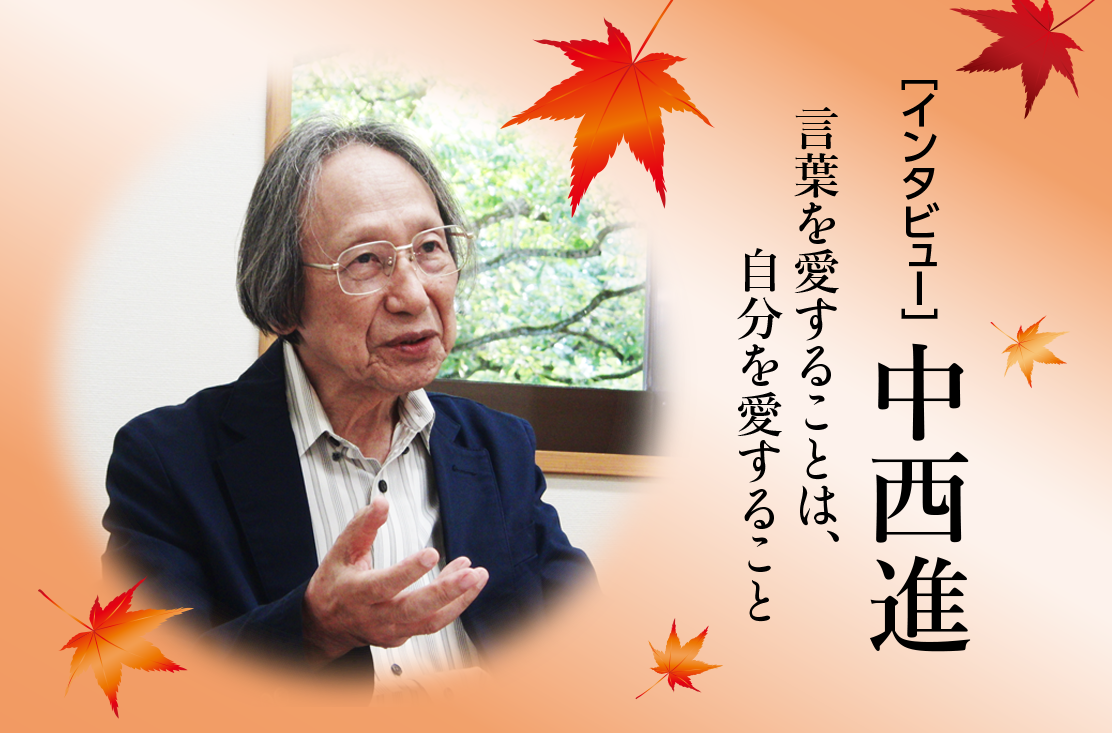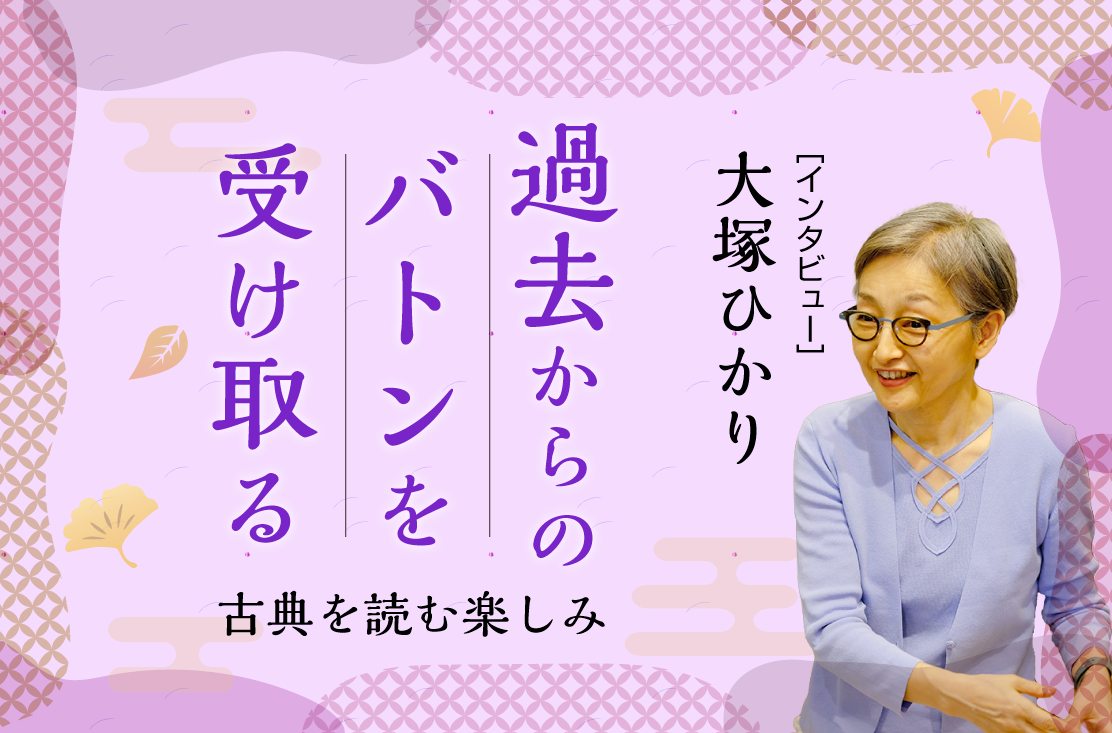〈インタビュー〉平野啓一郎 聞き手:高橋龍夫
文学とは「問い」である ──鷗外の魅力と普遍性
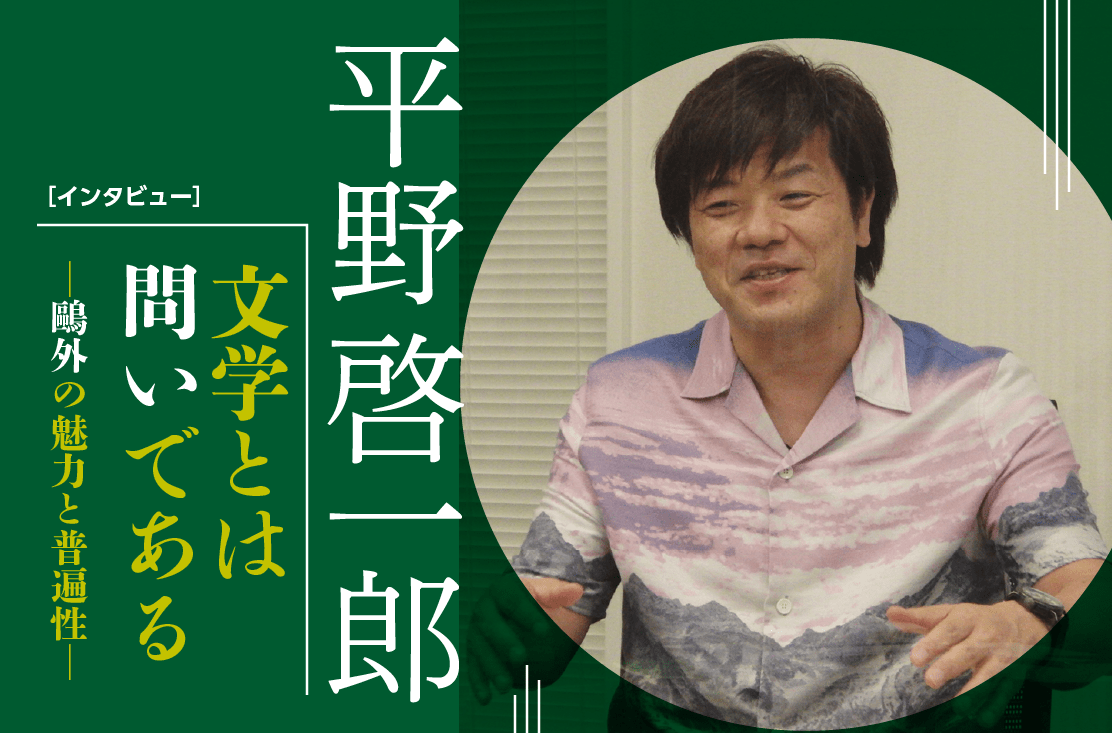
──講演や文京区立森鷗外記念館の特別展「読み継がれる鷗外」への企画協力など、森鷗外について精力的に発信し続けている平野啓一郎先生に、森鷗外の人物像やその作品の魅力についてお話をうかがいました。
鷗外からの影響
──まずは、鷗外から受けた影響についてうかがいたいと思います。平野先生は鷗外の小説作品すべてを読まれたとお聞きしました。
小説と翻訳の作品はすべて読みました。「舞姫」から「北条霞亭」までを通して読んだのは大学時代です。自分の文体を形成する上で、鷗外の作品を一通り読んだことは圧倒的な影響がありました。ほかにも、小説家になるなら読まなければ、と考えて、漱石や芥川の小説もすべて読みましたが、鷗外がいちばん肌に合いました。
デビュー作の「日蝕」は、鷗外の史伝や「即興詩人」などの文体・語彙の影響が大きいです。鷗外の史伝の文体は「春秋左氏伝」などを元にしていて、語彙もそのまま用いていることがあります。「日蝕」が中国語訳されたときも、中国人の訳者に、「中国語で訳せない語彙は一切ない」と言われました。擬古文というわけでもなく、鷗外にヒントを得ながら自分なりにアレンジした結果生まれた文体でした。当時、中西進先生にも「新しい文体だ」と評価していただけて心強かったですね。
──漱石、鷗外、芥川の中でも特に鷗外に魅力を感じたのはどのような点でしょうか。
作家として、漱石や芥川よりもはるかに大きいと感じます。自然科学者でもあって、問題のとらえ方が大きく、人間としておおらかさもある。
主に筑摩書房の文学全集を愛読していたのですが、注釈が詳しく、見開き単位で入っていて非常に役立ちました。初めは全部読めるかなという不安もありましたが、文体に魅力を感じつつ、どんどんのめり込んでいって読み通すことができました。自分の文体を作り上げて小説家になろうとしていた時期でしたので、どういう文体で、どういう構成だと読者が納得するのか、という点に関心があったんです。論理的整合性だけでなく、リズムや呼吸による説得力という点も非常に大きいと思います。
鷗外の文体はリズムも心地よく、それを身につけたいと思い、読むだけでなく、新潮社の朗読テープで、「高瀬舟」や「寒山拾得」の朗読をよく聞きました。
文学者たちが見た鷗外
──私は芥川の研究を専門にしていますが、いろいろと読み直してみて、芥川も鷗外の影響が大きいのだなと感じました。
漱石より、直接的には鷗外の影響のほうが色濃いと思います。歴史を題材にした作品も多いですし。漱石のお葬式で受付をしていた芥川が鷗外に偶然会い、「あれが、森さんか」と非常に感激したとか。当時の文士たちから仰ぎ見られるような存在だったのでしょう。
一方で、観潮楼(鷗外の自宅)を訪ねた際の印象などを書いているものを読むと、わりと気さくな人だったことに気づきます。「失敬、失敬」と言いながら部屋に入ってきたり。
また、子供たちが残した思い出話などを読むと、本当に「こんなお父さんいるのかな」というくらい大きな愛情で、子どもたちを育てています。そうした本を読んで、やっと僕の中でも「鷗外ってこんな人なんだ」というところがわかってきたのです。
──作品から感じる距離感とは違う一面が感じられますね。
永井荷風の「断腸亭日常」を読んでも鷗外に対する尊敬というのは特別なものがありますよね。寂しそうに回想しているくだりもあります。
僕自身、十代で三島由紀夫の影響を受けたのですが、三島も鷗外を崇拝していました。好きな作家が尊敬している作家ということで、鷗外により関心をもったわけです。あとは谷崎、荷風、芥川など、好きな日本文学の系譜の作家たちの多くが鷗外を尊敬していたので、興味をもちました。
女性の描き方
そして、その彼らが漱石にはほとんど関心がない (笑)。個人的に、漱石は女性の描き方が好きではありません。二次元的過ぎて、生きた人間という感じがしないというか。「坊っちゃん」「草枕」「三四郎」などの女性を見ても、生きた女性のリアリティがすごく乏しくて、男性目線で書いた女性としか思えないですね。
その点、鷗外の描く女性はリアリティがあるし、芯が強くて「生きている女性」という感じがします。もともと樋口一葉を認めたのも鷗外ですし。当時ドイツで開かれた婦人解放運動のシンポジウムにも、日本人で唯一参加しています。当時のフェミニズム運動の起源に触れて帰国しているので、鷗外の作風にも影響が出ていると思います。
──漱石の木曜会も男性ばかりでしたね。
荷風や谷崎など、女性好きの作家はやっぱり漱石がぴんときてないのでしょう(笑)。教科書には「舞姫」しか載っていませんが、「うたかたの記」「文づかひ」も合わせてドイツ三部作を通して読むと、当時のヨーロッパ社会での鷗外の姿がよく見えます。極東からの留学生として、踊り子やカフェの女給といった階層の女性とはフランクに付き合えるけれど、「文づかひ」のような貴族の女性とは手紙のお使いほどの役割しか果たせない、というような。「舞姫」のエリスだけでなく、三部作で見ると、それぞれの社会階層の女性がどうやって生きてきたかということがよく描かれていることがわかる。「文づかひ」におけるイイダ姫のような非常にしっかりした自分の意志をもって道を切り開く女性。「舞姫」のエリスのような社会の底辺で苦しむ女性。「うたかたの記」に描かれる、宮廷画家の娘がカフェの女給という庶民の身分に没落した姿……。社会階層と属性、そして自分がどの程度関与できるのかという視点から、当時の女性の現実をうまく書き分けていると思います。
──明治時代に、ドイツ三部作のような作品を日本に書いて伝えてくれた功績は大きいですね。
あの男尊女卑の時代で、貧富の差もある中で、この貧しい踊り子の女性は、かわいそうじゃないか、ということをうまく描いているというのは重要なことです。豊太郎自身も美化して書いているわけではなく、一つの問題として提示している。ただお話を作るだけではなく、「文学作品とは、何かを問題化することだ」ということをよく理解していた作家だと思います。
自己責任論に抗して
──鷗外の思想についてはどうお考えですか。
鷗外の思想は、最初はよくわかりませんでした。作品を読んでも、思想などよりも「経緯」や「事情」をずっと書いているという気がしていました。
段々わかってきたのは、「反自己責任論」が通底しているということ。これは、ある意味、鷗外を物足りなく感じる人もいる原因かもしれませんが。ヒロイックに現実を切り拓いて問題を解決していく主人公ではなく、歴史的な事情や偶然、無意識などによって翻弄される人物たちの事情をずっと書いている。運命への不可抗力を作品に感じるようになってから、急にさまざまな彼の作品を見通せるようになりました。鷗外は自然科学の研究者でもあったので、彼の短編にはその見地も生きています。実験のように、ある条件を定めて、その過程の中で人はどういうことになるか、ということを考えていたのではないかと思います。

──鷗外は社会なり因習なりの環境設定をして、人間がそのどうしようもない状況の中で右往左往する様子を書いている、ということですね。
鷗外は子どもが悪いことをしたときも頭ごなしに叱るのではなく、「なぜそうしたのか話を聞かねばならない」と妻に常々言っていたそうです。問題が起こったとき、何が背景にあってそうせざるを得なかったのかを理解しようとする、いかにも鷗外らしいエピソードだと思います。
鷗外は江戸時代の武士の家に生まれ、切腹の作法や蘭学・漢籍を学んだ最後の世代です。それをふまえて、近代以降の日本に生きるという感覚がありました。さらに、ヨーロッパでの強烈な体験。この三つの視点をもって考えたとき、環境次第で人間は違ったものの考え方をする、という相対主義的な見方を身につけていったのでしょう。
「諦念」と構造的社会観・人間観
──「諦念」についてはいかがでしょう。
「諦念」は個人の努力や決断の限界を意識していた鷗外だからこそ出てきた思想です。人間が社会構造の中で相当規定されてしまっているという見地に立つと、他者に対しては、仕方なかったのではないか、という理解につながり、自分に対しては「諦念」につながるというのが鷗外の基本的な考え方だったのではないかと思います。
僕がそのように考えるきかっけとなった、「魔睡」という小説があります。魔睡とは催眠術のことなのですが、主人公の妻が病院で催眠術をかけられて、知らないうちに性的な行為をされたのではないか、という話で、自分の意志で抗うことのできない状況での行いなので、罪を問いようがない、というのが鷗外の考え方です。当時はまだ姦通罪もありましたが。本人が自己責任で立ち向かえないような状況にあるのなら、それは仕方ないのではないか、と考えているのです。
「山椒大夫」も同様で、原作では厨子王が捕まえた山椒大夫の首を竹のノコギリで切って復讐を果たすという生々しい勧善懲悪の話です。それを鷗外は厨子王が人身売買禁止の法律を作り、それに従って山椒大夫も奴隷をやめて給料を払うことにした結果、山椒大夫はますます富み栄えたという話に改変しています。
僕は何とも言えない強い印象を受けました。個人の人格的な善悪を小説の中で追求してもしょうがないと鷗外は思っているのです。山椒大夫も人身売買が普通だからしているのであって、法律を定めたら、それに則ってビジネスとしてもっとうまく進めていく。勧善懲悪の痛快さなどはありませんが、そのような点こそ、鷗外作品が現代的な問題も含む理由だと思います。
──鷗外作品の人物像は一つのアイデンティティにとらわれず、周りから規定されている面がありますね。
そうですね。そして、その鷗外の相対主義には二つの面があったと思います。一つは、自然科学者としての面。科学者は分野に応じて別の学者の説を援用することは当然ですが、日本では、状況によって別々の学者の説を支持すると、「自分の考えがない」と批判されたりもしました。それに対して、鷗外は自然科学的に、フェアに物事を判断する力をもっていたと思います。
もう一つは、「歴史其儘」の態度にもつながってきますが、人格的な問題よりも状況的な問題に焦点を当てて作品を書こうとする面。史伝を書く際の、歴史的な資料に表れている、人間が生まれてから死んでいくまでの自然な姿を描こうとする姿勢ですね。特権的に主人公を際立たせようとするわけではなく、淡々と構造や状況を描こうとする考えがあったと思います。
──そうした鷗外の姿勢もご自身の創作につながっていますか。
私自身は完全なロスト・ジェネレーション世代なので、反自己責任論者であると思います。エンタメというものはキャラクター偏向になりがちですが、それも一種の自己責任論なのですね。どんな困難もキャラクターの超人的な能力で切り開いていくが、そのような能力をもたないキャラクターは不幸になっていく。
しかし、小説はそれではいけないと思っています。ある一人の主人公がどういう運命を辿るかを描くときには、構造的なところからアプローチしないと噓になってしまう。僕は、最初は鷗外の文体に惹かれたのですが、小説の書き方という意味でもかなり影響を受けたと思います。
ただ、鷗外ほどフラットに作品を書いてしまうと、現代では読者が面白みを感じられなくて厳しいというのも事実です(笑)。ある程度はキャラクターの輪郭を濃くしないと本を読んでもらえないですから。
「舞姫」をどう読むか
──「舞姫」を学校で読むと、「エリスがかわいそう」「豊太郎はひどい男だ」という感想になりがちですが、あらためて、今の時代に「舞姫」を読む意味は何でしょうか。
「エリスがかわいそう」だということをいちばん強調しているのは、作者の鷗外自身です。だから、作者である鷗外がひどい、と非難する読み方はよくわからないですね。「エリスがかわいそう」という読みは、鷗外の意図どおりの読みなのに、作者の意図どおりに読んだ人が作者へ反発しているところが、あの作品の妙なところです(笑)。
ただ逆に、多くの古典的な作品は現代の読者にはリアリティのない話になりがちなのに、これだけ多くの人が「豊太郎ひどい」とか「エリスがかわいそう」とか、感情を揺さぶられて読んでいるというのはすごいことです。文学作品としての力強さがあります。あれほど難解な文体の作品が、今でも読者の心を動かすんだ、ということの意味こそ、もっと考えるべきだと思います。
文学とは「問い」である
──読者の心を動かすことが、文学の醍醐味の一つですよね。
文学とは「問い」なんですね。算数のように決まった答えがあるものではない。作品に、もやもやしたものを感じたところから、文学鑑賞も深まっていくのです。
例えば、「エリスがかわいそうだ」と思う人には、なぜそう思うのか、それこそ鷗外の執筆意図ではないかと問いかけることが考えられます。また「日本での立身出世に目がくらんだ豊太郎はひどい」という読み方をしている人もいますが、実際には、ひたすら人に言われるがままの人生なんですね。どこを読んでも、野心的に立身出世を目指す豊太郎の姿は書かれていません。そういう読みをしている人には、「どこにそう書いていると思うか」「豊太郎をひどいと思うのは本当は別の理由じゃないのか」「すべてをなげうって、エリスと結ばれる結末が本当によかったのか」「エリスが違う階層の人物だったらどうだったか」などの問いを与えることが考えられます。そのように、さまざまな問いにつながっていくところが文学のおもしろさで、それこそがあの作品のすごさだと思います。
教科書には「舞姫」だけではなく「うたかたの記」「文づかひ」も入れてはどうでしょう。ドイツ三部作それぞれで、女性の描き方が全く違うと説明すれば、高校生も「鷗外の女性観がひどい」などの短絡的な感想にはならないのではと思います。小説家の作品というのは、デビューから亡くなるまでの間の位置づけや、作品間の関係性を考えることが重要です。
教科書では、「舞姫」という一作だけに、ぽん、と出会いますが、国語便覧における作家の年譜や作品の系譜、創作時の状況などもふまえて理解するほうがよいでしょう。生徒自身が興味をもってほかの作品を読むことにもつながるはずです。
テキスト論が全盛の時代もありましたが、テキストを重んじて、せっかくたくさん残っている作家の情報に意図的に目を背けるよりも、やはり、作者の意図をふまえて読むほうが文学はおもしろいと僕は思います。特に森鷗外は人物としても興味深い人間ですから、それも併せて読むというのは重要な体験ではないかと思います。
高校生に読んでほしい鷗外作品
──最後に、高校生に読んでほしい鷗外作品を教えていただけないでしょうか。
「最後の一句」は短いけれど衝撃的な作品です。本当に考えさせられる話ですね。読み終わった後に議論をたくさんするべき作品です。
また「食堂」などの作品を、大逆事件といった歴史的背景をふまえて読むのも勉強になるでしょう。複雑な社会的背景をふまえて非常に微妙な書き方をしています。その行間を読むのも、文学の醍醐味だと思います。近代文学は、歴史と連動しているからこそのおもしろさがあります。個別の作品のおもしろさだけでなく、社会背景との関係がわかると、もっと文学を楽しめるのではないでしょうか。歴史の授業で勉強したことと併せて読む、ということが大事です。
──ありがとうございました。

『国語教室』第118号より転載
プロフィール

平野 啓一郎(ひらの けいいちろう)
小説家。一九七五年、愛知県生まれ。福岡県出身。京都大学法学部卒業。主な著書に「日蝕」「ドーン」「ある男」「本心」「三島由紀夫論」など。
Twitter: https://twitter.com/hiranok
公式サイト: https://k-hirano.com/

髙橋 龍夫(たかはし たつお)
専修大学教授。大修館書店国語教科書編集委員。
一覧に戻る