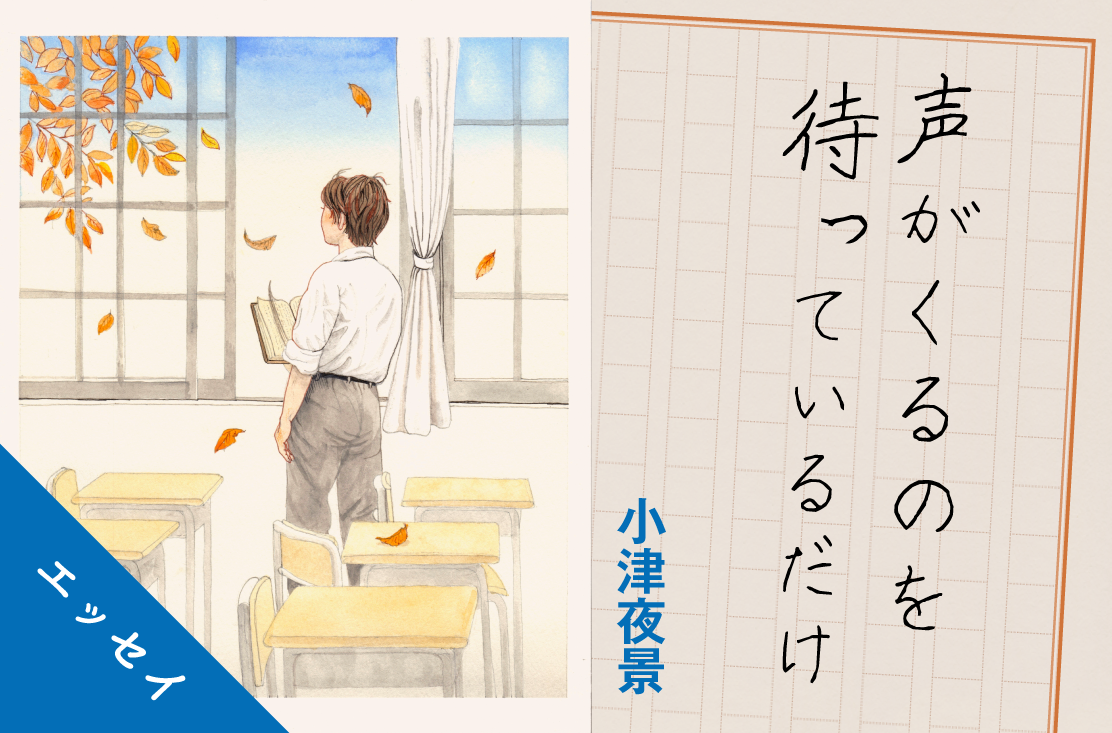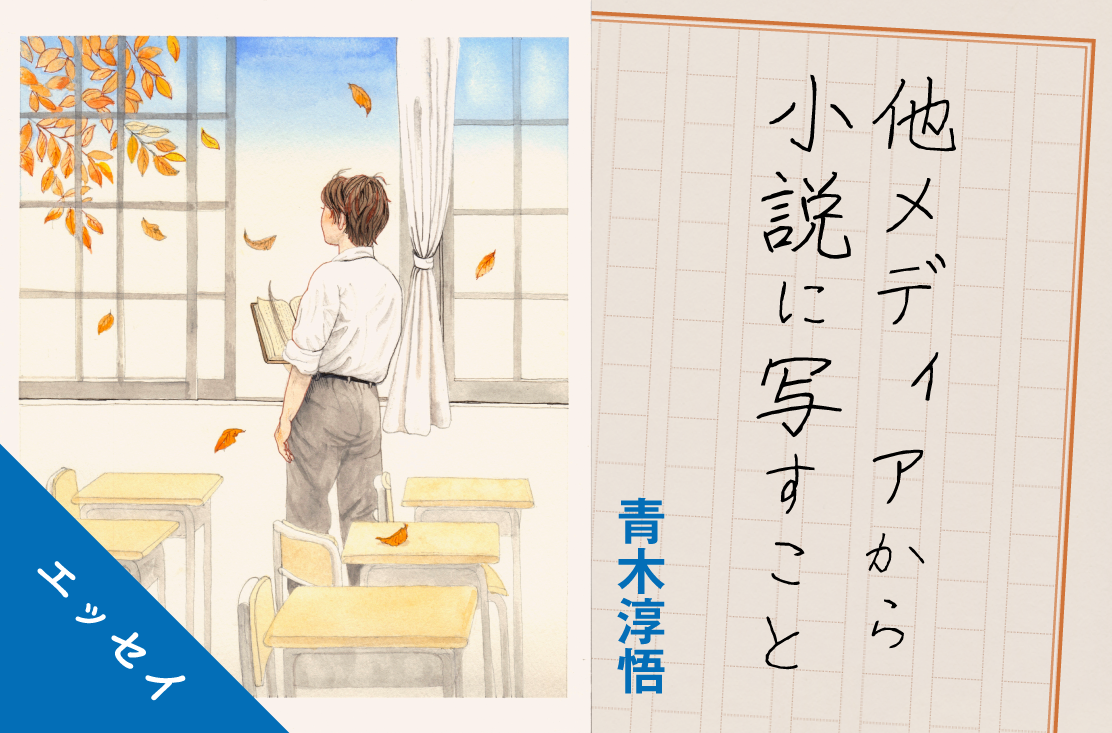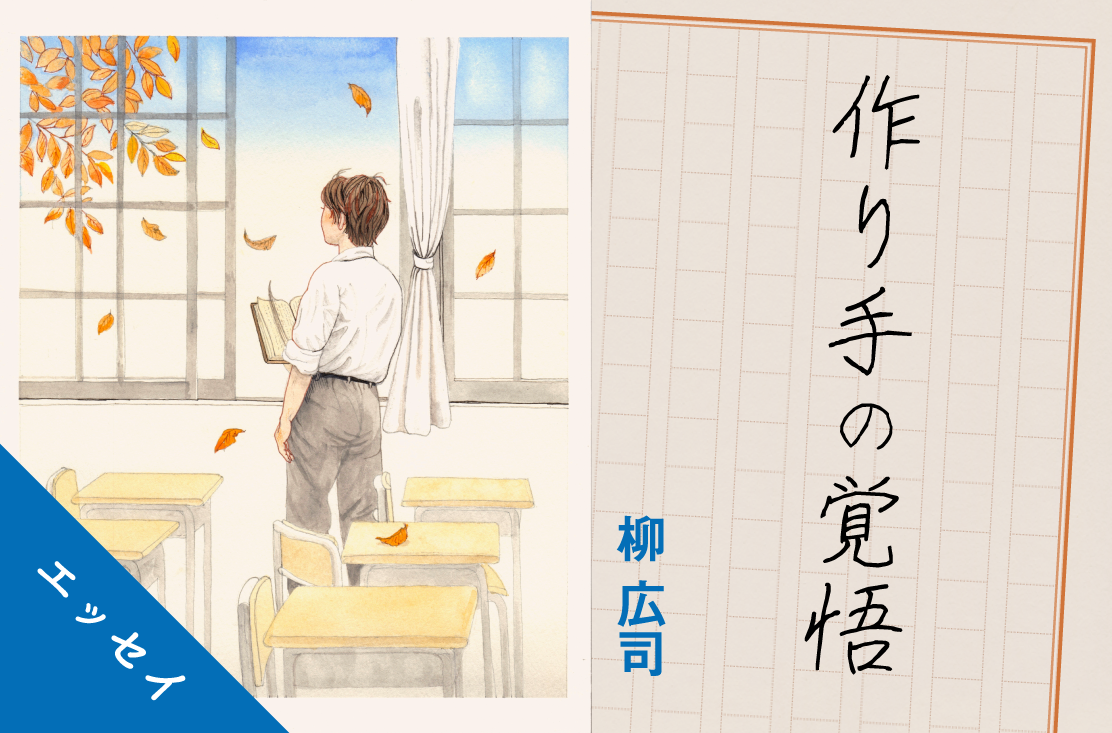文学エッセイ
”ほんとうの世界”を見せてくれるもの
苫野一徳
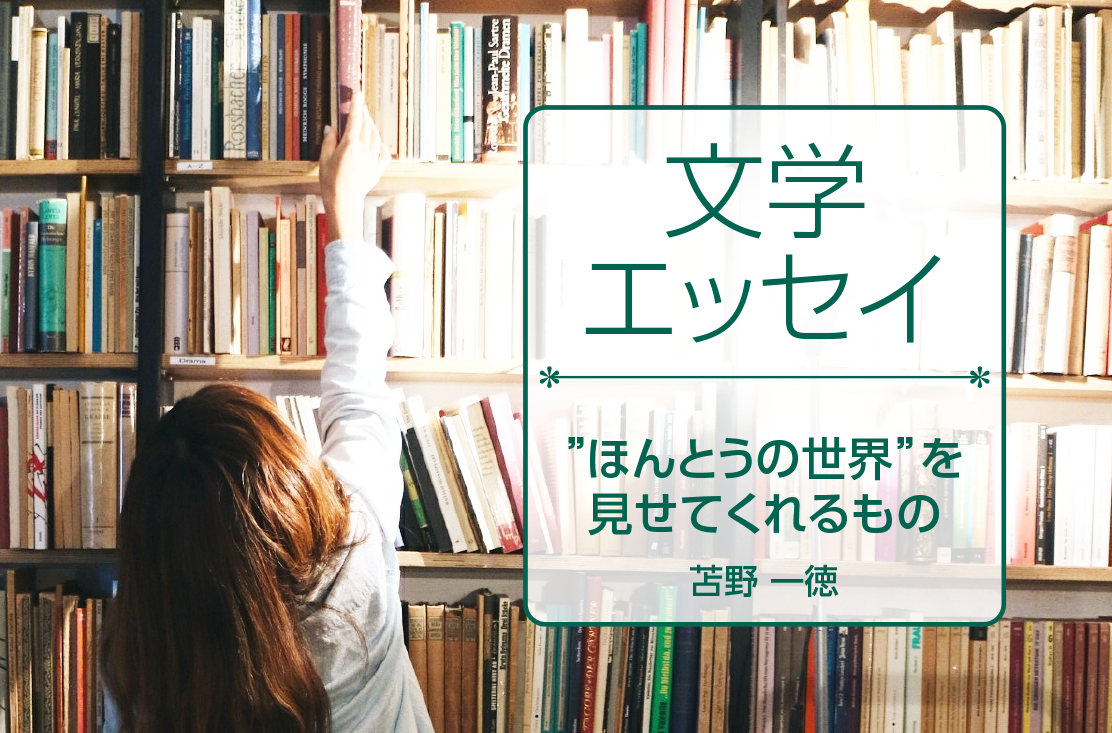
今となっては非常に恥ずかしい話なのですが、10代後半から20代半ば過ぎまで、わたしはずっと、小説家になることを夢見ていました。長編は10本ほど、短編や中編は、おそらく40本以上は書いたのではないかと思います。
実は小学生の頃の夢はマンガ家になることで、文学をモチーフにした作品も多い手塚治虫の影響から、シェイクスピアの『ハムレット』などをマンガ化したりもしていました。そうしてそのまま、10代初め頃から、文学作品に強い興味と憧れを抱くようになったのでした。
大学に入ってからは、とりわけ西洋文学に惹かれ、ゲーテを”神”と仰ぎ、『若きウェルテルの悩み』を常にポケットに携帯し(これもまた、青臭い恥ずかしい話です)、岩波文庫の赤帯はおそらくその大半を読みました。
文学の、いったい何がわたしを惹きつけたのか。今になって、わたしはその理由がよく分かります。
「芸術とは真理の生成であり生起である」とハイデガーは言っていますが(『芸術作品の根源』)、解釈次第では、これはきわめてすぐれた芸術の本質洞察です。本来であればいくつかの注釈を加えなければならないのですが、ひとまずここでは、このハイデガーの言葉を、「芸術とは、わたしたちにとっての”ほんとう”の”意味世界”を生起させるものである」という意味で捉え直しておくことにしたいと思います。
文学を含むあらゆる芸術は、わたしたちに「このような”ほんとうの世界”があったのか」と知らしめてくれるものなのです。そのような”意味”を、わたしたちのうちに生起させるものなのです。
美しい音楽に酔いしれる時、わたしたちは、「このような”ほんとうの世界”があったのか」と思わずにはいられません。すぐれた文学においてわたしたちが感じ取るのは、わたしたちの人生においてありうべき、あるいはあれかしと願う、ある”ほんとうの世界”にほかなりません。
もちろん、文学が描き出すのは何も美しい世界ばかりではありません。『罪と罰』でドストエフスキーが描いたのは、まさに罪と罰の”ほんとうの世界”です。主人公が犯した罪、そのために彼が味わうことになった罰。作家が読者の前に描いてみせたのは、これこそが人間的な罪と罰の”ほんとう”であるとわたしたちに迫る——一言で言うならば、それはわたしたちが二度と取り戻すことのできない関係性の断絶です——”ほんとうの世界”そのものなのです。
逆に言えば、そのような”ほんとうの世界”を開示しないものを、わたしたちが文学や芸術の名で呼ぶことはありません。単なる技巧、単なる心地よさ、単なる模倣作品、お決まりの感動……そうしたものを、わたしたちが芸術(としての文学)と呼ぶことはないのです。
もちろん、どのような作品を芸術・文学と呼ぶかは、特権的な誰かによって決められるものではありません。それは人びとの自由な批評を通して、時に長い時間をかけて合意されていくものです。しかしいずれにしても、わたしたちは、ある作品を芸術だと確信する時、そこに”ほんとうの世界”という意味の生成を必ず感じ取っているのです。
とりわけ若者にとって、このような”ほんとうの世界”は、時にえも言われぬ力でその心をとらえるものです。その理由は明らかで、多くの若者は、特に何らかの満たされなさや挫折を味わったことのある若者たちは、だからこそ、その胸のうちに、ありうべき、あるいはあれかしと願う何らかの”ほんとうの世界”を夢見ているからです。そしてある時、そんな”ほんとうの世界”が、文学作品の中に広がっていることを知るのです。
それは決して、ただの現実逃避であるわけではありません。むしろ文学は、いささか逆説的ではありますが、その虚構の中の圧倒的なリアリティによって、この世界には”ほんとうの世界”が確かにありうることを知らしめてくれるものなのです。
誰もが文学を必要とするわけではないし、誰もがそのような作品に出会わなければならないわけでもありません。でもわたしは、多くの若い人たちに、そのような出会いに恵まれる幸福をぜひ味わってもらいたいなと思っています。文学との出会いは、わたしたちに、わたしたちは「ただ生きる」のではなく、”ほんとう”を求め、それに「憧れつつ生きる」ことの喜びを与えてくれるはずだからです。
『国語教室』第112号より転載
著者プロフィール
苫野 一徳(とまの いっとく)
熊本大学准教授。専門は哲学・教育学。著書に、『「自由」はいかに可能か――社会構想のための哲学』『どのような教育が「よい」教育か』『愛』など多数。

詳しくはこちら
一覧に戻る