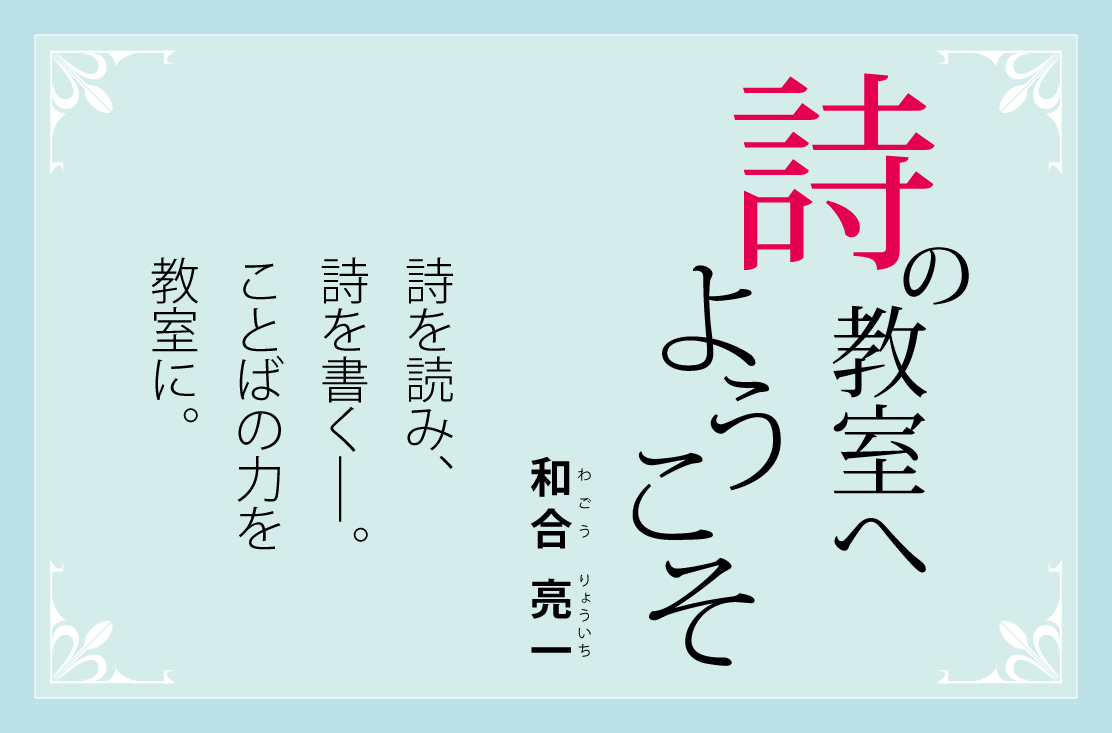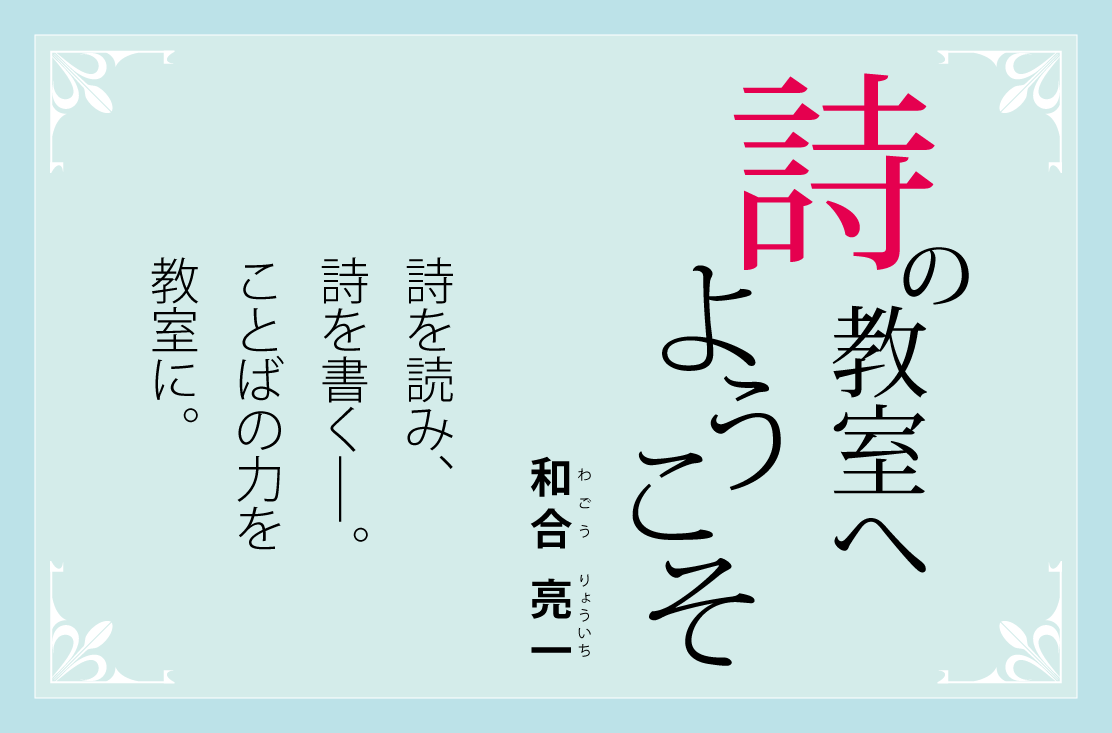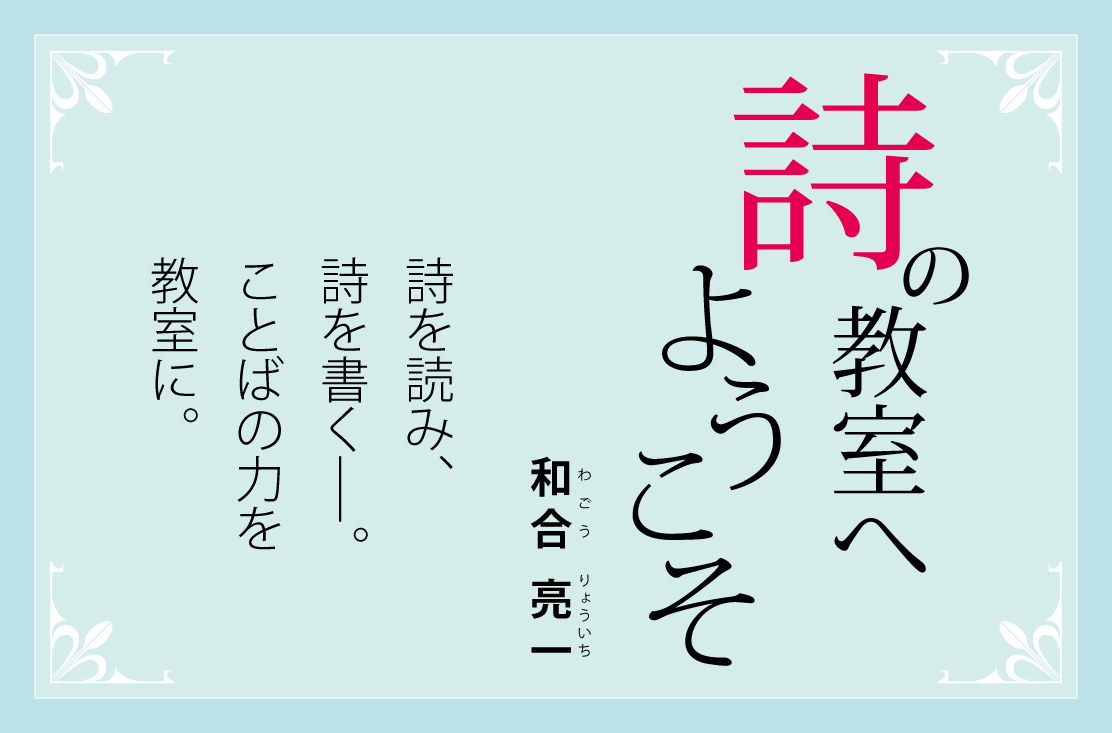詩の教室へようこそ
第1回 「ほんとうのうた」の扉へ
和合亮一
- 2020.11.30
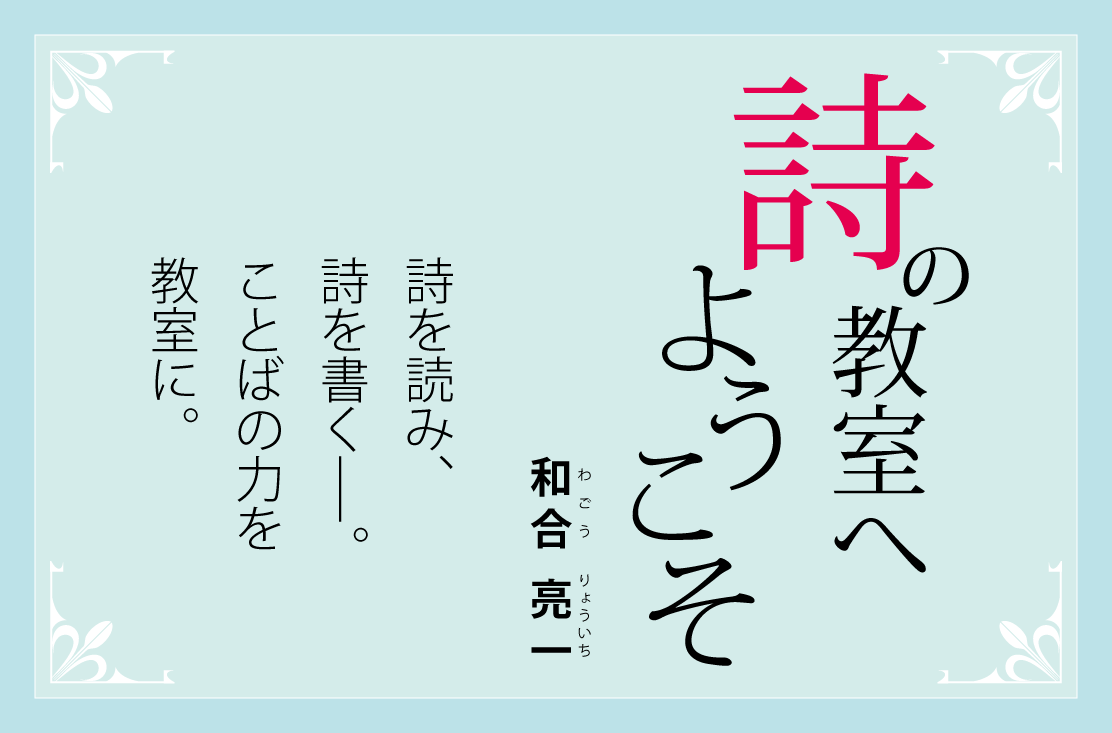
◆時空間の発見のよろこび
よし。今日は朝の4時に起きることが出来ました。これで出勤まで、およそ2時間ぐらいは机に向かうことが出来ます。もちろん、いつも上手くいくわけではありません。
元々は学生時代から典型的な夜型人間でした。しかし現在は午後10時には寝床に入り、午前4時過ぎに起床するというのが、自分にとって最も良い形となっています。もはや正反対の暮らしをしています。
連載の冒頭から何の話かと思われているかもしれません。早朝の時間に詩を読んだり書いたりすることの楽しさや自由を感じてきたことをまずは伝えたいだけなのです。夜明け前の感覚。言わば起きがけの半覚醒のような状態とこれから日常を送ろうとする意識とが交わる時空間にて、最も心の中に言葉が湧き出してくる気がするのです。その時をぜひとらえたいといつも思っています。
そもそも詩とは多かれ少なかれ、時空間の発見そのものに満ちている文学であると言えるのではないかと思います。例えばそれは、
宇宙はどんどん膨らんでゆく
それ故みんなは不安である
二十億光年の孤独に
僕は思わずくしゃみをした
という谷川俊太郎の代表詩の一つの詩句においても、独特の宇宙への感覚が宿っていることがとても伝わってきます。
ちなみにこの詩は出発作の一つですが、青年期独特の憂鬱や孤独感と、ユーモアの隠し味とが混ざっているスケールの大きな一篇です。数々の彼のその後の作品世界をスタート地点から占っているかに見えてきます。本人とお会いして雑談した折にこの詩に触れながら「今は宇宙の年齢は20億光年ではなくて、138億光年と判明しているから、いつか書き直さなくちゃいけないのかもね」といたずらっぽく笑っていたことを良く思い出します。こんなふとした一言からも、はるかなる彼方の時と空間への深遠なる眼差しのようなものが感じられますね。
例えば学校生活においては時間割が絶対に欠かせないものであるように、私たちは社会という名のもとにタイムスケジュール通りに行動することが求められ、それに従って生きています。しかし感性や感覚というものは、何にも縛られずに育っていきたいものなのです。正に「どんどん膨らんでゆく」。そして心の姿は決して横並びではありません。
だからこそ詩を分かち合うことの面白さとは、そこに託されているそれぞれの気持ちや感性・感覚の自由を共に味わうことにあると思います。それを真ん中に置いて、人生や社会、生きることの意味を感じて、考えていくこと。そこに新しい発見と感動が必ずあります。
まずこれは国語教師としての自分の指導の日々を振り返ってみての感慨ですが、現在の国語教育の現場において、残念ながらそうした機会がいささか足りないように思います。詩を書き、読むことを愛する者として、同じ時代を生きて共鳴し合うことのかけがえのなさを、もっと知りたいと願っています。
◆震災の体験から生まれた詩
ここで震災の年の直後に書かれた詩を少しだけ紹介したいと思います。当時小学校五年生の菊田心くんの書いた「ありがとう」という作品です。
文房具ありがとう
えんぴつ、分度き、コンパス大切にします。
花のなえありがとう
お母さんとはちに植えました。
花が咲くのが楽しみです。
うちわありがとう
あつい時うちわであおいでいます。
津波の被害を受けてしまい、しばらく気仙沼の避難所にいた彼が、生まれて初めて書いた詩です。
応援の言葉ありがとう
心が元気になりました。
たくさんの支援について感謝の気持ちを伝えたいと思い、素直な気持ちを綴りました。そして最後にこのようにまとめています。
最後に
おじいちゃん見つけてくれてありがとう
さよならすることができました。
涙を禁じえませんでした。最後の「ありがとう」が、他とは全く違うものとして心に強く響いてくるのが感じられました。そこに祖父と自分との歳月の重みが託されているのが良く分かりました。波にさらわれてしまった祖父との死別の悲しみや寂しさと共に、それを乗り越えて生きていこうとする菊田君の成長が見えた気がしました。
時が経って、このような作品とも出会いました。
海の音 聞こえる心に 変化あり
津波の大きな被害のあった福島県の海沿いに暮らしている、当時は小学生であり、現在は中学校に通っている女子生徒の一句です。震災から5年ほど経った頃のある日に書かれた心の呟きのような言葉に触れて、やはり気持ちの変化と成長とが見えた気がしました。
津波を経験したばかりの子どもの耳には、たとえそれがその後の海辺の静かな凪であったとしても、ひどく恐ろしい「海の音」として届いていたに違いありません。しかし歳月を経て、変わることのない同じ波の音であるのに、どこか違って聞こえ始めていることがうかがえました。
たとえほんのわずかな「ありがとう」や「変化あり」の一言であったとしても、その背後に震災という大きな何かが抱えられている時、言葉を超えて迫ってくるものがあることを教えられました。
◆人生の今を深く見つめて
最近に出会ったばかりの素敵な作品も紹介したいと思います。「時速100㎞」という、宮城県の中学生の大久保観さんの詩です。二連構成の短い詩。一連目はこのように書かれています。
夜のハイウェイ
繰り返す群青の山々とテールランプ
戦後を伝えるカーラジオ
ミラーに映える小さなオレンジ花火
はじける夏の寂しさと危うさ
家族と向かう
故郷が迎える
夏と夏がすれ違う
東北道下り線
とてもテンポが良いのは、体言止めが多用されているからだと思います。帰省の時。心地よいスピード感。夏の盛り。二連目はこんなふうにまとめられています。
朝のハイウェイ
通り過ぎる風と雲
ラジオからは甲子園準決勝
祖母手作りの葡萄ジュース
青くさい夏の甘さとほろ苦さ
思い出と思いを一杯に詰め込んで
夏と秋がすれ違う
東北道上り線
これは帰り道。一連目の「夜」という出だしに対して「朝」からの始まりだったり、暗闇の「テールランプ」に対して眩しい朝方の「風と雲」だったり、「下り」ではなく「上り」であったり、様々に対位法が用いられていて、読む側にくっきりとした印象を与えています。
一連目の「夏と夏とがすれ違う」。なるほど。行き交う車を季節に見立てているのがユニークです。二連目ではそれが「夏と秋」に変わっていく。歳月の移り変わりがきちんと受け止められています。季節の変わり目を見つめる気持ちの新鮮さが、ハイウェイを行く速度の中に小気味良く感じ取ることが出来るかのようです。
看過してしまうかのような心の動きや変化をすれ違う車や移動する風景へと重ねています。読み終えると夏の終わりの切なさと共に若い筆者の成長感覚にふと包まれて、やがて静かに満たされていくような気がします。書いた人の日々や年月がそこに映し出されていく。その時にしか感じられない呼吸の真実が見えてくる。
詩を書くことを勧めることは、人生の今を深く見つめるまなざしを分かち合うことにつながるのではないでしょうか。作品の良し悪しなどは二の次、三の次にして、まずは生徒たちと楽しんでみてはいかがでしょう。出来上がった詩を真ん中に置いて、人生や暮らしについて語り合うことを大事にしていくような、コミュニケーションの機会をおススメしたいのです。
授業中に取り組ませてみたものでも文芸部やサークルなどで創作を促してみた作品でも、または見つけてしまったふとノートの片隅に書かれた短いフレーズでもいいと思います。生徒さんたちからの詩の投稿を本欄にて呼びかけてみたい。そして短い紙幅ですが、ぜひいくつか紹介したいと考えています。詩となると敷居が高いというのであれば、言葉の塊のようなもので可、というぐらいでまずはどうでしょうか。
◆「ほんとうのうた」を探しに
最近、ブッシュ孝子さんの詩集『暗やみの中で一人枕をぬらす夜は』(新泉社)と出会いました。この本は、若くして病を患ってしまい、その闘病中にドイツ人青年と結婚した日本人の女性が、命を終えるまでのおよそ五カ月の短い間に、一冊のノートに初めて綴った詩の言葉を日付順に並べて構成したものです。
28歳の短い生涯でした。迫りくる死への予感を抱きながらも、生きることの全ての意味を言葉へと刻むようにして、92篇の詩を残してやがてこの世を去りました。
最初の9月9日にはこんなふうに記されてあります。
美しい言葉が次々と浮かび出て
眠れぬ夜がある
新しい詩が次々と生れでて
眠れぬ夜がある
死を前にしながらも「次々と」という詩作への目覚めを新しく得ている場面に心打たれました。
9月13日にはこんなふうに書いています。
私は信じる
私にも詩がかけるのだと
誰が何といおうと
これは私のほんとうのうた
これは私の魂のうた
生徒たち、そして私たちにとっての「ほんとうのうた」。それをみなさんと共にこの欄で探してみたいと思っています。詩とは言葉と心さえあれば誰にでも開かれている扉なのです。
『国語教室』第114号より転載
筆者プロフィール
福島県立本宮高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。
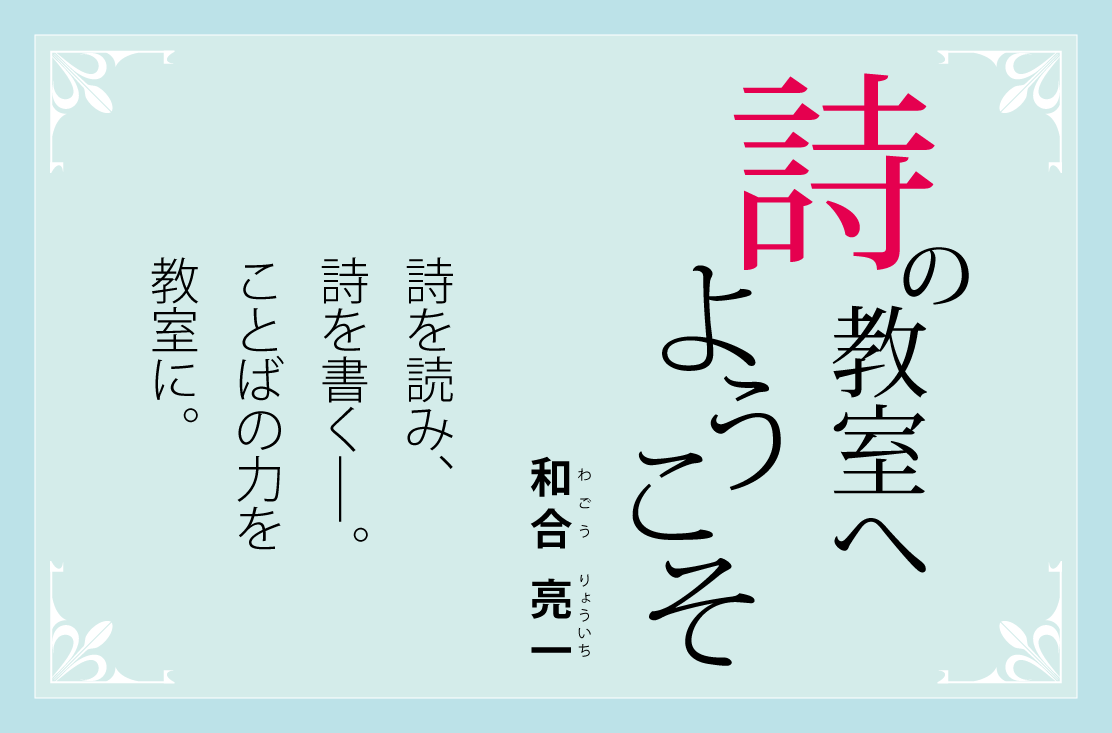
詳しくはこちら
一覧に戻る