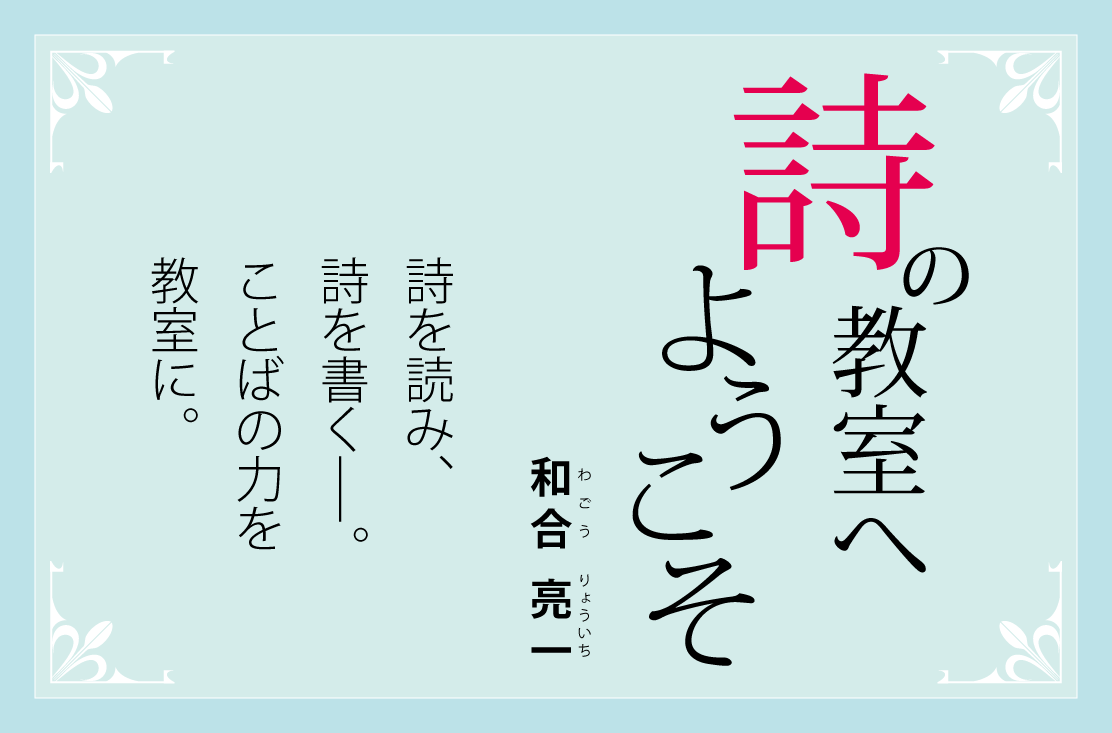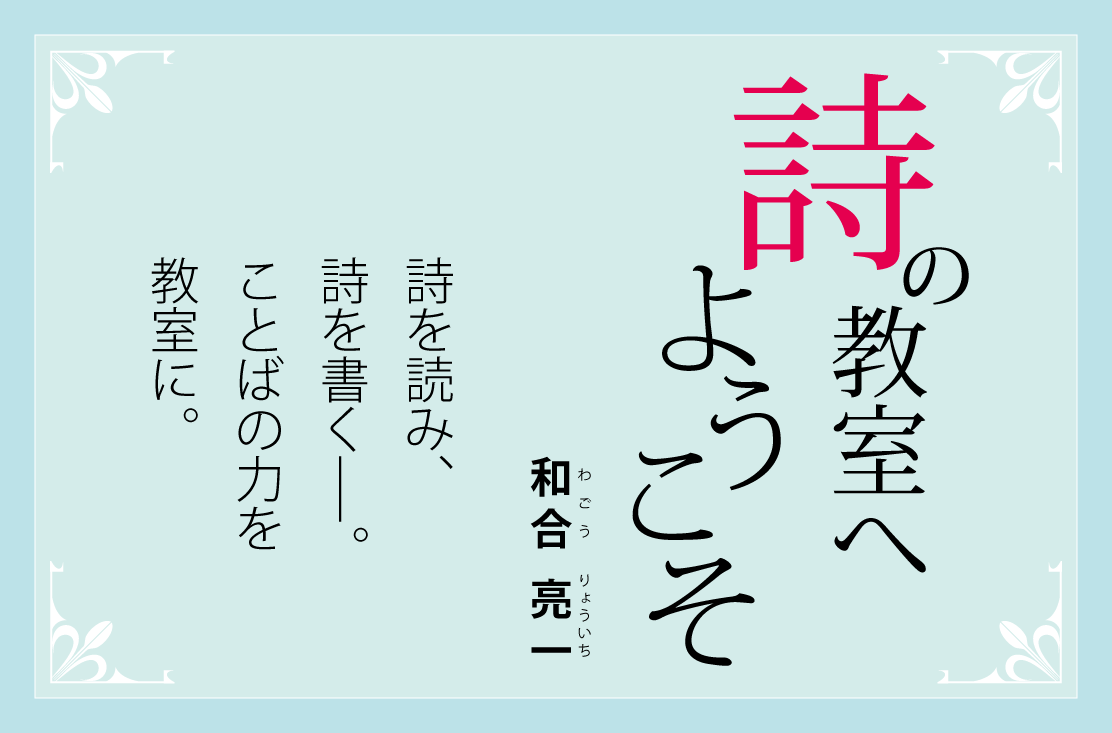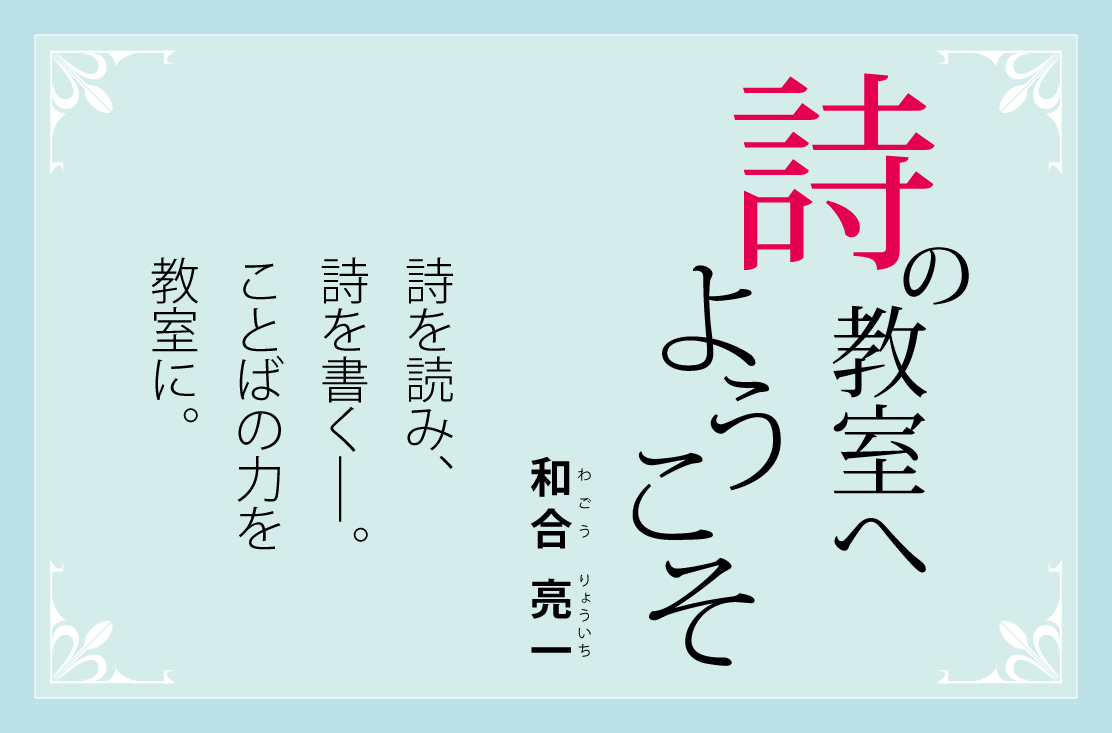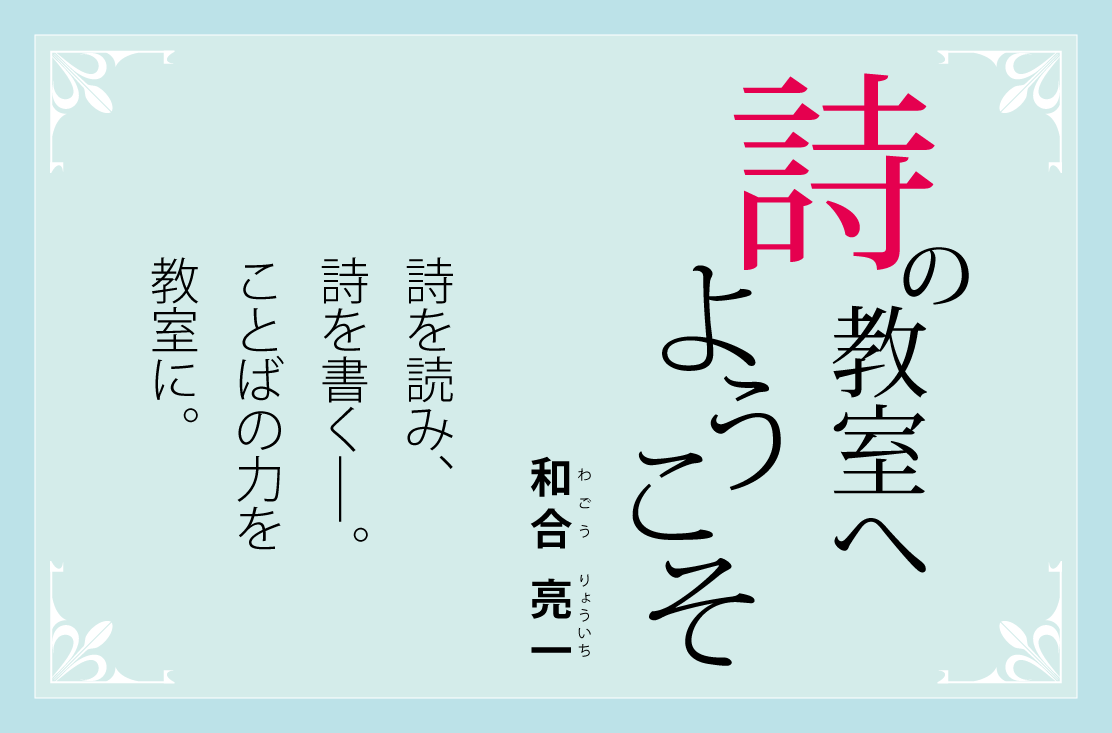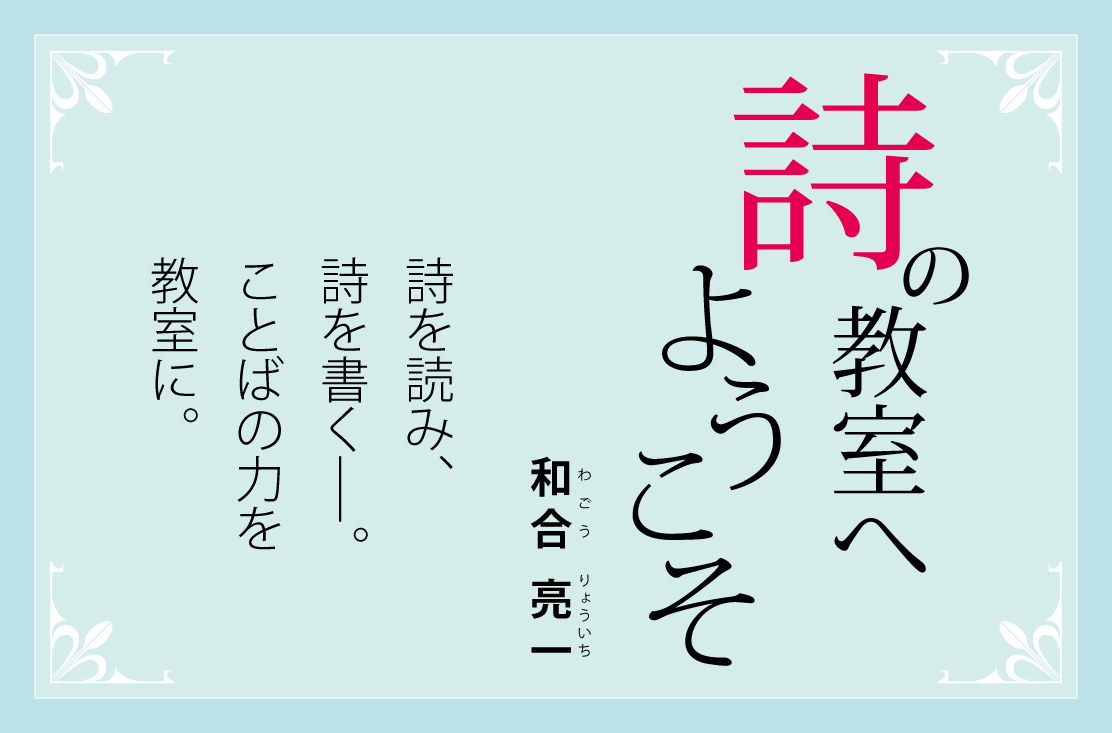詩の教室へようこそ
第7回 種まく人よ
和合亮一
- 2023.10.31
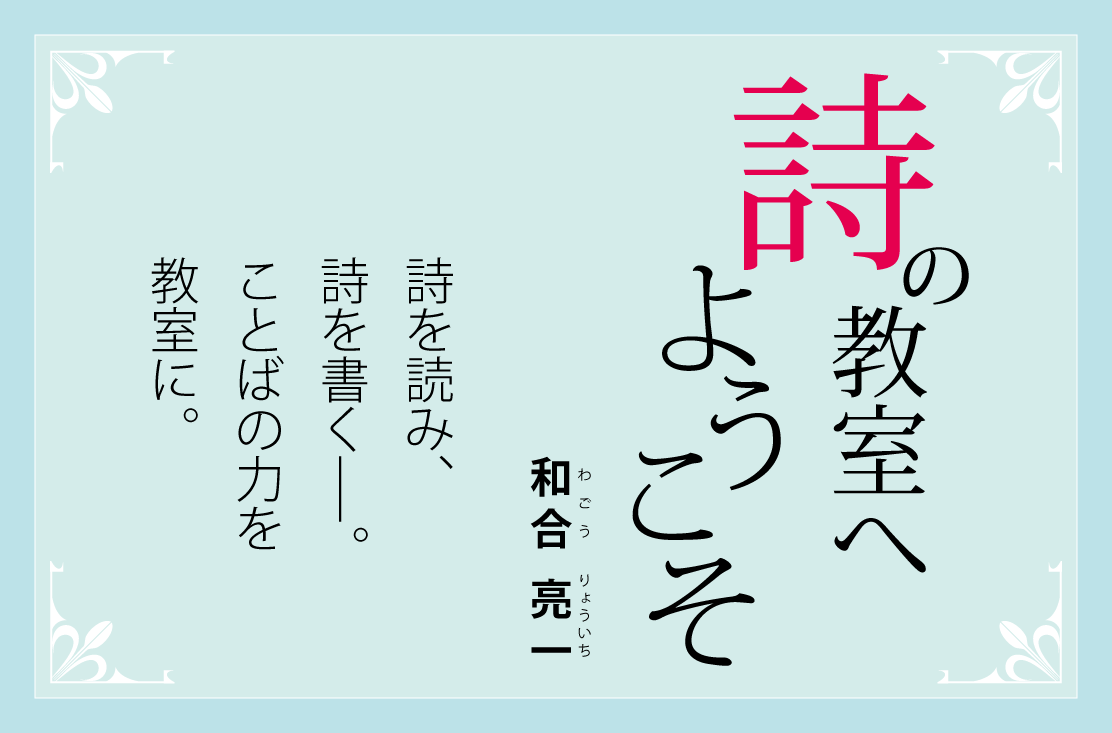
◆日本語の音楽性
詩を書き続けてきて、さまざまな出会いをいただく機会が多いことを、とても幸運に思っています。今回は、私なりの音楽との出会いについてお話をさせていただきます。
そもそも私は幼い頃から音楽を聴くのが大好きでした。いつしかそれに関わり続けるような人生を送りたいと思うようになりました。しかし、ただ単に好きなだけであり、音楽の素養や経験は全くなく過ごしてまいりました。例えば、ギターでもピアノでもドラムでもできれば、と何度も思ってきましたし、実際に楽器の練習を試みたこともありました。しかし、いつしか断念してしまいました。
そのような時に、萩原朔太郎の次の言葉に出会ったのです。「詩は何より音楽でなければならない」。朔太郎は音楽をこよなく愛し、マンドリンという楽器を好んで演奏していたことでもよく知られています。ならば私も偉大な詩人の真似をして、さっそくマンドリンでも…。いや断念してからはその気は起きませんでしたが、その後に自然と詩を書くことに心が向かっていったのも、やはり日本語が本来もっている、音楽性に心惹かれたからにほかなりません。
日本人は古来から、いわゆる定型のもたらす音韻とリズムに親しんで、朗詠してきたという歴史を有しています。このことからも、日本語の音楽性の存在ははっきりしていると言えるでしょう。
時折、授業で百人一首大会をやります。私が読み手となり、自己流に読み上げて、生徒たちと夢中になるという時間が流れます。ずっと声に出していくうちに、名歌がもっている音楽性というものに、うっとりとしている自分に気づかされます。日本語と音楽性とは親密なつながりをもっているのだと、声に出しながら実感いたします。
◆言葉のスケッチ
詩を書き続けていくうちに、校歌や合唱曲、市歌などの作詞の機会をいただくようになりました。それは初めからうまくいったというものではありません。私の詩集をお読みくださっていた作曲家の新実徳英先生にアドバイスをいただきながら、少しずつ作詞の方法を身につけていきました。かれこれ20年ほど歌詞を作り続けておりますが、書くほどに奥の深さを感じます。
昨年に書かせていただきました、福島県立会津農林高等学校の校歌を、少しだけご紹介いたします。
種まく人よ
野へ 空へ
ハミングたかく
かがやく林
いのちを育て
星をみあげて
水のささやき
みちびく雲に
歌おう 友と
いちめんの花
まなざしに風
会津のありか
夜明けに
のぞむ
光の人に
種まく人に
校歌の一番を紹介させていただきました。それぞれ歴史のある、福島県立会津農林高校と福島県立耶麻農業高校が統合して、新生高校のスタートとなりました。
校歌を作る際は、まずは取材を重ねることにしています。校舎やグラウンド、そして生徒たちの登校の経路の風景や、近くにある公園などを歩きます。言葉のスケッチのようなものです。先生方や生徒たち、地元の商店街の方々にもお話をうかがいます。そうしているうちに、ヒントのようなものが必ず見えてきます。自宅に戻り、ノートに思いつく言葉を書き出してみます。
とにかく自由に、歌になりそうなフレーズが見えてくるまで、並べていきます。撮ってきた写真を見直したり、場合によっては、うかがったお話を録音したものを聞き直してみたりもします。
◆時間の波を超えていく強さ
ここで少し、私なりのコツのようなものを述べますと、まずは時折声に出してみて、気持ちのよい単語やフレーズを探ってみます。「気持ちのよい」と述べましたが、簡単に言えば声に出しやすい、響きのよさをもっているものと言えば、よろしいでしょうか。なかなか説明しにくいのですが、自作の詩を朗読をするという活動をずっとやってきているので、自分が声にしてみたいという言葉を見つけるのが、苦にならないところがあります。
そして、それらを3・5・7の奇数の音に、あてはめてみます。このほうが、歌いやすく、覚えやすい印象があり、校歌や市歌などの公の歌にはふさわしい感じがあります。あくまでも体験談に過ぎませんが、こうした目安のようなものがあると、まとめやすいのは事実です。
特に校歌は数十年、歌われ続けていきます。作詞者として、長い歳月を越えていって、ずっと愛され続けてほしいという思いを込めています。和歌・短歌や俳句の定型の音韻とリズムを、日本人が千数百年近くも愛し続けていることからもわかるように、そうした時間の波を越えていく強さが奇数の音という器に宿っているように、長年書き続けてきて思います。
◆言葉のアンテナを立てて
私は短歌や俳句が好きで、時折短歌を作ることもありますが、その経験が生きているようです。言葉の素描をしているうちに、作品の基調を成すフレーズを探していることを意識するようになります。
例えば、ある歌を思い出す折には、必ず印象深いものを口ずさむと思いますが、そうしたものを与える、作品の柱となるような一行。これはなかなか見つからないものですし、それが定まると、磁石に引かれるように書き出した言葉たちが不思議とそこに集まっていき、書こうとしている歌の景色がさっと見えてくるような気がします。
先ほどの校歌の柱のフレーズは「種まく人よ」です。まず、会津農林高等学校の校舎や農場を巡った折に、農業実習をしている生徒たちの熱心な姿が思い浮かびました。私は初任地が南相馬市にある福島県立相馬農業高校でしたので、生徒たちの顔を思い浮かべたりして、何だかとても懐かしくなりました。
そして、その数日後に、たまたまなのですが、あのフランスの画家のミレーの名画「種をまく人」と、山梨県立美術館で出会いました。明け方の情景のほの暗い画布の真ん中で、種をまいている印象的な姿が描かれていました。
それを見つめた瞬間に浮かんだのが「種まく人よ」という呼びかけでした。名画の力ももちろんありますが、言葉のスケッチをしているうちに心にアンテナが立って、絵を見た瞬間に大きく反応したのだと思います。目に入った瞬間に大いなるひらめきが生まれ、新しい歌への目覚めを授けていただいたような気がいたしました。
作詞に定石はありません。ほとんど偶然の産物であるインスピレーションを確実に呼び込むことはとても難しいことです。しかし、ある程度、それを待つための準備はできると思います。書き方は幾通りもありますが、こんなふうに取材した言葉をあたかも種をまくようにメモ帳の中にまいておくと、自然と口ずさみたくなるフレーズが呟きのようになって生まれたり、出会ったりすることを何度も経験してきました。ここまで述べてきたように、音数を意識した言葉でアンテナを立てている状態こそが、柱のフレーズと出会う確率を高めていきます。
◆後戻りをしないように
合唱曲の作詞について、お話しさせていただきます。
楽譜を開けば
野原に風が吹く
はだしになり
足のうらの
音符を蹴って
歌う 鳥と光と
汗 ひとつぶ
見つけた
風の中に
真っ赤な風船
ほんとうは
風ではないのです
雲からの
ささやき
かなたまで
飛んでいけ
わたしたち
まるごとの
息吹き
(中略)
見上げよ
一番星だ
わたしと
きみだ
楽譜を開けば
野原に
風が吹く
これは、「楽譜を開けば野原に風が吹く」(作曲 信長貴富)の一部です。とても長いタイトルだと思われたかもしれません。国内で歌われている合唱曲の中でも、珍しい長さのタイトルかもしれませんね。
校歌では3・5・7などの奇数の音数で言葉を選んでいると述べましたが、合唱曲はそうした枠から出た、もっと自由なものとして考えます。
この曲は、合唱をする方々へのエールの意味を込めて作詞しました。楽譜と野原のイメージを重ね合わせてみて、歌い手が楽譜を開いて歌おうとする様子と、野原を自由奔放にかけめぐる姿とを重ねてみました。生き生きとした表情で合唱に取り組んでいる合唱部の生徒さんの姿を想像しながら、想いを歌に込めてみたつもりです。
私は十数年ほど前に、「しずおか連詩の会」というイベントに参加させていただいたことがあります。これは詩人の大岡信さんが提唱した、連歌や連句ならぬ、連詩の理念に基づいて、毎年、静岡で開催されているものです。そこでいくつかの連詩の決まりを学ばせていただきましたが、一つ印象的だったのは、イメージの後戻りをしない、というルールでした。
例えば、朝目覚めて、洗顔して着替えをして、玄関から外に出て、学校へと向かう、といったようなイメージがあったとします。ところが、目覚めてすぐに布団に潜ったり、一度着た服から別のものに着替えたり、玄関から出て忘れ物に気づいて一度戻ったり、といったことを日常ではいたします。しかし、連詩ではそのような後戻りをしない…ということだ、と。
何かしらアクションを起こしたら、それを後ろ向きに戻さないということを、大岡さんは決まりとして提唱されていたそうです。実際に、5人の詩人たちと2泊3日のスケジュールでずっと連詩を書き続けて、それをしないということが、生き生きとした何かを作品に与えることにつながると、実作の現場でわかりました。
わたしは合唱曲の作詞をたくさんさせていただき、言うなれば一人連詩のような気持ちで、後戻りをしないようにして書いている自分に、ふと気がついたことがありました。
それは歌い手のみなさんに、いつも生きる力を込めて、精一杯、元気に取り組んでいってほしいという願いが前提にあるからです。
サビの部分の「見あげよ/一番星だ/わたしと/きみだ」には、仲間との連携の想いを込めています。一つの星を一人で見あげるのではなく、歌う全員で見あげてほしい。
校歌も合唱曲も、みんなで口ずさむものです。その音楽活動に言葉の担当者として参加させていただきながら、音楽への憧れをこれからも宿し続けていきたいと願っています。
『国語教室』第120号より転載
プロフィール
和合亮一(わごう りょういち)
福島県立福島北高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。
一覧に戻る