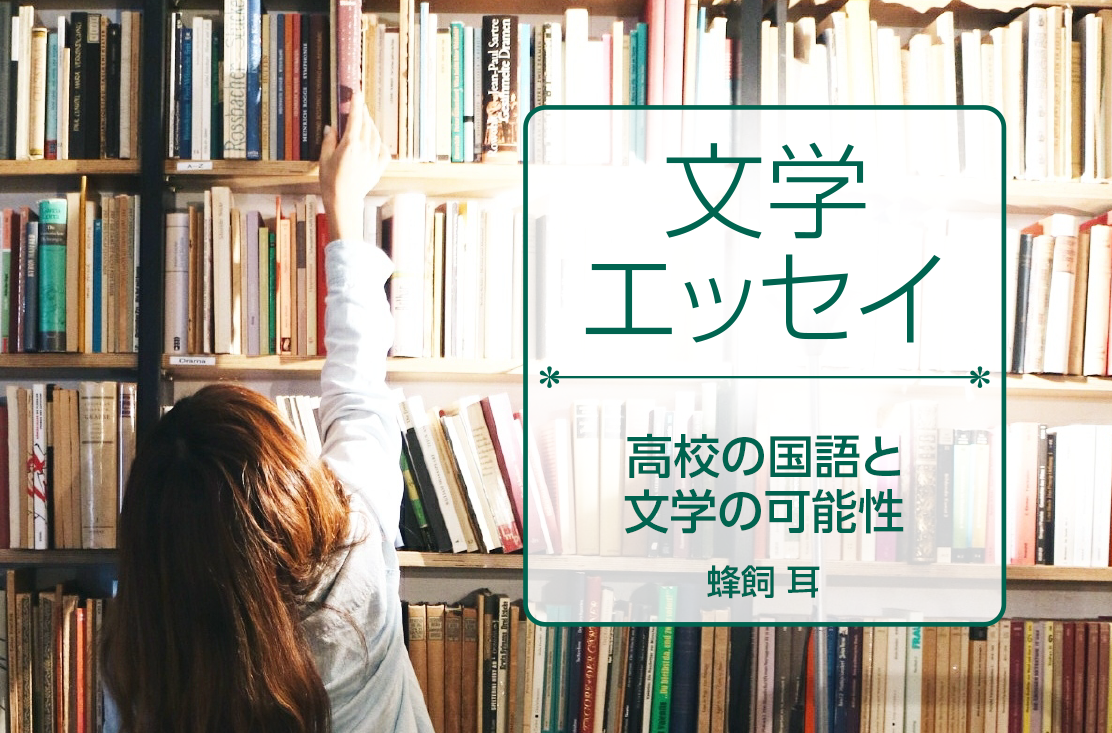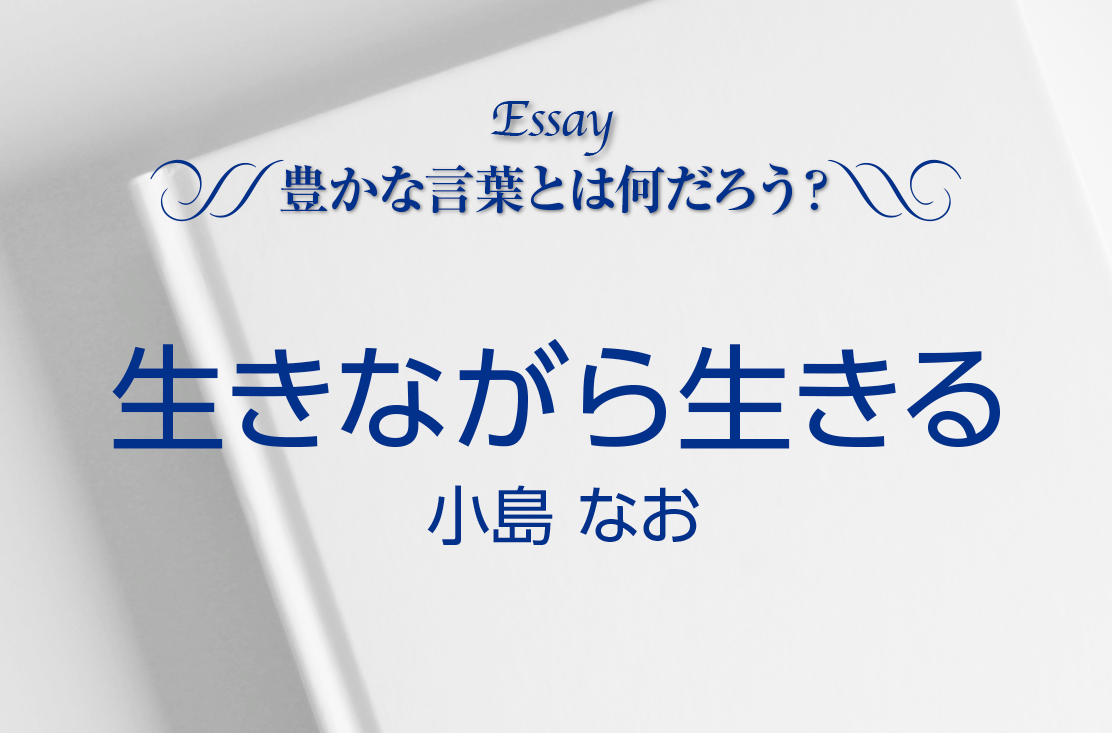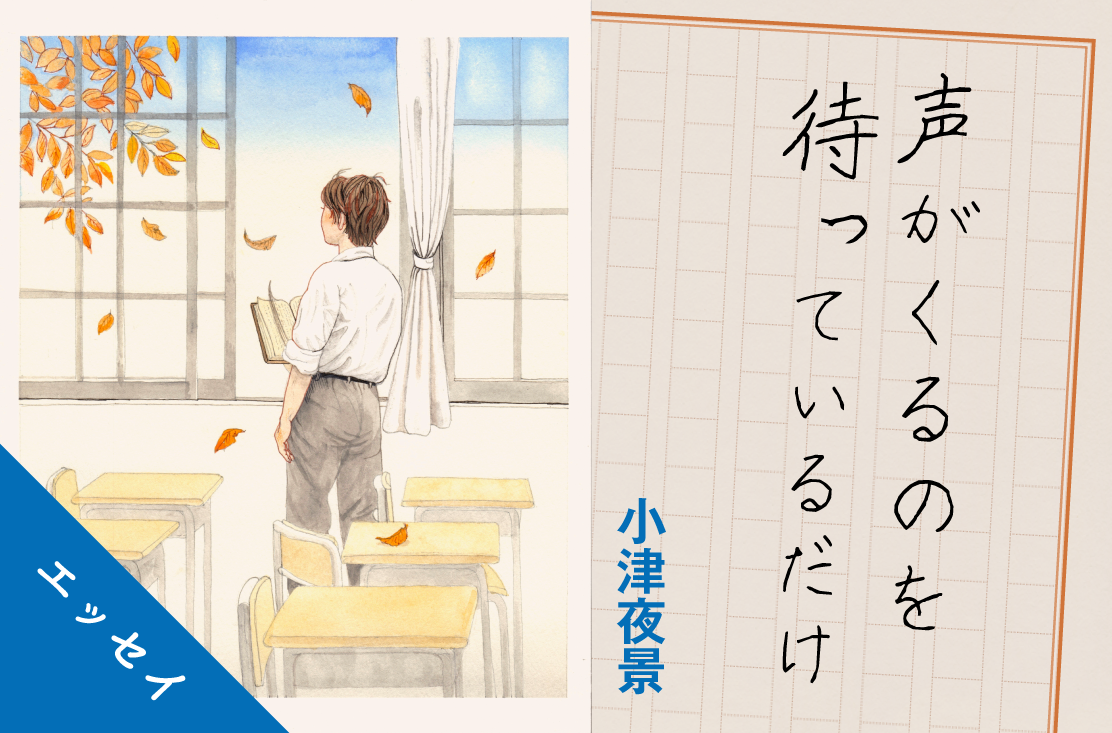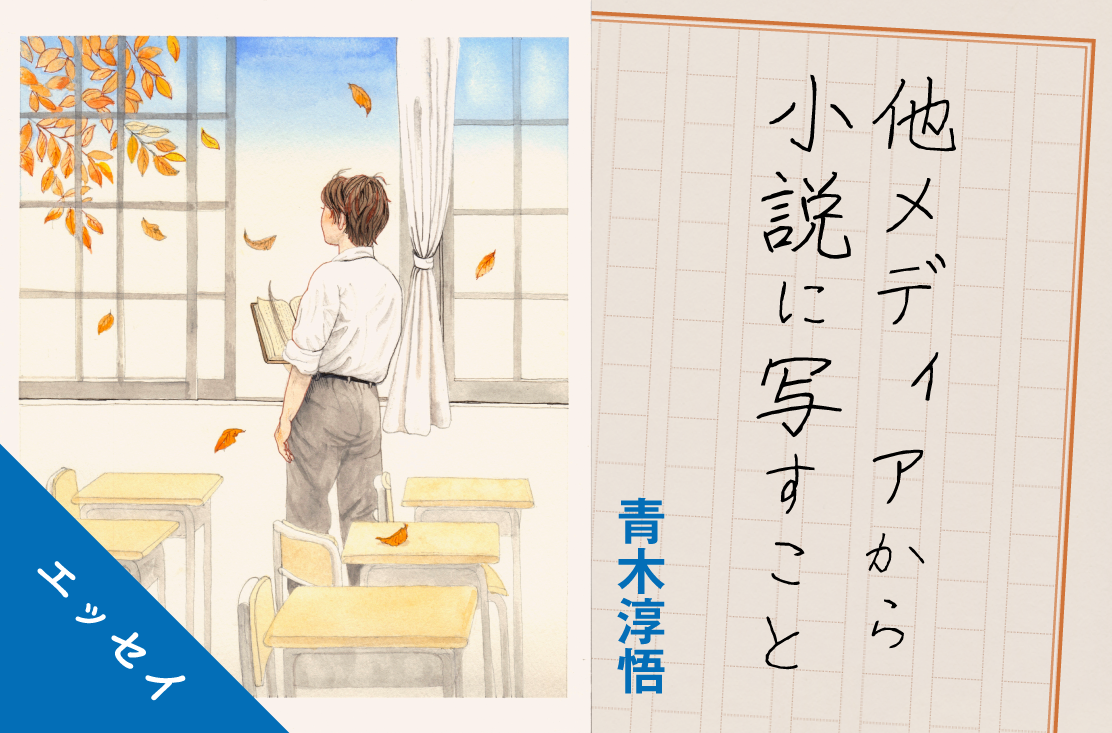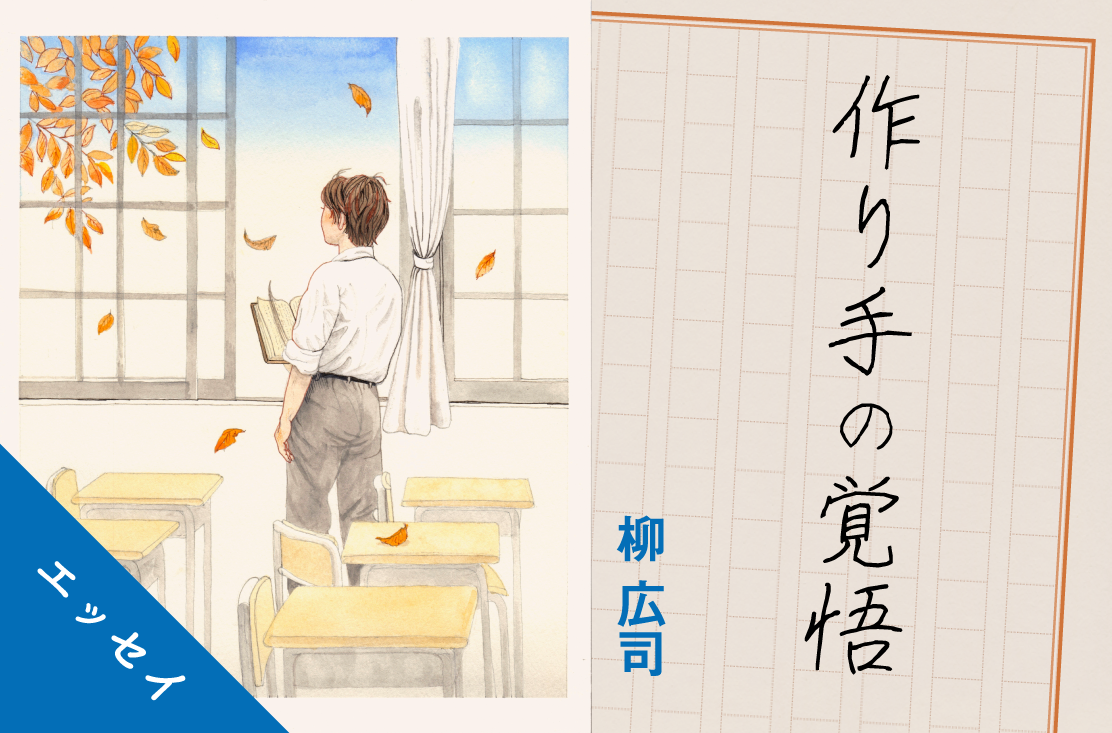Essay 豊かな言葉とは何だろう?
世界への入り口
温又柔
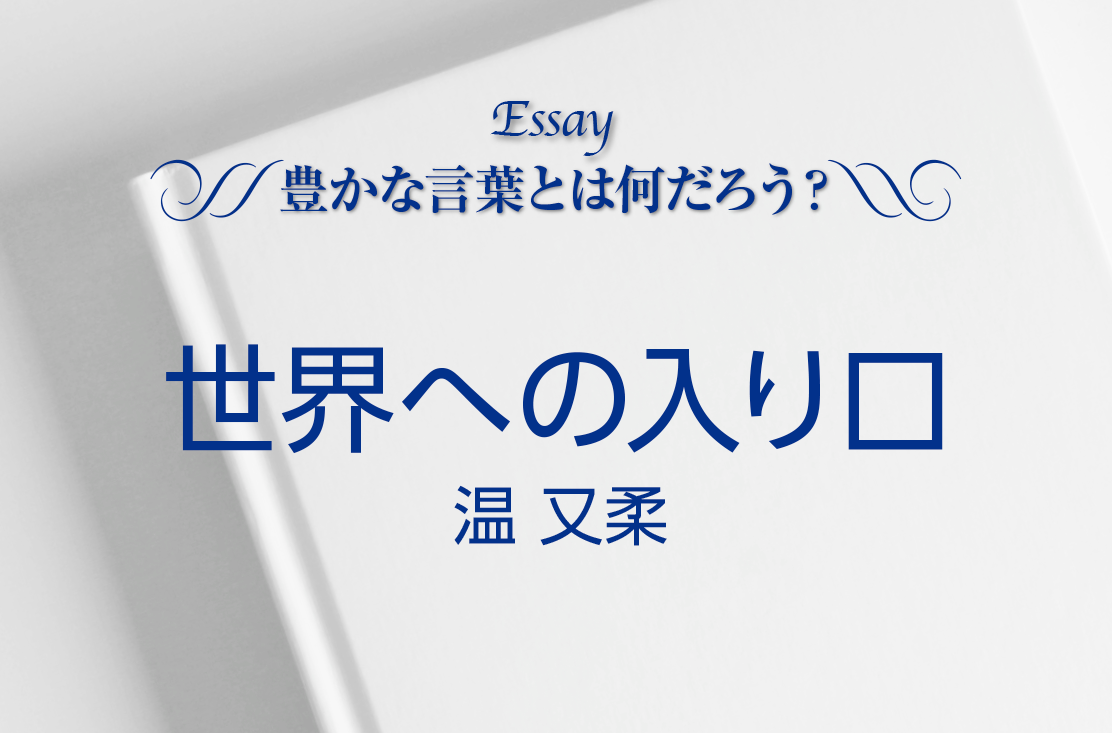
昔々、私のランドセルがぴかぴかだった頃、学校の勉強の中ではサンスウやリカやシャカイよりもゴクゴがいちばん大好きなの、と言ったことがあった。そんな私にむかって父が、ゴクゴではなくコクゴだよ、と教えてくれた。コ、と、ゴ、の音のちがいを幼い私が聞き分けられるように父は、コ・ク・ゴ、と何度か繰り返した。
あの頃の父は、私よりも日本語がじょうずだった。私の父は台湾出身だ。母もそうである。父の仕事の都合で一家揃って日本に来ることがなかったら、7歳の私は台湾の小学校に進学したことだろう。けれども私は日本の学校に通う小学生として、コクゴ、と出合った。
コクゴの時間に、ア、イ、ウ、エ、オ、という音は、あ、い、う、え、お、という形で示せるのだと知った。
あ(ア)からはじまり、ん(ン)で終わる50の文字を覚えると、私の世界は一気に広がった。本の中にも、言葉が溢れていると知ったのだ。「よかったね」「おいしい」「まって」……お気に入りの絵本を広げて、文字を一つずつ唱えると、それは皆、何かの言葉になる。本の中の言葉たちは、世界はとても広くて面白いのだと私に感じさせてくれる。それだけではない。私は自分でも文字を書くようになる。音でしかなかった自分の言葉が次々と文字になるのを楽しむ。
読むことと書くことをたくさん味わえるから、私はコクゴが好きだった。
両親は私がコクゴが好きであることを喜んだ。何しろ、コクゴができなければサンスウやリカやシャカイも、ちんぷんかんぷんだったはずだから。
コクゴは、すべての基本なのである。
それからものの数年もせずに、家族の中でいちばん日本語が得意なのは、父ではなく、私になった。
台湾に帰ると、この子はまるで日本人みたいだね、と可笑しがられた。ふだん私のまわりで日本語以外の言葉を話すのは父と母ぐらいなのに、台湾にいると、ほとんどの人たちは日本語を話せない。たくさんいる伯父や叔母。それにいとこたちも皆、中国語を喋っていた。私も台湾ではカタコトの中国語を喋った。
あるとき、従姉が私の持ち歩いていたノートを見せてほしいと言った。従姉のことが好きだったから、私は喜んでノートを広げて見せた。わあ日本語だ、と感嘆した従姉はよっぽど興味深いのか、ノートに刻まれた私の筆跡にじっと目を凝らす。それから、学校、という部分を指さすと、xué xiào(シュェ・シャォ)、と言った。私は笑った。ちがうよ、これはガッコウと読むの。すると従姉は、あなたにとってはガッコウだけど私たちにはxué xiào(シュェ・シャォ)だもん、と言ったのだ。
日本語ならガッコウ。中国語だとxué xiào(シュェ・シャォ)。
その後、私は時々、考えるようになった。私も、「学校」をガッコウではなくxué xiào(シュェ・シャォ)と読む私たちの一員だったのかもしれない、と。そう、日本ではなく台湾で育っていたのなら、きっと私も。
学校の勉強ではゴクゴがいちばん好きなの、と言っていた自分の声がよみがえる。国語は正しくは、コクゴ、と読む。でも中国語だと、guó yǔ(グゥォ・ユー)になる。
コクゴ、と、guó yǔ(グゥォ・ユー)。
日本語と中国語がまざりあう世界で生きていた私は、ひらがなを覚えることで、本の中にも言葉が溢れているのだと知った。今もあの興奮を覚えている。ちっぽけな自分の、狭い世界にいるのが息苦しくなったら、いつも本を開いた。本をめくれば、たくさんの言葉たちが、私に読まれるのを待っている(と信じている)。本の中にはいつも、私がまだ知らない途方もなく豊かな、本の外の世界が広がっている。
guó yǔ(グゥォ・ユー)ではなく、コクゴの時間に文字の読み書きを習得した私の世界への入り口は、今も日本語だ。たぶん、今、これを読んでくれているあなたと同じように。
『国語教室』第114号より転載
著者プロフィール
小説家。台北市生まれ。著書に、『台湾生まれ 日本語育ち』『真ん中の子どもたち』『空港時光』『「国語」から旅立って』など。最新刊は『魯肉飯のさえずり』。
一覧に戻る