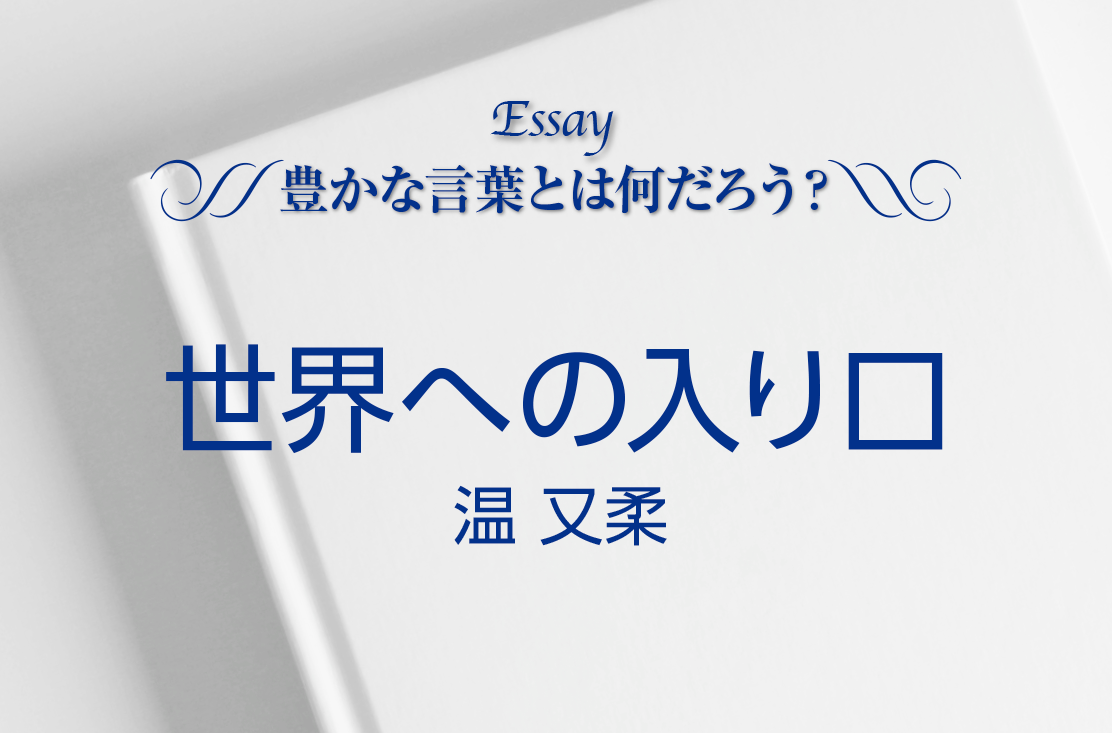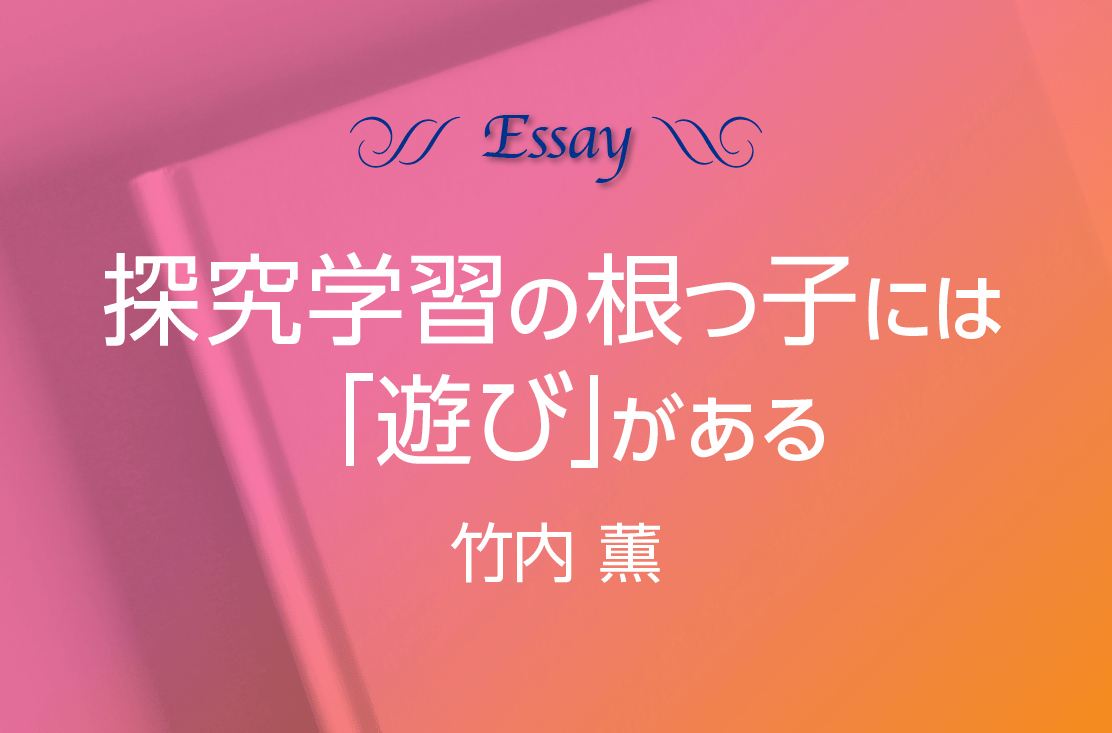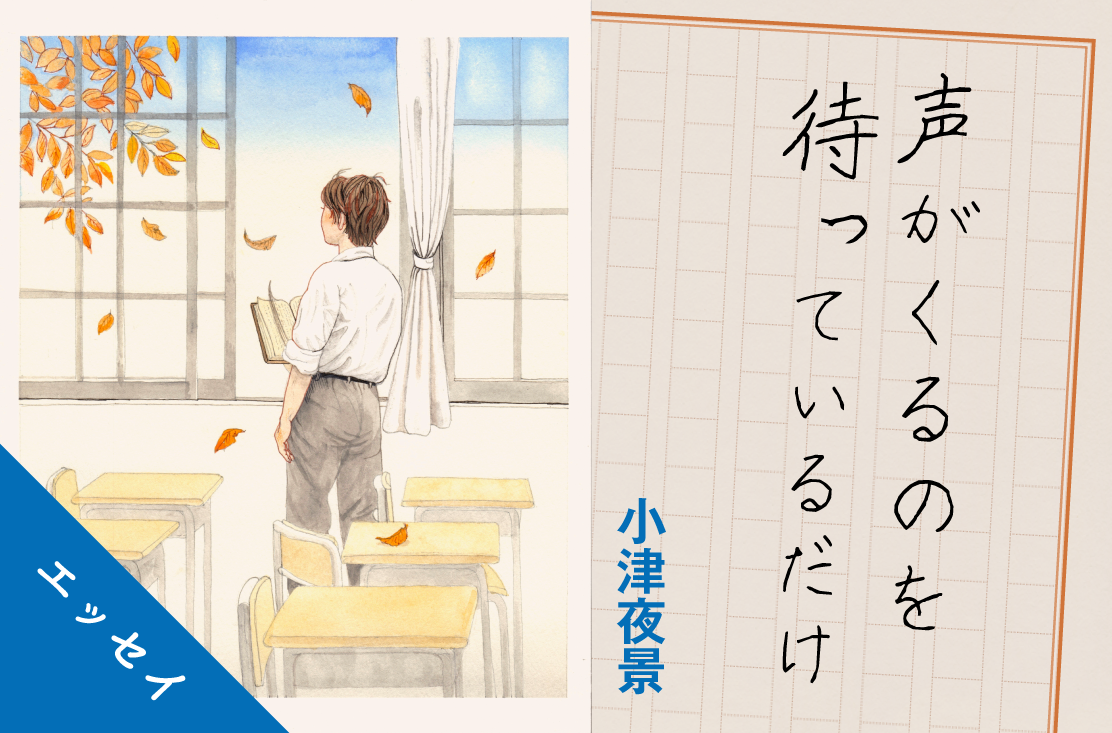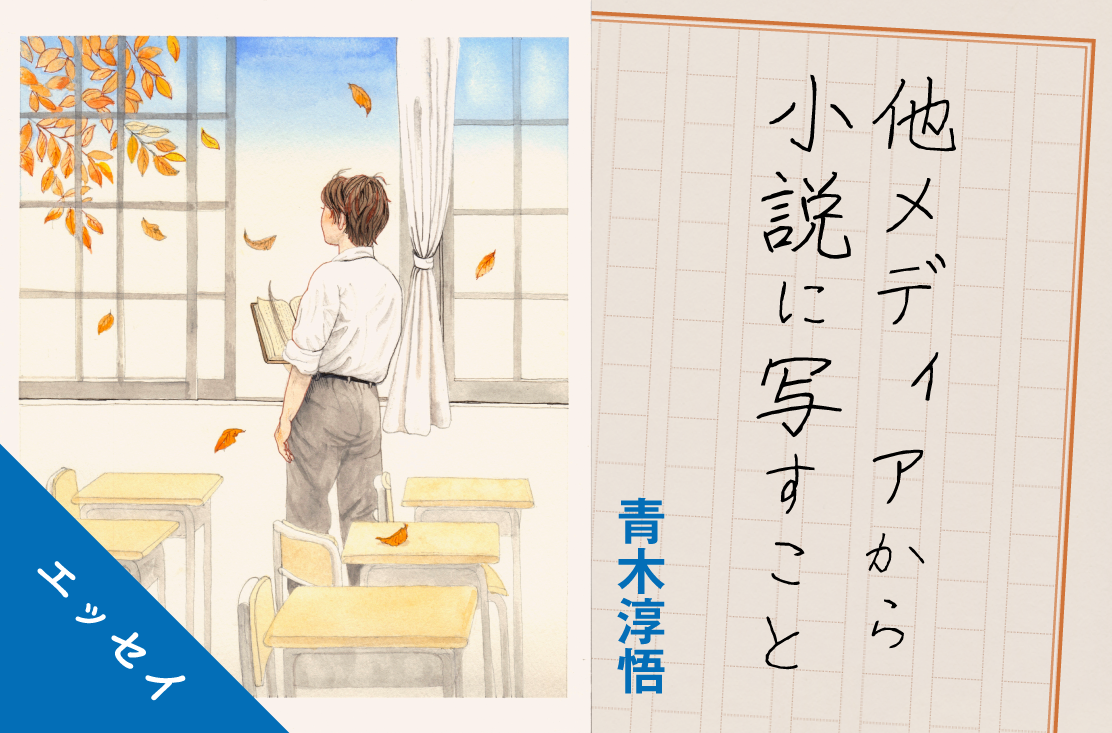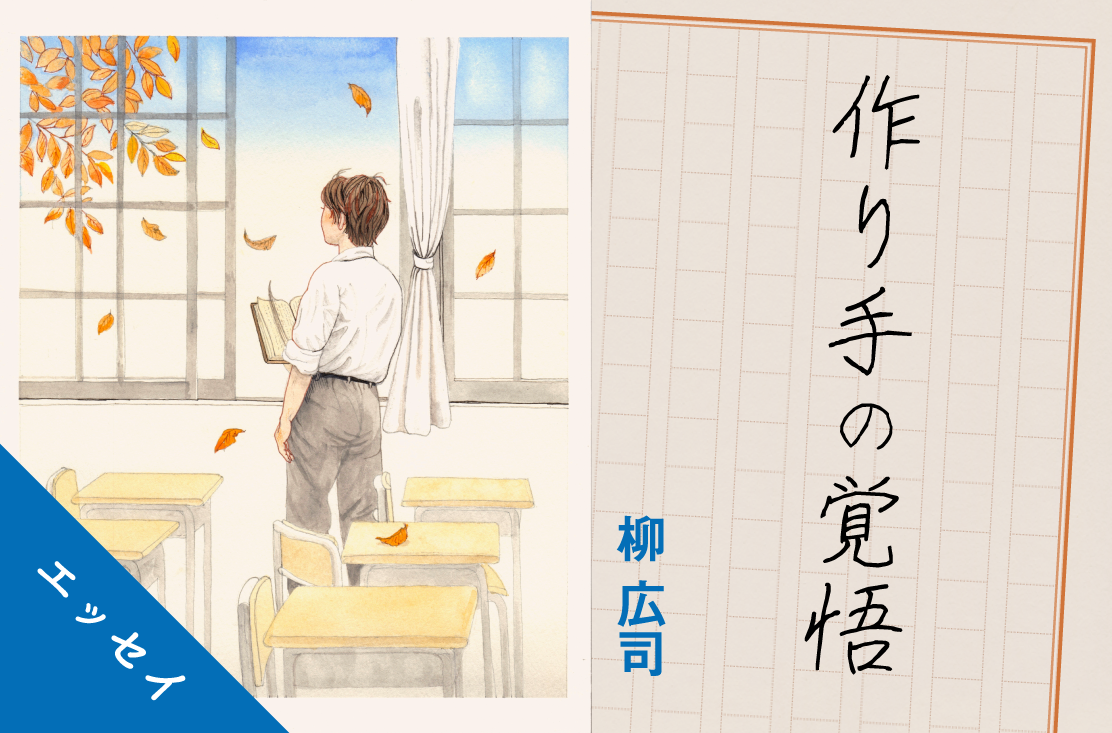Essay 豊かな言葉とは何だろう?
生きながら生きる
小島なお
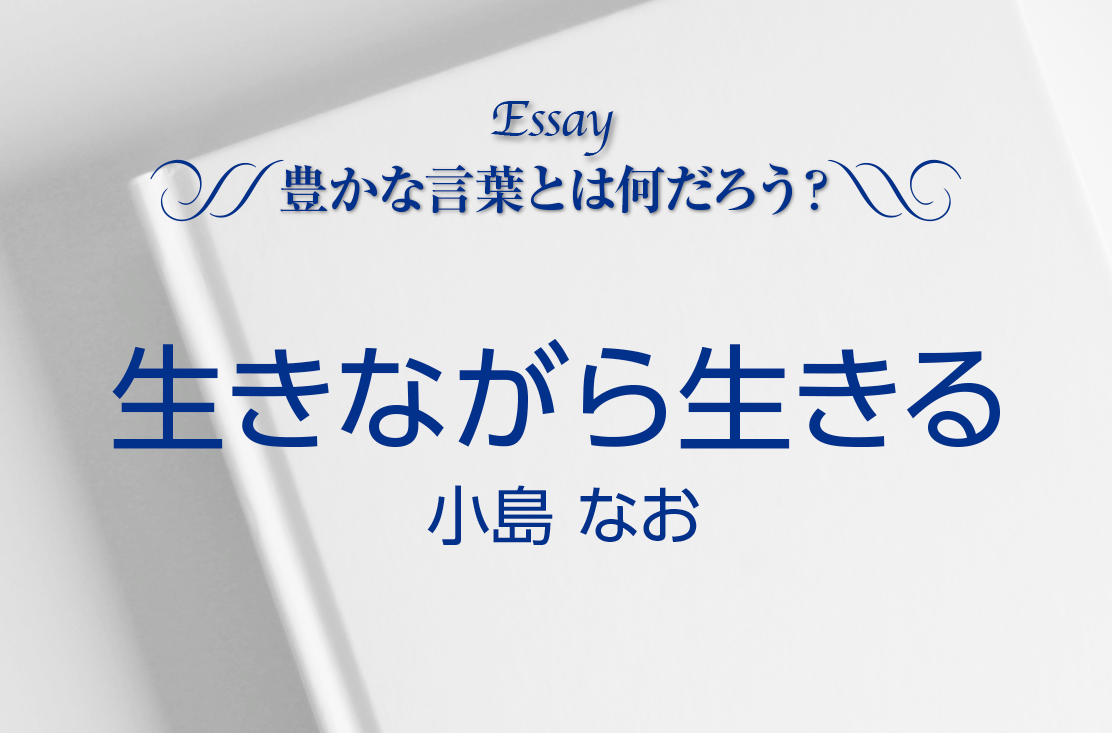
雨はふる、降りながら降る 生きながら生きるやりかたを教へてください 藪内亮輔
大学の講義で、高校の一日短歌授業で、最後に毎回「これまでに紹介した短歌の中でいちばん心に残ったものはどれでしたか」と質問します。すると、多くの学生がこの歌を挙げてくれます。
雨はふる、/降りながら降る/生きながら/生きるやりかたを/教へてください
わかりやすく読むために句と句の間に印を入れてみます。5・7・5・8・8と下句はやや字余りのリズムです。声の届かない誰かに訴えるような、モノローグとも取れるような文体。一行詩にも似たこの短歌には今、強い求心力があると実感します。
「雨はふる、」と言われたとき、私たちの多くは雨が降っている光景を漠然と思い浮かべるはずです。しかし「降りながら降る」と続くとき、視界は雨の風景から、雨粒の一つ一つへカメラのフォーカスを絞るように移行し、落下してはまた生まれる新しい一滴が見えてくる。「雨」という語には、雨粒すべてを総称した現象としての雨を指す場合と、一滴の雨を指す場合とがあることに気が付きます。一つとして同じものはない雨粒が無限に空に生まれ地面に消えてゆく。そのほんのひとときの滞空時間が一滴の「降りながら降る」命であるのです。
それでは「生きながら生きる」とは。当然この問いは私たちひとりひとりの問題であるでしょう。「生きている」ことと、「生きる」ことの間には微妙な隔たりがあるはずです。今は多くの人が心に傍からは見えないほどの小さい傷をたくさん抱えている時代と言えると思います。特にデジタルネイティブ世代は常に自分ひとりでは到底受け止めきれないほどの他者の情報に晒されている。「生きている」状態にありながら、自分一個の〈生〉についてどれほどの人が相対的でなく考えることができているのか。「生きるやりかたを教へてください」という普遍的な問いが、改めて今の学生の心と深く共鳴しているようです。
短歌に正解はありません。しかし優れた表現は、長い時間をかけて私たちのなかに沁み込んでくるものだと考えます。5年後、10年後、もっと先の未来に、新しく理解が深まったり、魅力が更新されてゆくものだとも。瞬間的にぱっと多くの人の心を摑むフレーズも刺激的だけれど、言葉の底力はもっと説明のつかない謎に満ちたところに眠っているのではないか。情報のスピードが高速化している今だからこそ、長い時間をかけて言葉の謎、すなわち生きることの謎と向き合う面白さを学生には知ってほしいと思います。
うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思へば 大伴家持
教科書で誰もが一度は目にしたことのある家持の最高傑作とも評される一首。うららかな春の景色に同化できず、自分ひとりだけがそこに取り残されたような翳りが映し出されています。注目するのは「ひとりし思へば」という表現。万葉集の中にひとりであることを詠った作は他にもあるけれど、〈ひとり思ふ〉としたのは家持の発明なのです。「心悲しも」の内実は示されていない。ここにあるのはなにかの契機によって導き出されてきたものではなく、心の深部からおのずと滲んできた気分のみです。その捉えどころのない悲しみこそが、〈生〉に伴う根源的な存在の孤独だと考えています。
廃れる廃れると言われ続けながら、細く長く、1300年生き残っているのが短歌という詩形です。なぜ私たちがこの詩を手放さないのか。歴史として残さなければ、というさまざまな人の使命感も往々にして作用しているとは思いますが……、それでもコミュニケーションの道具としてではない言葉の引力が、ひとりひとりの孤独と呼応するからではないでしょうか。孤独はマイナスの感情ではありません。自分がここに在る不可思議。自分と他者の交換不可能性。自分の孤独と時間をかけて対峙することこそが、豊かな言葉を生む原動力になると信じています。
『国語教室』第114号より転載
著者プロフィール
歌人。コスモス短歌会所属。2004年、高校在学中に角川短歌賞受賞。歌集に『乱反射』、『サリンジャーは死んでしまった』、『展開図』。
一覧に戻る