教室が活発になる授業のアイディア①
詩を評価し、表現や効果を深く考える授業~「竹」(萩原 朔太郎)
都立大泉高等学校・附属中学校 玉腰朱里
- 2019.04.03
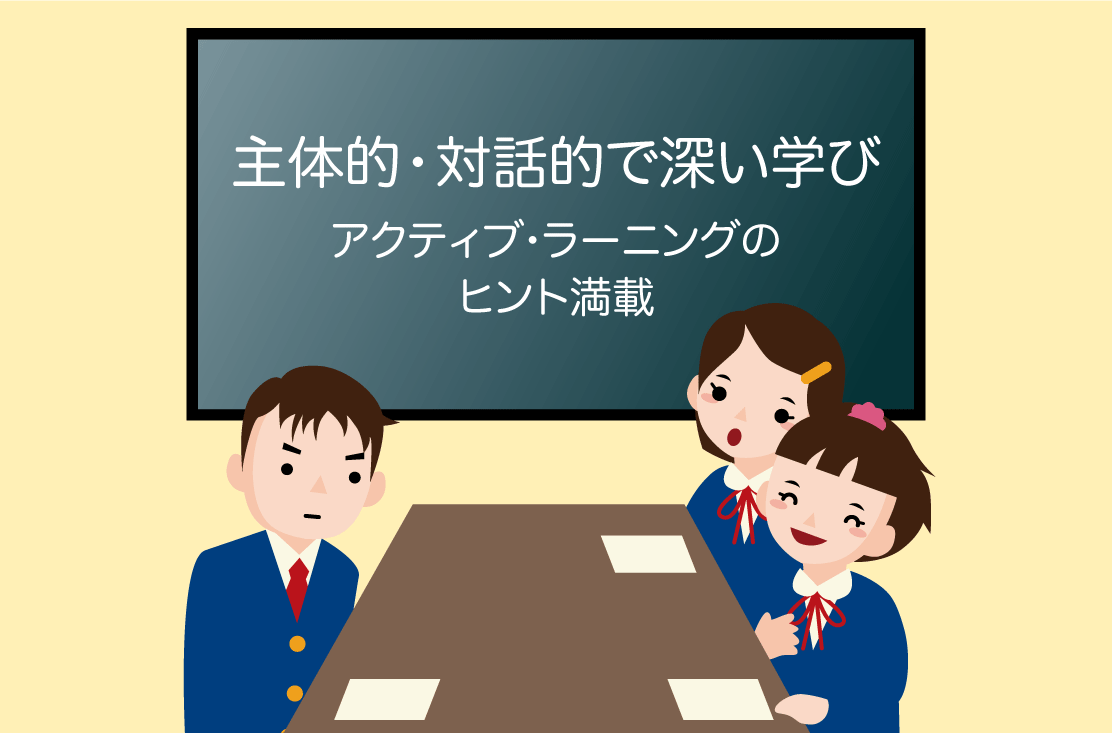

はじめに
「現代文」の近現代詩や短歌、授業ではどのように扱っていますか。
生徒が詩に興味をもって作品を読み味わうために、どのような活動が考えられるのでしょう。
都立校で教壇に立っていらっしゃる先生のご実践を紹介します!
1.学習のねらい
この授業では、萩原朔太郎[1]の近代詩「竹」を2時間で扱います。
「詩の授業」というと、どんなイメージがあるでしょうか。考査後の授業の余りの時間に、パーッと表現技法と文学史を確認しておしまい……私はこれまでにそんな授業をしてしまったことがあります。そうではなく、短い時数の中でも、生徒同士が主体的に詩の理解を深め、楽しく深く詩を味わうことができないかと考え、この授業を実践しました。
この授業のねらいは、マトリックス(評価軸)を使ったグループワークを通して、詩の表現の特色や効果を深く正確に考えることです。第1時で、生徒は初読の感想と評価を書き、一斉授業の形態で詩の表現技法を学習します。さらに第2時では、詩の情景に関する話し合い活動をしながら詩を再評価するという展開です。
ポイントは、評価の観点を明示したマトリックスを使うことです。これにより、生徒の初読の感想や評価を生徒同士が共有しやすくすると同時に、初読の感想から読解後の感想への読みの変容を視覚的にわかりやすく示すことができます。
2.学習の目標
学習の目標は次のとおりです。
| 学習目標 | 学習指導要領との対応 |
|---|---|
| 詩の内容や表現技法を正確に理解して、詩を読み味わう。 | 3(1)イ |
| 詩を批評して話し合い、その内容や表現の仕方を評価する。 | 3(1)ウ |
※表を指で横になぞるとスクロールして全体を見ることができます
| 評価の観点 | 評価基準例 | |
|---|---|---|
| 関 | ○ | 意見交換に役割をもって貢献し、多様な見方を知ろうとしている。 |
| 読 | ◎ | 詩の情景を正確に読み取り、詩を読み味わっている。 |
| 言 | ○ | 詩の表現技法やその特色を理解し、内容理解に活かしている。 |
※表を指で横になぞるとスクロールして全体を見ることができます
3.授業の流れ
ここからは、授業全体の流れを紹介します。授業は全2時間扱いです。まず第1時では、2つの問いを提示し、その問いに対する考えを生徒が個人で記述します。その活動をふまえ、教材をより深く正確に理解するために、第2時ではグループで意見を交換し、詩を再評価したり、その内容を一言でまとめたりします。表にまとめると、次のようになります。
| 学習活動 | 学習形態 | ワークシート | |
|---|---|---|---|
| 1 | 一斉授業個人学習 | ||
| 2 |
|
グループ学習一斉授業個人学習 |
※表を指で横になぞるとスクロールして全体を見ることができます
授業展開の詳細やポイント
第1時では、読みの確認をしてから、初読の感想と詩の評価を書きます。生徒が書いた感想や評価を学級全体で共有した上で、まずは一斉授業の形態で詩や教材に関する正確な知識を学習します。語義・表現技法・表現の特色・リズムやその効果などの基礎的な知識をふまえて、
- 作品の季節はいつか。
- 「光る地面」と「固き地面」が持つ意味やその効果は何か。
という2つの問いを考えさせます。ここで、「自分の考えの根拠を明確にする」ことが次の活動につながる大切なポイントです。
第2時では、前時に考えた2つの問いについて、グループで話し合います。4人グループになって、本文や事実に明確な根拠があるかどうかを確認しながら、意見を交流します。ここで、グループ内の評価が高い意見や、ユニークな意見を学級全体で共有すると、多角的な詩の読解の視点が発見できます。意見交流が終わったら、初読時と同じマトリックスで教材を再評価し、自身の意見や評価の変化をふまえて、教材の一言まとめを記入します。一言まとめの発表と、単元の学習活動の自己評価をし、授業のまとめとします。
グループワークを中心とした、第2時の展開の詳細
| 時間 | 学習活動 | 支援の留意点 | 学習形態 | |
|---|---|---|---|---|
| 導入 | 5分 | 1.前時に学んだ表現技法や読みを復習する。本単元の目標と本時の流れを確認する。 | ワークシート2のルーブリック[2]評価を先に確認し、達成度の目安を意識させてもよい。 | 一斉授業 |
| 展開 | 10分 | 2.①教材の季節はいつか、 ②「光る地面」と「固き地面」が持つ効果は何かという2点について、4人グループで話し合う。その際に、互いの意見は本文や事実に根拠があるかどうか確認して聞きあう。 |
わかりづらい点は質問しあいながら話し合い活動を進め、グループメンバーの意見をワークシートにメモをとるよう指示する。 | グループ学習 |
| 10分 | 3.グループ内で評価の高い意見やユニークな意見をいくつか学級で共有する。 ①の例:青竹の季語である夏、「凍れる」とあるから冬、第一連の竹の根の柔らかな様子は初夏~秋で、第二連の竹が青空に力強く伸びる様子は冬~初春、など。 ②の例:第一連の「光る地面」の下の柔らかい根と第二連の「固き地面」の上に伸びる力強い竹を対比して視点を広げる効果、可視の「光る」世界の下に広がる地下の不可視の世界を強調する効果、など。 |
解釈を統一するのではなく、多様な解釈に出会うことで生徒の初読の読みを揺さぶり、さらに深く正確に教材を読ませることを目的とする。 特に①に関しては、様々な解釈の可能性を挙げさせた上で、季節にとらわれない叙情的な要素があることを確認する。 | 一斉授業 | |
| まとめ | 10分 | 4.教材の再評価とその理由を書き、初読の感想と比べた自己の考えや評価の変容をふまえて、教材の一言まとめを記入する。 | 「『竹』は~な詩である。」の形で、短くまとめさせる。 | 個人学習 |
| 10分 | 5.教材の一言まとめを数名が発表する。 例:見えない地面の上下や青空にまで読者の視点を動かす詩である。竹の叙景詩というより繊細な生の不安を感じさせる詩である。竹に象徴される生命感覚を描いた詩である。など。 |
一斉授業 | ||
| 5分 | 6.単元の学習活動をルーブリックで自己評価する。関心意欲態度・読む能力・知識理解の3観点4段階で評価し、3観点のバランスを確認する。 | 時間に余裕があれば、別の詩を使って、表現技法やその特色に注目して読んだり評価したりできるかを確認させる。 | 個人学習 |
※表を指で横になぞるとスクロールして全体を見ることができます
4.学習の実際と生徒たちの様子
この授業実践の時の、生徒の様子を紹介します。
第1時
授業ではまず、教材の難読語の読みを確認し、生徒に繰り返し音読させることから始めました。全員起立して、本文を3度音読し終えた生徒から座るよう指示したところ、1度目は恐る恐る読みを確認しながら音読していましたが、周りの生徒の音読を聞く余裕も出る2度目・3度目は、リズムを意識しながらテンポ良く音読する生徒も増えていきました。
初読の感想では、次のような感想が見られました。
- 最後の部分の竹を連呼しているところに力強さ、そして見渡す限り竹が生えている様子を描いているところに情景を感じた。読んでみて、竹になったような感じがした。
- 竹のまっすぐ伸びる力強い様子が浮かぶように感じた。
- 竹の生き様を細やかに描いている印象を持った。繊細な描き方からは、竹という植物ののびのびとした美しさを感じた。
また、初読の評価では、「風景」と「力強さ」を表すマトリックス上の左上に★をつける生徒が大多数を占めました。こうして書いた感想や評価を、席の近い生徒で交流したり、何名か発表したりしたあと、文学史や近代詩の表現技法の学習に移りました。小・中学校時代に「竹」を学んだことがある生徒が複数いたため、文学史・リズムの良さ・表現技法の学習などは既習事項の復習という形で、生徒とのやり取りを中心に簡単に学習しました。
基本的な知識を学習し終えてから、第1時の最後に、展開例で示した①と②について個人の意見を書きました。①の季節については、「凍れる節々」という言葉を根拠にして、「冬」とする生徒が多くいましたが、机間指導の中で「本当にそう言い切れる?」、「おっ、春って書いている人もいるよ」などと言って揺さぶりをかけると、生徒は改めて「青竹」という言葉を辞書で調べたり、国語便覧をめくったりしながら、「柔らかい根が生えるのは初夏」、「青竹が季語だから、夏」など、意見を様々な方向に膨らませました。
第2時
第2時では、前時の復習と音読をした後、①と②の2つの問いについて4人グループで話し合いをしました。話し合いの中では、「『光る地面』には、暑い太陽が降り注ぐ夏の季節を強調する効果があるのかも!」などと根拠に欠ける考えを述べる生徒もいましたが、メモを取り、互いに根拠を確認しあう中で、その生徒の考えも修正されていく様子が見られました。
こうして4人グループで話し合った意見のいくつかを学級で共有した上で、席をもとの形に戻して個人で教材の再評価を行い、評価の理由と教材の一言まとめを書きました。生徒の多くは、初読の時の自分の感想や評価と比較したり、グループでの意見交換をふまえたりして、この詩を評価・考察していました。生徒の感想をいくつか紹介します。
- 初めは、ただ竹が生える様子を様々な言い方で表現している詩だと思っていたが、考えてみれば、目に見えないところ(地下)で繊毛が「かすかにふるへ。」などと表現されているから、この詩は竹以外の何か人の心や生き方などの心情を竹に喩えたものだと思った。
- 力強くそびえ立つ竹の生え始めの頃の「不安」な気持ちを、細い根の様子などを出して表していることに気づいた。景色をそのまま書いているように感じたが、実は竹の成長と感情とを合わせたものを、流れるようなリズムで書いているのだと思った。第一連があることで、第二連に書かれている力強さが強調されていて、全体を通して力強さが感じられる詩になっている。
- 竹が伸びる姿から、私は、その場の景色を描いているのではないかと初めは思った。しかし、土の中まで描く繊細さを感じる人がいたり、風景・心情どちらでもないのではないかと言う人がいたり、詩は同じでもこんなに色んな意見があるんだ、という気持ちになった。
これらの意見や教材の一言まとめを数名に発表してもらい、これらの学習活動を自己評価して、授業のまとめとしました。
5.評価について
本単元はワークシートとグループでの話し合いを中心に授業を進めるため、教師の評価はそれらの点検や観察で行うことができます。また、第1時に学ぶ、表現技法や詩の表現の特色がもたらす効果を、根拠を明確にして答えられるかどうかを、発問や考査で問いかけてもよいでしょう。
ワークシート②の最後にはルーブリック[2]による単元の自己評価表をつけており、生徒自身も単元の学習の自己評価を行います。このルーブリックは、単元の学習に入る前に確認し、達成度の目安を意識させることもできます。ワークシート②では、関心意欲態度・読む能力・知識理解の3観点をS~Cの4段階でルーブリック評価させるだけでなく、3観点をバランスよく習得することを生徒自身に意識させるために、自己評価の下にあるレーダー表に色塗りをさせます。
この中で、関心意欲態度として評価する「話し合い活動への貢献の仕方」は、周囲の人への話題提供や、話し合い活動を円滑に進めるための雰囲気作り、司会や書記など、生徒の個性とグループのメンバーに応じた貢献の仕方が考えられるでしょう。本単元のみの単発的な指導ではなく、同じ形態の授業や、同じ評価軸での自己評価を続けることで、言語活動を取り入れた授業を行いやすい学級の雰囲気作りもする必要があります。
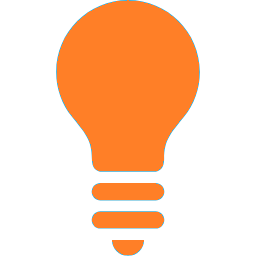 こんなとき、どうする?
こんなとき、どうする?

→教科書に掲載されている他の詩や既習作品を比較対象として提示し、「この詩と比べると、どちらが力強い感じがする?」などと具体的に問いかけると、評価の手がかりとなります。また、学級の学力や学習状況に応じて、評価の観点を「明るいイメージ~暗いイメージ」、「実在の竹~架空の竹」など平易なものに変更すると評価しやすいでしょう。
他教材への活用
授業の導入や理解の確認にマトリックスを用いた評価を用いる手法は、詩・短歌・俳句などの韻文全体に活用することができます。また、文学教材の分析や、評論教材における筆者の意見の読み取りなどに応用することで、授業の導入部から生徒に授業で考えさせたい部分に焦点を絞って読む仕組みを作ることもできます。
例:短歌「白鳥はかなしからずや空の青海のあをにも染まずただよふ」(若山牧水)を、「竹」で使ったマトリックス(「風景~心情」、「力強さ~繊細さ」)で評価する。
このコーナーでは、高校国語の教材を使った活動的な授業実践、指導案の紹介をしています。
自分が教えているあの教材を、他の先生はどのように教えているのだろう、いつもと違った手法を取り入れてみたい、という先生方のお役に立つような、活動的で「教室が活発になる」授業の実践が見つかります!
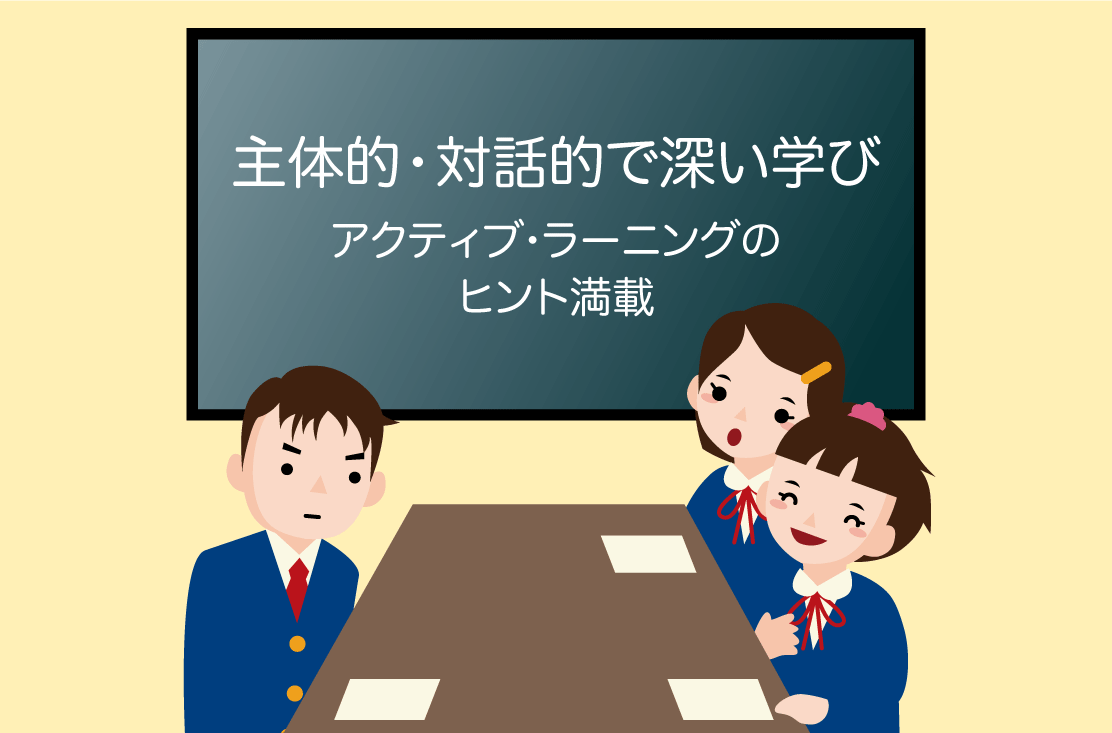
詳しくはこちら
一覧に戻る






