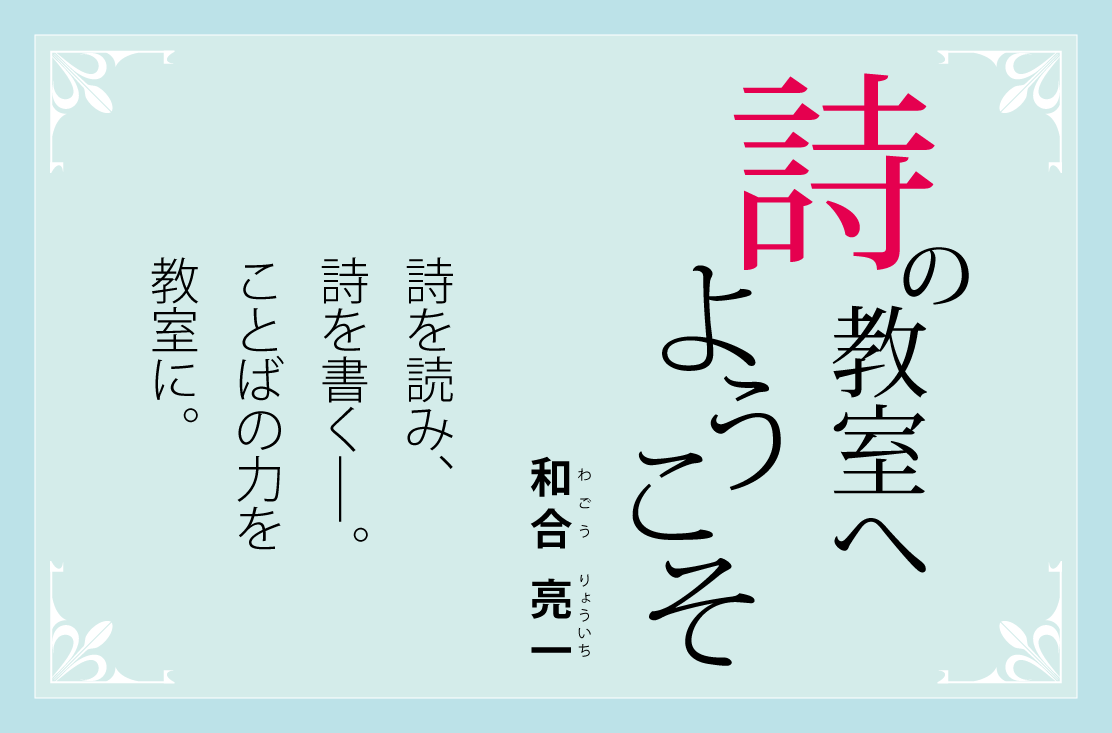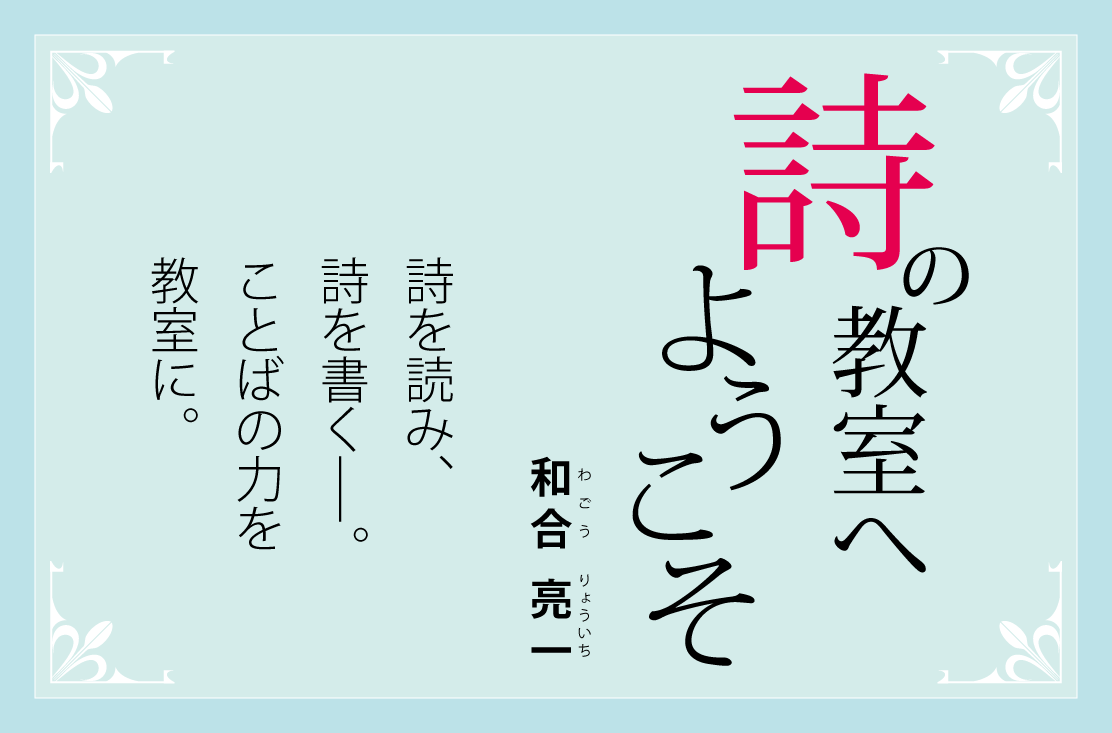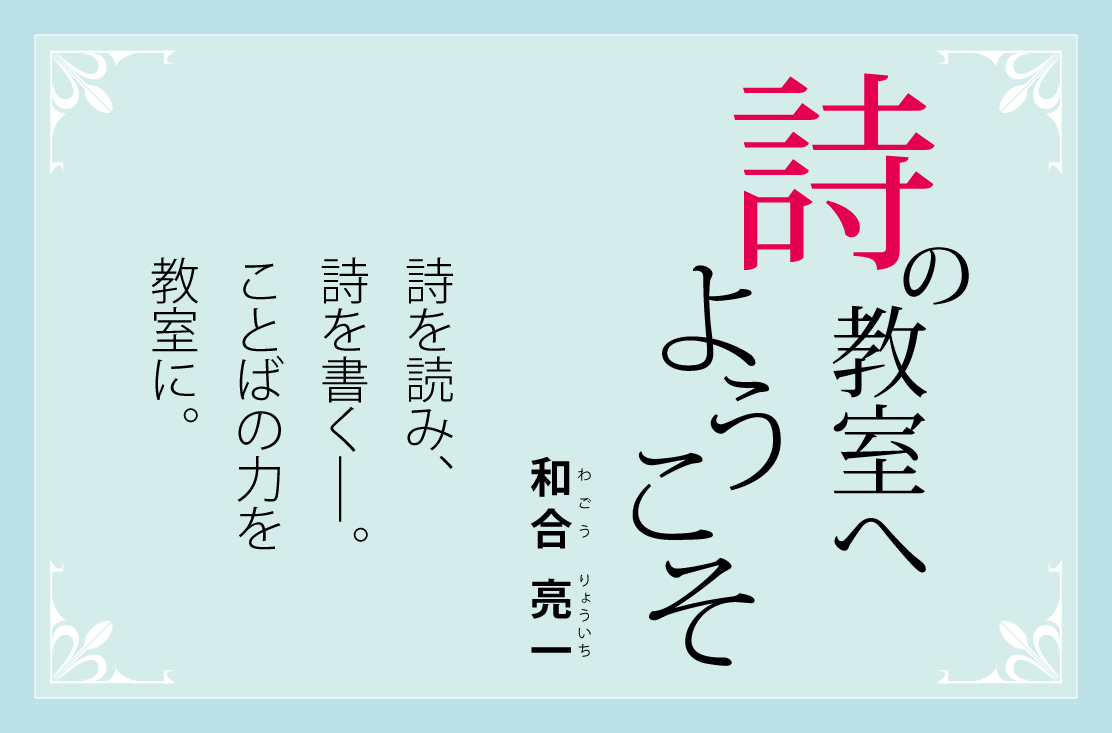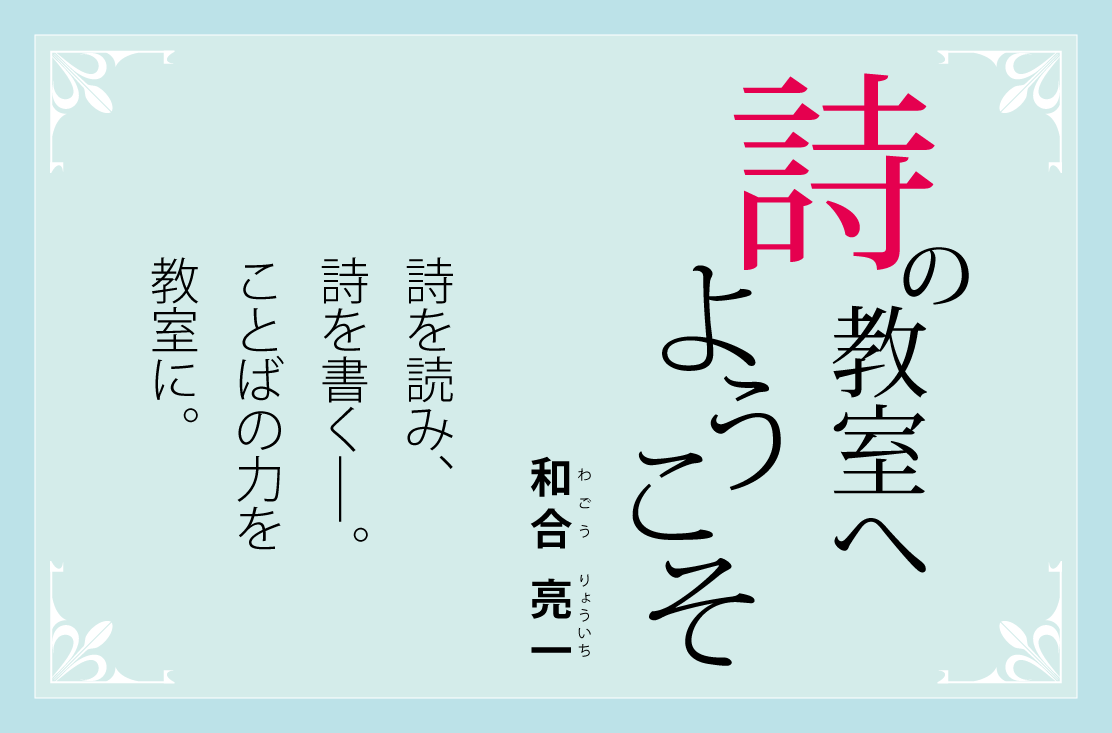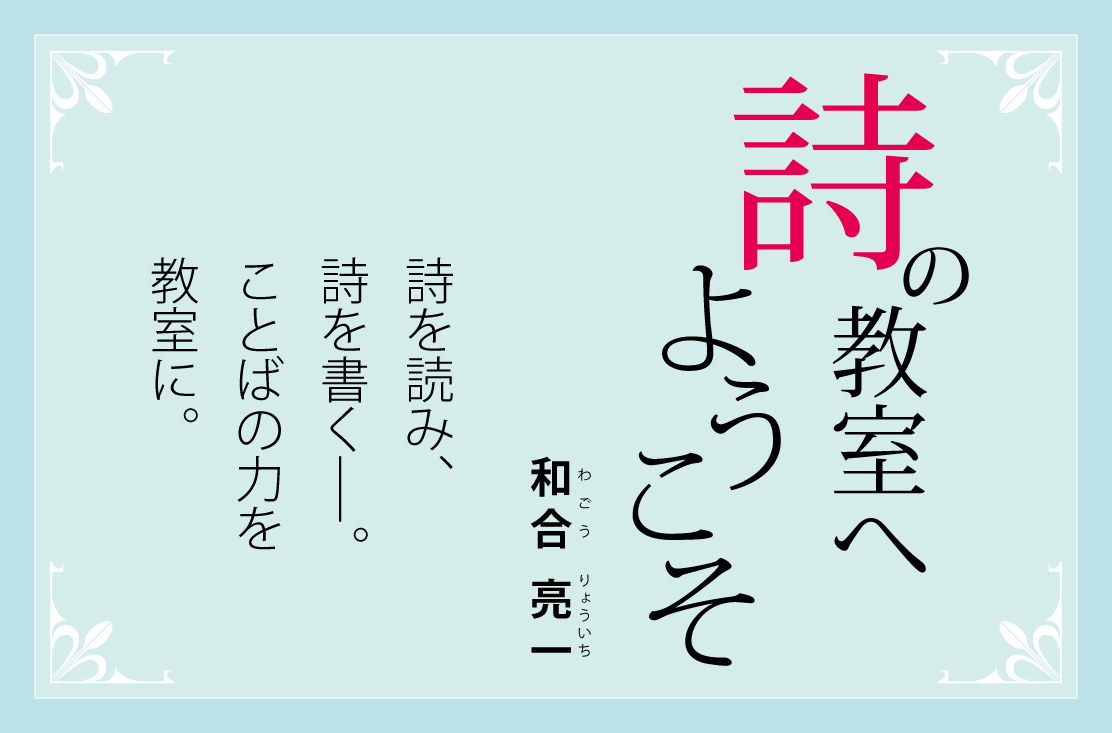詩の教室へようこそ
第3回 大きな何かと出会うために
和合亮一
- 2021.12.09
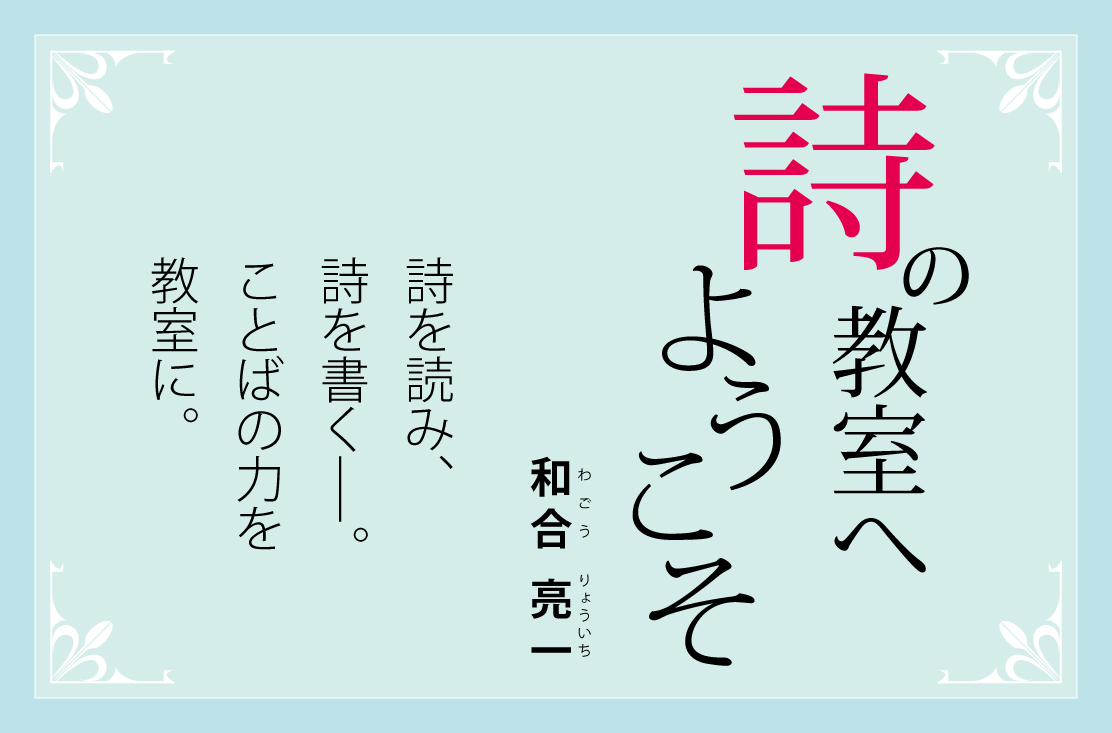
◆人生のレシピとしての詩
詩作を始めてから、早くも30数年が経っています。こんなに長く続けることになるなんて…と、意外な気持ちがいたします。私は何をやっても飽きっぽくて、次から次へと目移りしてしまう性格なのです。これを続けてきたと思えるものを一つでも持つことが出来たということについては、知命と呼ばれる50歳を過ぎて振り返ってみて、自分でも正直なところ、驚いています。
どうして続けてこれたのでしょうか。ズバリ、好きだからです。詩を書くことも読むことも、自分の人生のレシピにとっては、もはや必要不可欠なことだと言えるでしょう。詩と向き合うことが当たり前の日常ですが、それを生徒さんにも先生方にもおススメしたいというのが変わらずにあります。
これまでも詩作について教えてもらえないかというお話をいただいてまいりました。まあ何事も、習うより慣れろと申しましょうか。まずはたくさんの詩を読み作品世界に触れることから始まると言えます。しかしそれだけをお伝えするのではなかなか、詩作へと誘いこむのは難しいと日頃から教師の現場で感じてまいりました。
分かりやすい方法はないものかとしだいに模索を重ねるようになり、現在に至ります。長い歳月においての取り組みや実践、その際に用いたワークシートなどを、『詩の寺子屋』(岩波ジュニア文庫)という一冊にまとめていますので詳しくはそれを参考にしていただけますと幸いですが、ここで少しだけ簡単なものをご紹介させてください。
◆詩作のミニレッスン
その1「思い浮かぶ言葉を書いてみる」。
まずは五分間でも十分間でも、心に浮かんだことをなんでも良いとして書いてみることから始めてみましょう。筆が動くままに何かを白紙に連ねてみる。出来る、出来ない…の度合いはとても様々だと思いますが、机を並べている隣の誰かがそれを始めると、不思議とそうしようとする気持ちが湧いてくるのです。あたかも熱心に本を読み耽っている人がいると、自分も静かに読んでみようという気持ちになるように。
まずはそれを思うがまま記してみて、時間が来たら、筆を置いてみる。書いたものをあらためて眺めてみる。言わば自由に記した言葉の落書きのようなものを。
普段なら捨て去ってしまうでしょう。しかしそれを自分の心の鏡のようなものなのだとして受け止めてみる。自分なりに新鮮さや面白さを感じた言葉やフレーズに線を引いてみる。少しでも何かの発見があれば、試みとして成功だと思います。ほんの少しでもたくさんでも。それを見直してマークをしてみることで、自分の書いた何かを違う眼差しで見つめる=客体化することが出来ます。実際にこれを毎日続けていくと、白紙に描く落書きの中味がみるみるうちに変わっていきます。このようなイメージやメモ書きが、実は詩を書く第一歩になるのだという説明を添えます。
その2「言葉を持ち寄ってみる」。
思い浮かぶ言葉をグループの中で持ち寄ってみましょう。好きなものでも良いし、教師の側でテーマを決めてみるのも良いと思います(例えば「秋」を感じさせるものとか、色彩が感じられるものなど)。メンバーの顔ぶれによってかなりの数になる時もあれば、わずかな場合もあるでしょう。とりあえずその中から三つの言葉をあれこれ話し合わせて選ばせてみましょう。
単語カードのようなものを渡して並べて選んでみるのも良い方法です。ちなみに実際に小学校などのワークショップでは、夏なら魚、秋なら木の葉の形に、子どもたちに色画用紙などを渡して、切り抜きをしてもらいます。一つひとつ手作りのカードに言葉を記して、机の上に並べてもらうと、にぎやかな感じになります。それをグループで眺め渡しながら選んでみることによって、集団の=別のまなざしが生まれている瞬間があるということを子どもたちの楽しそうな姿から感じてきました。
その3「組み合わせてみる」。
取り出した言葉を無理やりにでも組み合わせて、フレーズを作り出してみようと促します。自分の言葉あるいはそうでないものを目の前にして、そのつながりを考えてみる。私がこのような場合に参考として挙げるのが多いのは俳句の作品です。
例えば「うつくし」「天の川」「障子」の三つの語を用いて考えてみましょう…。これをクイズのようにして、無理やりにでもフレーズを作ってみようと呼びかけます。
例えば「昨晩は美しい天の川が出ていたのに、窓ガラスの前の障子が開かなくて見ることができなかった」など各グループから名(?)回答が飛び出します。このことへの正解というわけではないのですが、小林一茶の句「うつくしや障子の穴の天の川」の一例を伝えます。三つの言葉が組み合って、名句や名詩は生まれているのだ、とも。
アイディアとはそもそも、何かと何かを組み合わせることから始まるのだという説明を添えます。良し悪しではありません。ここで組み合わせ=「言葉の塊」のようなものを作ることの面白さを知ってほしいと願っています。
その4「塊を大きくしてみる」。
例えば三つの言葉の組み合わせを他にもし続けていき、出来上がっていく様々なフレーズを、三行、五行、十行…と全員で組み合わせていくことで、その塊はどんどん大きくなります。必ずしも自分の言葉でなくても出来上がるものなのだという経験をして欲しいと思います。こだわりを捨てて良い言葉をいつも捕まえようとする姿勢こそが大事なのだと伝えたいです。それをあらためて皆で清書してみると、少なくとも詩に似ている何かが、出来上がっていることに気付かされます。
その5「朗読してみる」。
出来上がったものをグループごとに朗読してもらいます。代表者一名でも、あるいは全員で工夫して読んでみるのも良いと思います。音声にしてみることで、さらにひらめくこともありますし、何よりもそのようにして声で形にしてみることで、そこに文字の世界ばかりではない命が吹き込まれていくような感覚を少なからず実感できると思います。
「言葉の塊」を通して、生きた言葉の時間を教室で共有することが出来れば、普段とは違う仲間とのコミュニケーションの深まりが見つかることが分かります。そして体験したことを基にして、今度は一人でも実践して書いてみようとする気持ちが芽生えるきっかけになると指導者として感じてきました。
◆投稿作品より
投稿作品をいくつか、ご紹介させていただきます。まず一作目。高校三年生(匿名 東京都)さんの作品です。
どうして星は夜しかみえないの
それはね
星は夜になると忙しいから
楽しい夢をみんなに届けて
朝の澄んだ空気の準備をするの
あちこち忙しく動き回るから
キラキラ光って見えるのよ
美しい星空をテーマに、幼い頃に家族と交わした会話を、ふと思い出させてくれるかのような懐かしさと、宇宙の広がりが感じられるような素敵な作品でした。二作目は浦野恵多さん(埼玉県立大宮中央高等学校 三年)の作品「流体」です。
流体
拾ってきた食卓には
暖かな料理が並べられ
わたしと友人は
手をつけない
(カチ カチ)
影の韻律は
響くばかりで
身体をわたしたちから遠ざけながら
(ね)
小さな銀を足場に渡っていく
(ね、ね?)
洗い流され
はるか はるかの水の底
丸裸にされて
二人で一緒に 海に着く
海のイメージの深まりと向き合った不思議な印象を受ける作品ですが、時間と歳月の波の中で、生きていくこととは何かを考えさせられました。福島で震災を経験した私としては、津波の被害を受けた二〇一一年から、今年で十年が経ったことを思い浮かべました。
◆自分の存在を込めて書く
紙幅が尽きてまいりました。最後に岩崎航の新詩集「震えたのは」(ナナロク社)から、一つの詩句を紹介したいと思います。作者は幼い頃から筋ジストロフィーという難病を患ってこられました。やがて彼は詩作と出会います。一冊のなかのそれぞれのフレーズには病床で握っているペンの力が、しっかりと手渡されている感触があります。岩崎さんにとっての二冊目の詩集になります。
重度の障害と向き合う日々。装着しなくてはならない器具や誰かの介助なしでは生きられない現実が言葉に記されています。
いつまでも
子どもあつかいされる
厭わしさ
やりきれなさと
かなしき怒りと
十七歳の時に絶望感が募り、自殺までも考えたこともあったそうです。しかし第一詩集の刊行後に、これまでの心に変化が訪れたと続けて語っています。「自分の意志で暮らしを作っていきたいと思うようになりました」と。ありのままの自分を詩に書くことで鍵のようなものが見つかったのではないでしょうか。その姿が随所に見えてくる詩集です。
経管栄養や呼吸器を
使うのは
ひとつの喪失で
それ以上の生きる力を取り戻す
活の手段なのだ
短くとも迫力のある言葉の数々です。この二行に特に励まされます。
病と向き合い
堂々と生きる
生きるとは、大きな何かと向き合い続けること。岩崎さんは難病と、そして詩を書くという時間に、堂々と対峙しています。
自分の存在を込めて書くことのかけがえのなさを、生徒たちと見つけることが出来たらと強く祈りながら、私も教壇に立っています。
『国語教室』第116号より転載
筆者プロフィール
福島県立本宮高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。
一覧に戻る