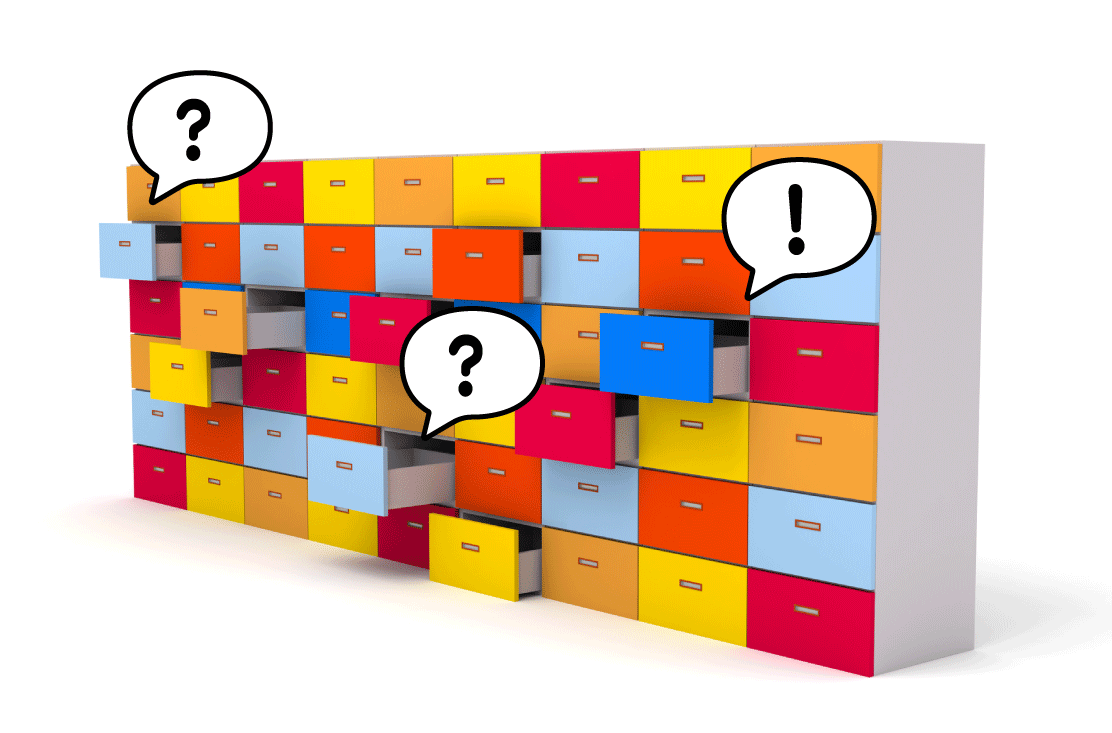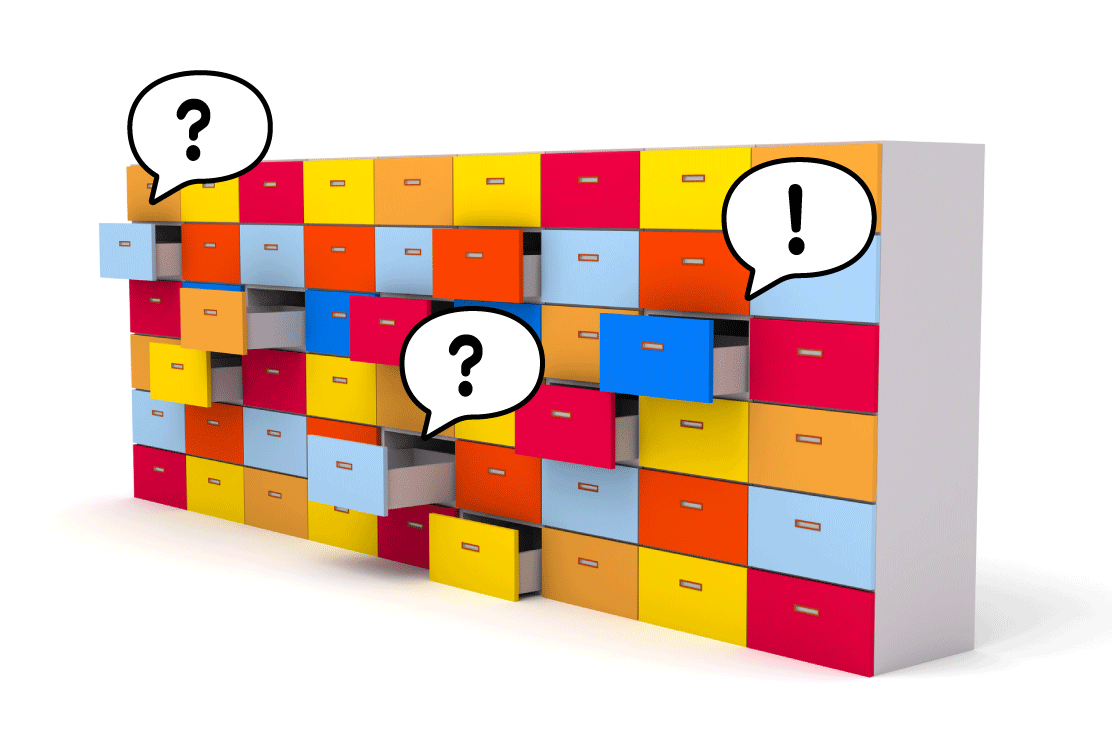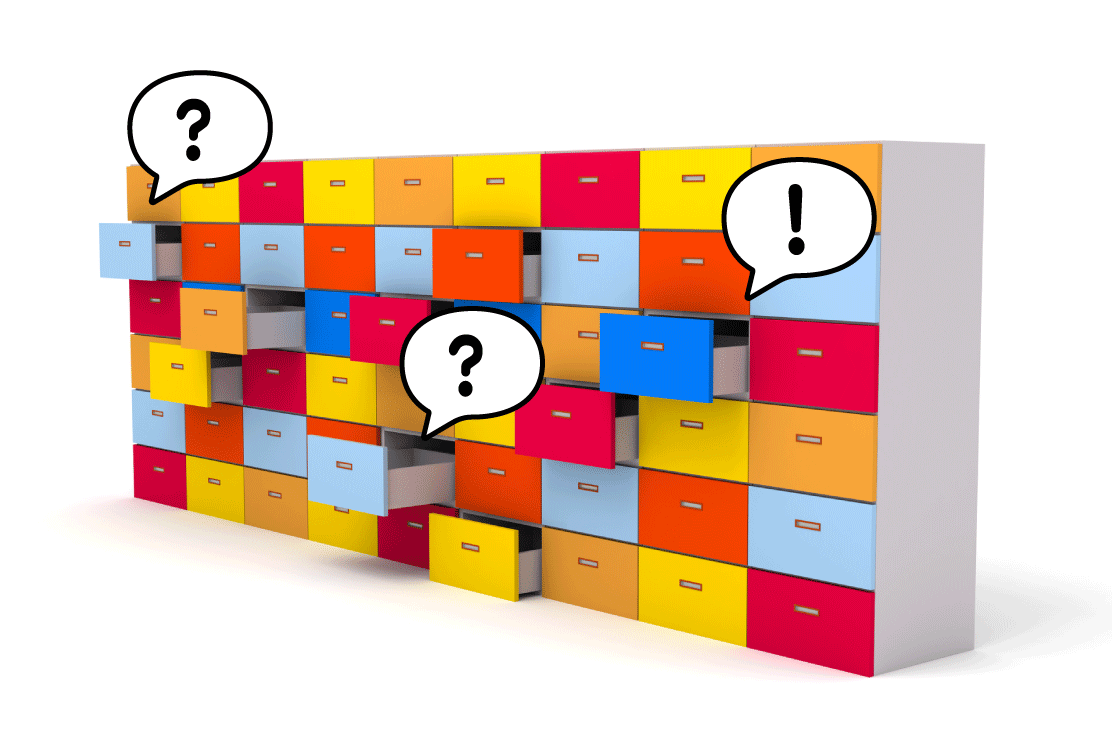コトバのひきだし ――ふさわしい日本語の選び方
第1回 あわや本音があらわに?
関根健一
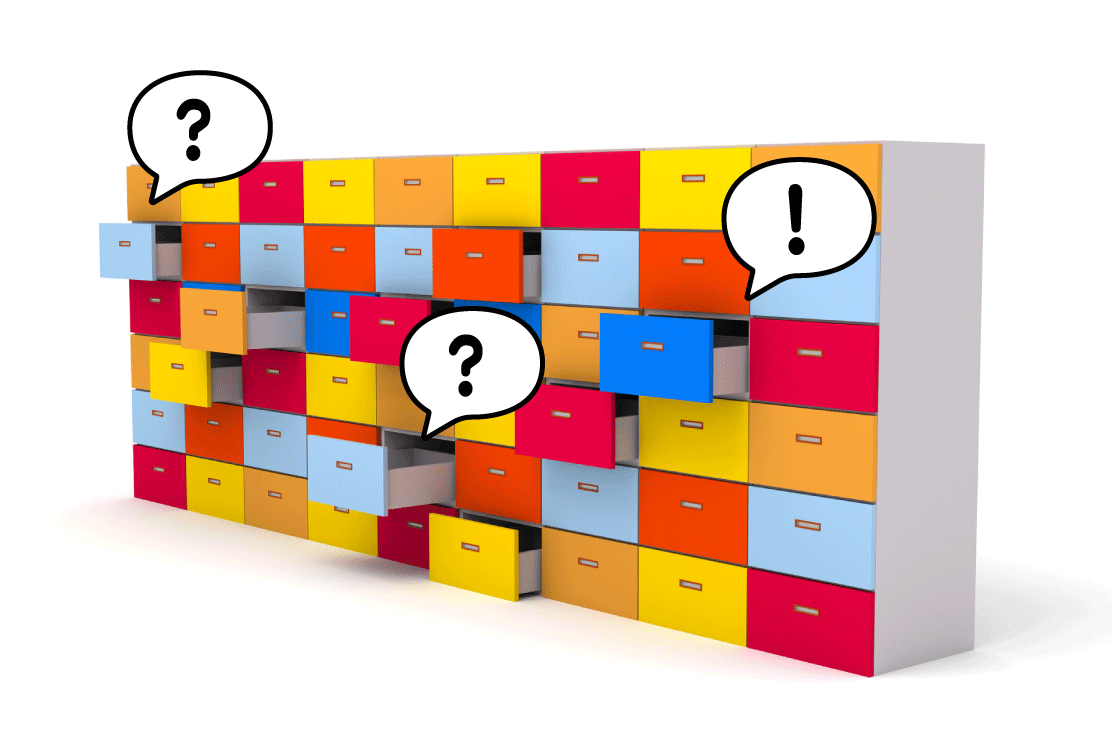
人との付き合いというのはなかなか気を使うもので、趣味とか食べ物の好き嫌いとか、むりやり合わせたり、興味のないことでも関心があるように装ったり、苦労することもありますね。
たとえば、プロ野球のひいきの球団。相手に合わせようとして、思わぬ展開になることも――。
「私は子どものころからの巨人ファンでね、つい熱くなっちゃうんだよ。きみはどこのファン?」
「も、もちろん、ジャイアンツファンですよ。野球は巨人、決まっているじゃないですか」
「そうか、そうか。そりゃ、気が合うね。巨人ファン同士となると、商談もスムーズに進みそうだね。ところで、昨日の巨人‐阪神戦、見た? 惜しかったねえ。いい試合だったんだけど、延長戦の末、引き分けだもんね」
「まったく、もう少しのところで……残念でしたね」
「ほらほら、九回裏の巨人の攻撃、ツーアウト満塁で、すごいいい当たりだったのになあ。ファウルになっちゃって」
「そうそう、あれ、あわやホームランかと思いました」
「うんうん、そうそう、あわやね、えっ、あわやホームランだって? きみー、ホントは巨人ファンじゃないな!」
*****
「あわや」は、目の前に迫った危険を寸前で回避したときに思わず発する言葉に由来します。「あわやぶつかりそうになった」「あわや大惨事となるところ」など、好ましくないこと、そうなって欲しくないことが起こりかけたときに使われる副詞です。つまり、「あわやホームラン」は、ホームランを好ましくないことと捉えた言い方になります。「ホームランになるところだったけど、ならなくてほっとした(巨人に点が入らなくてよかった)」という気持ちが、はしなくも出てしまったというわけです。あるいは、本当に巨人ファンだとしても、「あわや」を使った以上、アンチ巨人かと誤解されても仕方がないともいえます。
「あわや」は、「もう少しのところで」といった中立的、客観的な意味を表すだけでなく、「そうなって欲しくない」という発話者(書き手)の気持ちが込められている言葉なのです。『明鏡国語辞典 第二版』にも「幸運や成功についていうのは誤り」とあり、「あわや記録達成というところで失敗する」の誤用例が載っています。
ただし、誰かの幸運・成功が、ほかの誰かを悔しがらせたり、落ち込ませたりすることは世の習い。逆に、他人の不運・失敗に得たりとほくそ笑む輩もいるのもご承知の通り。「あわや」が適切かどうかは、人により、立場により、変わってきます。ときには、発した者の隠れた思い、立ち位置をあらわにしたり、いらぬ誤解を与えてしまったりすることもあるでしょう。
*****
文化審議会国語分科会は2018年3月、「分かり合うための言語コミュニケーション(報告)」をまとめました。そこでは、言語コミュニケーションで考慮すべき要素の一つに「ふさわしさ」を挙げています。言語コミュニケーションの障害となるのは、意味の取り違えや、語形の誤り、文法的な規範の逸脱ばかりではありません。文法的に正しくても、ある価値判断を含む言葉をそれと意識せず用いるのは、「ふさわしさ」に欠けます。「そうなって欲しかった」ことが実現せず、がっかりしている相手に対して、「あわや…だったね」と声をかけるのは、ふさわしいとは言えません。
報告では、「台風の当たり年」を例に挙げています。本来、作物がたくさんとれる年を指す「当たり年」を、農業にも大きな影響を及ぼす台風の数の多さに用いるのは、比喩表現として適切かどうか。迷惑を被った人たち、被害に苦しむ人たちの心情を傷つけるおそれもあります。
*****
ふさわしさを考慮して伝え合うためには、「語彙の引き出し」をいっぱいにし、きちんと整理しておかねばなりません。新学習指導要領でも、小学校から高等学校まですべてにわたって、「語彙を豊かにすること」と締めくくられる項目が入りました。たとえば、高等学校(「現代の国語」)では、「話や文章の中で使うことを通して、語感を磨き語彙を豊かにすること」とあります。やみくもに語彙の量を増やすのではなく、文章の目的や対象にかなった語彙を選択できる力、表面的な意味だけでなく、与える印象や細かな用法の違いを意識して使えるセンス、といったことが求められているのではないでしょうか。
「あわや」や「当たり年」のように、ある価値観や、プラスもしくはマイナスの方向性が潜んでいる言葉の存在に気づき、類語を探したり、別の表現ができないか工夫したりすることは、語彙を豊かにするきっかけになるはずです。
「もう少しでホームランだった」は、攻守どちらからも使えます。守る側とそれを応援する観客のほっとした気持ちを表すのが「あわやホームランだった」です。「危うく」「危なく」にすると、もっと危機感が伝わるでしょうか。同じ状況を、攻める側の切ない思いを代弁するなら、「もう一息で、ホームランだった」「惜しくもホームランにならなかった」となります。
*****
「まいったな、筋金入りの阪神ファンとしては、巨人びいきのふりをするのは至難の業。あの部長もしつこいのなんの。やっと、解放されたよ」
「やっと、で悪かったね」
「ギョッ、今の独り言、聞いてたんですか」
長い時間をかけて実現することについて用いる副詞が「やっと」です。それが実現することを期待する思いが含まれています。
では、「大災害の全貌が明らかになり、最悪の事態がやっと判明した」は、どうでしょうか。全貌判明は期待されていたとはいえ、それが最悪の結果だったとしたら……。「ふさわしさ」の視点から考えてみてください。
『国語教室』第109号(2019年2月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。文化審議会国語分科会委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室』『ちびまる子ちゃんの敬語教室』『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(以上、集英社)、『上質な大人のための日本語』(PHP研究所)など。
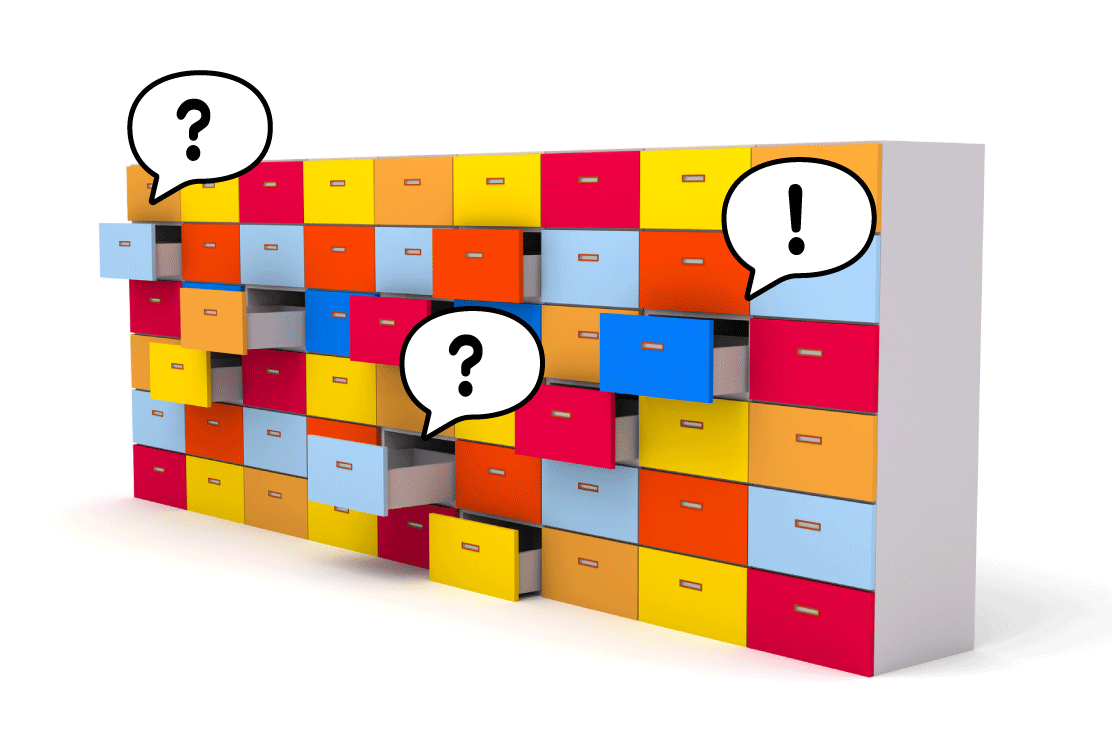
詳しくはこちら
一覧に戻る