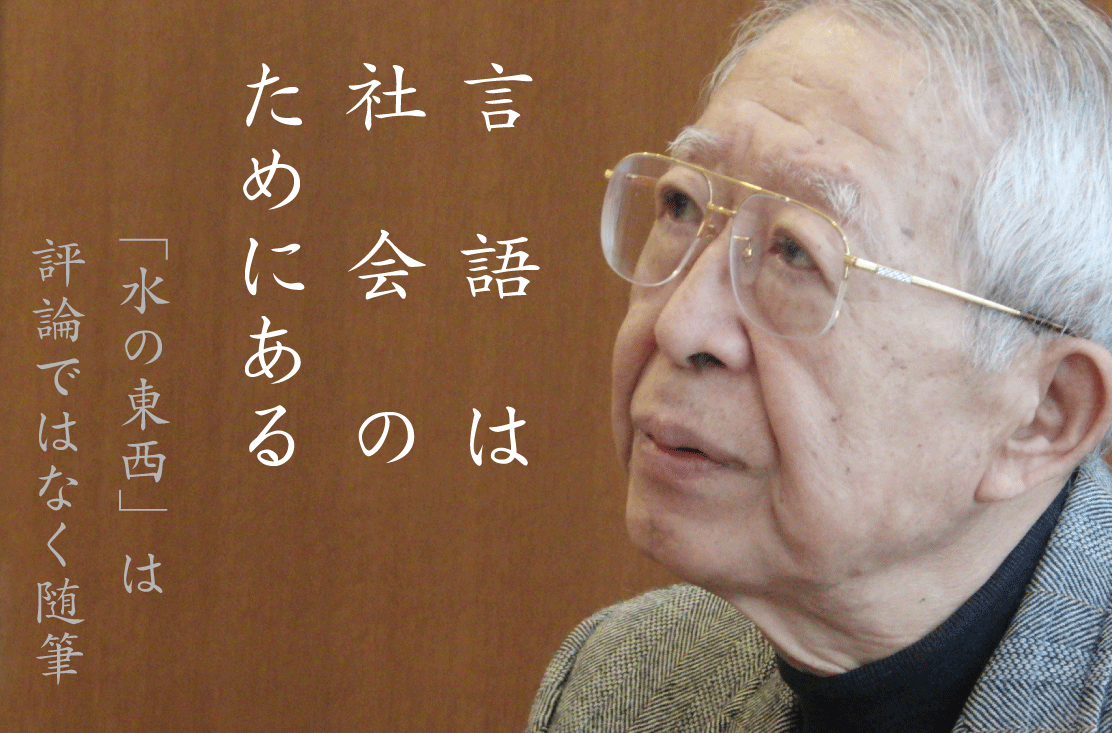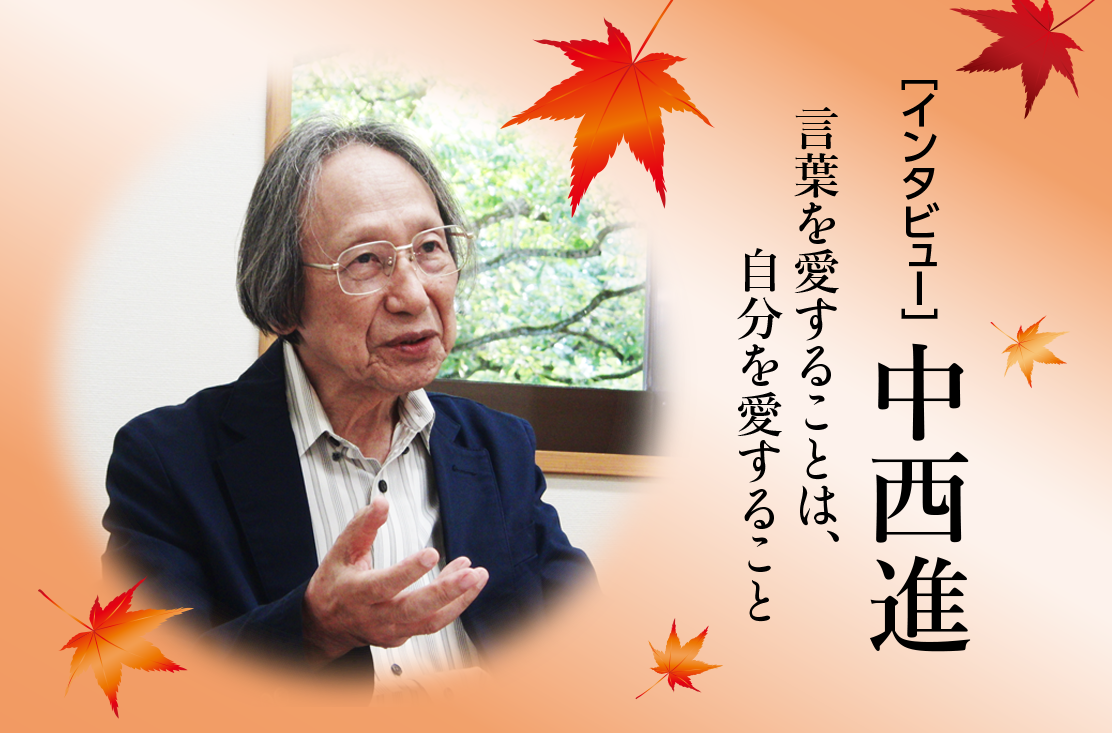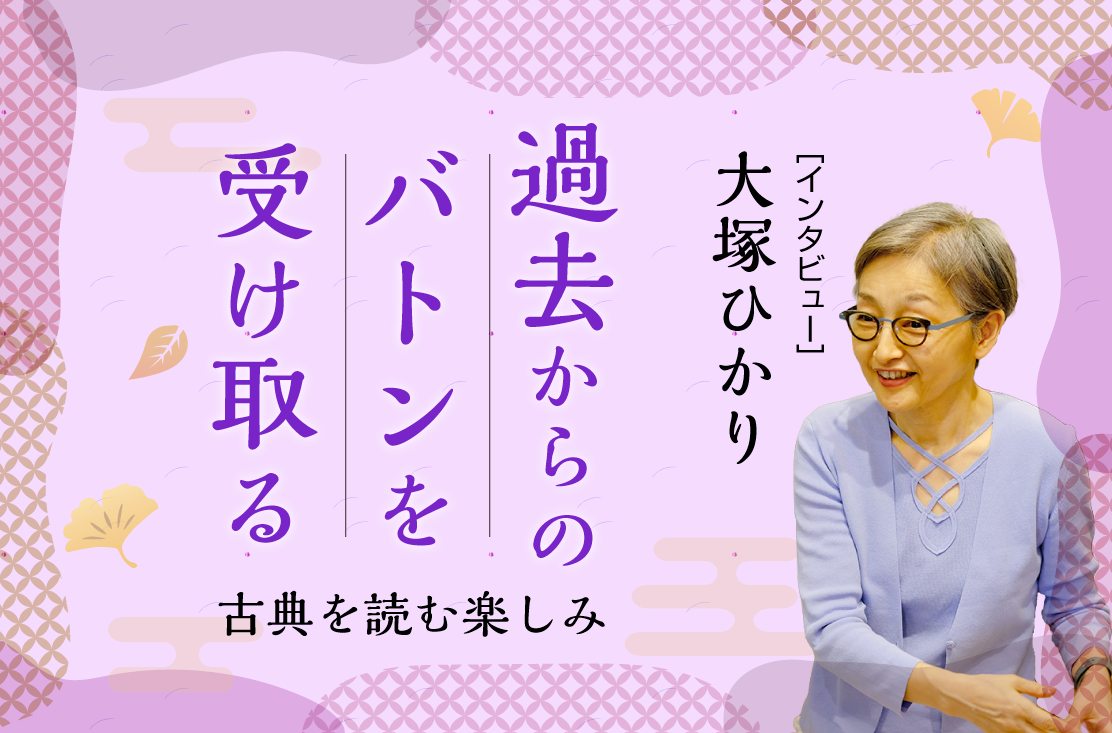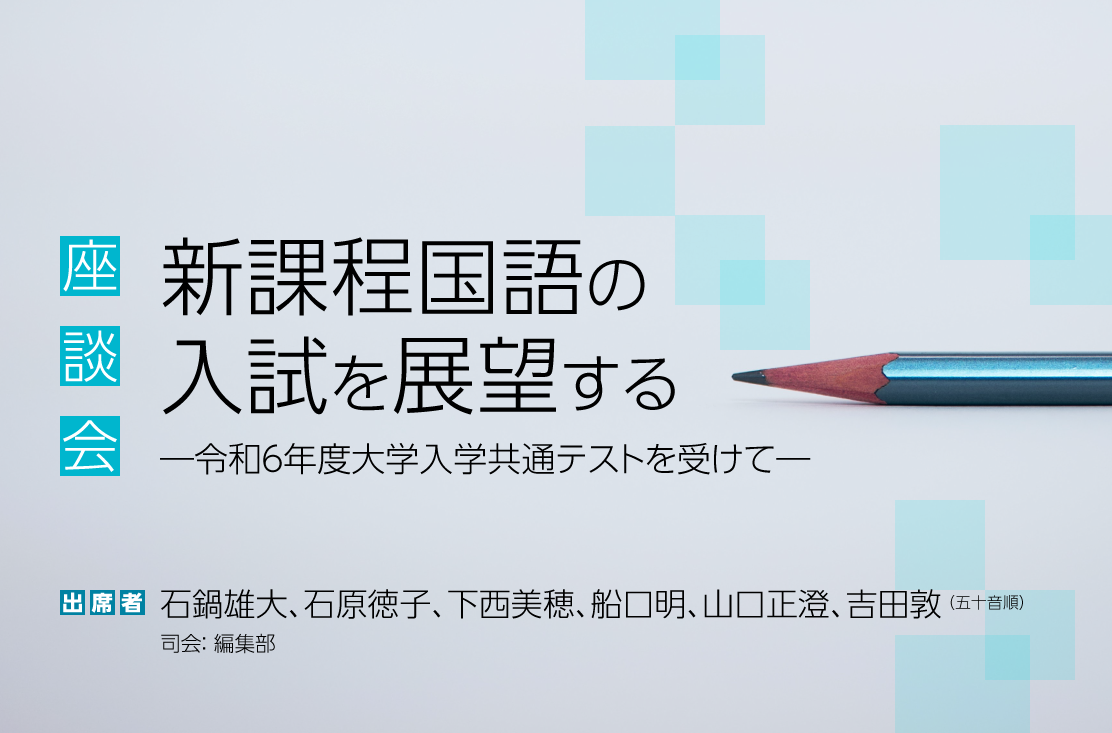〈インタビュー〉阿川佐和子
コミュニケーションにマニュアルはない 大切なのは相手に興味をもつこと
阿川佐和子
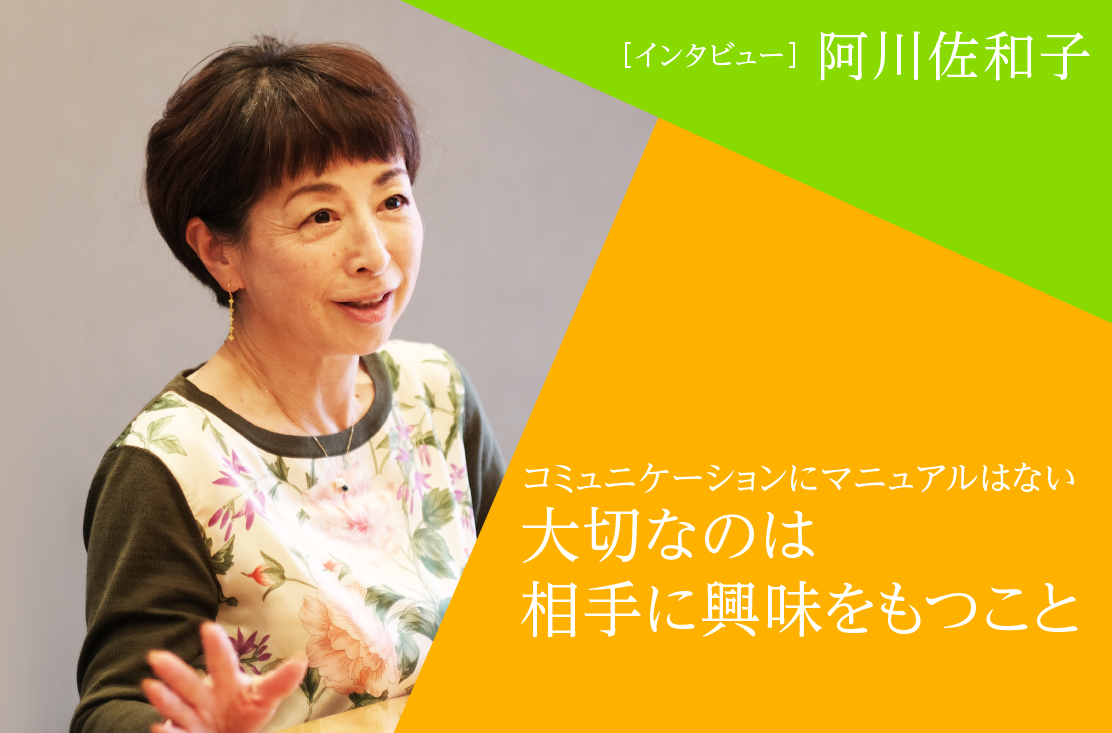
コミュニケーション能力が重視される今日。高校国語でも「話す・聞く」力の育成が求められています。コミュニケーションや対話、「聞く」力について、阿川佐和子さんにお話をうかがいました。
「聞き書き甲子園」と高校生たち
──「話すこと・聞くこと」について、高校生にお話をされることもあるそうですね。
もう15年ぐらい前から、林野庁などが主催している「聞き書き甲子園」に、聞き書きのプロ、塩野米松さんと私が講師として呼ばれているんです。
山や海で働いている人たちにインタビューする高校生に向けて、「行ってらっしゃい」と送り出すときと、「お帰りなさい」と迎えるときと、年に2回イベントを開く。8月に送り出すときには塩野さんと2人で、子どもたちにエールを送るような講演をしています。高校生は夏休みを使って山や海に行き、帰ってきて、レポートを書く。3月には成果発表会があって、5人ぐらいのレポートが優秀作品として選ばれる。名人とそのレポートを書いた高校生を舞台に上げて、私と塩野さんが感想を聞くんです。
「聞き書き甲子園」は、高校生100人を全国から募って、その地域の名人といわれる人たちとタイアップさせる。この子は宮崎だから、この辺りの焼畑のおばあちゃんを訪ねたらどうかとか、仙台だったら、ここにいる椎茸作りの人と会わせようだとか。
後継者なんてもう諦めているような人たちのところに、突然、「すべてを語ってください」と高校生が訪ねてくる。最初は、高校生もどこからどう質問していいかわからない。だから、ずっと黙っていると、名人のほうが心配になって、一人でしゃべりはじめる。頼りないと思うと、質問される側もなんとかしなきゃかわいそうだと思うんですね。そんなふうに、訥々と高校生相手に話した結果、発表会で「今まで家族にも自分の仕事なんて語ることなんてなかったけども、こうやって語ることがうれしかった」と振り返る名人がたくさんいらっしゃいました。そういう意味でもやりがいがあると思います。
そうやって書き上げた作文なんだけど、優秀作品に選ばれた子に「将来は?」なんて聞くと、「いや、サッカー選手になりたいです」と。「だからって人生変わったわけではありません」みたいな感じが、素直でいいんですけどね。
ほかにも、「通うのがつらかったです」とか、「帰ろうと思ったら嵐にあって泊めてもらいました」とか、いろんな出会いがある。志の高い子ばかりが集まっているわけでもない。でも中には、受験があるからそんなことにかまけている場合じゃないだろうって親に反対されても、どうしてもやってみたかったという女の子もいましたね。
コミュニケーション能力は本当に必要か?
──高校生がコミュニケーションを学ぶことについて、どうお考えですか?
近年、社会に出るにあたってコミュニケーション能力が必要だとか、就職の場でコミュニケーション能力がものすごく求められていると言われるようになっているみたいですね。私が続けてきた仕事の中にいくつか、小さなコツやノウハウというものは、ないわけではない。でも、『聞く力』なんて本を出しておいて言うのもなんですけど――これだけやれば大丈夫、すべてマニュアル化できるというものはないと思っています。
むしろ最近思うのは、コミュニケーション能力ってそんなに必要か? ということです。今は、コミュニケーション能力がないと優秀じゃないとか、社会で活躍できないとか、人に認められないという強迫観念にかられている時代なんじゃないかと。私はインタビューでさまざまな分野の人たちに話を聞くけれど、世の中でいろんなかたちで大成している人でも、子ども時代に必ずしもコミュニケーション能力が優れていたわけではない。むしろ、真逆だったという人のほうが多い気がする。人とどう接すればいいか、自分の好きなものをどう表現していいか、人にどう伝えればいいかということがわからない。もう悶々と、悶々として、大きくなったら小説家で、歌手で、役者でボカーンと爆発するという人は、案外多いんですよ。
若いころから周りとの関係を作るのに長けている人だけが、自分のやりたいことや、いたい場所を見つけることができるかというと、そうとも言えないんじゃないかと思う。ただ、教育というのは、網羅的にある程度の水準に持っていかなきゃいけないから、ある程度は教える必要があるかもしれない。でも、水準に達しない子どもがいたとしても、だめだと決めつけたり、子ども自身が自分はだめなんだと思い込んだりする必要はまったくないということを、ちゃんと言っておかないと。それぞれに、ほかに何か能力があるかもしれないし。
たとえば、小説家の角田光代さんに初めてインタビューしたとき、「九九は苦手なんです」っておっしゃるのね。「じゃあ、8×9は?」とたずねたら、「そういう大きい数字はだめなんです」と。「じゃあ、どこまで?」と聞くと、「5×5まではできます」。あれだけ素晴らしい日本語を書く人が、「8×9」ができないという落差に驚いて、笑っちゃって、そのインタビューは終わったんです。
 この間、もう一度角田さんにインタビューする機会があって、あらためて伺ったら、幼稚園のときから、コミュニケーション能力がなかったんですって。友だちに自分の気持ちをどう表していいか、先生にどう言っていいかがわからなかった。ケガをしても「ケガをした」ということを先生に伝えられなくて、うちへ帰って、「なぜ先生に言わなかったのか」と聞かれても、それにも答えられないという、自分でもどうしようもないジレンマの中で苦しんでいた。
この間、もう一度角田さんにインタビューする機会があって、あらためて伺ったら、幼稚園のときから、コミュニケーション能力がなかったんですって。友だちに自分の気持ちをどう表していいか、先生にどう言っていいかがわからなかった。ケガをしても「ケガをした」ということを先生に伝えられなくて、うちへ帰って、「なぜ先生に言わなかったのか」と聞かれても、それにも答えられないという、自分でもどうしようもないジレンマの中で苦しんでいた。
そしたら、小学校に入ったとき物語に出会ったんだそうです。物語の世界に魅了されて、ワクワクしちゃった。言葉と言葉をつなげると、物語になるということを知って、小学校低学年で「私は小説家になる」と決める。そんな職業があると気づくこと自体がすごいけど、物語を作る人間になると決めるんですよ。果敢な少女だと思いますね。そのとき、小説を書くために必要な学問以外はいらないと思ったんだそうです。算数の授業も理科の授業も出なくていいと思って、だから九九ができないんだって。
そういうアンバランスを背負いながら、物語に出会ったときに角田さんは解放されたんですよね。今は楽しい方だし、おしゃべりもできるし、いろんな人たちと接していらっしゃると思います。だけど、何をしたいかわかるまでに、時間のかからない子もいれば、時間のかかる子もいる。何にワクワクするかも人によって違うことを知って、衝撃を受けちゃったんです。
「待つ」ことができない現代
少し前までは、会社に入っても、学校に入っても、しばらく様子を見てもらえる時間があったと思うんですよ。ところが今、社会がものすごくスピードアップしているから置いていかれる不安があって、遅れると取り返しがつかないという精神状態になる。昔のほうがよかったとか、楽だったとはいわないけれど、少なくとも違うのは、スピードのような気がするんですよね。
新幹線もそうだし、電話もそうだけど、日本の文明の進歩というものは、速く行けて便利、速くできて便利ということを追い求めてきた。だけど、人間の脳みそは科学ほど順応性がない。人によってもスピードが異なるのに、「みんなと同じスピードで走りなさい」となると、どうしてもついていけない人間が出てくる。それを「しばらく待ってみよう」という場所も時間もなくなっているでしょう。
昔は、家族がもっと大勢いましたから。家の中で、お母さんとうまくいかなかったら、おばあちゃんがいるとか、おじいちゃんがいるとか、近所の人がいるとか、逃げ道があった。今はそういう逃げ道が少なくなっているし、先生も先生で、子どもだけを見つめていればいいという時代じゃなくなっていますものね。
今は理想の子どもに育てるんだっていうエネルギーが集中しているから、親御さんも子どもから目が離せないようですね。小児科のお医者さんもおっしゃってました。お母さんと一緒に来た子どもに「今日はどうしたの?」と聞くと、「おなかが痛いっていうんです」とお母さんが答える。「いつ痛くなったの?」というと、「きのうの夜からなんです」。「どういうふうに痛い?」「ずっとシクシクするっていってるんです」と。「いや、この子に聞いてるんで、お母さん、黙っててください」という現象が起こる。お母さんは心配でならないし、正しい方向に導くのは自分だと思っている。それも大事かもしれないけど、ちょっと放置してみることが誰もできなくなっているなと思って。
自分独自の世界でどう判断するかということを、何回も経験しているうちに学んでいくんだと思うけど、どうも今、大学を卒業するまで常に助け舟がいるらしい。だから会社に入ると、上司にちょっと怒られただけで泣いちゃったり、辞めちゃったりする社員が多い。社会環境もあると思うけど、やっぱりやわになっている気がしますよね。自分がだめでもともと、失敗して当然、みんなに笑われてオッケーと気楽に考えればいいのに、用心深すぎる気がします。
先生の役割とは
私はアメリカにいたとき、ワシントンのスミソニアン博物館の中の保育所で、ボランティアとして幼児部のアシスタントをしていました。アメリカは進んでいるからなのか、コミュニケーション能力の育成にしっかりしたメソッドがありますね。
たとえば、4〜5歳の子に、日直みたいなものを任せるんです。1日に2人、君たちがリーダーだよって。子どもたちはリーダーになる日、自分の宝物を持ってきて、みんなに披露する。これはどうして自分にとって宝物なのかをスピーチするの。「これは去年、おじいちゃんにクリスマスプレゼントに買ってもらって、これは機能的にこういうところが、ぼくは気に入っている。ここを押すとこうやって動くんだ」と。機関車でもなんでもいいんだけど、とにかく宝物に関するスピーチをする。
それで、「これを1日どうする?」って先生が聞くのね。そうすると、「ぼくが見ているところならば、触ってよろしい」とか、「絶対触っちゃだめ」とか、「好きに触っていい」とか、どう取り扱うかをリーダーが決める。その約束は守るようにということで1日過ごすんです。この年頃からスピーチをしているのかと思ったら、すごいですよね。もちろん、みんなが優等生じゃないし、できない子もいるかもしれないけど、自分の番は必ず回ってくる。
それと、もう一つ驚いたことがあって。この保育所はスミソニアンの博物館の一角にあるから、自然史博物館とか、アメリカ歴史博物館とかに、ぞろぞろと二列縦隊でみんなで行く。そこに学芸員のお母さんがいたりすると、時間が空いていれば、子どもたちを案内してくれたりする。
あるとき、保育士の先生が、「今日はみんなで美術館に行く。みんなが見に行く絵は先生もまだ見てないんだけど、ものすごく大きな抽象画だ」っていうんですよ。4〜5歳の子に抽象画見せるのかなと思って聞いていたら、「すごく大きな絵なんで、絵描きさんは何日もかけて描いたんだ」と話し始める。「何日も何日も、朝から晩までアトリエで描き続けてた。ある朝、さあ、今日も描こうと思ったら、描きかけの絵の中にゴキブリが一匹ベタッとくっついていた。うわっと思ってどけようとしたんだけど、面倒くさいと思って、その上からペイントを塗っちゃった。だから、今日みんなが見る絵の中にはゴキブリが一匹潜んでる。さあ、探しに行こう」。
子どもたちにこう話してから出発するの。私の記憶では、グレーと黒とブルーと白の、幾何学模様が描かれた大きな絵でしたけど、確かにゴキブリの跡みたいのがあるんですね。先生が話したことは事実なの。私がその跡を見つけたら、「サワコ、すごーい」と褒められた。
私がびっくりしたのは、先生は、抽象画とは何なのかとか、これは誰が描いた絵だとか、国宝だとか、何も教えないこと。コックローチがいるんだということしか教えない。絵を見た後も「さあ、ランチタイムだから帰ろう」と帰っちゃう。それでどうなるかを想像すると、子どもたちの心の中には、コックローチがいた絵だということしか残らない。だけど、中学生になってまた美術館に遊びに行ったとき、「俺、コックローチのいる絵知ってるよ」と、友だちに教えてあげるかもしれない。そのときに、「あ、隣にもちょっと色違いがあるんだ」と気づくかもしれないし、「抽象画って何なんだ?」と疑問をもつかもしれない。
その絵に近づくきっかけだけを作ったら、あとは放置するという考えなんでしょう。これはすばらしい教育だなと思ったんです。つまり、先生というものは、興味をもつきっかけを与えることを、正しいか正しくないかを教えるより優先するべきなんじゃないかと思いました。そこから先は、もしかするとちゃんと勉強するかもしれないし、「いや、数学のほうが好きだね、俺は」と思うかもしれないけど。
そういえば、本郷和人先生という日本史の先生も、同じようなことをおしゃっていましたね。今は大学受験の影響もあって、歴史が暗記科目になっちゃったことを憂えてらした。たとえば、「承久の乱は1221年」と。本当は「承久の乱を機に、朝廷から幕府へと完全に実権が移って、明治維新までずっと武家社会が続いた」とか、歴史の見方のおもしろさをもっと伝えたい。年号とか単語を暗記するだけだから、子どもたちの歴史離れが起こるんじゃないかと。それで、「大学受験に日本史を入れなかったら先生方は自由に教えられて、もっとおもしろい授業ができるようになるだろう」とおっしゃっていたのね。
暗記した点と点とを線でつなぐと、奥行きとおもしろさが変わってくるということを、学校でも教えてくれるといいなと思うんです。それこそ国語なんて正解のないものだから、まず興味をもたせて、おもしろいと思わせることが大事なんじゃないかな。
一人一人と向き合う教育を
今の子たちが何に関心をもつのかはわからないけど、友だちを作りたいと思うのはコミュニケーション能力の一つですよね。私が中学生になったとき、あの子とお友だちになりたいなと思って「かわいいね、そのスカート」と話しかけたという昔話を同級生とよくします。「つまんない話題から始めたよね、私たち」って。でも、気がついたことをどういうふうに持ち出すか、一言からどう波紋が広がるかが大切です。だから、会社に入るためのコミュニケーション能力を身につけましょうなんて言うよりも、「友だちになりたいと思っている子に話しかけるとき、どんな話題を選ぶ?」と生徒に問いかけて、「あ、その手があるか」とか、「あ、自分だったらこれだな」とか気づかせることができればいい。正解はなくていいと思うんです。
──学校の先生はどういう態度で接すれば、生徒が自分の考えを話せるようになるのでしょうか。
聞く側の人間である先生とかインタビュアーとか司会が、精一杯尽くしているけど、完璧じゃないところもあることがわかると、子どもは安心する。いざというときは、あなたたちを守るけれども、だからといって、完全な人間ではない。人間とはそういうものであって、だめなところがある。だから、謝るときには子どもにだって謝る。「ごめんなさい、私が間違っていました」と言える先生は、信頼できるんじゃないかな。
ただ、この先生はちゃんとみんなを、一人一人を見てくれているという絶対的な確信さえもってもらえれば、先生が間違ったっていいんじゃないですか?
むしろ子どもに教えてもらうこともあるかも。でも、「あなたに大変興味があります」という心は、いつももってないといけない。ちゃんと聞く気があるし、おもしろいと思っていますと態度に示すことは、いわば先生から生徒に対する愛みたいなもの。だから、少子化は学校のビジネスとしては問題かもしれないけれど、今がチャンスなんじゃないかな。子どもの数が少ないからこそ、一人一人が見えてくるんじゃないかと期待しています。
(2019年2月12日、聞き手:編集部)
『国語教室』第110号より転載
著者プロフィール
阿川 佐和子(あがわ さわこ)

エッセイスト、小説家。2012年『聞く力』が年間ベストセラーとなる。『週刊文春』の対談記事「阿川佐和子のこの人に会いたい」は連載1000回を超える。
一覧に戻る