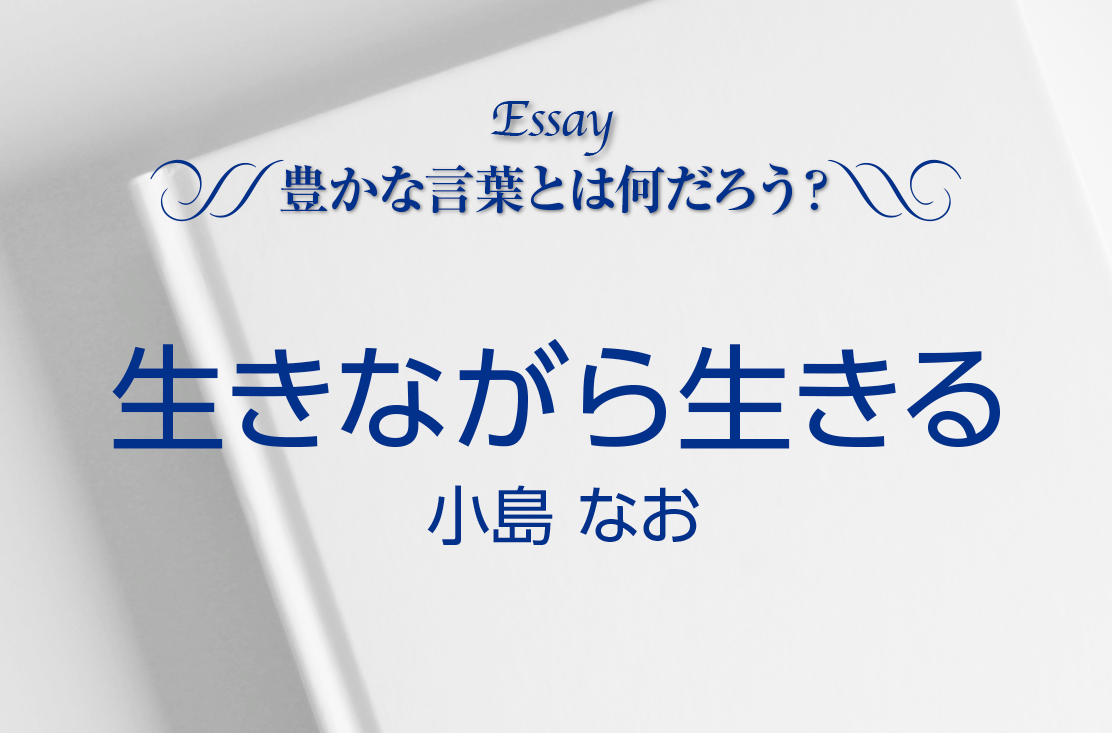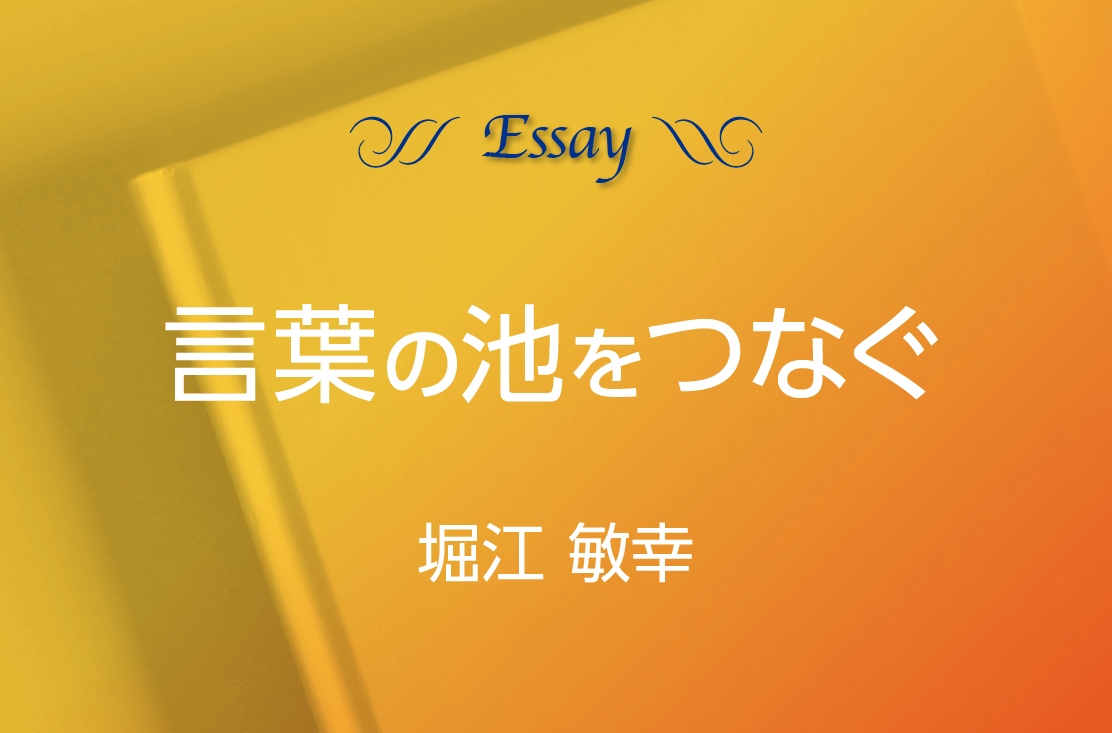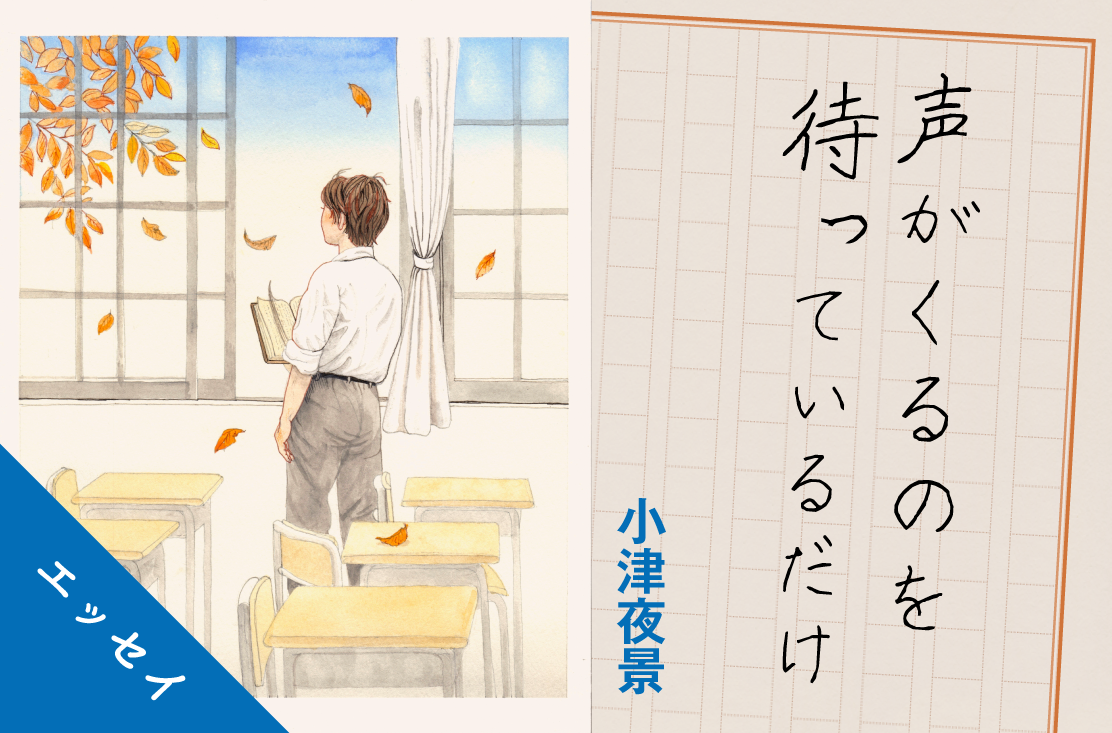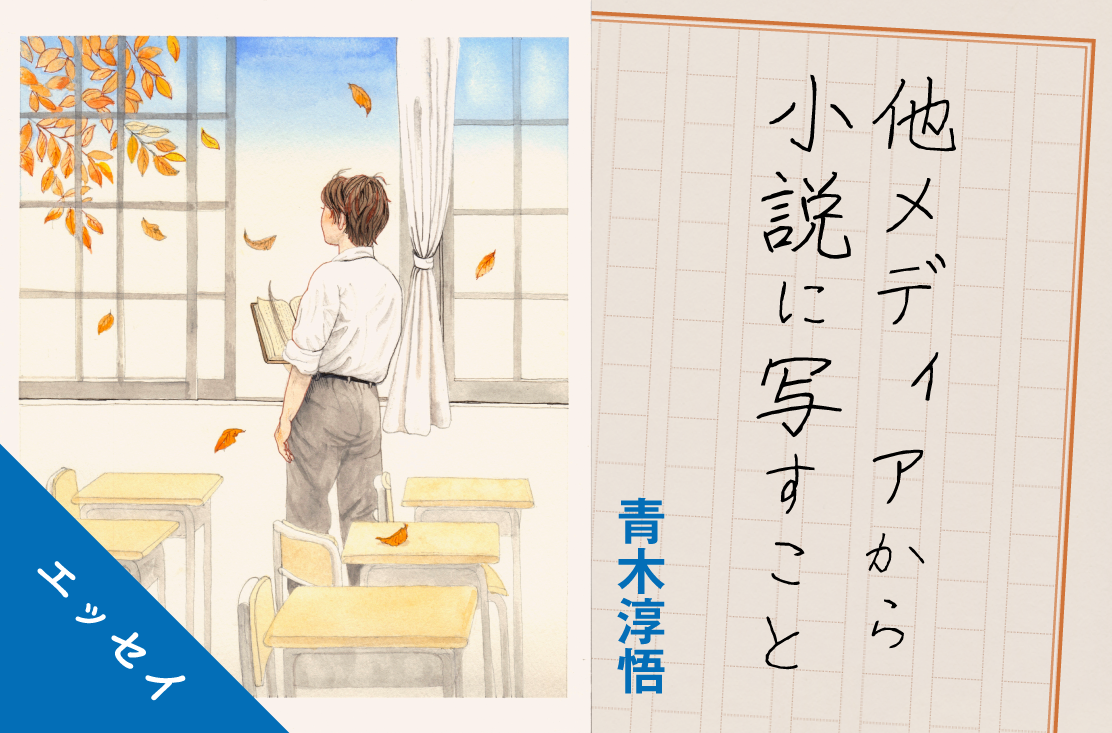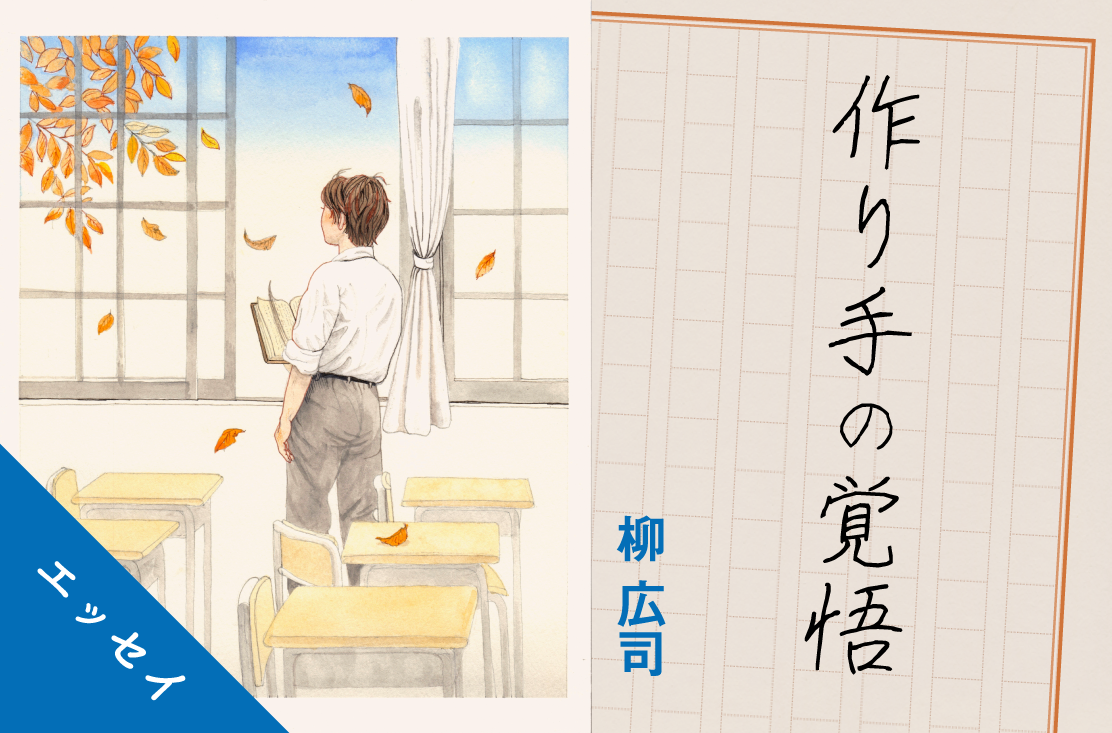エッセイ
探究学習の根っ子には「遊び」がある
竹内 薫
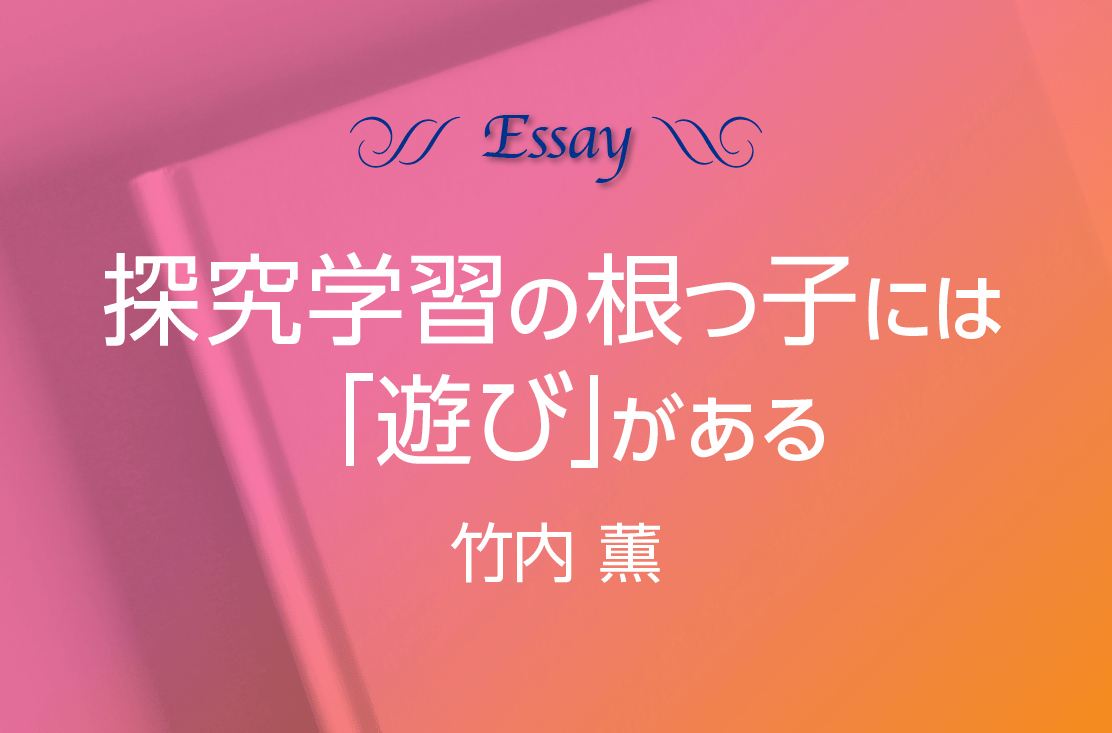
「探究」とはなんでしょうか。それを考えるには、反対語を頭に思い浮かべるのが一番。探究の反対語は「暗記」です。変化し続ける社会情勢の中において、探究と暗記という二つの行為が反対の意味を持つようになってきたのです。
なぜ、探究と暗記が反対の意味を持つようになったのかと言えば、第四次産業革命が進行しつつあり、とりわけ人工知能(AI)が台頭し、これまで人間がやってきた仕事を受け持つようになったからです。AIは「暗記」が得意中の得意。世界一、暗記力がある人間よりも、AIのほうがたくさん正確に暗記できます。
でも、いまのAIには「自我」(言い換えると、意識や心)がありません。だからAIは探究が苦手なのです。探究とは、自分で考え、深く追究することを意味しますが、そもそも自我を持たないAIは、命令された計算をやっているに過ぎないのです。
これまで、日本に限らず、世界中で、学校のテストや受験において、暗記力が試されることが多かったように思います。しかし、これまでのような勉強法だと、社会に出てからAIに仕事を奪われてしまうという考えのもと、探究学習を取り入れる国が増えてきています。
この流れは誰にも止めることができません。それはビジネスの世界において、人間よりもAIがやったほうがコストが下がる、という仕組みがあり、コストを下げ続けないと企業が競争に負けてしまうからです。
私には12歳になる娘がいますが、ここ10年ほど、AI技術の最前線を取材しながら、どうやったら娘が社会に出ても食いっぱぐれないのかを必死に考えてきました。
私の結論は単純でした。AIと同じ土俵で戦おうとするからAIに仕事を奪われてしまうのだ。それならば、AIが苦手な仕事をすればいいではないか。つまり、暗記型の仕事ではなく、探究型の仕事に就けばいいだけの話ではないのか。そのためには学校にいるときから探究型の発想法や行動に慣れる必要がある。
でも、これまでずっと暗記型の授業を続けてきた先生や生徒のみなさんに、「はい、今日から探究型の授業をしましょう」と言っても、すぐには切り替えられませんよね。
私はここ7年ほど、探究型の授業を実践してきました。自分でフリースクールを設立し、現場で試行錯誤を重ねてきたのです。そこで、ここで探究型の授業について、私なりのコツを書いてみたいと思います。と言っても、そんなに難しいことではありません。
まず第一に、暗記をゼロにして、何も覚えなくてもいい、ということではありません。探究学習をする場合も、基礎となる知識は必要です。基本的な漢字が書けたり、百人一首を覚えたりして、悪いわけがありません。最低限の暗記はしてもいいのです。
次に、誰しも子供の頃は、いっぱい遊んだはずですが、その遊び心を思い出してみて、ということ。探究心は遊び心に通ずるところがあります。私はたくさんの取材を通じて知りましたが、探究心旺盛なノーベル賞受賞者の多くは、子供の心のまま大人になり、学問の世界で真剣に遊び続けている人々なのです。
ええと、趣味で好きなことをしているときは、強制されなくても、自然と楽しく学びますよね? あるいは、試験前に急に好きな小説を読みたくなったり、ゲームをやりたくなったりしたことはありませんか? それこそが探究なのです。
これまでの窮屈な授業を少しずつ変えていって、みんなが楽しく遊んでいるような雰囲気になったときこそ、みなさんは探究型の授業に移行できたのだと私は思います。
私の授業では、生徒を5〜8名のグループに分けて、論理パズルの解き方を発表してもらったり、ルービックキューブで競ったりしますが、哲学や科学の文章の意味をみんなで「解読」することもあります。
みんなが楽しく笑いながら文章の意味を考え、自由に意見を述べ合い、面白い創作を発表できたら、それは立派な探究授業だと言えるでしょう。
これまで勉強が苦しかったのは、意味のない暗記が多かったせい。でもこれからは、遊びの延長線上にある探究で勉強も楽しくなる。そう考えれば、AIの台頭は、決して恐ろしいことではなく、むしろ歓迎すべき変化だと思うのです。
『国語教室』第119号より転載

「探究する力」
AIの台頭など、目まぐるしく変化する現代社会。そこで生き残るために必要なものは自ら考え、「探究」する力だ──新時代を生きる生徒への熱く優しいメッセージ。
(『新編 論理国語』〔論国706〕)
著者プロフィール
1960(昭和35)年生まれ。科学作家。科学に関する評論やエッセイに加え、小説なども手がける。著書に『99・9%は仮説』『アバウトアインシュタイン70のミステリー』などがある。
一覧に戻る