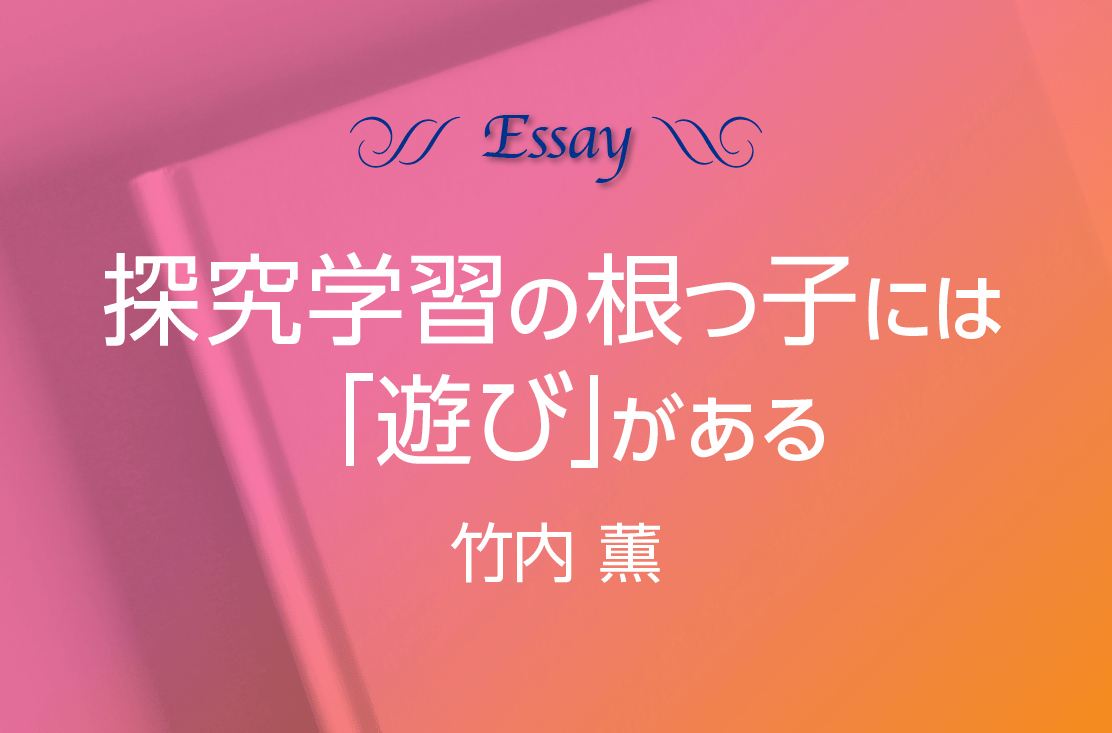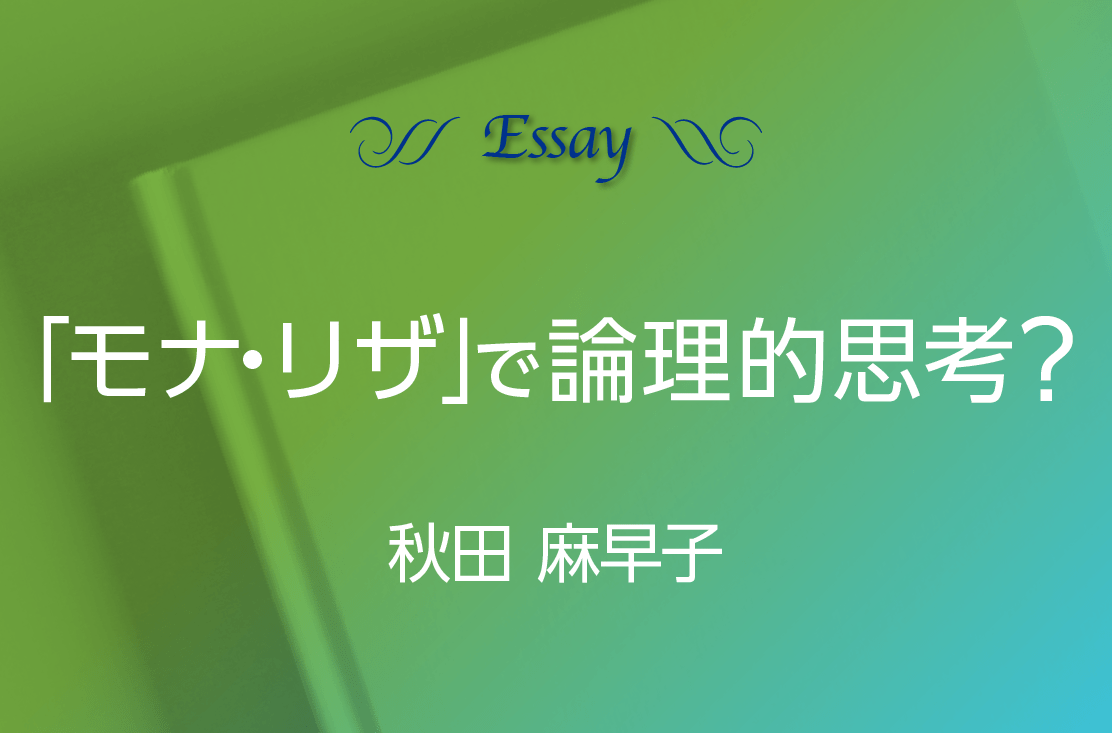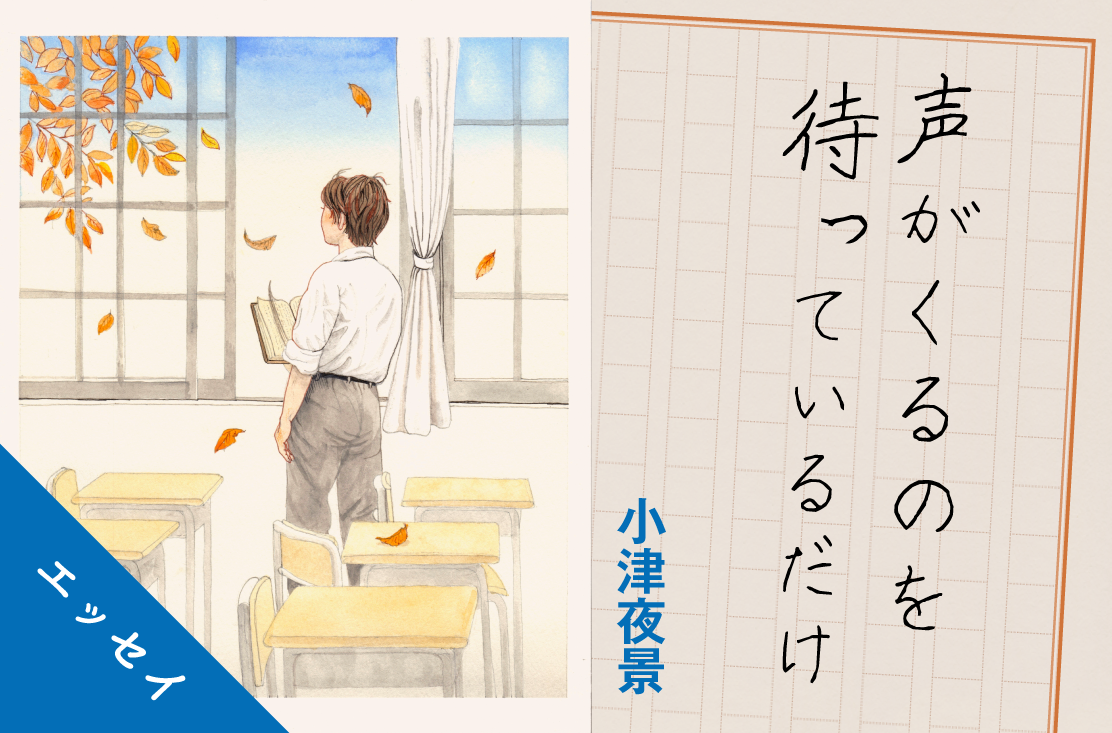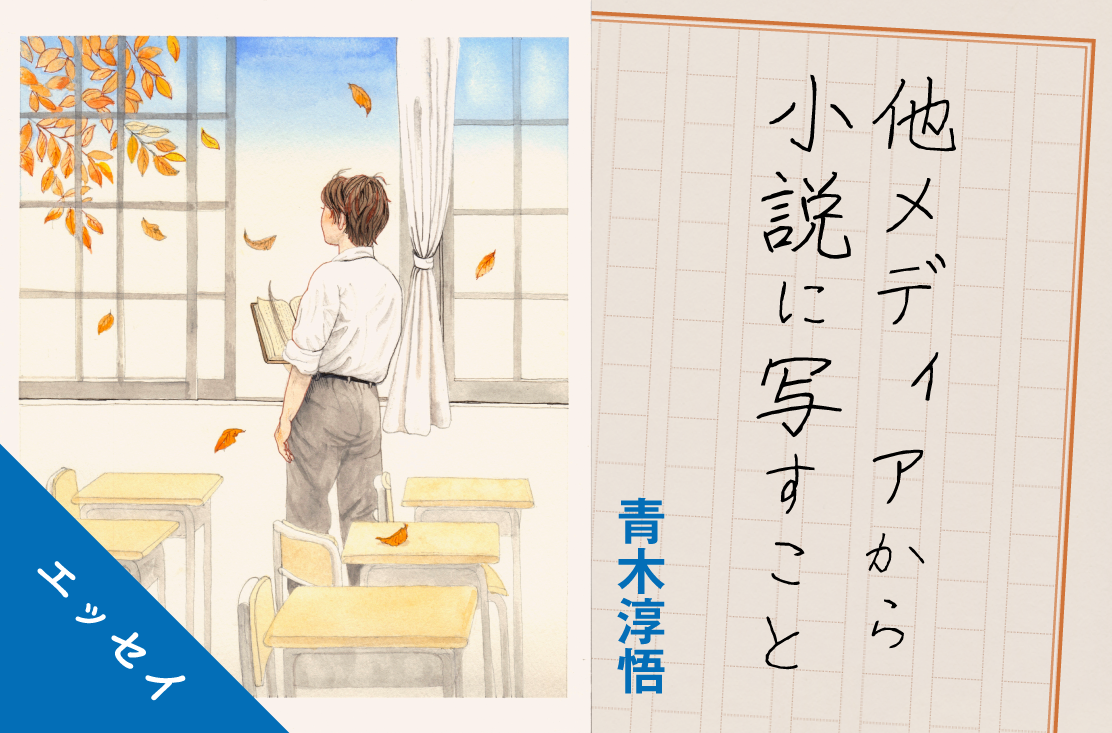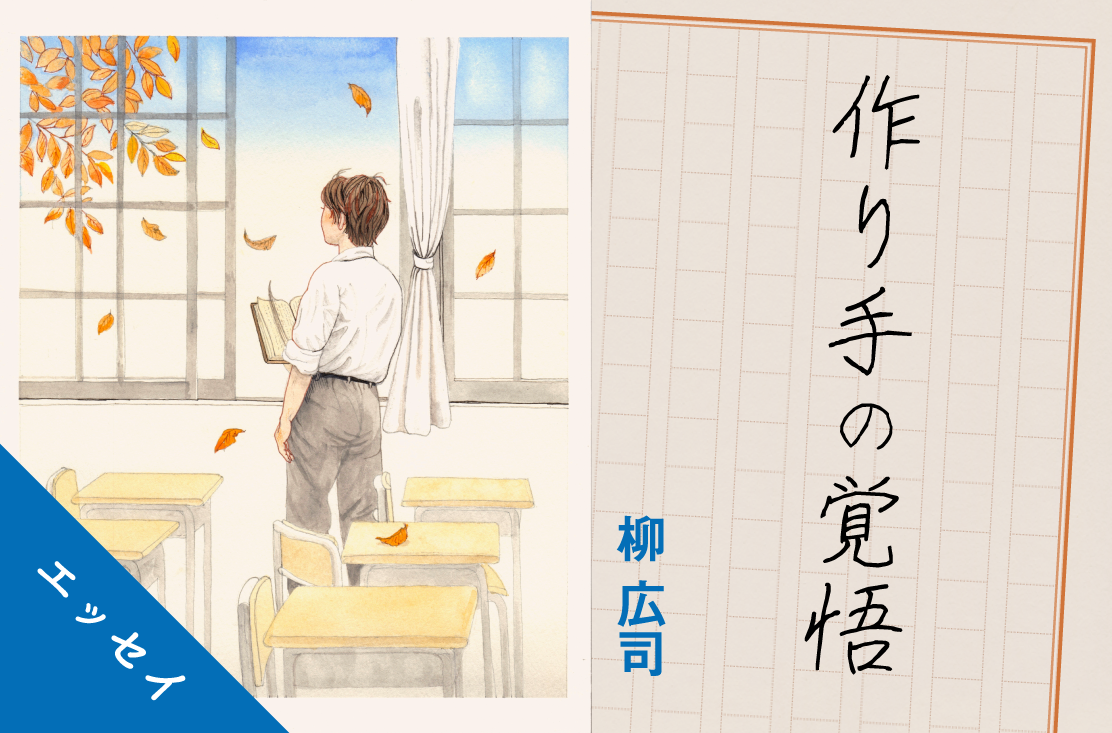エッセイ
言葉の池をつなぐ
堀江敏幸
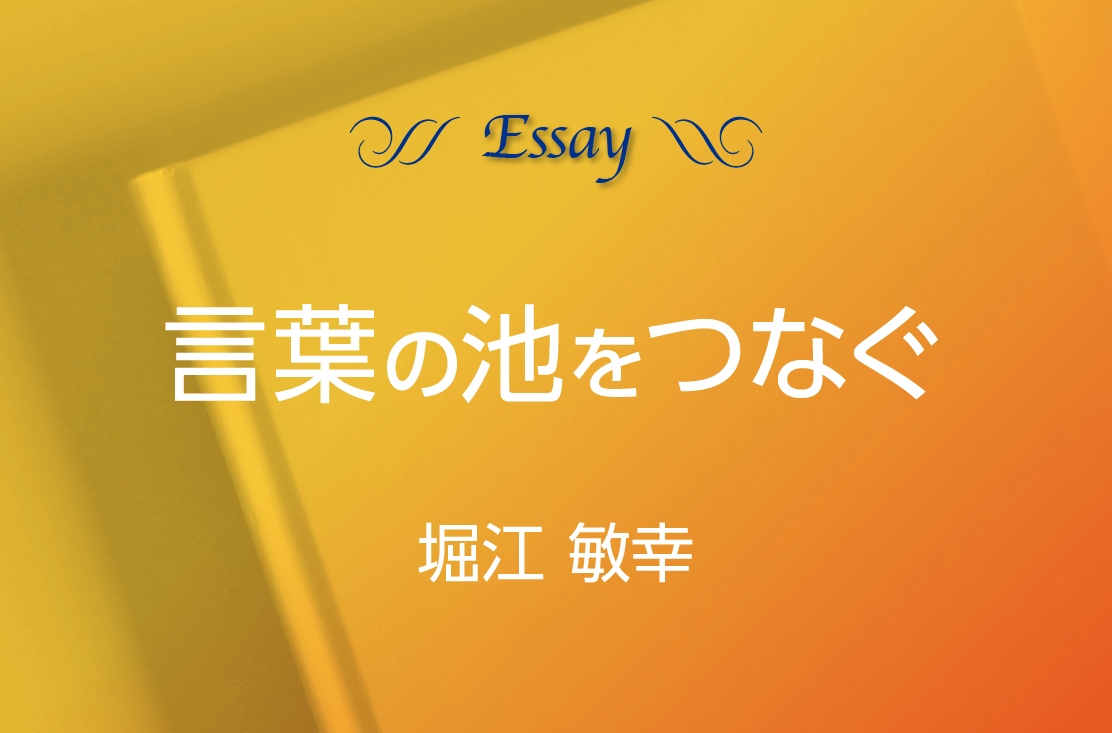
言葉で表現できないからこそ存在価値のある分野の作品に接したとき、湧きあがってくる想いを野放しにしないで、なんとか心のうちにとどめておきたいと考えるのは、ごくふつうのことである。たとえば一枚の絵の前に立って、描かれている対象をひたすら見つめ、そこから漂ってくる色彩の香りに身をゆだねて、二次元の音楽に耳を傾ける。なにがその絵を絵としてあらしめているのかを厳しく考えなくても、そこで味わった感覚を忘れたくない、なんとか記憶にとどめたいと願う心の動きが大切なのだ。
ただし、記憶にとどめる器はふたつある。ひとつは直接的な身体感覚をともなう記憶。もうひとつはそこから少し距離を置いて選び取った言葉。前者は一種の触媒と言ってもいい。あとから出会ったべつの作品が過去の記憶の一部と化学反応を起こし、眼前の絵に対して抱きつつある想いと二重写しになる。すると、以前は気づかなかった部分が鮮明に見えてきて、よみがえってきた絵のどこに惹かれていたのかを自問する貴重な機会となるだろう。体験はこうして生き直され、来るべき反応に備えて貯蔵される。
重要なのは、自分のなかにという点である。いくら反芻しても、留め置かれた個人の体験をそのままの形で外に出し、他者にぶつけることはできない。当然ながら、それを伝えるには、どうしても言葉に頼るしかない。言葉を必要としない作品のすばらしさを他者と共有するために言葉を用いるというのはなんとも大きな矛盾だが、その矛盾を乗り越えなければ伝達も共有も継承も不可能になってしまう。
それだけではない。これはよかった、あれはよかったと相槌と同意に近い感想を述べあい、互いの印象を肯定しあうことに留まっていたら、どこがどうよかったのかが明確にならないだろう。もちろん対話をつづけているうち、ふと相手が口にしたひとことで、不意に視野が開けることもある。小さな、わずかな言葉が、受け手にとっては生涯忘れられない決定的な指標にもなりうるのだが、口にした当人は、単なる思いつきであって十分に考え抜いた表現ではないと言うかもしれない。たとえそれが本当であっても、寸評の切れ味と即効性は、どれだけの言葉を体内に寝かせてきたのかによって、さらには言葉と言葉をつなぐ未発見の経路をどれだけ内蔵しているかによって効き目がちがってくる。無意識の発言であっても、いや、無意識の発言だからこそ、言語化という過程への向き合い方が露わになるのだ。人に伝え得たひとことは、結局、自分のために時間をかけて育ててきた思考のかけらなのである。
とすれば、絵画や音楽作品についての想いを言葉で他者に伝えることと、言葉で書かれた小説や詩歌などから得た感動やつまずきを語ることとのあいだに、本質的な差はなくなってくる。なぜそのような言葉で語られなければならなかったのかを考えることは、すぐに解き明かせない感情を辛抱強く煮詰めて言葉に変える作業と深く結びついている。
体験はそのつど身体に染みこんで、小さな池をつくる。池はいくつあってもいい。やがてその水を汲み出すための言葉が縁に添えられる。読書とは、こうした体験と感覚の池を自分のなかにいくつもこしらえていく作業である。ただ、それだけでは足りない。池と池を水路でつなげなければならない。最初は運河になり、それが自然な川のようになるまでには、ながい時間がかかる。急がずあわてず、体のいい時間短縮と効率の誘惑に屈することなく、点と点を結ぶ流れができたあとも、周りに取り残された池に対する注視を怠らないことが望ましい。川がゆるやかに蛇行し、湾曲部分が土砂の堆積で分離されて三日月湖ができても、最初から点在していた池とはまったく異なる力がそこに宿っている可能性を棄ててはならないだろう。
口頭でなにげないひとことを発する土台は、こんなふうに徐々に整備される。自分の感覚が言葉として共有されることがわかると、今度は書くことへの通路が開かれる。書くこともまた、池と池の連結を目指す息の長い作業であり、それが読むことをさらに豊かにしていく。この幸福な循環を裁ち切ってはならない。本を読み、読んで書き、また読んで言葉と対話した想いを人に伝えよう。際限のないこの沃野に身を委ねる喜びが、自分だけのものであってはならないのだから。
『国語教室』第119号より転載
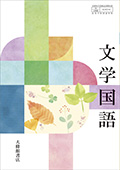
「負の座標に向かって」
単色でありながら単一の色ではない、真っ青な空。青空に覚えた不安の正体に考えをめぐらせる、第二部冒頭単元の随想。
(『文学国語』〔文国704〕)
著者プロフィール
早稲田大学文学学術院教授。小説家、フランス文学者。岐阜県生まれ。『おぱらばん』で三島由紀夫賞、「熊の敷石」で芥川賞など、数々の賞を受賞。著書に『雪沼とその周辺』『坂を見あげて』など。
一覧に戻る