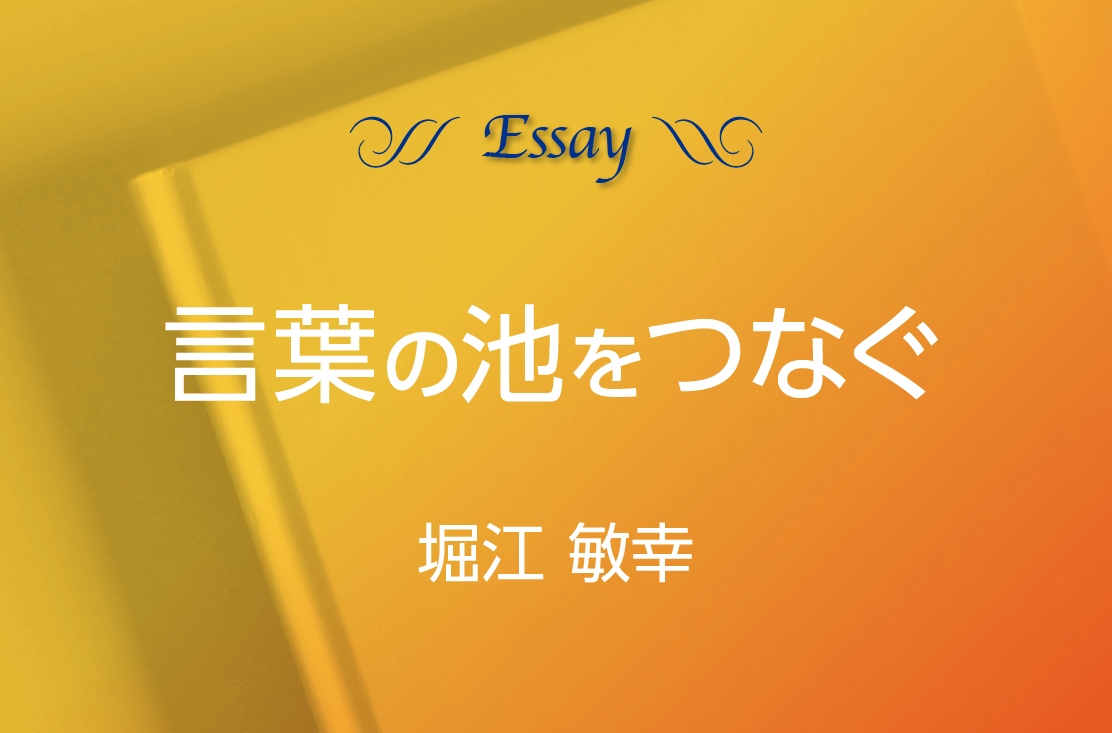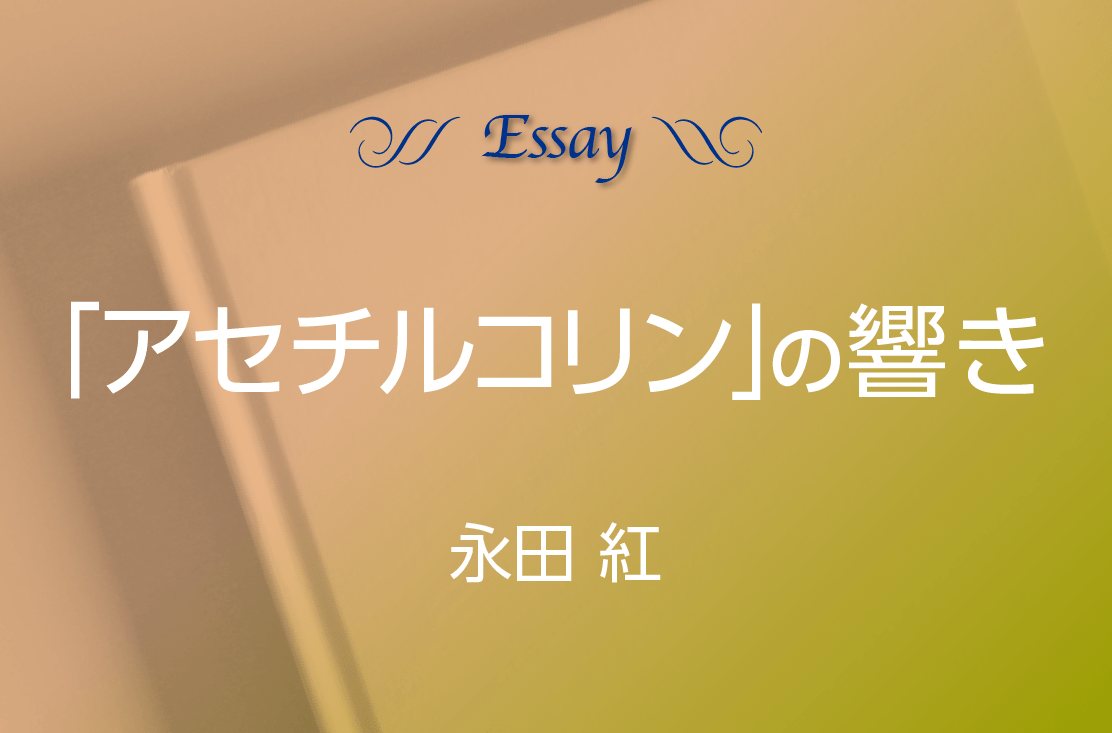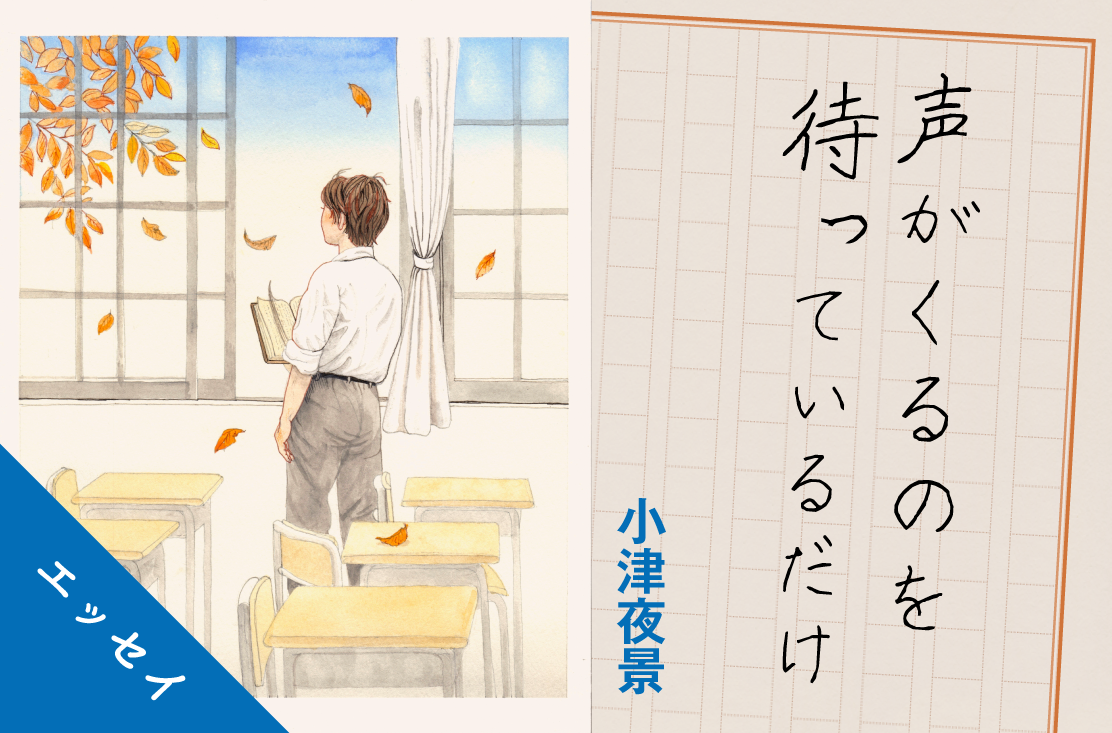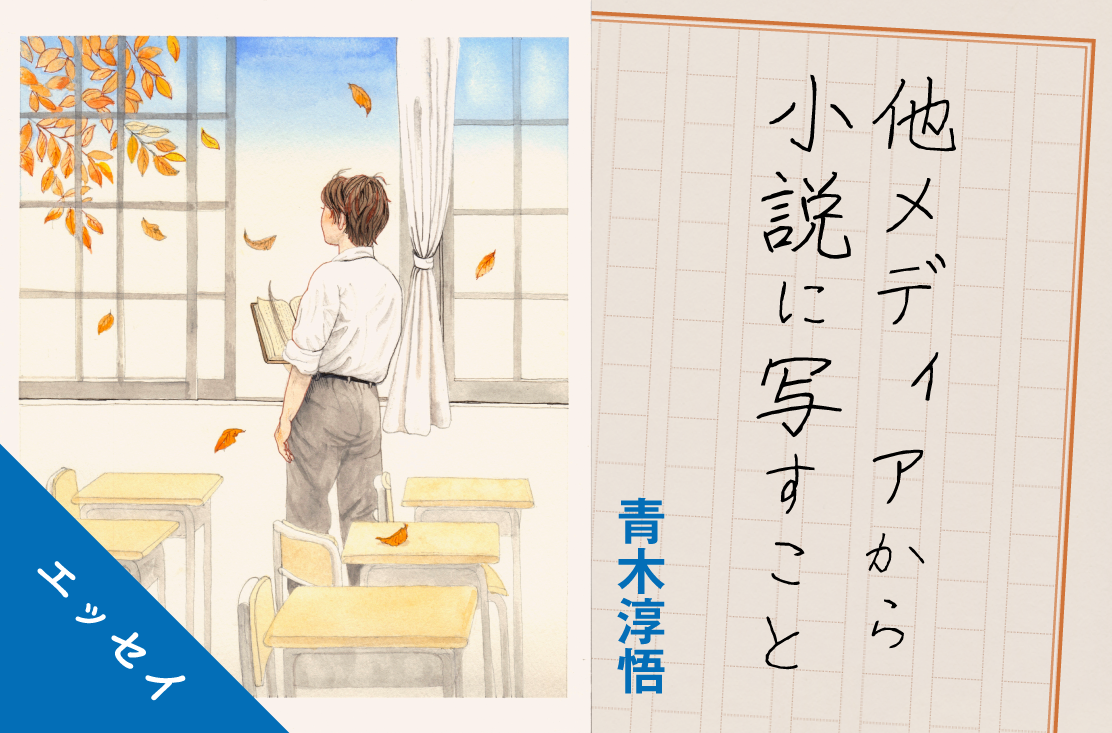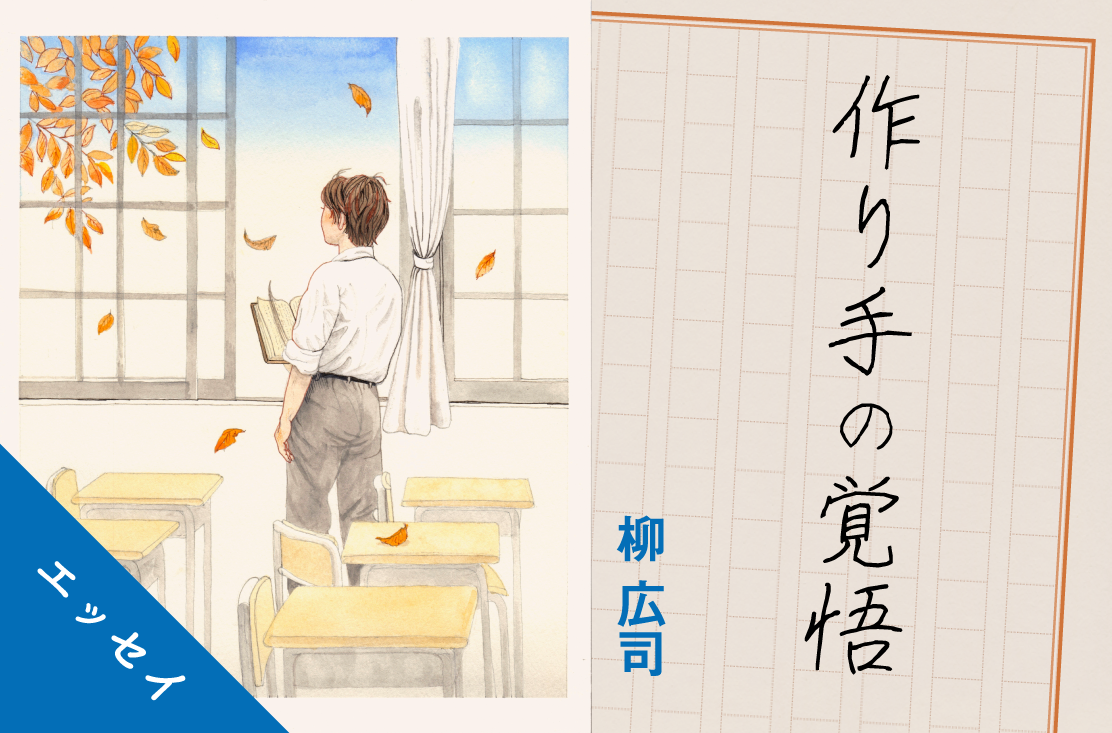エッセイ
「モナ・リザ」で論理的思考?
秋田麻早子
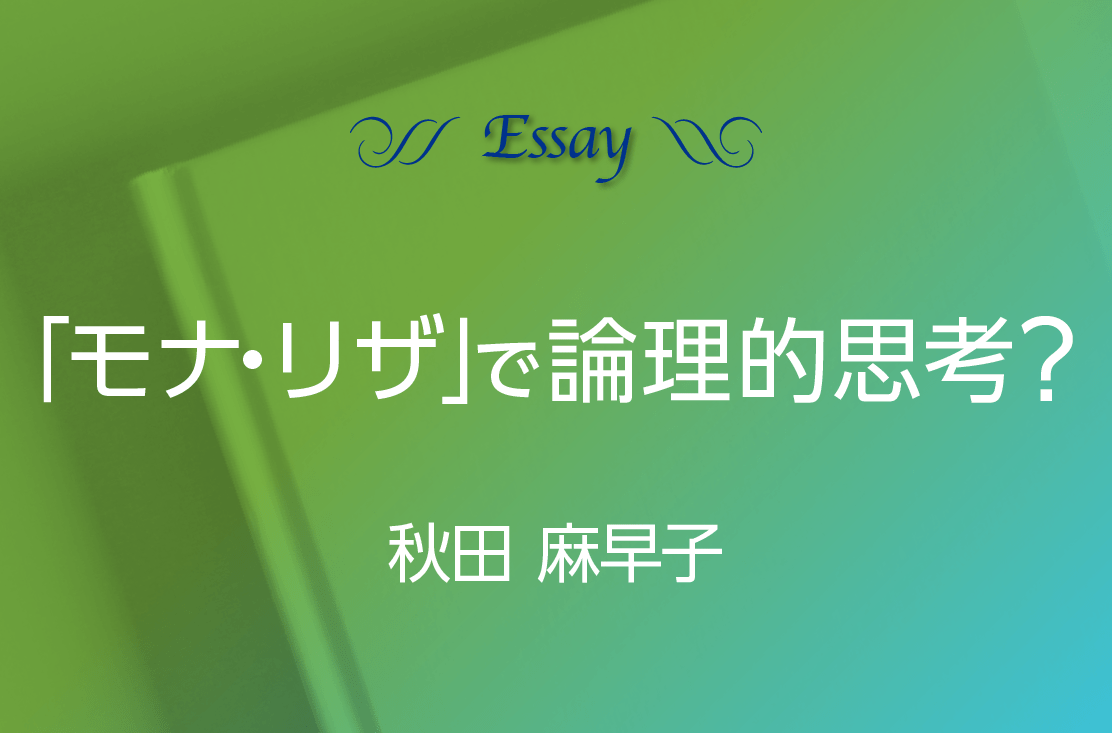
「論理国語」になぜ絵画の見方が出てくるのかと、疑問に思った人も多いでしょう。絵画の話になると、感覚的なものだと思いがちです。論理的な思考は言葉や数式で行うもので、直観的に把握する絵画の世界とは相容れないものだと思うかもしれません。また、芸術作品について理屈っぽい話をするのは野暮だと感じるかもしれません。
では「論理国語」で「絵を見る技術」を取り上げるねらいはどこにあるのでしょう。まず、絵画に限らず図版一般から情報を抽出する方法を学ぶこと、そして、思考の枠組みについて学び、ものの見方を広げるということも、ねらいとして考えられるのではないでしょうか。ひとつ目のねらいはともかく、あとのねらいはすぐにはピンと来ないかもしれません。
どういうことなのか、有名な絵を例に考えてみましょう。レオナルド・ダ・ヴィンチ作「モナ・リザ」という絵があります。その絵に対し、あなたはどんなことを感じ、思い、考えますか? また、他の人の意見を聞いたとき、どんなことを考えましたか?
ある人は「世界一有名な絵」、別の人は「ルネサンス時代の傑作」と言うかもしれません。また、「暗い」「怖い」「不気味」と言う人も、「売ったら高そう」と言う人も出てくるでしょう。
これらは全て違う意見ですが、ちょっと考えてみると、それぞれ違う観点で見ているのだと分かります。言い換えると、違う枠組みで見ているのです。
最初の意見は「モナ・リザ」が歴史的・社会的にどういうポジションにあるか、という枠組みで見ていて、次は歴史的・技術的枠組みで見ています。「暗い」「怖い」「不気味」は、絵の色合いや人物の表情などに対する感想で、造形的・図像的な枠組みを通して感じられたことです。そして最後は、金銭に交換可能な価値という枠組みで見ているということが分かります。
共感するかどうかは別として、各々がどんな枠組みを通して見ているかが分かれば、それぞれの意見を理解することが可能になるでしょう。ここに、思考の枠組みを学び、見方を広げるヒントがありそうです。
「絵を見る技術」では、絵から情報を読み取るための基本的な枠組みをいくつか紹介しています。漫然と見ているとき、人は意外なほどいろんな情報を見落としています。しかし、見るための枠組みが複数あると知っていれば、より多くの情報を絵から抽出することができます。そして自分がどういう枠組みで見ているかを客観視し、見方を変えたいときは意識的に別の枠組みで見ることもできます。
一方で、感覚的な見方も大事にしたいと思うのも当然です。感覚的な見方とは一人の人間が余計なことを考えず、自分の感覚を総動員し、絵を全体として受け止めようとすることだと思います。この見方の問題は、どんな視点で見ているのか不明瞭になりがちで、自分と他者の感想が違っていたら、自分はズレているんじゃないかと少し不安になったりすることです。
そんなときこそ、自分の感覚を守り育むために、論理的に見る技術が大事になると思います。
論理的な見方の良さは、「分けて見る」ことにあります。絵がどう描かれているのか、何が描かれているのか、なぜ描かれたのか、といったことを分けて見る、そして、自分の見方と人の見方を分けて見る、ということです。
違う意見に遭遇したときは、その人はどういう枠組みで見ているのか、と考えてみることです。あわせて、自分はどこに着眼しているのか、どういう枠組みで見ているのか分析してみるのです。その過程で漠然とした不安の正体が分かり、それを解消する道筋も見えてくるのではないでしょうか。
感覚的と思われていることの中にも論理的な側面はあり、逆もしかりです。むしろ補完しあって高め合う性質のものでしょう。
教室は、先生や他の人たちの意見に触れる機会にもなり、そのような訓練の場としてぴったりだと思います。その場に多様性があるほど、学ぶチャンスです。違う意見が出るほど、互いに新しい枠組みを獲得し、それだけ見方を広げることができるからです。そして同時に、自分だけの感覚・意見というものがよりはっきりと浮かび上がってくるはず。皆さんがそれを大切に温めていけることを願っています。
『国語教室』第119号より転載

「絵を見る技術」
絵の造形的な特徴を見るポイントを豊富な事例をとおして紹介。漠然と「見る」のではなく、しっかりと「観察」することの大切さを説く。
(『論理国語』〔論国705〕)
著者プロフィール
1976(昭和51)年生まれ。美術史研究家。執筆活動や講座の開催をとおして、人々が自分の言葉で芸術や美について語れるよう、絵を見る技術を広める。著書に『絵を見る技術』などがある。
一覧に戻る