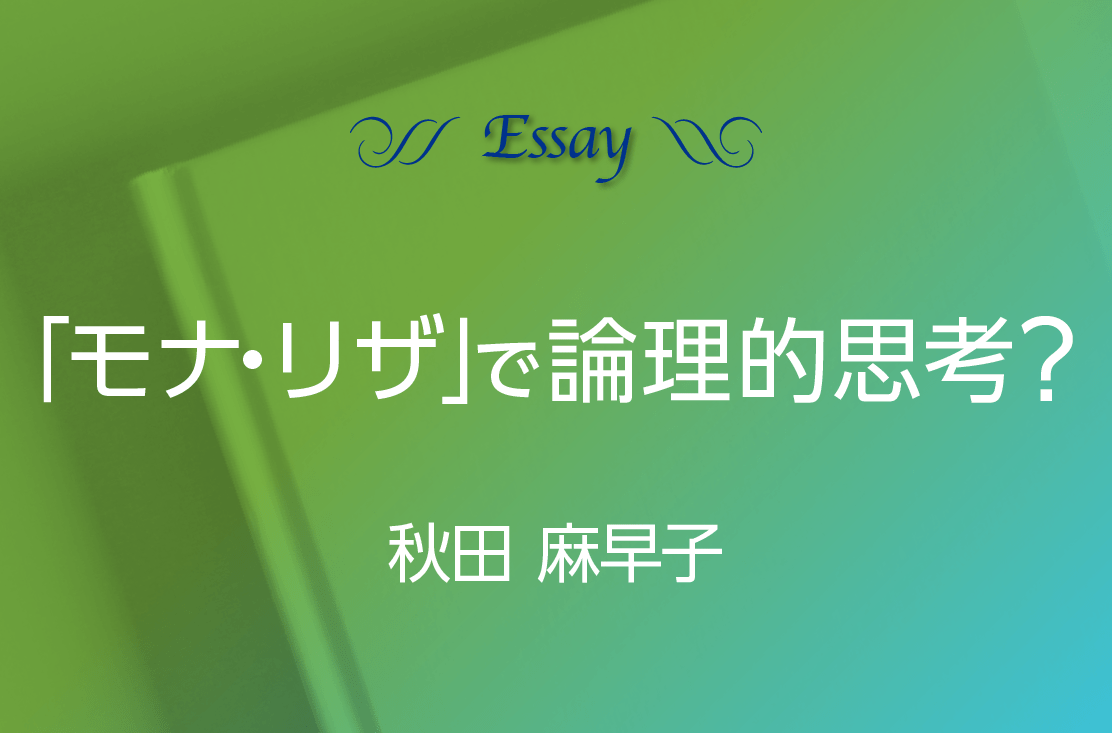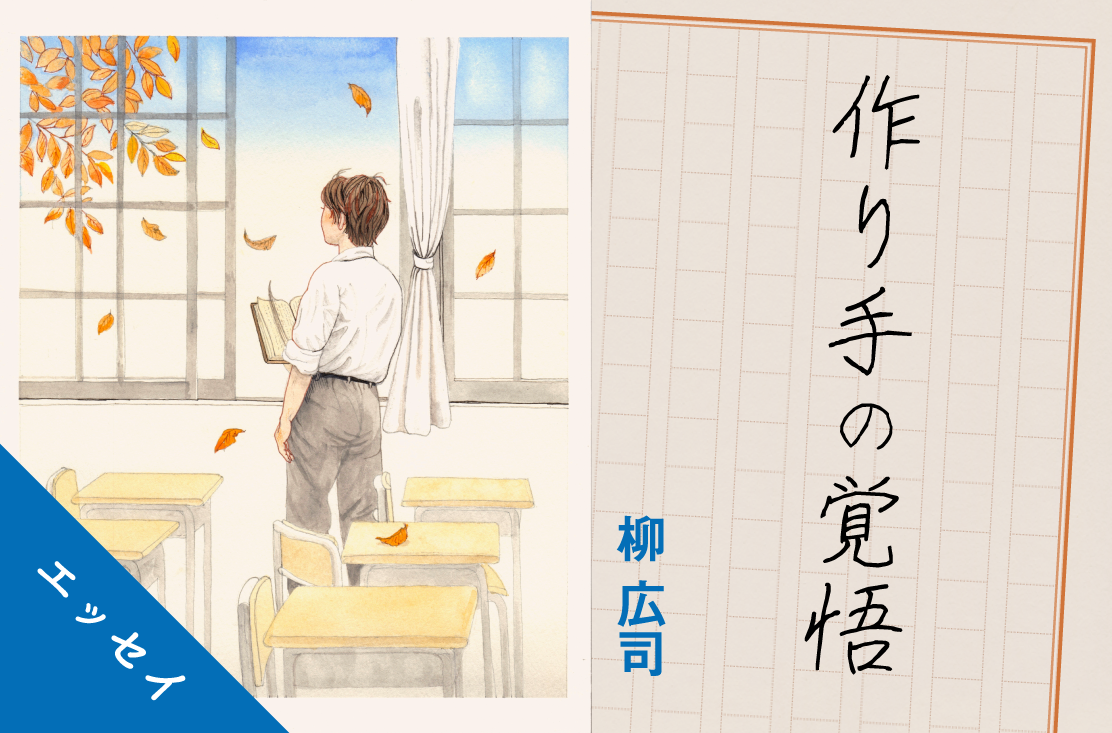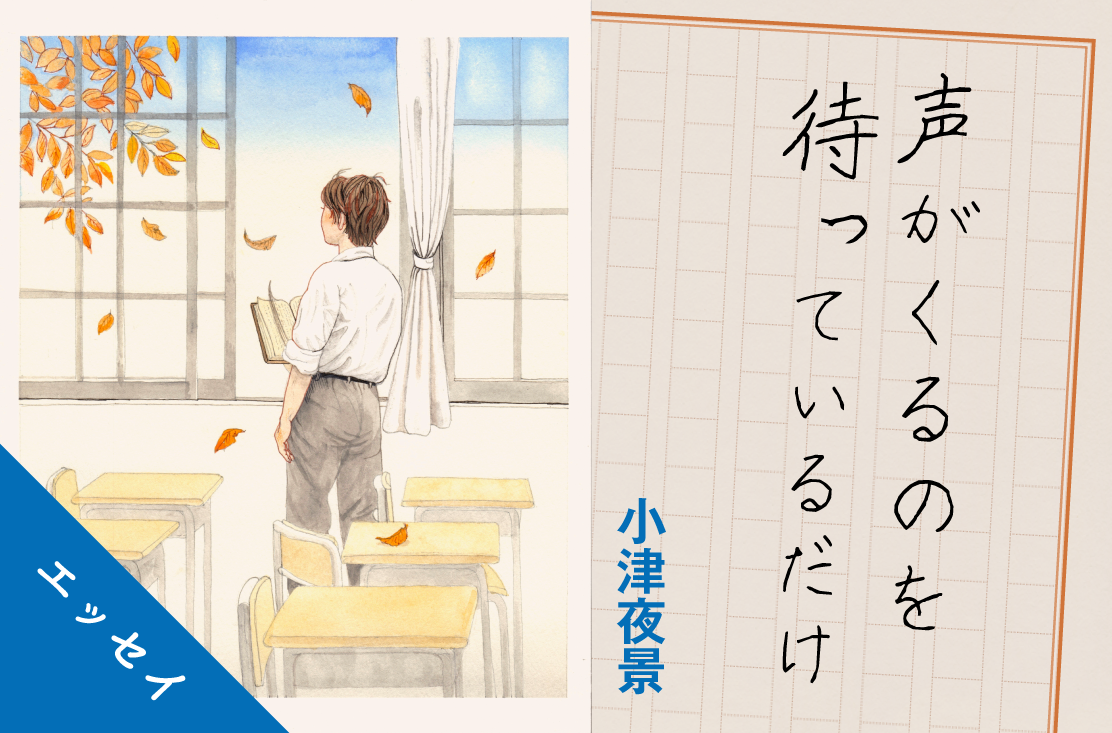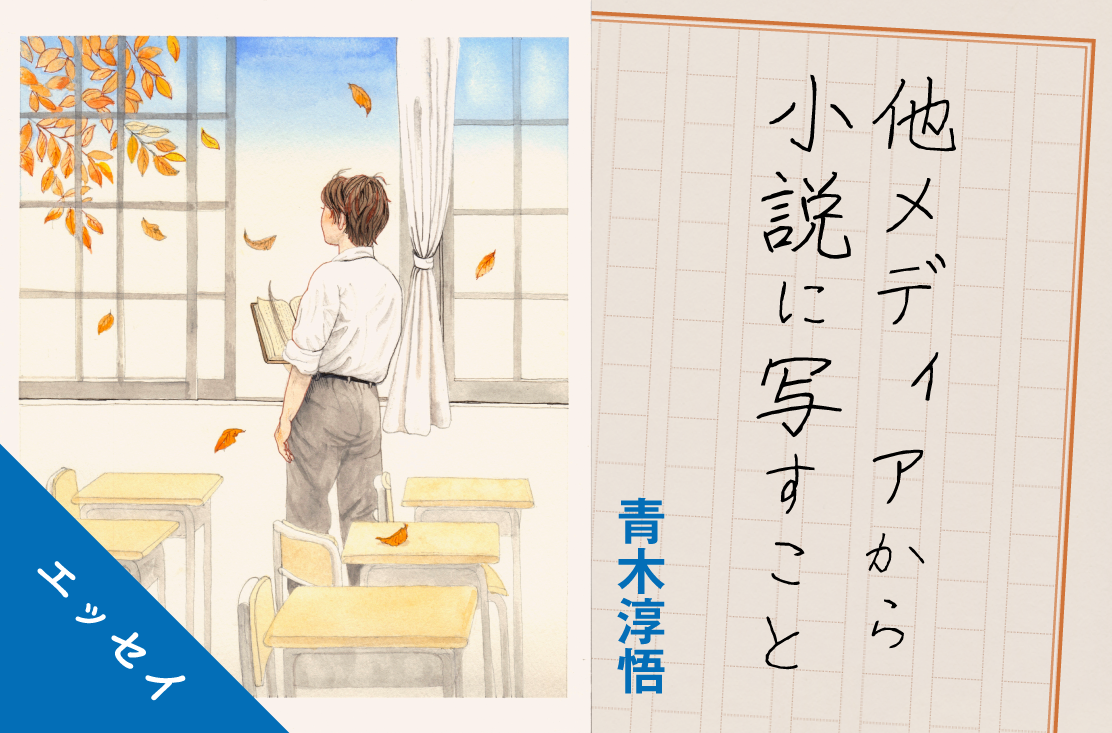エッセイ
「アセチルコリン」の響き
永田 紅
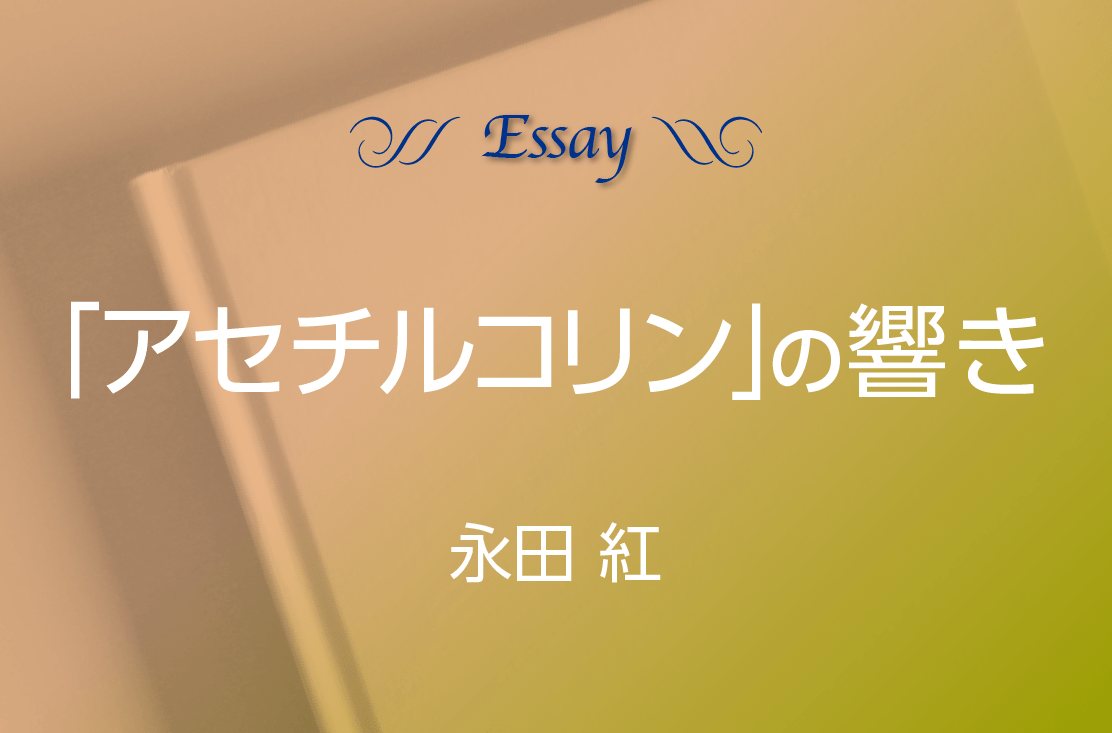
短歌を作り始めたのは、中学に入る前の春休みだった。二歳年上の兄が、なぜか「俺、歌を作る」と言い出したのにくっついて、私も始めた。両親が歌人なので、小さなころから短歌や歌集は身近なものだったが、それ以前に実際に作ったのは、小学校の宿題の一首くらいのものだった。
兄とふたり、父が主宰していた短歌会に入会した。毎月送られてくる雑誌の最後のページには原稿用紙が綴じ込まれていて、これに十首を書いて選者に送る。ミシン目を切り離すときのちょっとわくわくする感じ、そして自分の歌の何首かが活字になって誌上に載ったときのうれしさが、作歌の原点だろう。
何でもかんでも、指折り五七五七七に乗せていった。新しい表現手段を得ると、それまで見えていなかったものが見え始める。歌の題材にならないかなと、窓を流れる雨滴の様子、電車の風圧で揺れる沿線のススキ、陽に透ける木槿(むくげ)の葉っぱを見つめた。たぶん、歌を作ろうと思わなければ、漠然と視界を過ぎていくだけの景だろう。歌一首を作るだけで、記憶に付箋がつく。
実感したのは、言葉は「逃げる」ということだった。湯舟や布団の中でいいフレーズを思いつき、あとで一首に仕上げようと思っていても、お風呂を出たとき、翌朝目覚めたときには、その言葉の組み合わせは跡形もなく消えている。二度と再現できない口惜しさ。
だから、何か新しいフレーズを思いつくと、授業中でもプリントの裏に書き留めるようにした。言葉の断片を自分の内に溜め込むことは、表現の基礎体力になる。そしてまた、人の詩歌の断片を自分の内に溜め込むことも、世界をこの上なく面白く見せてくれる。
定期的に締切りがあるというのも、案外大事なことだった。自分は何かすばらしいものを表現できるんじゃないか、という若い漠然とした思いや情熱、衝迫感があったとしても、表現手段と締切りがなければ、せっかくの内面も形を取り得ない。
中学、高校のあいだ、そんなふうに毎月短歌を送り続け、浪人生に。人生うまくいっていないときのほうが何かを表現したくなるもので、浪人のときこそ歌を作りたい気持ちが強かったが、そこは一年間我慢。晴れて大学生となり、二十一歳のときに応募して新人賞を受賞した三十首の一連に入っていたのが、『新編 文学国語』に掲載していただいたこの一首である。
今日君と目が合いました指先にアセチルコリンが溜まる気がした 『日輪』 永田 紅
「アセチルコリン」は神経伝達物質である。生命科学をやりたくて農学部に進んだので、『細胞の分子生物学』などの教科書を読み、出会った言葉だっただろうか。ドキッと胸に迫るものがあるとき、私は手のひらから指先へかけて、何か緊張のような感覚が走る。「君」と目が合ったときのそのような感じを、指の先に神経伝達物質が溜まるようだ、と表現したくなったのだった。本当にアセチルコリンが溜まるのかどうかは知らない。科学的根拠のある歌ではない。ただ、アセチルコリンという言葉の響きに惹かれ、心の動きに伴って神経細胞間のシナプスに物質が放出されるイメージを体感したような気がして、生まれた歌だった。理解してもらえないかもしれない専門用語も、詩の一部として取り入れたい気持ちもあった。
「うれしい」「悲しい」という一般的な形容詞を使わずに、それらをどう表現するか。感情は、はじめからはっきりと分かりやすい形で存在するものばかりではない。むしろ、表現してゆく中で、輪郭をもってくるもののほうが多い。「悲しい」を表現した一首ができても、その下の層にはさらに別の悲しみがある。剝がしてゆくたび、表現してゆくたびに新しい感情の相が現れる。表現を耕しながら、開拓しながら、自分の心に出会ってゆくのだ。
短歌は飛躍と省略の文芸なので、解釈が難しいことも多い。本来、作品の読み方に正解、不正解はないはずだが、試験に出るものであれば、正誤が設定されるのも致し方ない。けれど、気晴らしに教科書をぱらぱらと眺めるときには、「うまく説明できないけど、何かいいな」「意味はわからなくてもしびれる」という緩さと無責任さで、楽しんでもらうのが一番だと思う。そして、教科書の一首をきっかけに、自分でも作ってみようかなと思ってもらえたなら、作者冥利に尽きる。十代の歌は、十代のときにしか作れないのだから。
『国語教室』第119号より転載

単元「恋のうた」
中島みゆきから「長恨歌」まで。現代から近代、古典へと時代を遡りながら、恋する心をうたう古今の詩歌を集めた単元。
(『新編 文学国語』〔文国705〕)
著者プロフィール
歌人、細胞生物学研究者。京都大学特任助教。父の永田和宏、母の河野裕子、兄の永田淳も歌人。歌集に『日輪』『春の顕微鏡』など。
一覧に戻る