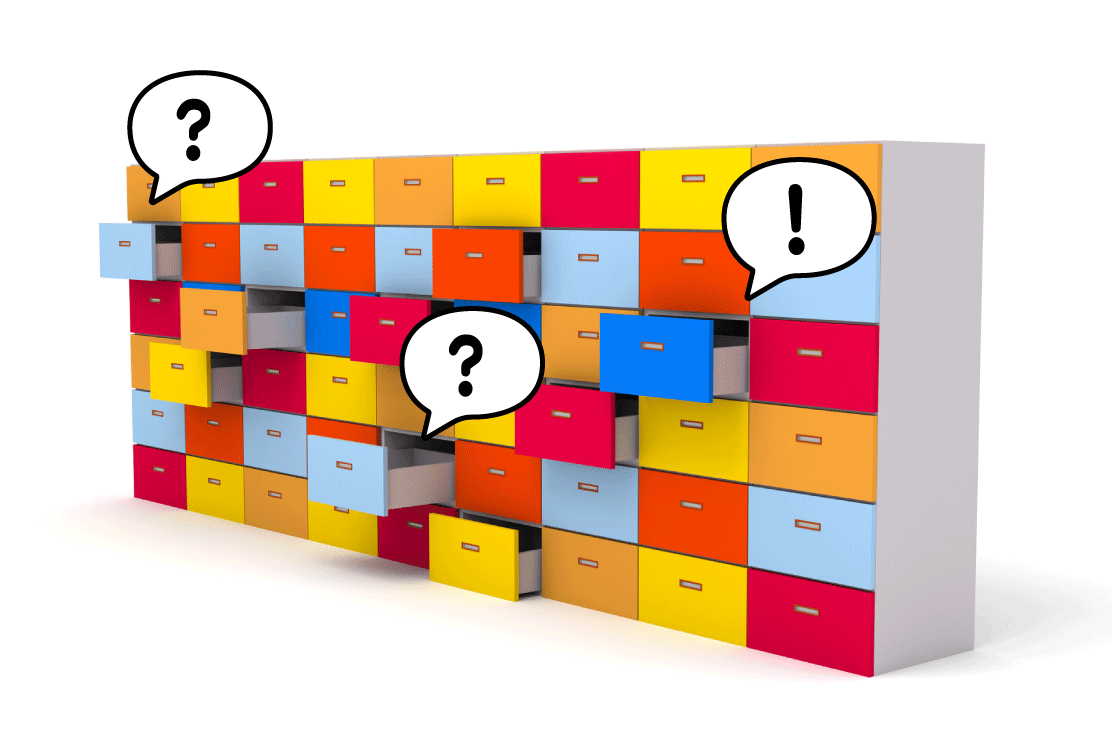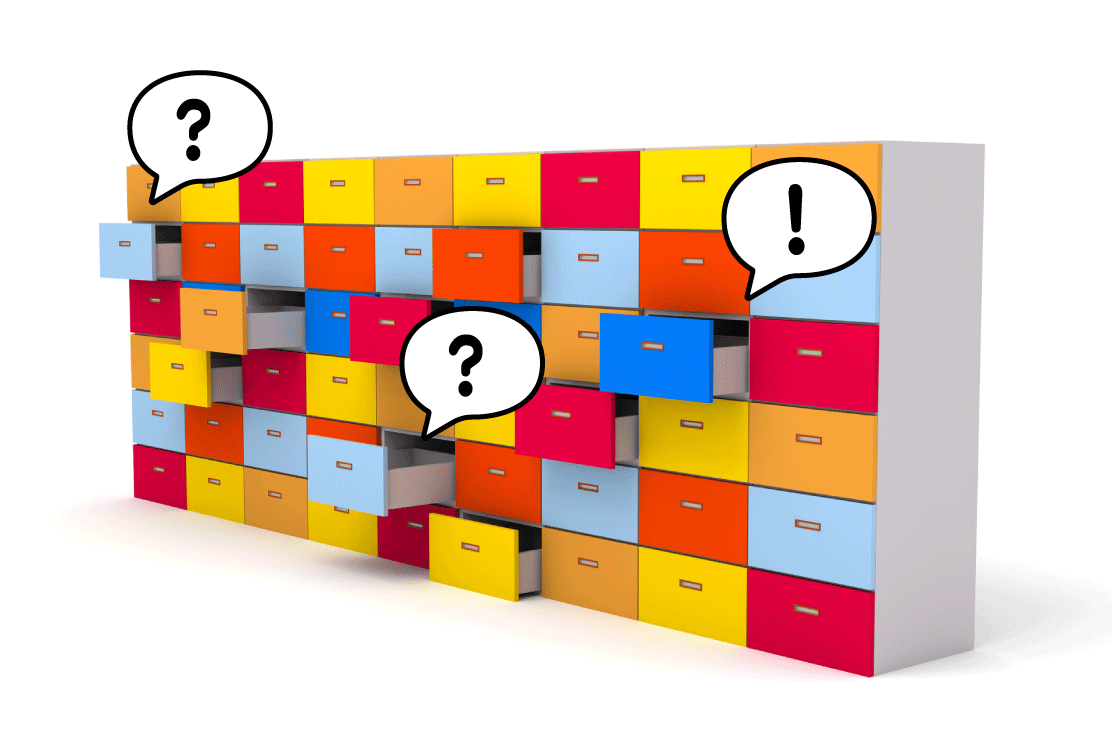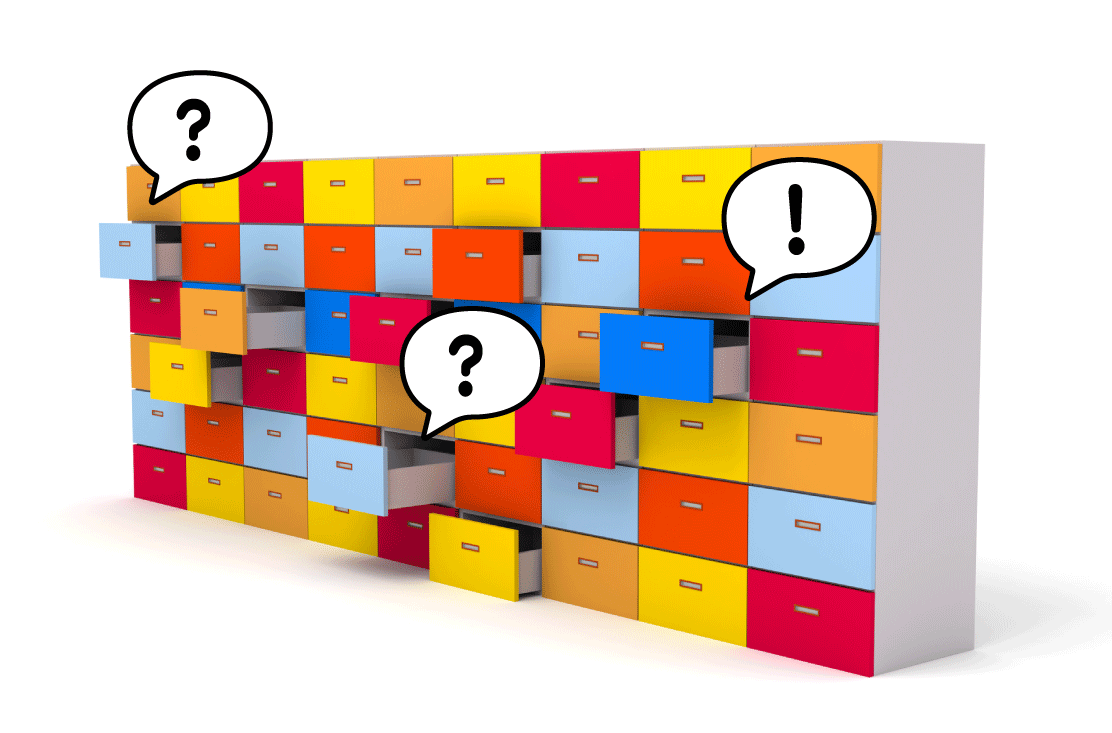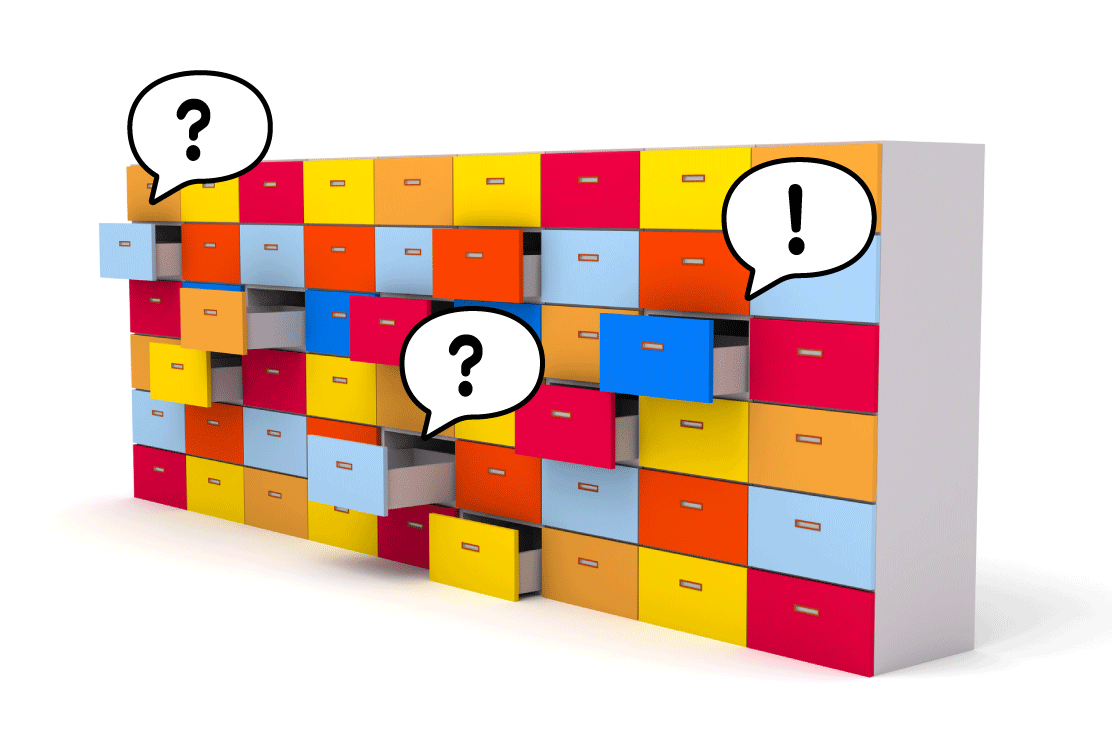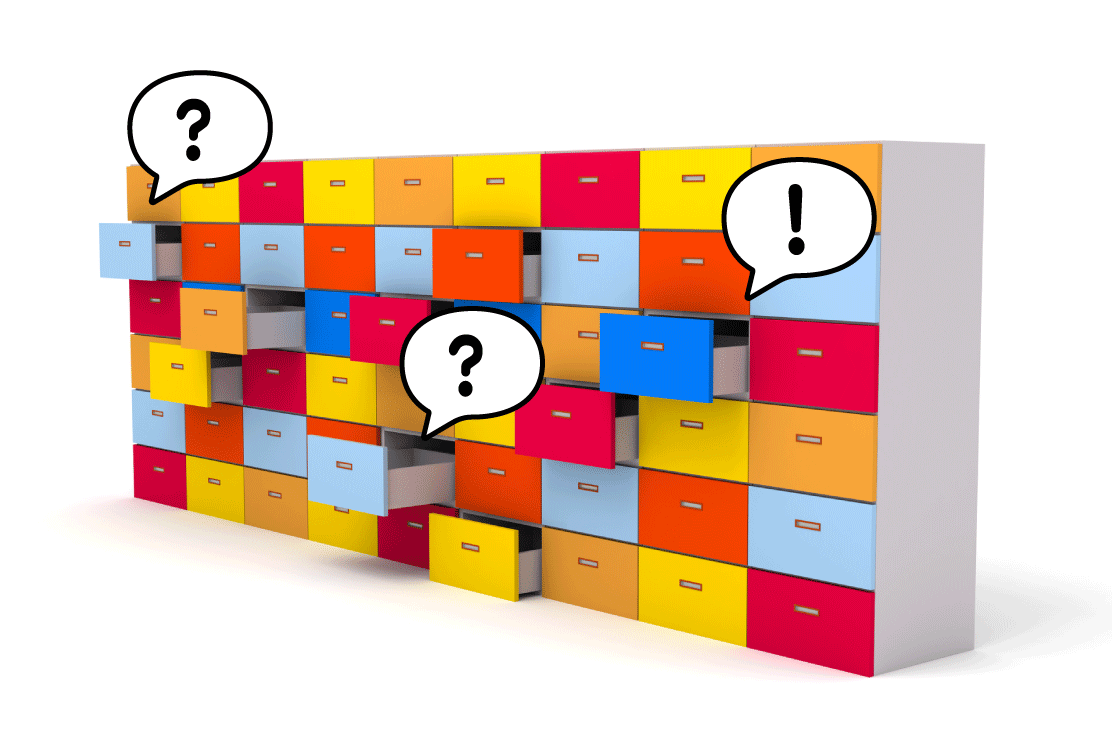コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第4回 はかなく消える「見果てぬ夢」
関根健一
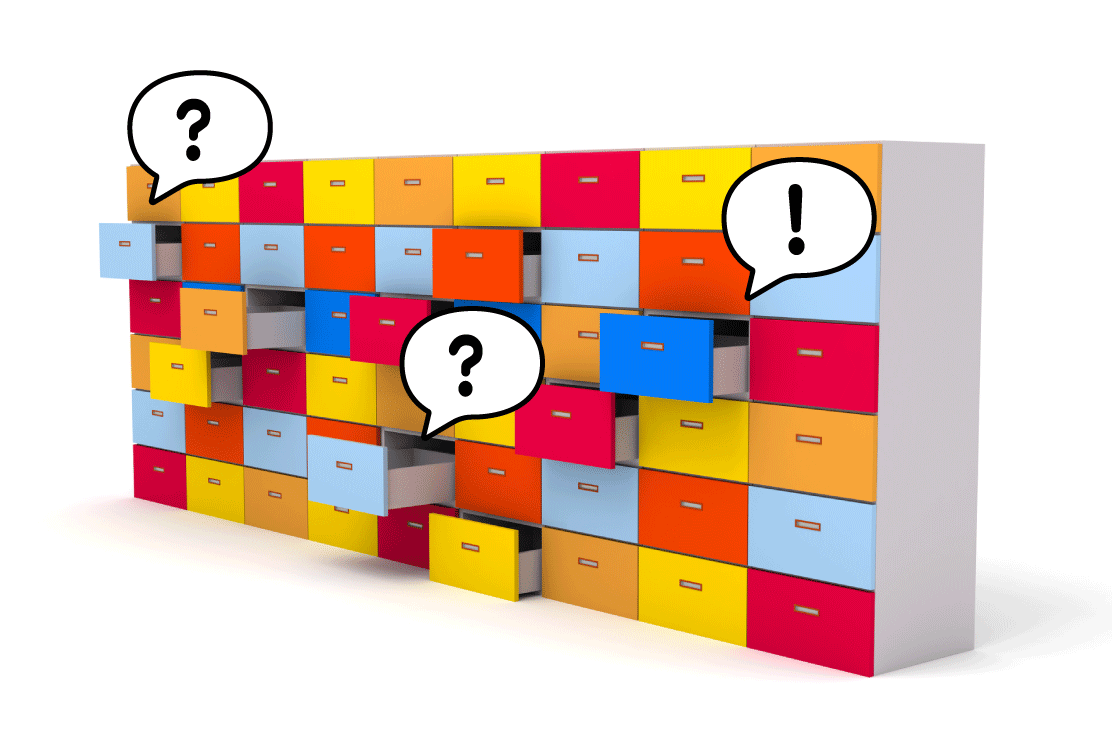
卒業アルバムの表紙に何か素敵なタイトルを付けたいと、生徒たちが意見を出し合っています。「夢」という言葉を入れたフレーズにしたいようです。「私たちの夢」ではありきたり。「夢をかなえよう」では? 「夢に向かって」はどうかな。そうだ、「見果てぬ夢」なんてどうだろう。……いや、それはやめておいた方がいいでしょう。
*****
「見果てぬ」は「見果つ」(最後まで見る)の打ち消しで、「最後まで見ることができない」の意味になります。「見果てぬ夢」は最後まで見られない夢、そこから、永久に実現できない計画を表します。ミュージカル「ラ・マンチャの男」のテーマ曲「見果てぬ夢」の原題は “The Impossible Dream”(不可能な夢)です。いつか夢が実現すると信じて進んでいくのではなく、決して実現しない夢を追うがゆえに、ドン・キホーテは滑稽で、雄々しく、悲しくて美しいのです。心を揺さぶるメロディーにのせて朗々と歌い上げられるので、聴いていると明日への希望があふれてくる思いがしますが、歌詞には「太刀打ちできない敵」「耐えられない悲しみ」「届かない星」といった否定を表すun-が付いた言葉が続きます。
「見ることができない」のだから、「見果てぬ夢に終わった」のように、心残りであることをたとえるのが本来の用法です。「見果てぬ夢をかなえたい」「見果てぬ夢を探し求める」などと、夢をあきらめない意で使うのは誤用でしょう。卒業アルバムのタイトルにするにはちょっとふさわしくなさそうですね。
動詞連用形に付く「~果てる」は、「困り果てる」「あきれ果てる」「愛想もこそも尽き果てる」など、「すっかり~する」の意ですが、『明鏡国語辞典』は「多くマイナスに評価していう」と注釈を付けています。そのため反対の「果てぬ」について、何となくプラスの語感を抱いてしまうということもあるのでしょうか。
*****
古くは、眠って見ていた夢を、目が覚めてしまい、最後まで見られなかったという意味で「見果てぬ夢」が使われている例があります。
命にもまさりて惜しくあるものは見はてぬ夢の覚むるなりけり(壬生忠岑・古今集)
鳴く鹿の声に目覚めてしのぶかな見果てぬ夢の秋の思ひを(慈円・新古今集)
元来は睡眠中に見るのが「夢」で、そこから非現実的な空想やはかない出来事、心の迷いといった意味も生まれました。いつかは実現させたいと抱く思いを指すようになったのは、近代になってからのようです。こうした「夢」の持つ曖昧な多義性とも相まって、「見果てぬ夢」のフレーズにロマンチックな雰囲気を感じてしまうのかもしれません。
*****
アスナロ(翌檜)という木があります。ヒノキ(檜)の仲間で、ヒノキによく似ていますが、材質は少々劣り、そこから、「明日はヒノキになろう」と頑張っている、という意味で名付けられたとされます。「明日こそは」の希望を胸にひたむきに努力するイメージを浮かべる人もいるでしょう。でも、ちょっと意地悪い見方かもしれませんが、アスナロは、ヒノキになりたいと思っても、結局はなれない、希望はかなわないのです。
井上靖の小説「あすなろ物語」は、立身出世の成功物語ではありません。アスナロの木になぞらえて、望みを果たせず、もがき、劣等感に悩みながら生きて行く姿を描いた自伝的小説です。アスナロは「見果てぬ夢」の象徴ともいえるでしょう。
*****
どことなく感じのよい字面、語の並びが、言葉の本当の意味を見えにくくしているということもあるのです。
『国語教室』第112号(2020年2月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る