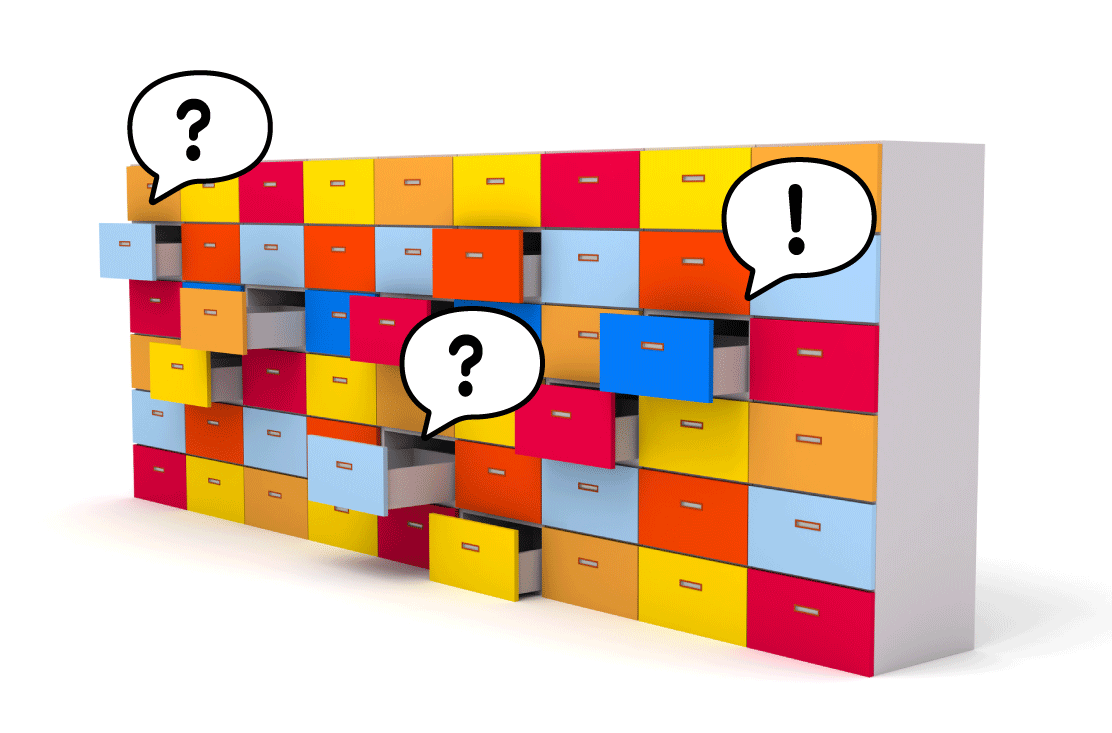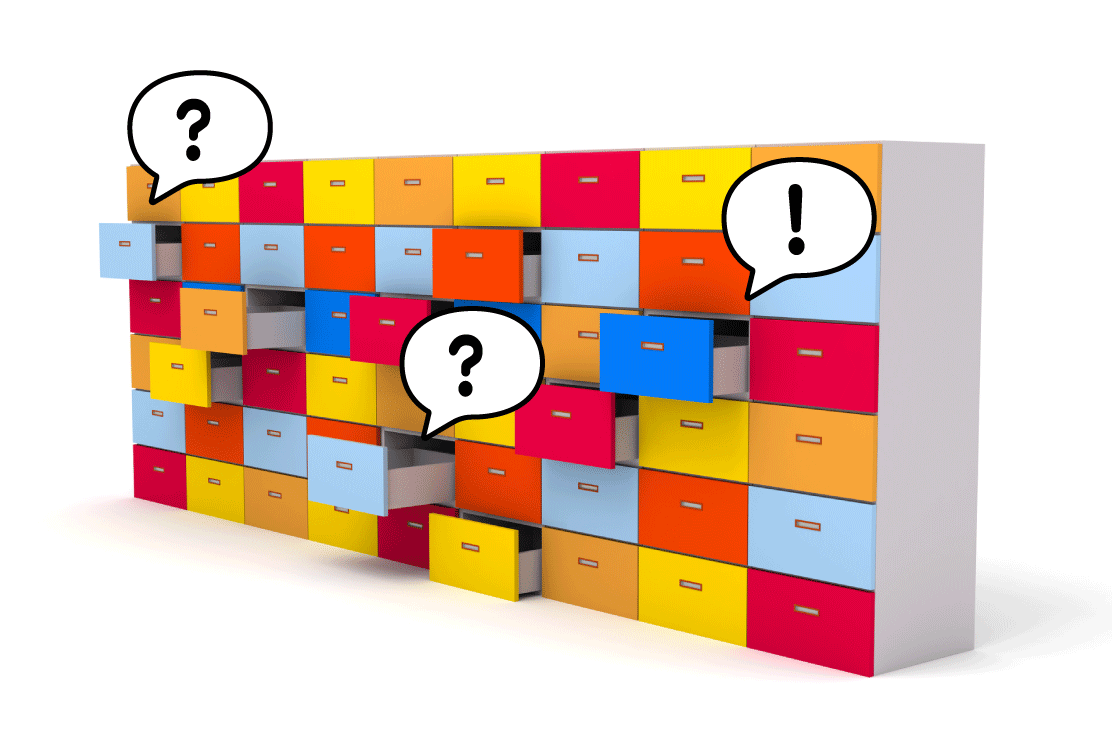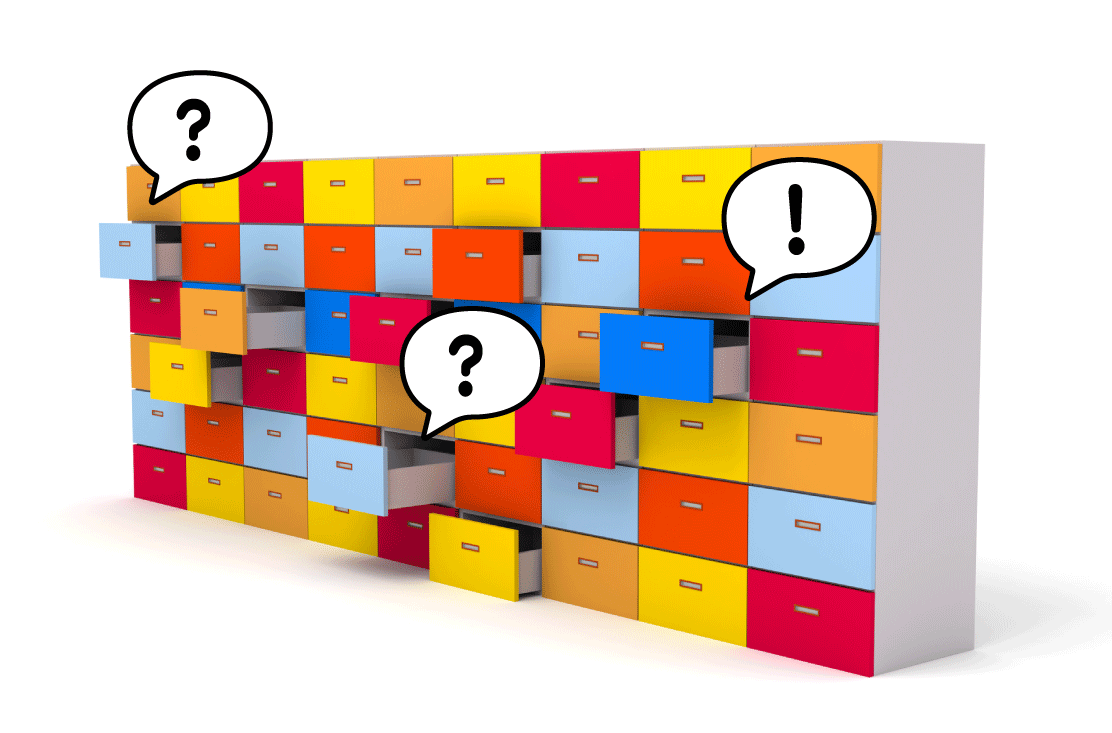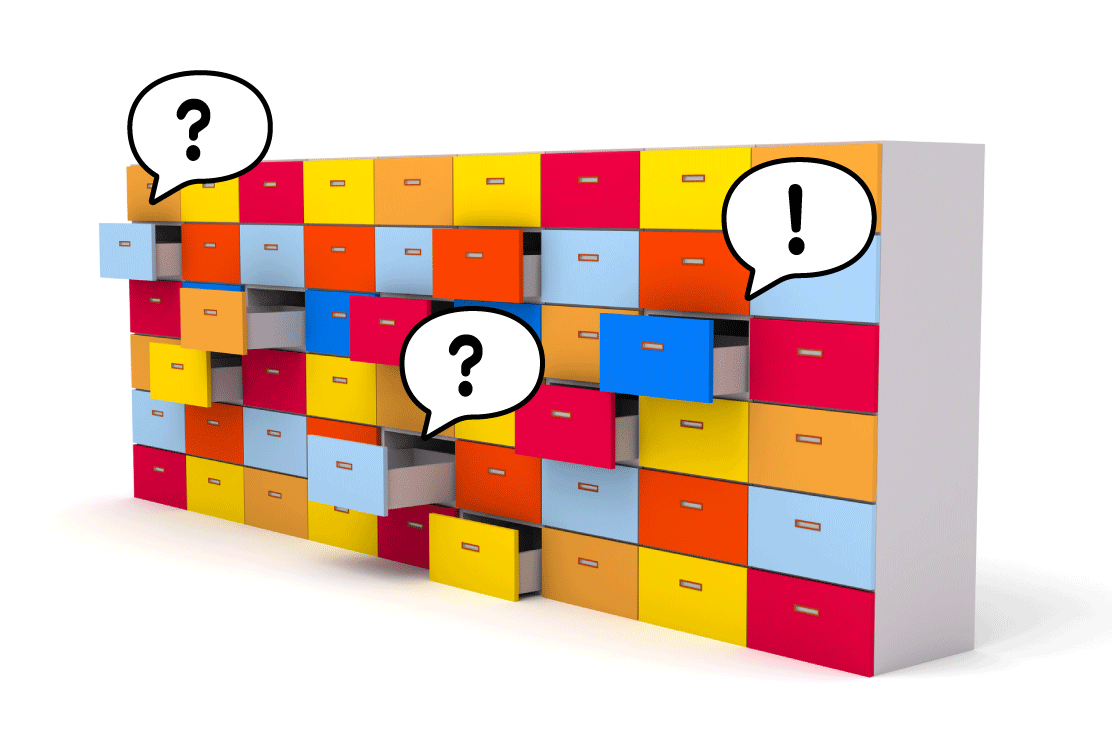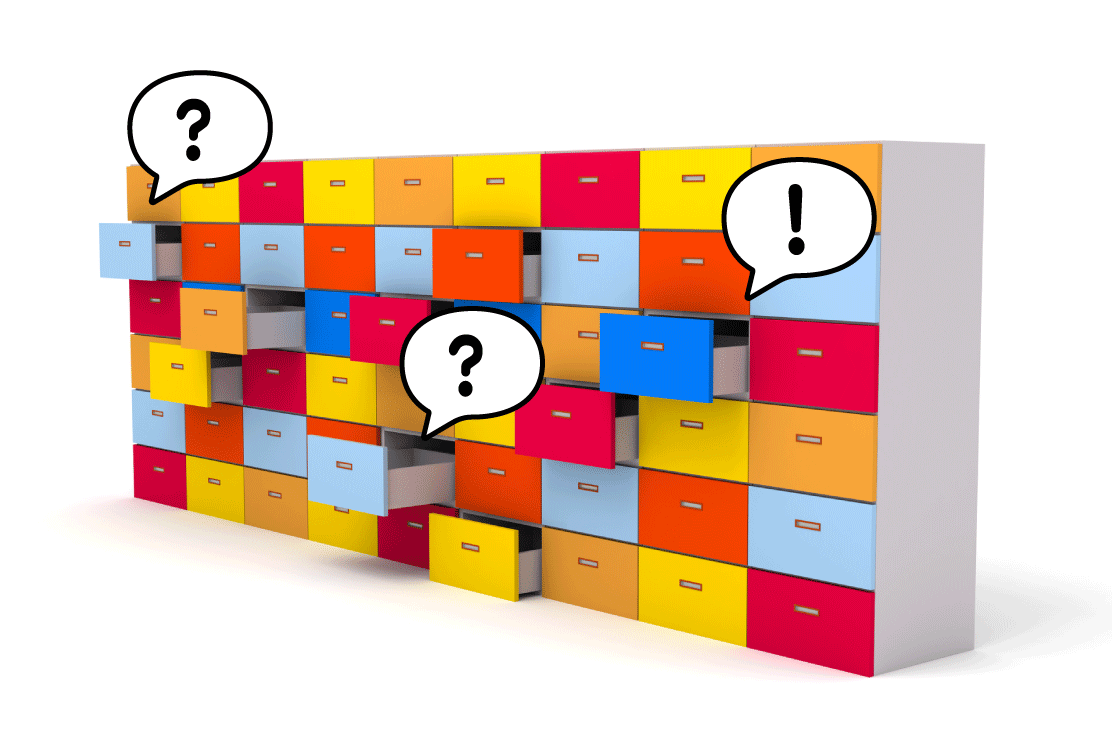コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第11回 「アジづくし定食」はアジずくめ?
関根健一
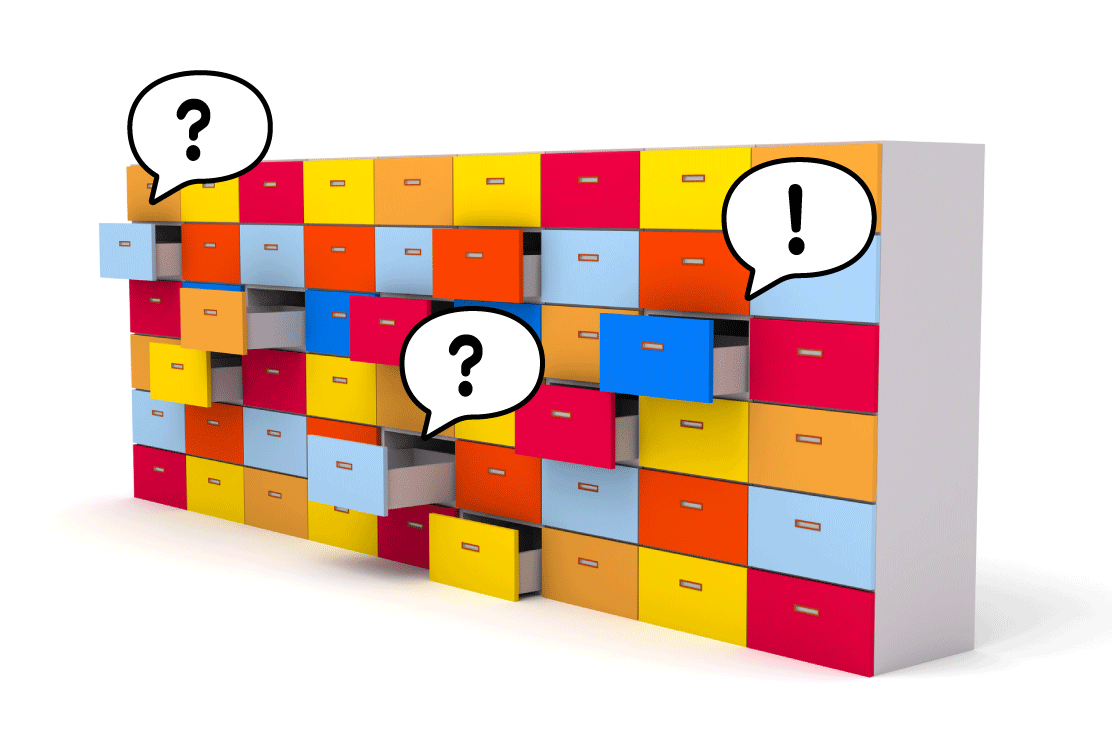
たたきにフライに南蛮漬け、なめろうも付いた「アジづくし定食」、刺身に酢味噌(みそ)和え、ゲソ揚げ、塩辛の「イカづくし御膳」──とにかく大好きなあれを思う存分食べたい! と矢も盾もたまらなくなったら、「××づくし」で検索してみてはいかが? お気に入りの食材を様々に調理したメニューのあれこれがヒットしますよ。
*****
「尽(づ)くし」は、「〈名詞に付いて〉同じ類のものをすべて並べ上げる意を表す(『明鏡国語辞典』)」ときに使われます。諸国の名を口調よく列挙したのが「国尽くし」。相撲甚句「花尽くし」は、〽正月寿(ことほ)ぐ福寿草/二月に咲くのが梅の花/三月桜や 四月藤……と、花の名を次々に挙げていきます。
ここである疑問が浮かびます。「アジづくし定食」は、アジと同類のものを並べ上げているわけではないのではということに。マアジ、ムロアジ、シマアジ……のように、様々な種類を提供するのであければ、「づくし」とは言えないはずです。
*****
見た目や味付けは違っても、使っているアジの種類は同じなら、「〈名詞などに付いて〉全体がそればかりであることを表す(同)」という意味の「ずくめ」が適切ということになります。
「ずくめ」は平たく言えば「何から何まで××ばかり」。ダース・ベイダーは全身黒一色の「黒ずくめ」のコスチュームに身を包んでいます。髪の結び方から男女交際まで、がんじがらめに縛りつける「規則ずくめ」の生活指導が問題になったのは記憶に新しいところです。元手はいらない、楽してもうかるなどという「結構ずくめ」のアルバイトの誘いには安易に乗ってはいけません。
「そればかり=ずくめ」と、「並べ上げる=づくし」は、混同されやすい言葉です。普通でないことばかり起こるのは「異例づくし」でなく「異例ずくめ」、「金もない仕事もない友達もいない」とないものを教えて嘆くのは「ないないずくめ」でなく「ないないづくし」です。
*****
つまり、前菜も主菜もお椀(わん)も何から何までアジを堪能できるのは「アジずくめ定食」です。ただ、あまりおいしそうに感じられないのはなぜでしょう。「そればかり」の意が協調されすぎて変化に乏しいイメージがするからかもしれません。実際、お品書きで「ずくめ」と名付けている例はほとんど見かけません。手を替え品を替え工夫を凝らした調理法がメニューに並べ上げられていると解釈すれば、「アジづくし定食」の表現もあながち間違いとは言えない気がします。料理名に関しては、「づくし」の語釈に検討の余地がありそうです。
*****
ところで、漢字で書けばどちらも「尽くし」「尽くめ」ですが、標準的な仮名遣いは、「づくし」「ずくめ」と異なります。「現代仮名遣い」(内閣告示)には、「二語の連合によって生じた『づ』」の例に「こころづくし」が挙がっています。「づくし」には「ありったけのものを出し切ってしまう」という「尽くす」の意味が残っているのです。
一方、「ずくめ」は「二語に分解しにくいものは『ず』を用いて書く」の規定に該当します。「尽くす」との関係が薄れているわけです。本来「竦(すく)む」に由来し、歴史的仮名遣いで慣用的に「づ」と表記してきただけという説(『大辞林 第4版、松村明編、三省堂』)もあります。
*****
「そればかり」の意味では、「~づめ」もありました。漢字を当てるなら「詰め」。名詞に付く「ずくめ」に対し、「づめ」は、「立ちづめ」「歩きづめ」「笑いづめ」のように、動詞の連用形に付いて、その動作・状態が続いている意を表します。朝から晩まで一日中休みなしの状態は「働きずくめ」ではなく「働きづめ」です。
『国語教室』第119号(2022年4月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る