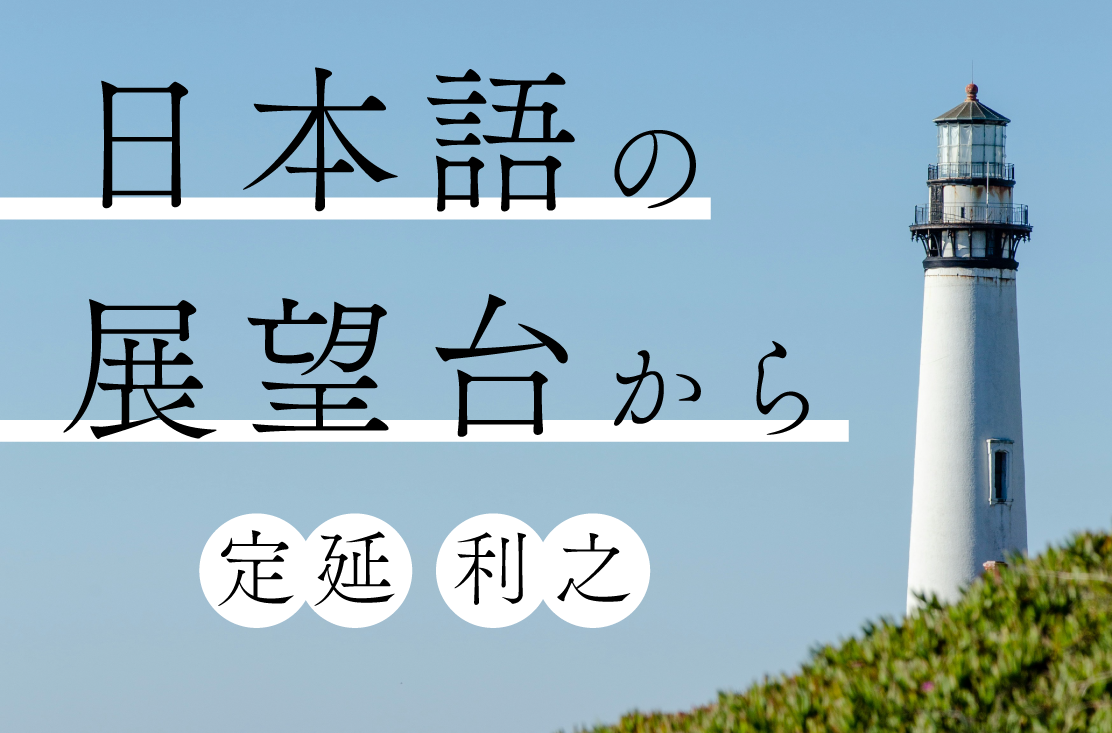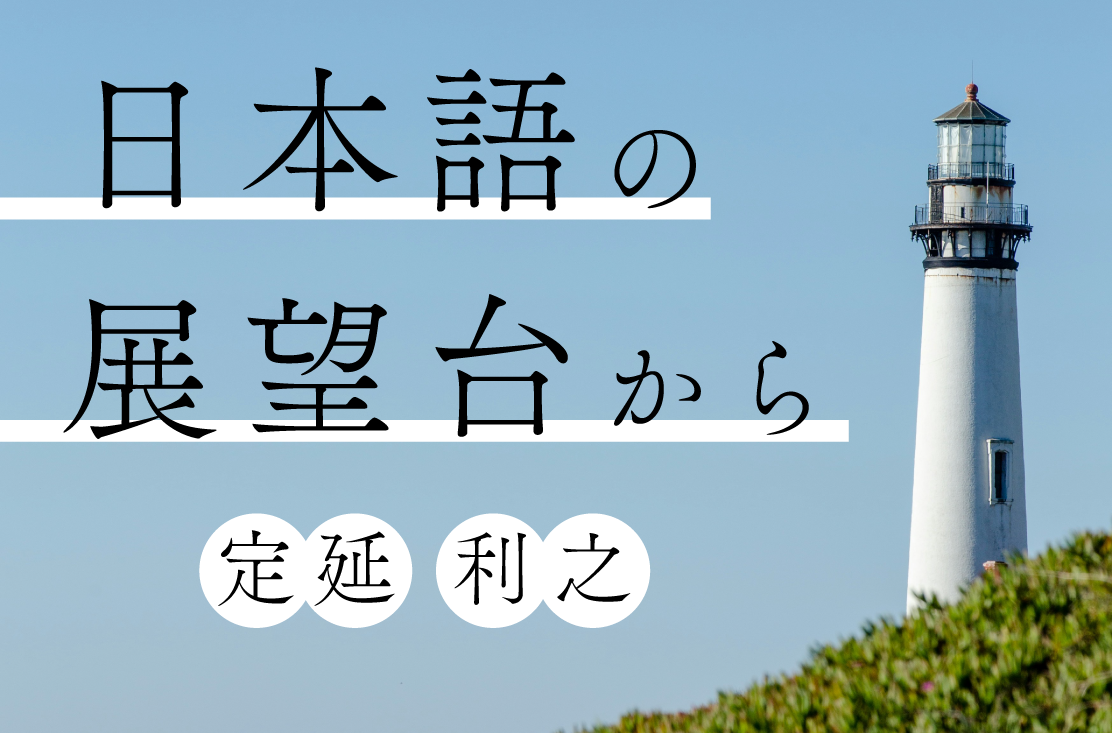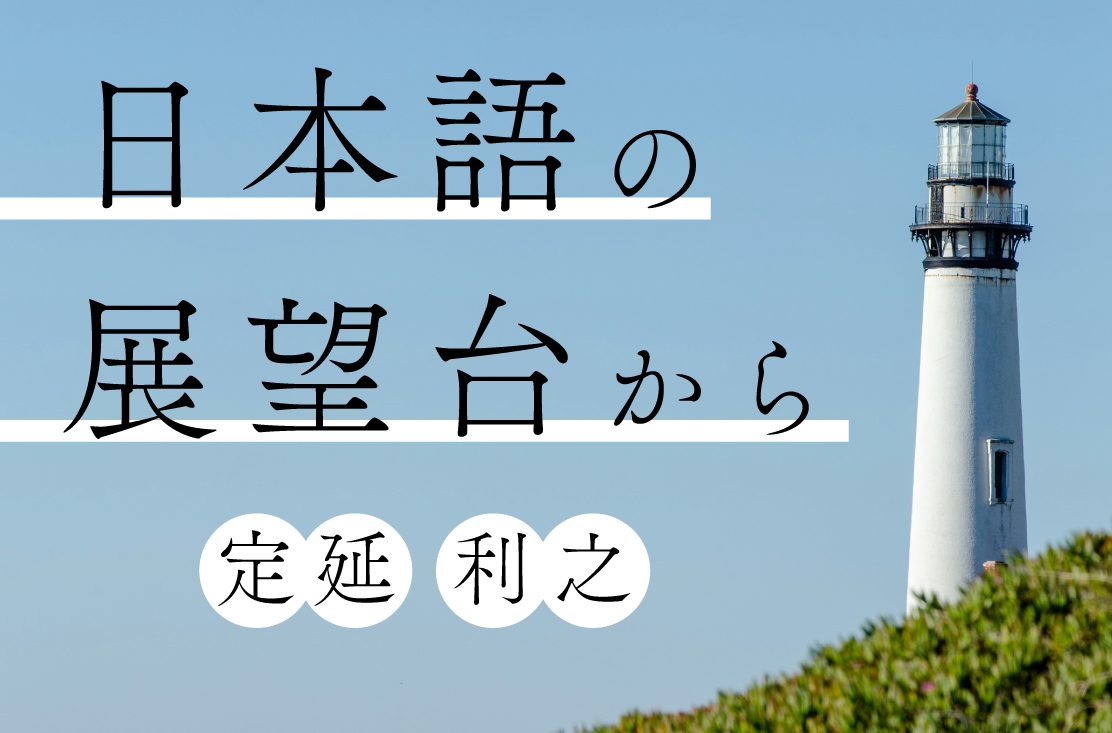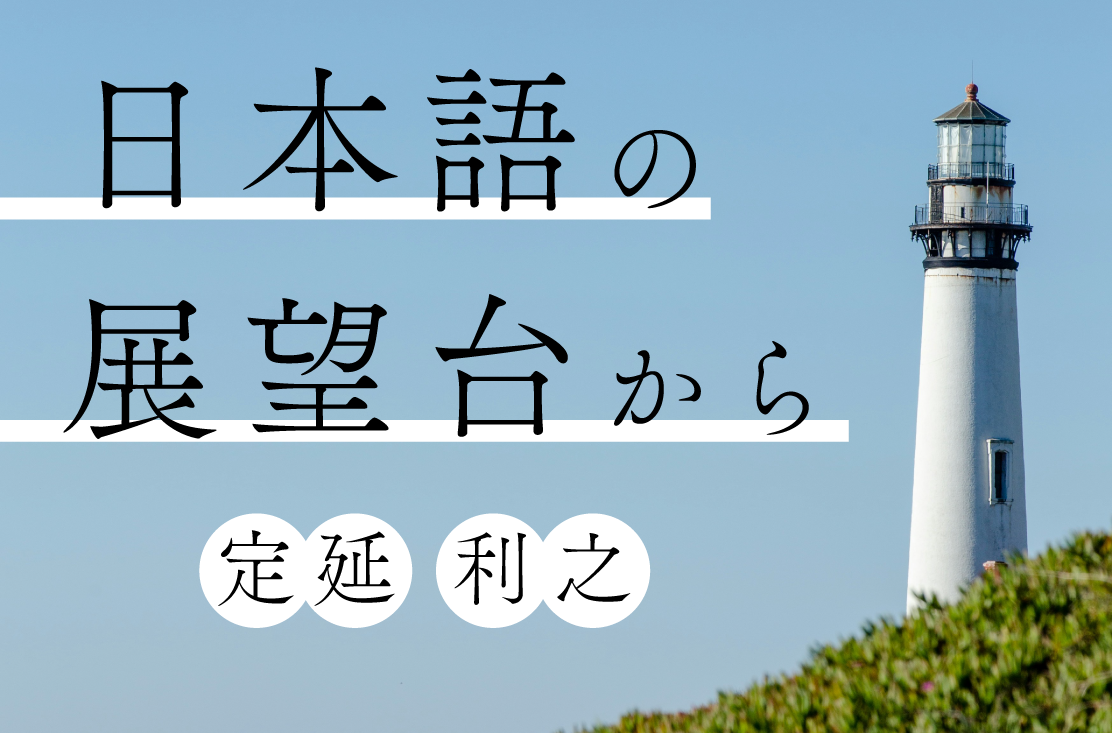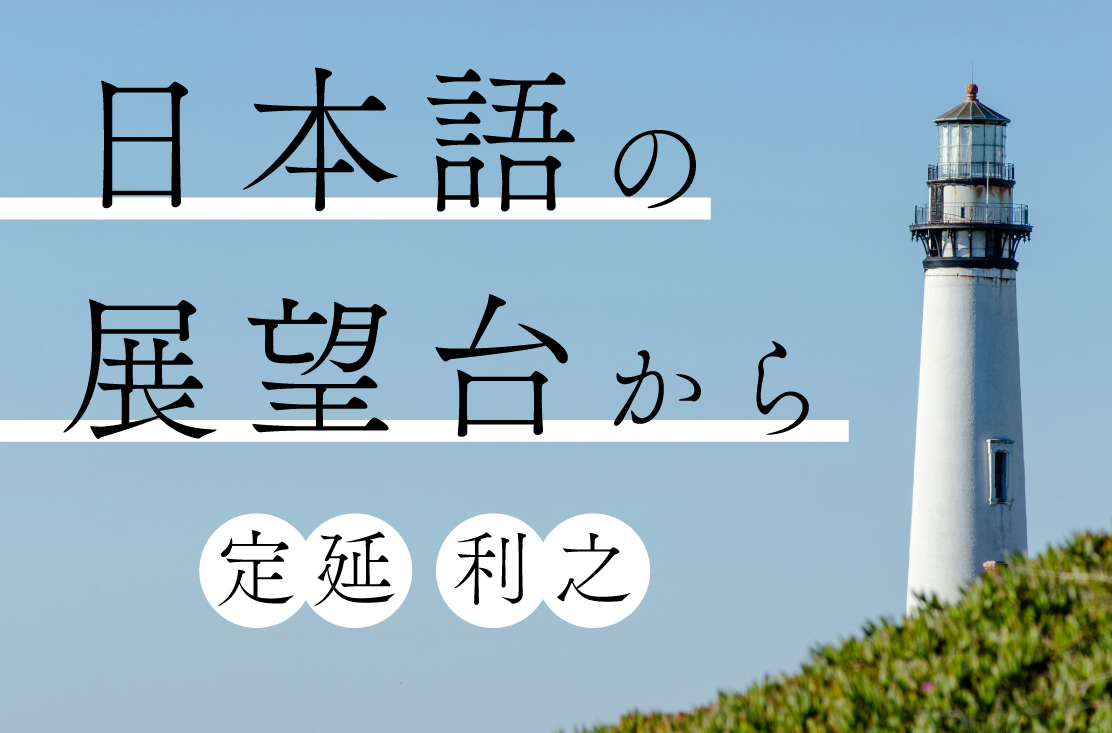日本語の展望台から
第6回 「ユリ」(低高)の花のような「ユリ」(高低)さん
定延利之
- 2025.04.25
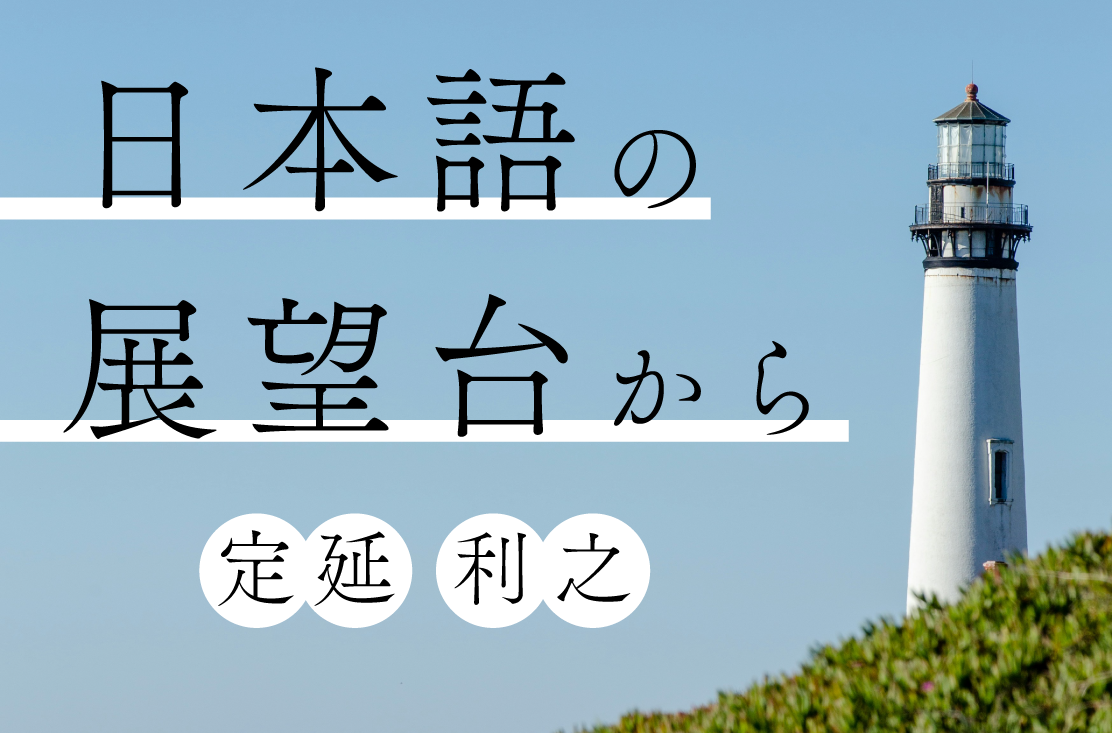
1.短い名前は頭高型アクセント
この子はユリの花のように美しく育ってほしいと,ユリに因んで名付けをしたとする。花の「ユリ」のアクセントは(現代日本語共通語では――以下略),「ユ」が低く「リ」が高い。ところがその子の名前は,「ユ」が高く「リ」が低い。
人やペットの名前(ファーストネーム)にはさまざまなものがある。長い名前は合成語のアクセントに影響されるが,短い名前はほとんど皆同じである。(ここでは「短い」とは「1~2音節で1~3モーラ」とする。)以下に100個ほど挙げてみる。
アイ アキ アミ アリ イネ ウメ エマ エミ エリ カナ カン キヨ クマ クミ ケイ ケリー ケン ゲン ケンジ ケント サキ サチ サム サヤ サリー シノ ジム ジェイク ジェニー ジェフ ジャック ジュン ジョン シンジ セイコ セナ ソラ タエ タカ タク タツ タミー タラ ダン チエ チカ トキ トシ ドナ トミ トム トメ トラ ナギ ナツ ナナ ナミ ニック ニーナ ニモ パティ ハナ ヒデ ヒロ フネ ポール ボブ ポリー マイ マキ マチ マック マナ マミ マユ マリ ミイ ミキ ミク メイ メグ モエ モモ ヤス ユキ ユミ ユリ ヨシ ラリー リエ リカ リク リサ リナ リノ リョウ リリー レイ レミ レン ロン
これらはすべて,最初の音つまり第1モーラが高く,その後の音つまり第2モーラ以降は低い。たとえば「アイ」なら第1モーラの「ア」が高く,第2モーラの「イ」は低い。「ユリ」も同様である。「この音までは高い。次の音からは低になる」という情報をアクセント核と呼ぶことにすると,これらの名前は,第1モーラ(「アイ」の「ア」,「ユリ」の「ユ」)がアクセント核を持っていることになる。このようなアクセントの型を頭高型と言う。
例外は「トオル」「芭蕉」「以蔵〔いぞう〕」「宇平〔うへい〕」(低高高)など,ごく僅かである。(塩田雄大氏のご教示による。)これらの語はアクセント核を持たない。つまり「直後の音から低になる」ことがないので,直後の音も高い。たとえば「トオルが」(低高高高)では「トオル」の「オル」だけでなく,直後の格助詞「が」も高である。このようなアクセントの型を平板型と言う。冒頭で述べた花の「ユリ」も,たとえば「ユリを」(低高高)と言えば「リ」だけでなく直後の格助詞「を」も高いように,平板型である。
人の名前には際限がない。あの人の名前は何型だった,この人はどうだったと,いちいち覚えていられない。それで,「困った時は頭高型」ということで,頭高型になっているのではないだろうか。
2.困った時は頭高型
アルファベットはA(エー)からZ(ゼット)まで,W(ダブリュー)のような4モーラのものも含めて,すべて頭高型である。
A(エー) B(ビー) C(シー) D(ディー) E(イー) F(エフ) G(ジー) H(エイチ) I(アイ) J(ジェー) K(ケー) L(エル) M(エム) N(エヌ) O(オー) P(ピー) Q(キュー) R(アール) S(エス) T(ティー) U(ユー) V(ブイ) W(ダブリュー) X(エックス) Y(ワイ) Z(ゼット)
これらは文字(ローマ字)である。文字は語(言語記号)ではない。文字には「語の意味」と言えるような意味は無い。たとえばF(エフ)と言えばどんな意味か,U(ユー)と聞けば何を思い浮かべるか,などと問われても,答えられないだろう。語ではないからアクセントは用意されていない。だが,その文字を1つずつ単独で発して,つまり文字を語扱いして,語として発するとなると話は別で,アクセントが要る。それで「困った時は頭高型」ということで,頭高型になっている。
ギリシャのアルファベットも同様で,α(アルファー)からω(オメガ)まで,基本的に頭高型である。
α(アルファー) β(ベータ) γ(ガンマ) δ(デルタ) ε(イプシロン) ζ(ゼータ) η(エータ) θ(テータ) ι(イオタ) κ(カッパ) λ(ラムダ) μ(ミュー) ν(ニュー) ξ(クシー) ο(オミクロン) π(パイ) ρ(ロー) σ(シグマ) τ(タウ) υ(ユプシロン) φ(ファイ) χ(キー) ψ(プシー) ω(オメガ)
これらのうち,ο(オミクロン)は,第2モーラ(「ミ」)がアクセント核を担う2型(低高低低低)が,コロナ騒動以前から多かったようである。これは ε(イプシロン)や υ(ユプシロン)と併せて,長いものとして別扱いすべきだろう。長いものは,合成語のアクセントの影響を受けて,アクセント核が中間部に生じやすい。
漢字を使った視力検査で,指されるがままに漢字を1文字ずつ音読みで読み上げるとする。この場合も,「文」(ブン)は高低,「法」(ホウ)も高低,「研」(ケン)も高低,「究」(キュウ)も高低というように,すべて頭高型になる。視力検査という状況で,いわゆる「語の意味」を考えず,意味を切り離した文字を,語として読むことになるからである。
音読みの場合ばかりではない。私の名字はかなり珍しく,電話などで説明することがよくあるが,「定(サダ)という字は~」と言う際の「定」(サダ)は,いつも頭高型で言っている。意味を考えず,文字として(そして引用された語として)読んでいるからである。
感動詞にも同様のことが観察できる。私自身は「原初的感動詞」と仮に呼んでいるが,呼び方はどうであれ,うめきや叫びなど,文字にならない発話は厳然としてある。この野生の発話が文中に取り込まれると野性味を失う。具体的に言えば,「箱を開けたらあら不思議」「箱を開けたらおや不思議」「箱を開けたらまあ大変」「箱を開けたらなんと中身は~」のように文の内部に取り込まれて他の語句と結びつくと,もはや野生の発話のままではいられない。日本語の語音(「あ」「ら」「お」「や」「ま」「あ」)やモーラ長(「あら」「おや」「まあ」は2モーラ。「なんと」は3モーラ)を持つようになり,つまり飼い慣らされる。そうなると,アクセントも持たねばならない。そして,これらのアクセント型は頭高型になっている。「困った時は頭高型」だからである。
極めつけは,「シクと読む字なんか無いでしょう」などと,存在しない文字を言う場合である。存在しないからアクセントも心内に登録されておらず発音できない,などということにはならない。たとえば「シクと読む字なんか無いでしょう」と言う時の「シク」は,「シ」が高く「ク」が低い,頭高型である。なぜか? 「困った時は頭高型」だからである。
3.従順な「お」と「ご」
いささか時代劇風になるが,先に挙げた短いファーストネームの前に,接頭辞の「お」を付けると,「お」は決まって低くなる。たとえば「トミ」(高低)の前に接頭辞の「お」を付けると「おトミ」(低高低)になる。「最初の音と2番目の音は高さが違う」という日本語共通語のアクセントのパターンに従い,かつ,「トミ」の「ト」がアクセント核を担っている(つまり高である)ことを尊重すると,「お」は低にならざるを得ない。他の名前も同様で,以下はすべて低高低である。
おけい おさき おしん おせい おたつ おとき おとみ おなつ おゆう おりん
名前を離れても,接頭辞の「お」は,結合相手のアクセント情報(具体的にはアクセント核の有無,そして有ならその位置)を一切変えず,ひたすら尊重することが多い。たとえば「勉強」(低高高高)のような平板型アクセントの語の直前に接頭辞「お」が付いても,結果としてでき上がる語(「お勉強」)のアクセント型は平板型のままである(「お勉強が」低高高高高高)。平板型であることを示すために,助詞「が」「に」「を」や判定詞(断定の助動詞)「だ」を付けておく。
お + 勉強が(低高高高高) = お勉強が(低高高高高高)
お + 仏壇に(低高高高高) = お仏壇に(低高高高高高)
お + 財布を(低高高高) = お財布を(低高高高高)
お + 散歩に(低高高高) = お散歩に(低高高高高)
お + 邪魔だ(低高高) = お邪魔だ(低高高高)
お + 世辞を(低高高) = お世辞を(低高高高)
もっとも,結合相手のアクセント情報が尊重されず,たとえば平板型の語(「洗濯」低高高高)に「お」が付いた結果,結合相手の第1モーラにアクセント核が移る(「お洗濯」低高低低低)ということもある。
お + 洗濯(低高高高) = お洗濯(低高低低低)
が,それは一般的な合成語のパターンである。類例を下に挙げる。
急 + 成長(低高高高) = 急成長(低高高低低低)
無 + 感動(低高高高) = 無感動(低高低低低)
重 + 過失(低高高) = 重過失(低高高低低)
過 + 呼吸(低高高) = 過呼吸(低高低低)
このことからすれば,際立つのは一般的なパターンから外れる,「お」の従順さである。
「お」と同じことは,接頭辞「ご」にも観察できる。次の「ご指導」のように,一般的なパターンどおり,結合相手のアクセント情報を変えてしまう場合もあるが,ごく僅かである。
ご + 指導(低高高) = ご指導(低高低低)
大抵の場合,「ご」は結合相手のアクセント情報(アクセント核の有無,そして有ならその位置)を一切変えず,これに従順にしたがう。平板型の結合相手と結合する場合の例を挙げておく。(ここでも助詞を付けて示す。)
ご + 専門が(低高高高高) = ご専門が(低高高高高高)
ご + 経験を(低高高高高) = ご経験を(低高高高高高)
ご + 病気に(低高高高) = ご病気に(低高高高高)
ご + 機嫌が(低高高高) = ご機嫌が(低高高高高)
接頭辞「お」「ご」がこのように従順なのはなぜか? 意味・音韻・文法の観点からそれぞれ言えるのは,これらが「目立たないことば」だということである。
まず,意味について。「お」も「ご」も,丁寧という意味を持っている。だが,たとえば「勉強」と言っても「お勉強」と言っても,指し示されている対象自体は同じである。このように,丁寧という意味は具体性に欠ける。研究者は普通こういう言い方をしないが,ごく大雑把に言ってしまえば「あってもなくても大体同じ意味」である。
次に,音韻について。「お」も「ご」も1音節,それも1モーラで,とにかく短い。ごく大雑把に言ってしまえば,「あるのかないのかわからない」。
最後に,文法について。接頭辞は自立性に欠ける。他のことばに付いて現れるのみで,単独で現れることはない。これも,ごく大雑把に言ってしまえば「おまけみたいなもの」である。
丁寧の接頭辞「お」と「ご」の従順さは,これらの目立たなさに注目すれば理解できる。「お」「ご」が付いても,結合相手のことばのアクセント情報が,まるで結合などしていないかのように一切変更されないのは,これらが目立たず,アクセントにおいてもないがしろにされているということだろう。
著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)
京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。
一覧に戻る