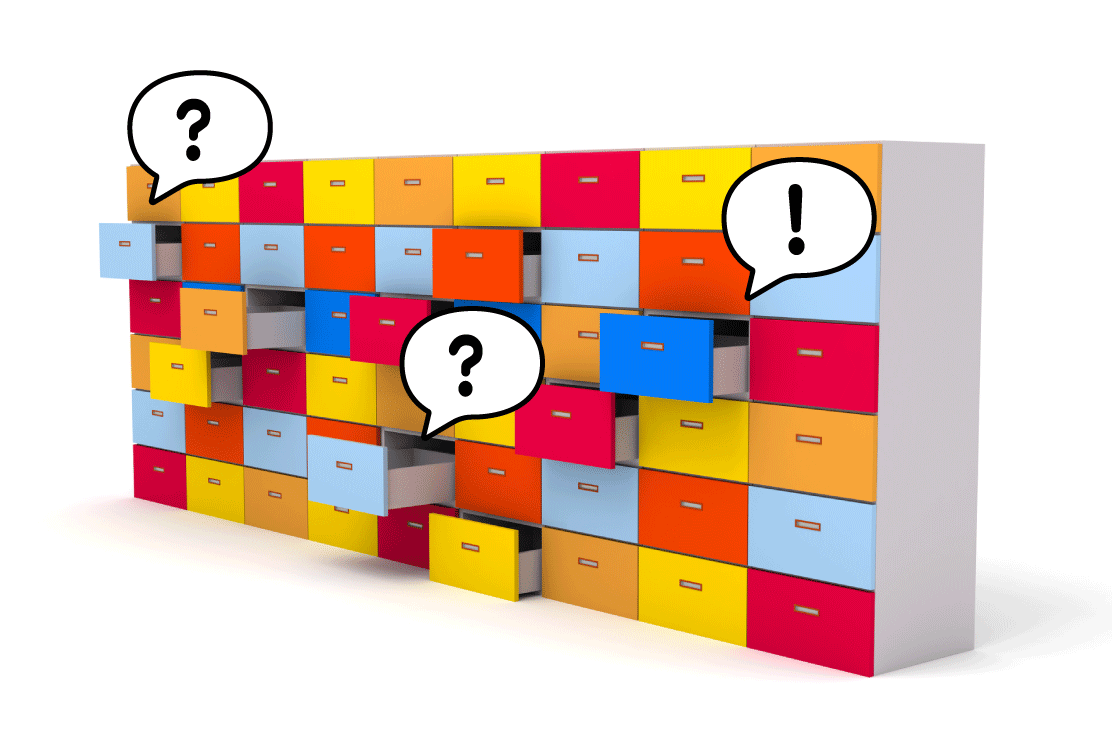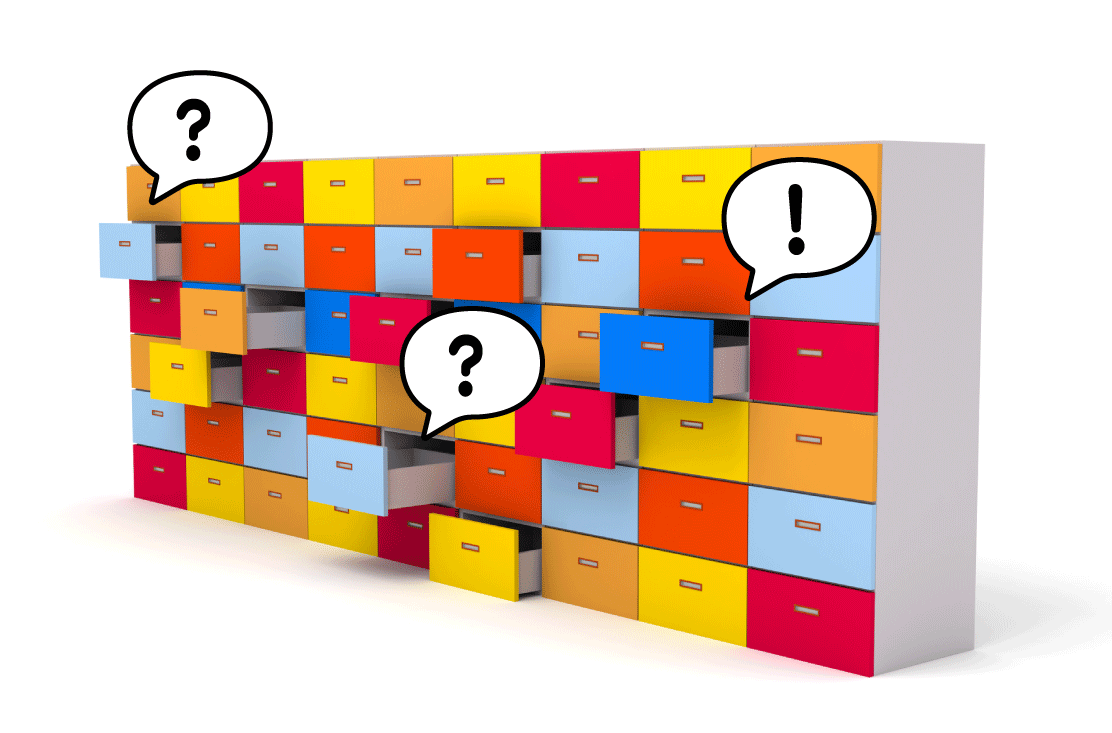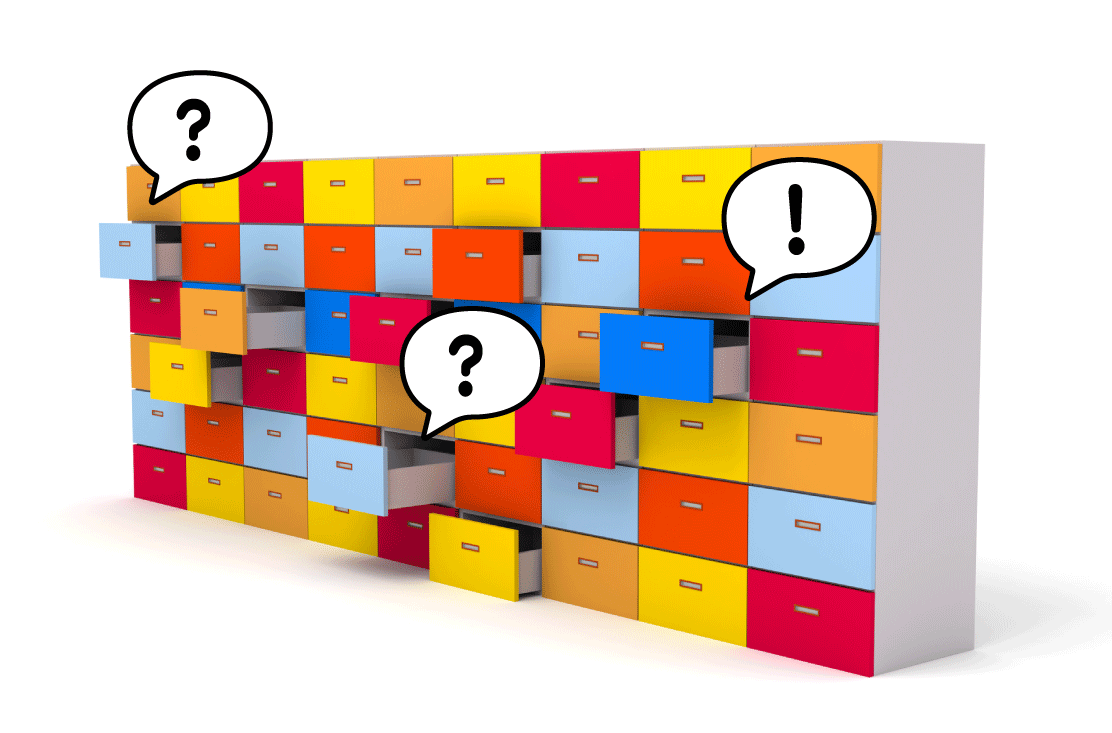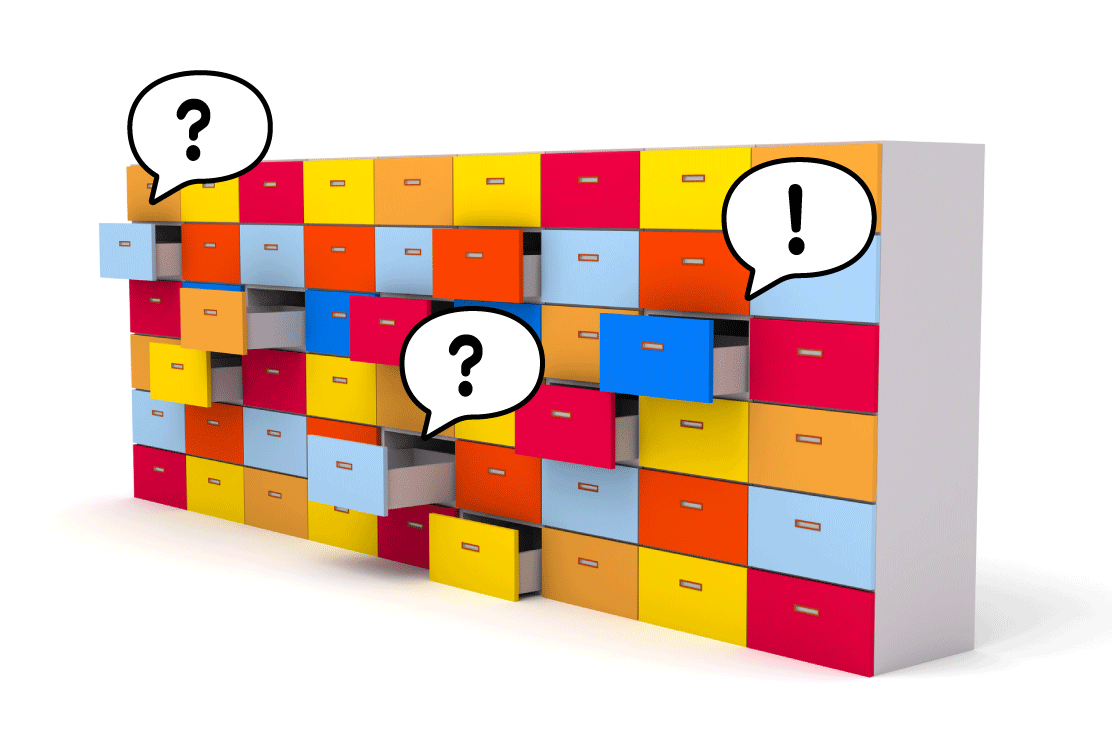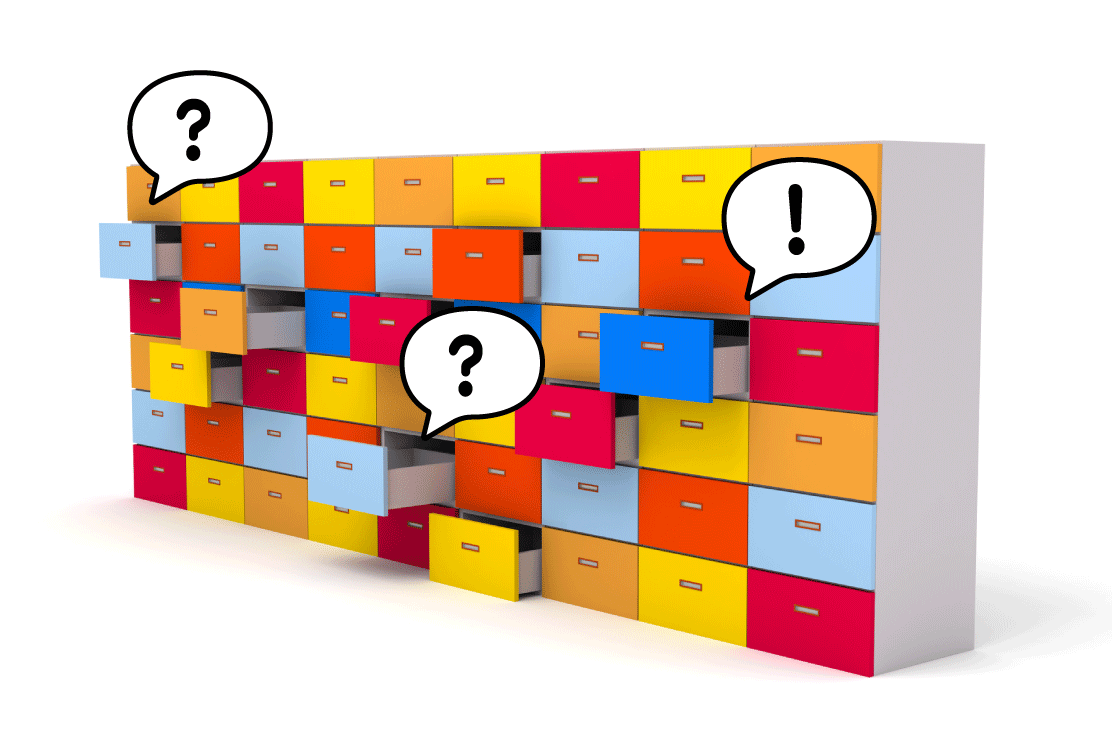コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第5回 入れ替えられない「心」と「気持ち」
関根健一
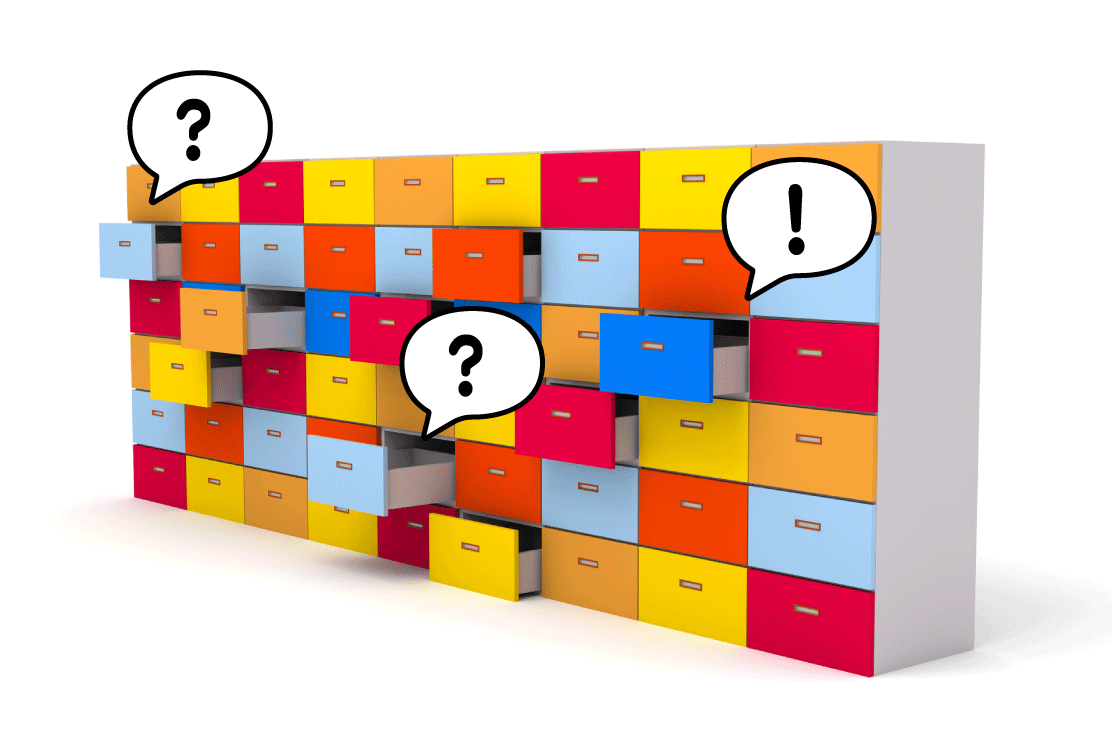
グラウンドの片隅に小さな花が咲いているのを見つけました。どこからか鳥の声が聞こえてきます。新シーズン到来! 昨年度は惜しくも初戦で敗退したわがチームも、いよいよ始動です。さて、決意のほどは? 「気持ちを入れ替えて取り組もう」──頑張って。「ぼくも、心を入れ替えて…」──おや、君は何かやらかしてしまったのかな。不祥事はまずいよ。
*****
「心」と「気持ち」は、どちらも人間の精神活動を指す言葉です。「心」は精神活動をつかさどる本体、精神の働きそのものを指します。一方、その都度変化する心の状態に注目するなら「気持ち」がふさわしいでしょう。失敗にめげずに前向きに考えよう、精神状態をプラスの方に持っていこう、というのが「気持ちを入れ替える」です。
「心を入れ替える」だと、精神活動の本体そのものを別のものに替える、それまでの考え方を改める(改心する)ことになってしまいます。なんだか、悪人が前非を悔いて再出発するようで、誤解されそうです。
「気持ちを入れ替える」は、「気持ちを切り替える」ともいいます。こちらが本来の言い方で、「心を入れ替える」に引かれて、「気持ちを入れ替える」ともいうようになったのかもしれませんが、意味は同じにはなりません。
*****
「~が揺れる」「~をつかむ」「親の~」といった場合は従来、主に「心」が使われてきましたが、「気持ち」でも意味が変わることはないでしょう。ただ、精神のよってきたる「心」を用いた方が深さ、強さが感じられます。デートに誘われて、行こうかどうか気持ちが揺れますが、突然、愛を告白されたら心が揺れます。有権者の気持ちをつかんで当選しても、期待に沿えなければすぐ離れていくでしょう。でも、いったん、心をつかめば岩盤支持層となって、ずっと支えてくれるに違いありません。一点でもよい成績を取ってほしいのが親の気持ちです。とはいえ、あまり無理して体を壊したりしないでねというのが親の心です。
*****
「心持ち」という言い方もありました。「気持ち」よりも古くからある言葉で、『日本国語大辞典』などによれば、もとは、心の持ち方、気立てを指しましたが、物事に感じた心の状態をいう場合が増え、「気持ち」と似た意味で使われるようになりました。ところが、現在では「気持ち」の使用が優勢になったため、「心持ち」というと、どことなく古めかしい響きがあります。
*****
心の持ち方、気立ての意味でなら、やはり古風ですが、「心ばえ」が好まれるでしょうか。「インスタ映え」の「映え」ではありません。漢字では「心延え」と書きます。「延える」は、長く延ばす、張り渡すことで、長い縄に釣り糸をつけて魚をとる「延縄(はえなわ)」の「延」と語源は同じです。
心の働きが外へ向かって行き渡り、相手の心に届けられるのが「心ばえ」でしょう。ことさらに「映え」させる必要はないのです。
*****
不快な心持ちを追い遣(や)って、発散させるのは「心遣り」と言います。「(長くて太い鼻を気にしている禅智内供(ぜんちないぐ)は)内典外典(ないてんげてん)の中に、自分と同じような鼻のある人物を見出して、せめても幾分の心やりにしようとさえ思った」(芥川龍之介「鼻」)。つまりは、うさばらしです。
ところが近年、「温かい心やりに感激する」「心やりの医療」といった使い方もされます。『三省堂国語辞典』には第二版(1974年)から、「思いやり。同情」の意味が載りました。「うさばらし」とは正反対の心の働きということになり、まだ認めていない辞書が多数派です。
『国語教室』第113号(2020年4月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る