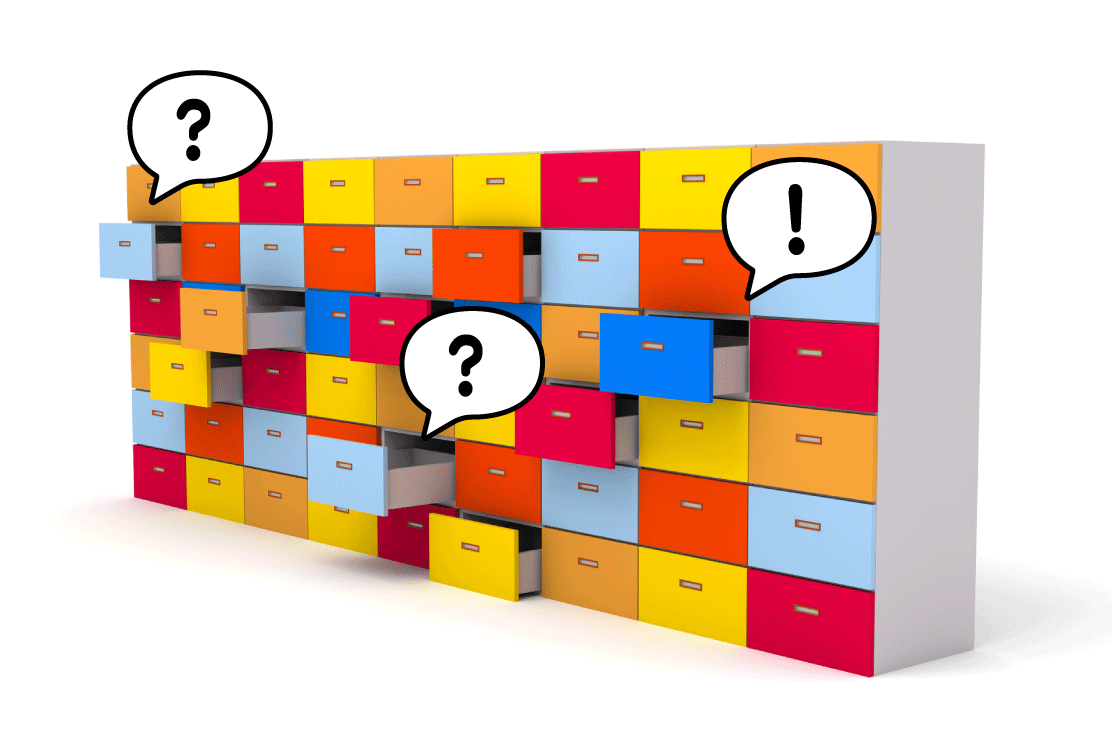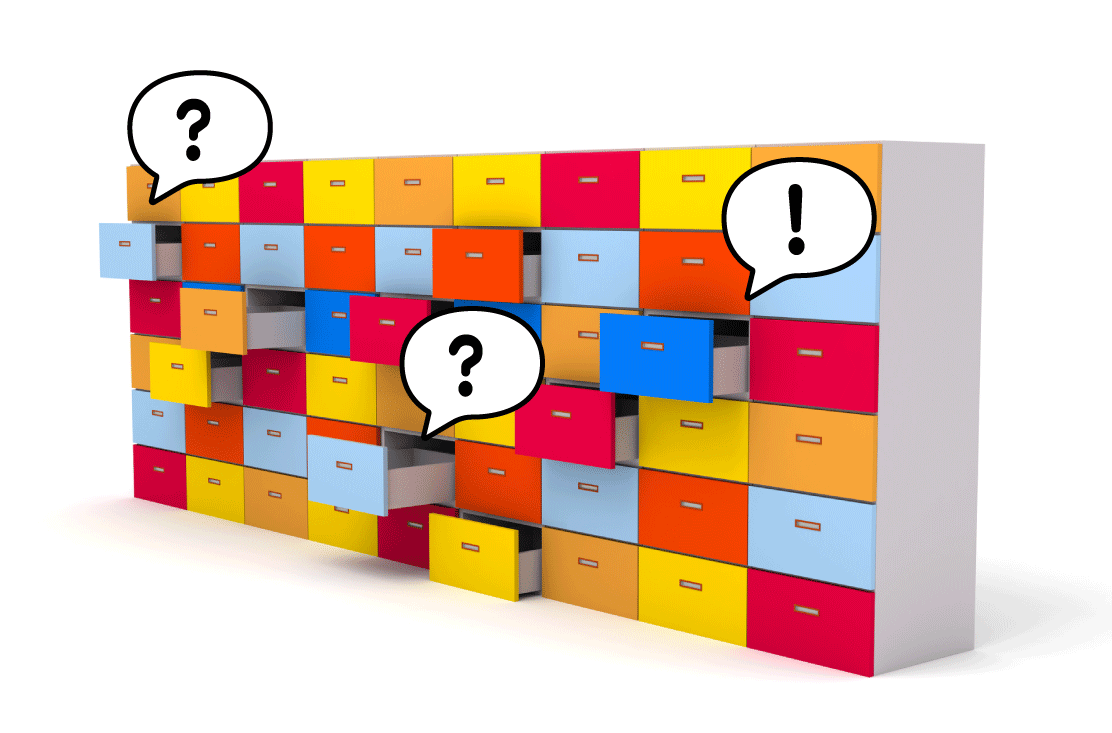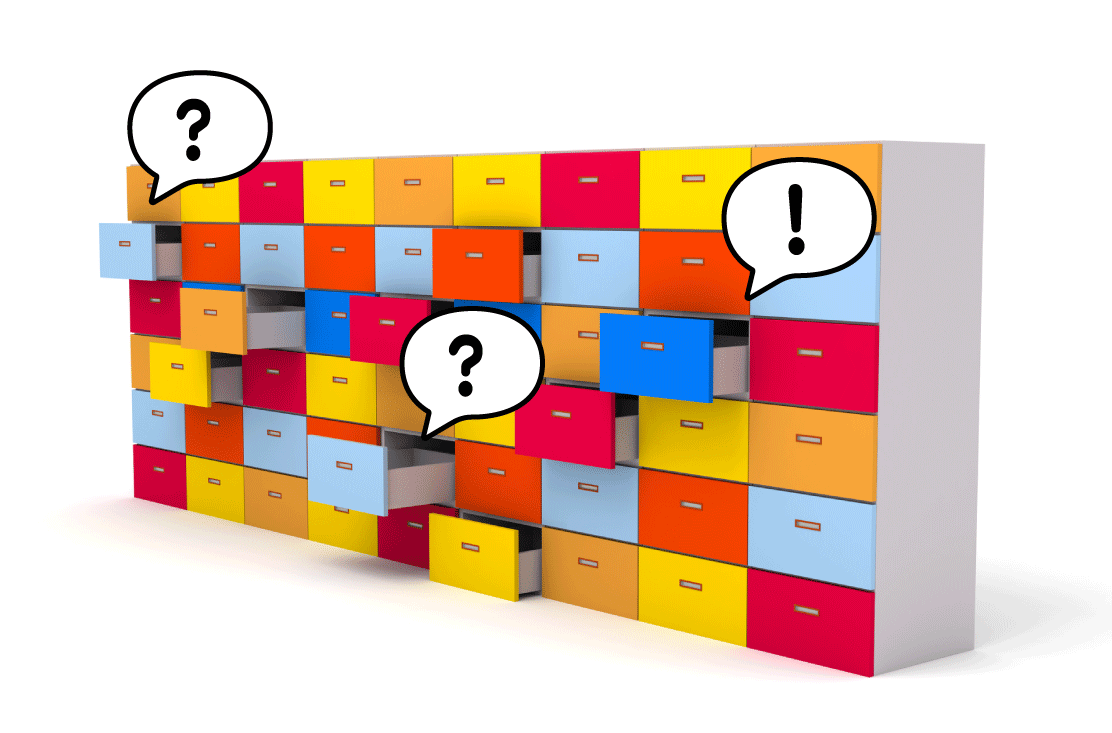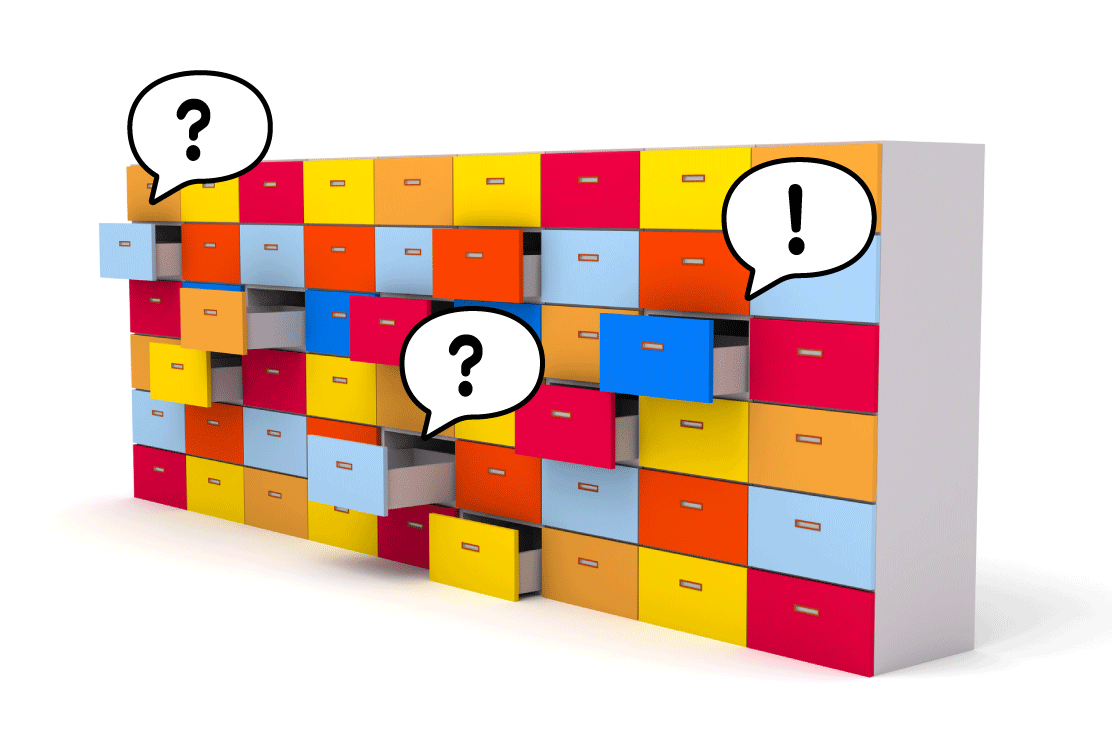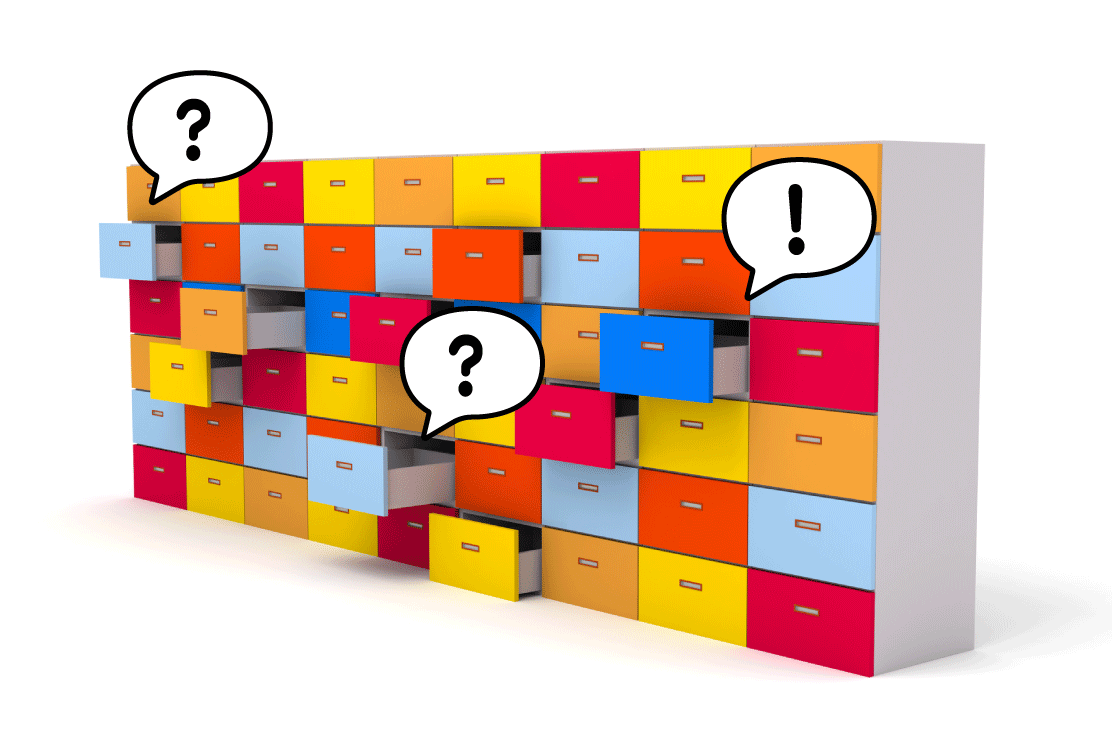コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第6回 誰の肝煎りなのかが、この話のキモだって?
関根健一
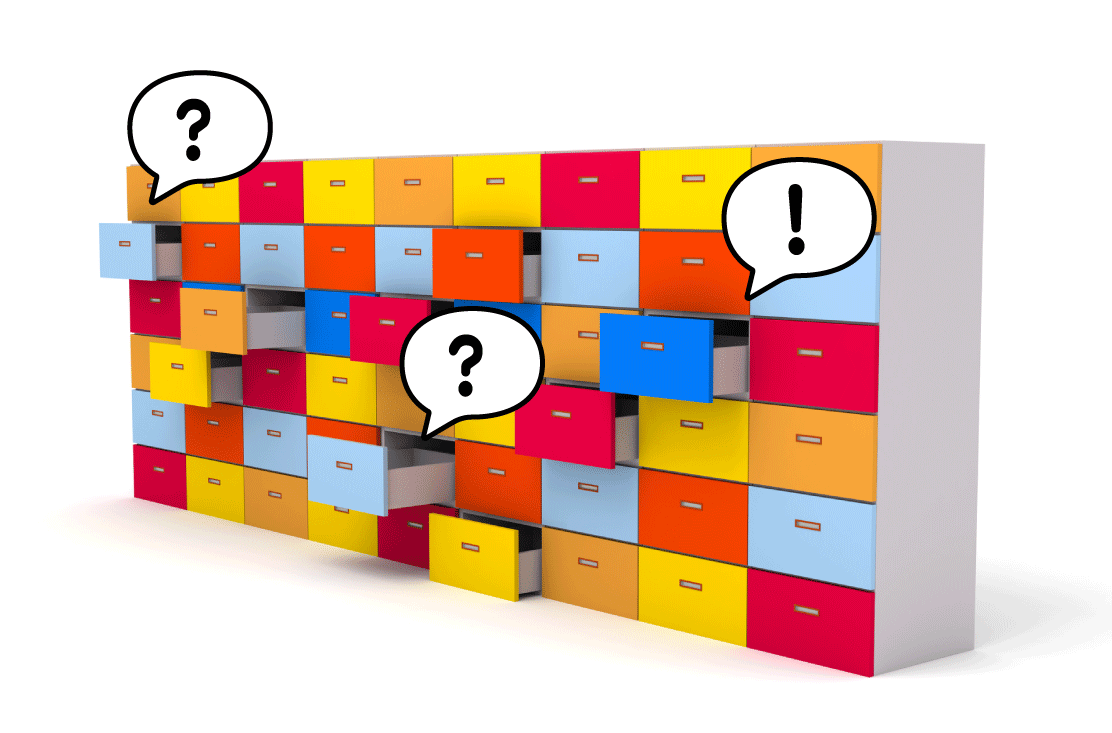
「さあ、ここ、ここだよ。ちゃんと覚えておいてね、必ず試験に出るから、ここがきょうの授業でいっちばん大事。この単元の××だよ」──全身全霊を傾けて訴えたいときってありますね。××のところ、何と言いますか。
*****
若い世代に伝わりやすいのは「キモ」でしょうか。漢字で書けば、「肝」、肝臓です。代謝を受け持つ大事な臓器で、心が宿る場所とも考えられたことから、「肝が太い」「肝が据わる」のように、精神、気力を指しても使われます。ただ、ゆるがせにはできないイメージがあるとはいえ、「この単元のキモ」「ここがキモだよ」などは比較的新しい使い方です。『日本国語大辞典』には、「物事の重要な点。急所」の意味が載っていますが、用例は室町から江戸時代のもので、現代の用法とは直接、関係なさそうです。現代語・新語を集めた『現代用語の基礎知識』(自由国民社)、『イミダス』(集英社)に初めて載ったのは、ともに1991年版でした。イミダスには「風俗・感覚語」として、「ステキの意」とも書かれていて、新語が広がり始めたときにありがちな用法の揺れがうかがわれます。
「肝腎」「肝要」といった熟語に引かれ、「キモ」という歯切れのよい語感も手伝って「要点、ねらい」の新用法が定着したのでしょう。そこで、『明鏡国語辞典 第三版』では、新語、新用法であることを示す〔新〕マーク付きで、この意味を追加しました。まぶたが重くなり始めた生徒たちの注意を促すには「ここがキモだぞ」の一言は効きそうです。ついでに、本来の意味と使い方を紹介して、言葉の変化の面白さを知ってもらう材料にもしてみてください。
*****
もっとも、毎回「ここがキモだ」では、効果が薄れてきます。別の言葉も探してみると……、ツボ、要所、要、眼目と来て、「さわり」が頭に浮かんだ方はいませんか。「さわり」は本来、義太夫節の曲の中の聴きどころを言い、そこから「さわりだけ聴く・読む」のように、最も印象的な箇所を指して使われます。語源からすると、楽曲や物語といった芸術作品について用いるのがふさわしい感じがしますが、『広辞苑』は「要点」という言葉を語釈に入れています。平成19年度「国語に関する世論調査」では、しばしば誤用と指摘される「話などの最初の部分のこと」に対し、「話などの要点のこと」を本来の意味として選択肢にしました。実用的な文書で「さわり」に該当する箇所は「要点」ということになるかもしれません。
*****
さて、『明鏡』ではもう一か所、「肝」絡みの言葉「肝煎り」に、〔新〕の語釈を追加しています。「肝を煎る」ごとく、あれこれ悩み、心をくだき、口添えしたり取り持ったりして、あれこれ差配するのが「肝煎り」です。頼まれて(お節介な人は頼まれなくても)仲介・紹介する行為について用いられてきました。
徳川幕府には「高家肝煎(こうけきもいり)」なる職があり、「忠臣蔵」の敵役・吉良上野介(きらこうずけのすけ)も就いていました。月番制で、儀式などを司る高家の中での責任者、世話役といった性格の役目だったようです。
ところが、最近は、「社長の肝煎りで始めた新事業」「首相肝煎りの布マスク配布」のように、単なる仲介役・世話役にとどまらず、自ら提案し、先頭に立って旗を振るような場合にも用いることが増えています。『明鏡』の解説でも、「〔新〕意見や考えを、中心になってとなえること。主唱。発案」としました。新聞やテレビではむしろこちらの使い方が主流になっています。「肝煎り」の新用法には、「肝」が持つに至った「要点、ねらい」のイメージが投影されている気もします。
『国語教室』第114号(2020年10月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る