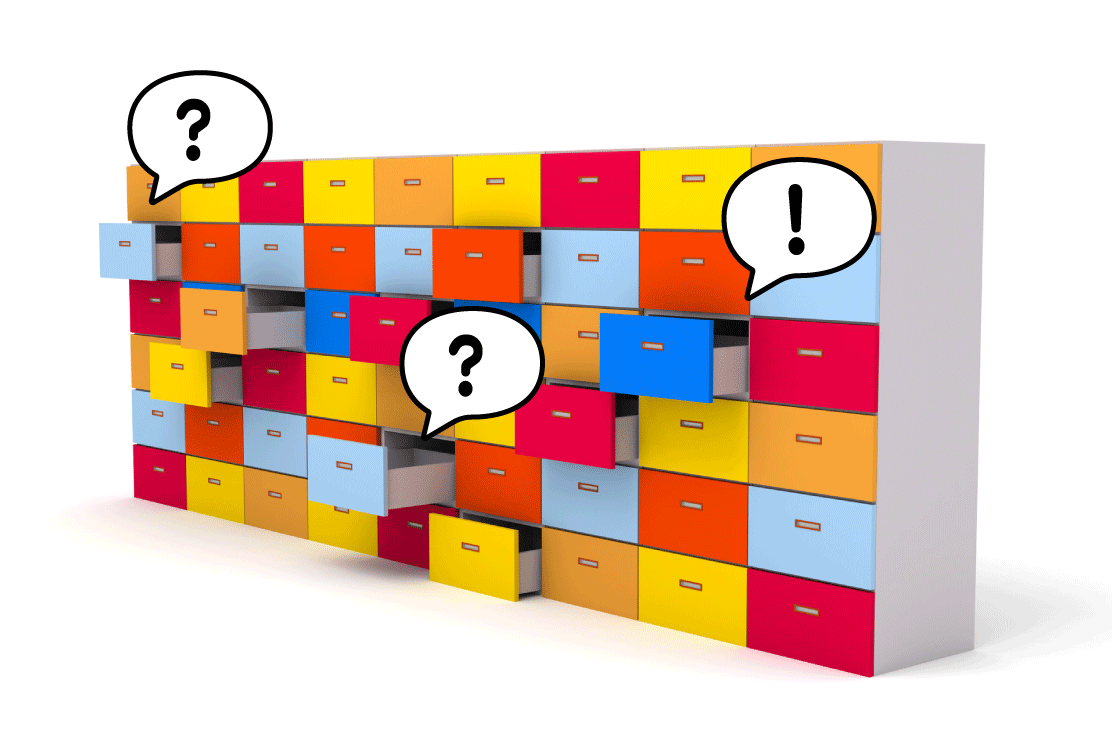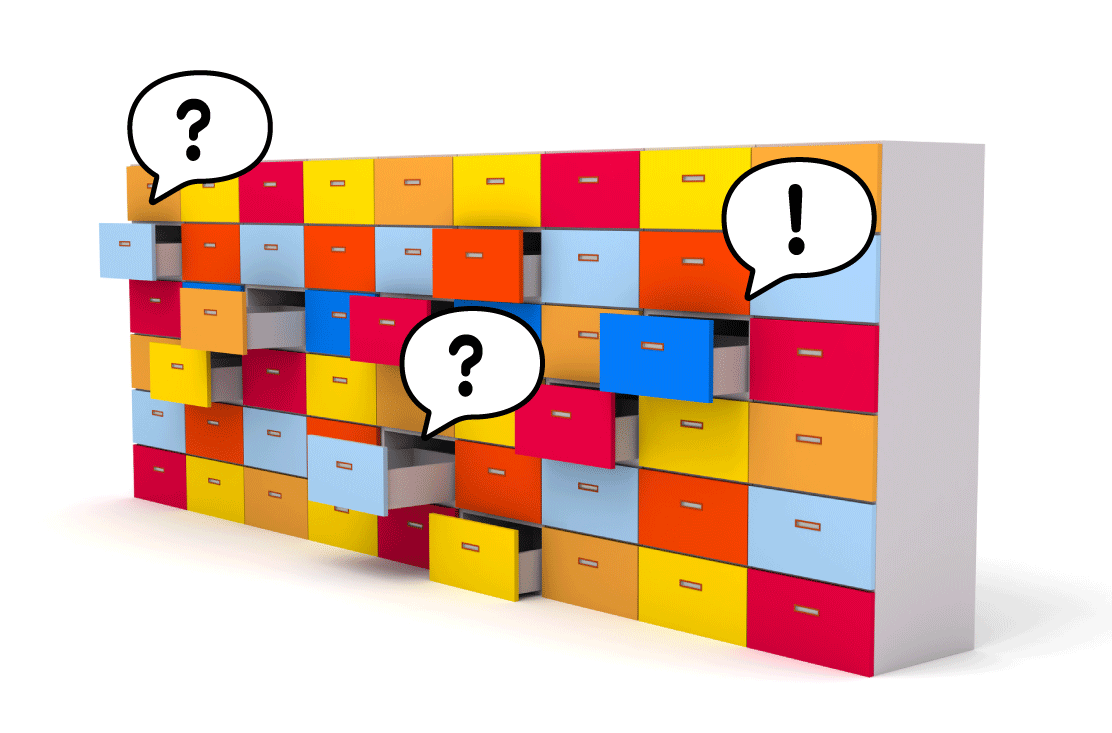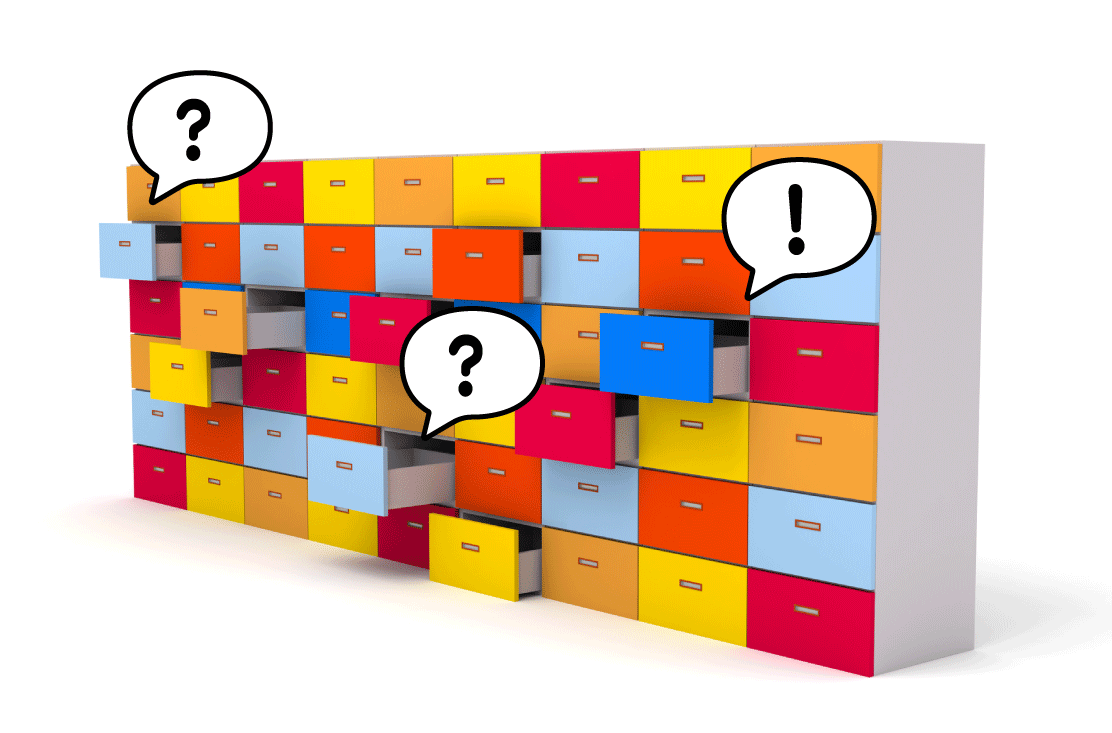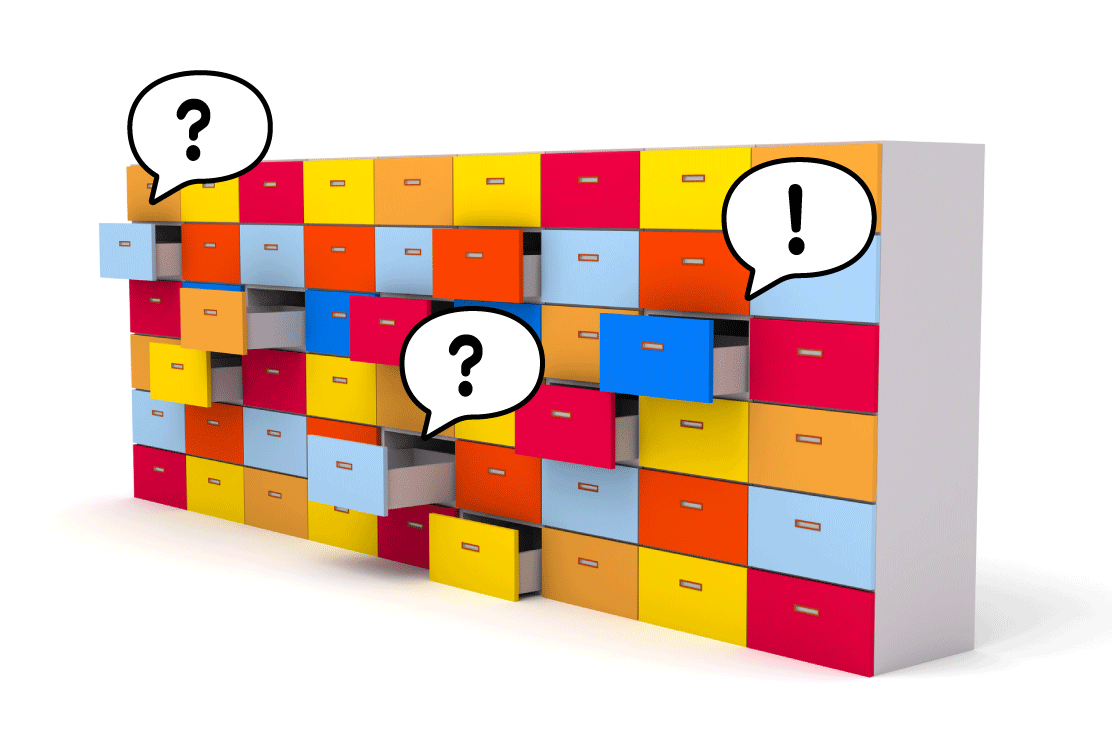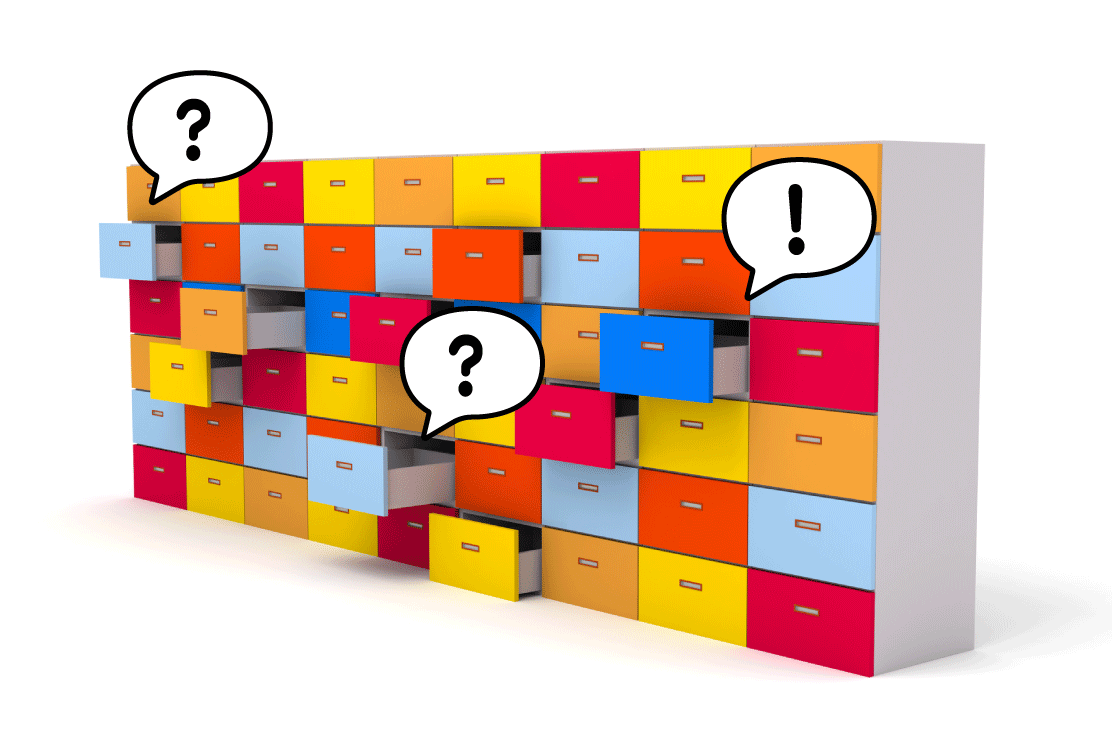コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第9回 「小細工がうまい利口者」って褒めたつもり?
関根健一
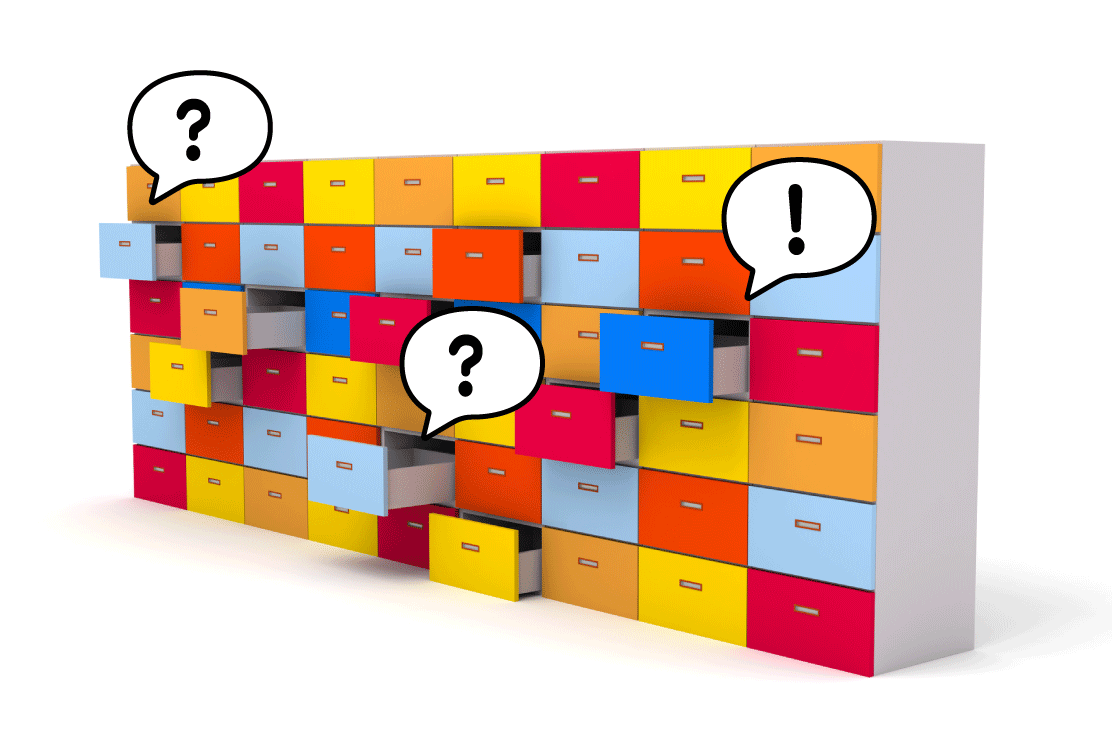
子どもの頃、「お利口さん」と言われたときには、ご褒美が待っていたものです。ところが、大人になって、「利口に立ち回っている」などとうわさされようものなら、人望を失っているおそれがあることを覚悟した方がよさそうです。面倒なことは他人に押し付け、うまくいったら自分の手柄、失敗したら知らん顔なんだから──なんて警戒されているのかもしれません。
「利口」はもともと口の利き方がうまい様子を指します。頭と舌の回転の速さが「利口」の本領ですから、本質を見極め、的確な判断を下す「聡明」や「賢明」と比べると、少々軽薄な部分はありますが、「利口」という語それ自体は褒め言葉でしょう。ただし、「立ち回る」と組み合わされると、非難するニュアンスが際立ちます。
言葉の意味には広がりがあり、使い方、受け取り方次第で、褒め言葉にもなれば、陰口、憎まれ口にもなります。
*****
もとの意味は中立的でも、よくないことの比喩として用いられる言葉もあります。「小細工」は、手先を使ってするこまごまとした細工を言います。「小細工ができる」のは優れた技術と忍耐力の賜物です。しかし、目先をごまかすだけの浅はかな策略をたとえる比喩的な用法があることに気付かず、「丁寧な説明だったよ。なかなか小細工がうまいね」などと言ったら、相手は不愉快な思いをしてしまいます。
金銭や損得の計算に細かく気を使うのを「計算高い」と表します。足し算、引き算ではなく、状況を判断して、その後の過程や結果を予測するのも「計算」ですが、「計算高い経営者」などというと、冷酷な人物像が浮かんできます。
*****
四季折々の草花が楽しめる、耳を澄ませば小川が流れる音と鳥の声が聞こえる──そんなときの決まり文句が「風情がある」です。日本人の美的趣向を表す「風情」という言葉には、それ自体、味わい深い趣が感じられます。
ところが、「〇〇風情」(〇〇には人の名前や役目、職業、地位などが入ります)と言ったときは、その〇〇が大したことがない、つまらない者であるという意味を表します。「私風情が~」なら謙遜する気持ちを示しますが、他人について使う場合は、その人をおとしめることになります。
*****
文章を書くときには、それぞれの言葉が持つ意味の広がりや、比喩的な用法などに注意して、内容や文脈にふさわしい使い方をする必要があるでしょう。だいたいこんな意味だろうと適当に組み合わせて文章を作ると、不快な思いをさせたり、傷つけたりすることもあります。「そんなつもりなんてない」と言っても、その「つもり」が表れてしまっては言い訳は利きません。
このたび、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』という本を書きました。書き手の意思・考えがきちんと読み手に伝わる文章を書くためにおさえておきたい、言葉の使い方、選び方を解説しています。「正確さ」と「分かりやすさ」への目配りに加え、今回紹介したような「ふさわしさ」の観点からの注意点も取り上げました。本格的に始まる新指導要領の「書く」活動の参考にもなると思います。「フツーに」の言い方が気になった方もぜひ手に取ってみてください。
『国語教室』第117号(2022年4月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る