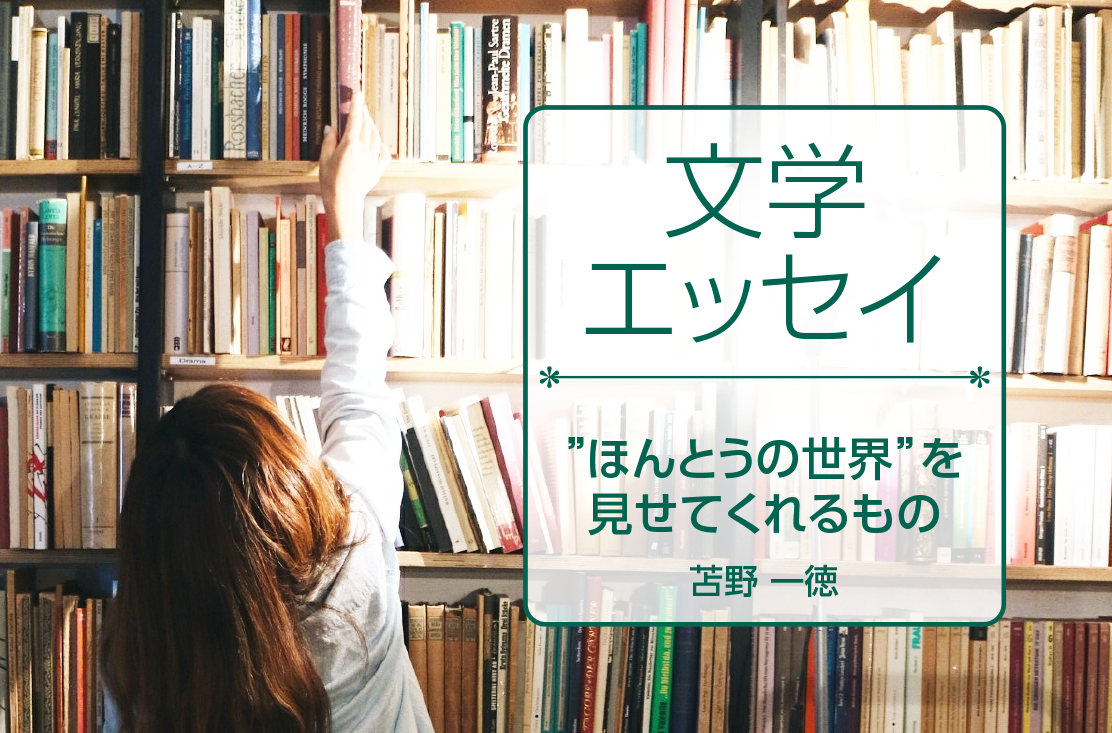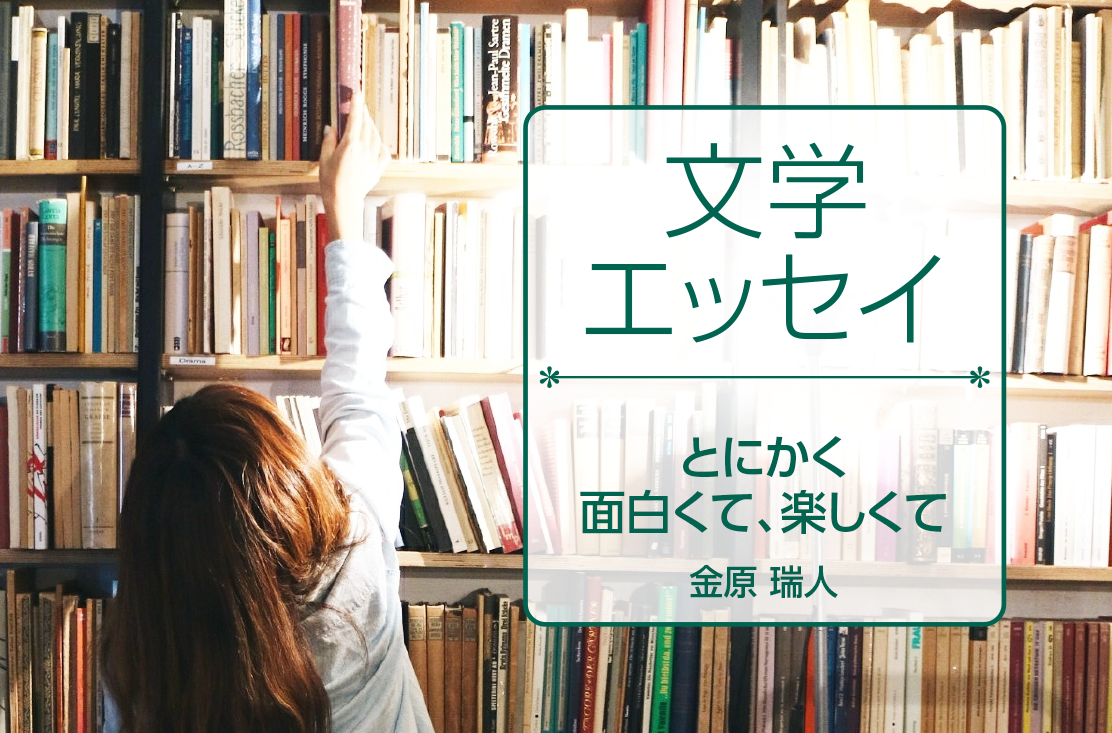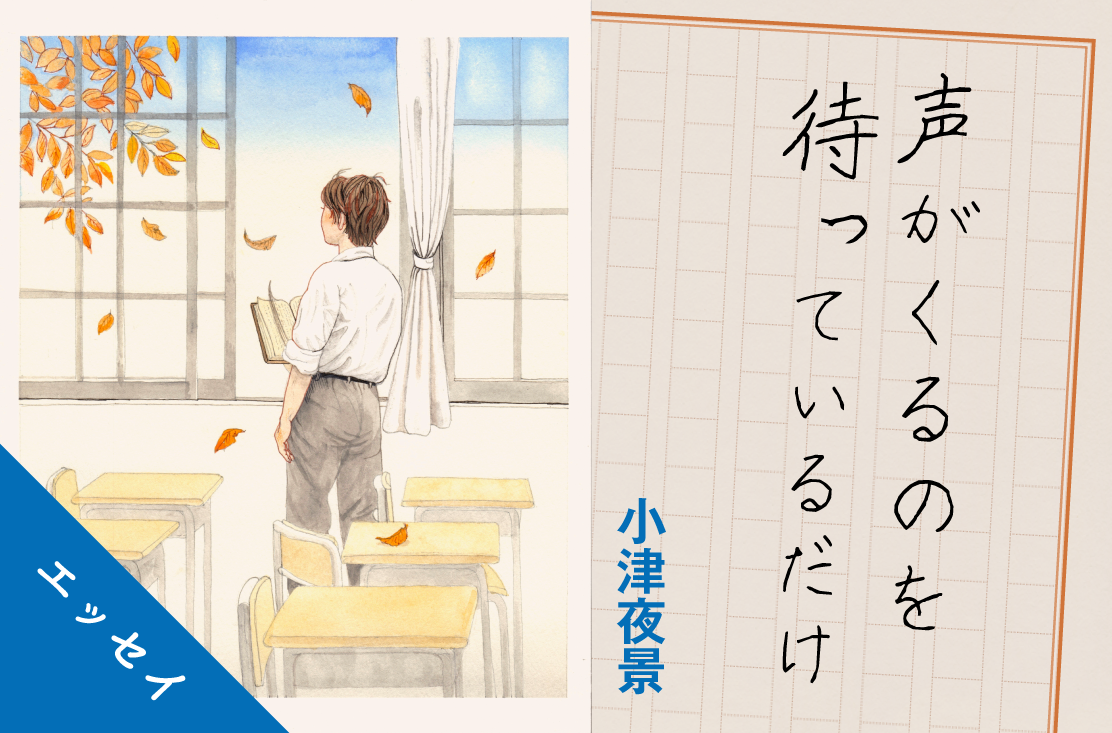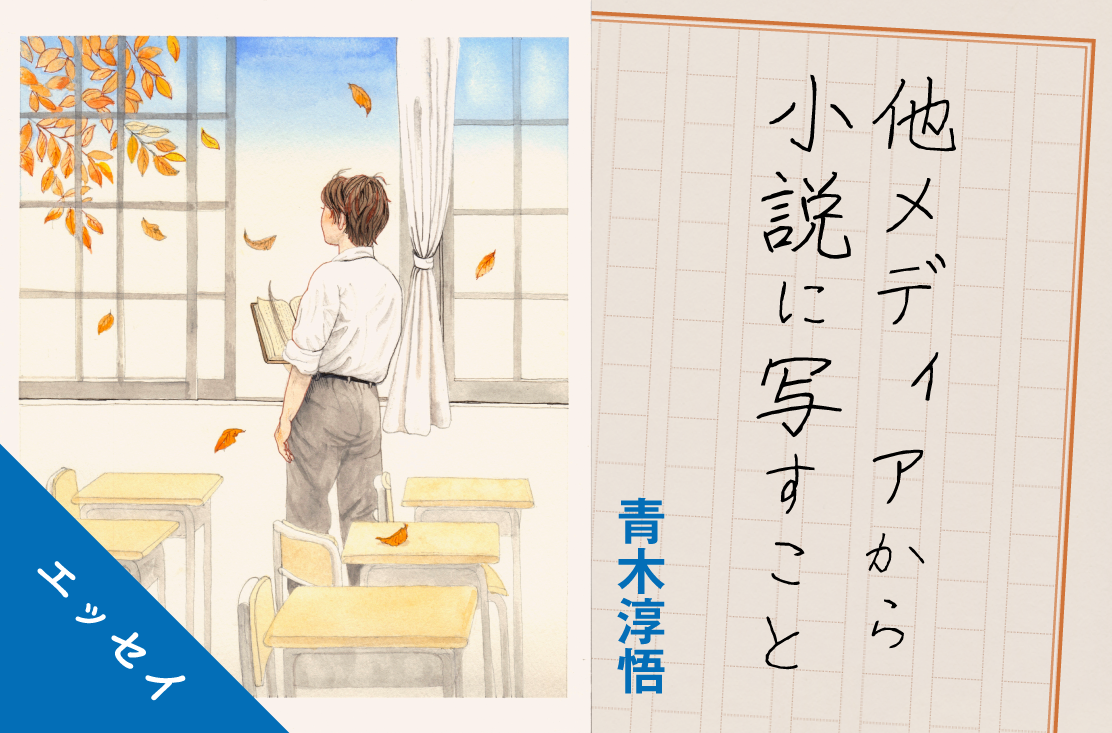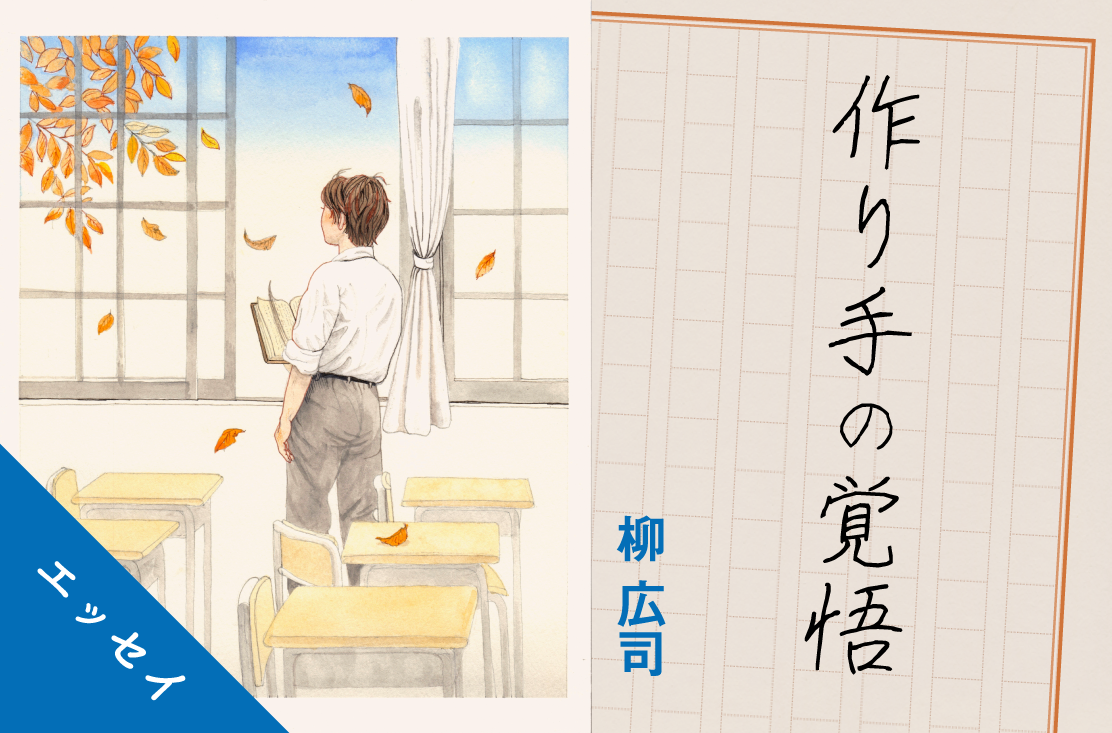文学エッセイ
時間をかけて読む
滝口悠生

去年から大学で週1回だけ演習の授業を持っている。授業といっても、学生と一緒に小説を読んでいるだけだ。私は研究者でも批評家でもないし、小説を読むのに小説家だろうが学生だろうが関係ない。みんなで読んで、あれこれ意見を交わす。そんなんでいいのか知らないが私は楽しいし学生も楽しそうに見える。
読書というのは基本的にひとりでしかできないから、自分の読み方を他人に伝えたり、他人の読み方を知ったりすると、気づくことがたくさんある。いろいろな読み方について、あれこれ議論する。結論を求めたがる者もいるが、授業内での結論は出さない。それぞれの読みが共振したりぶつかったりすることこそが大勢でひとつの小説を読むことの意義だと思う。議論は結構だが結論は出したい者が各々出せばいいし、出さなくてもいい。
今年、授業が終わったあと私のところに質問にきた学生が「自分は物語の展開がわかりやすくて、どんどんページをめくって読み進められるような小説しかおもしろいと思えないんです」と言った。
読書というのは好きな小説を好きなように読めばいいものだと思うが、大学の授業や演習で取り上げる小説には、なにも事件が起きないとか、主人公が延々思索をめぐらせるとか、とりとめない会話や風景描写が続くとか、展開らしい展開のない作品もまあ多い。たとえばリーダビリティの高いエンタメ小説を読み慣れていると、授業で読むような小説は平板でとっかかりがなく、どう楽しめばいいのかわからないのだろう。その学生は、そのことに少しコンプレックスを感じていたようだった。
「どうすれば展開のない小説をおもしろく読むことができますか」とその学生は私に訊いた。
「ゆっくり読んでみたらどうですか」と私は伝えた。
ふだん自分が読むより何倍も時間をかけて、一文一文を読んでみる。別に好みの合わない小説を選ぶ必要はない。ふだん読んでいるようなわかりやすい展開の小説でもいいから、読み方を変えてみよう。
スローモーションで動画を見ると、ふつうの再生速度では気がつかなかったことに気づく。それと同じで、ゆっくり読むと速く読んだときには気づかなかったことに必ず気がつく。いろんなものが目に入ってくる。どうしてこの語が選ばれたのか、どうしてこの語順なのか、どうしてこの表記なのか、どうしてここに読点があるのか、どうしてこの描写が必要だったのか。だんだん、そういう細部が気になってくる。
読者をはらはらさせたり、感動に導く展開は、たくさんある小説の楽しみ方のひとつに過ぎない。そういうものを期待しても、すべての小説がその期待に応えてくれるわけではない。しかし、どんな小説であれ、ゆっくり読めば読んだだけ発見がある、ということは間違いがない。
教室ではみんなと一緒に小説を読むくらいしかできないが、小説の実作者として学生に教えられることがあるとすれば、いくら時間をかけてもあなたがそれを虚心坦懐に読んだならば、小説はあなたを裏切らない、ということだ。時間をかければかけた分だけ、あなたは小説からなにかを感じ、なにかを考えることができる。もしかしたら小説を読むことで、なにか大切なことに気づいたり、新しい考えにたどり着いたりするかもしれない。小説というのはそういうもので、それは小説を書いている小説家だからよく知っている。もっとも、小説は読み終えたからといってなにかご褒美やお土産を用意してはいない。小説の楽しみは、読んでいる間だけのものだ。だからこそ、ゆっくりじっくりと読もう。ともかく小説のなかへなかへと入っていく。文章の隙間、言葉と言葉のあいだに分け入って、潜入するみたいに。ゆっくり読む、というのはそんなイメージだ。
たとえば他人が読み終わった小説のあらすじや感想をいくら聞いても、自分がその小説を読んだことにはならない。「どんな筋立てか」「なにについて書かれていたか」「主題はなにか」といったことは、小説の答えでも意味でもなく、空の容器のようなものに過ぎなくて、そういうものは小説のなかに入ると逆に見えない。そういうものは小説を外から包む包装紙のようなものである。
小説の文章を時間をかけて読めば読むだけ、その小説の言葉はあなただけの音や景色をともなった特別なものになる。平板に見えていた文章に、実はたくさんの起伏が、激しい展開が見てとれるようにもなっている。
『国語教室』第112号より転載
著者プロフィール
滝口 悠生(たきぐち ゆうしょう)
小説家。2016年、「死んでいない者」で芥川賞を受賞。主な著書に、『愛と人生』『ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス』『死んでいない者』『高架線』など。
一覧に戻る