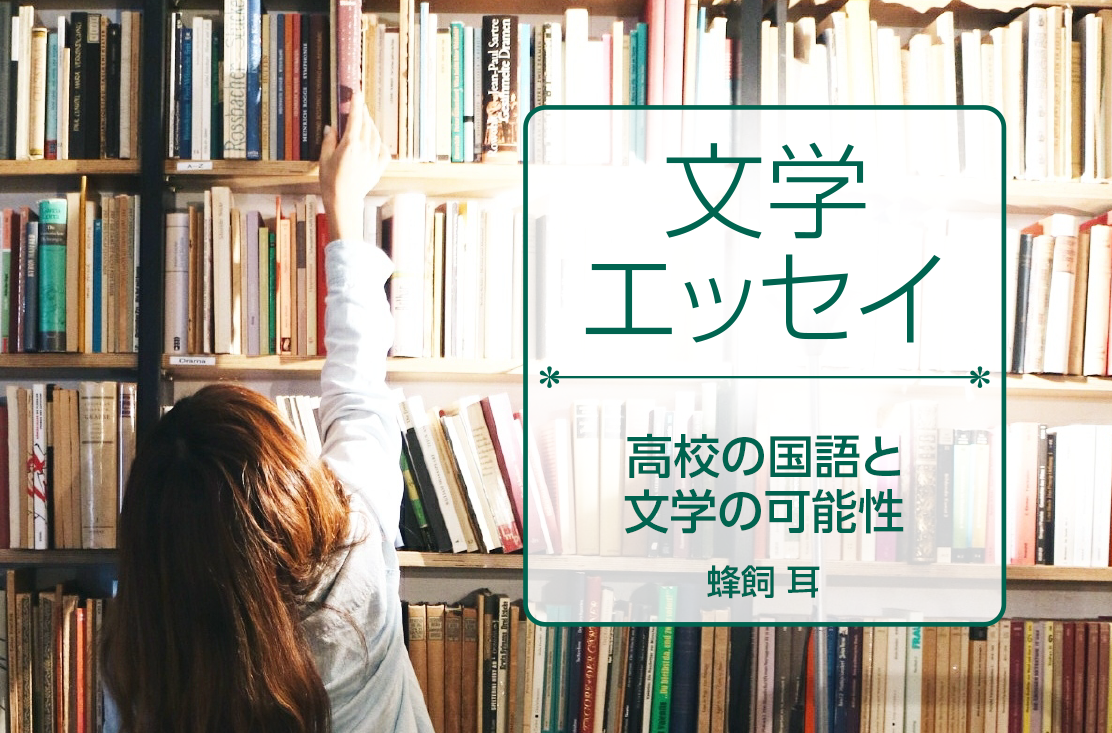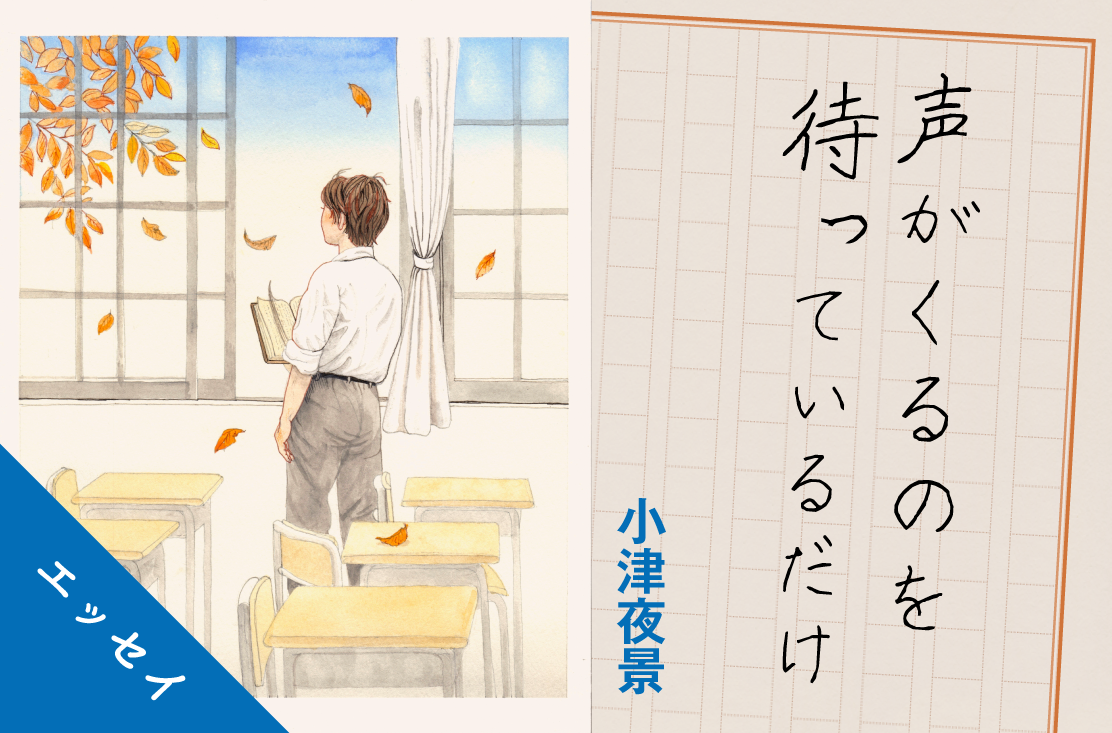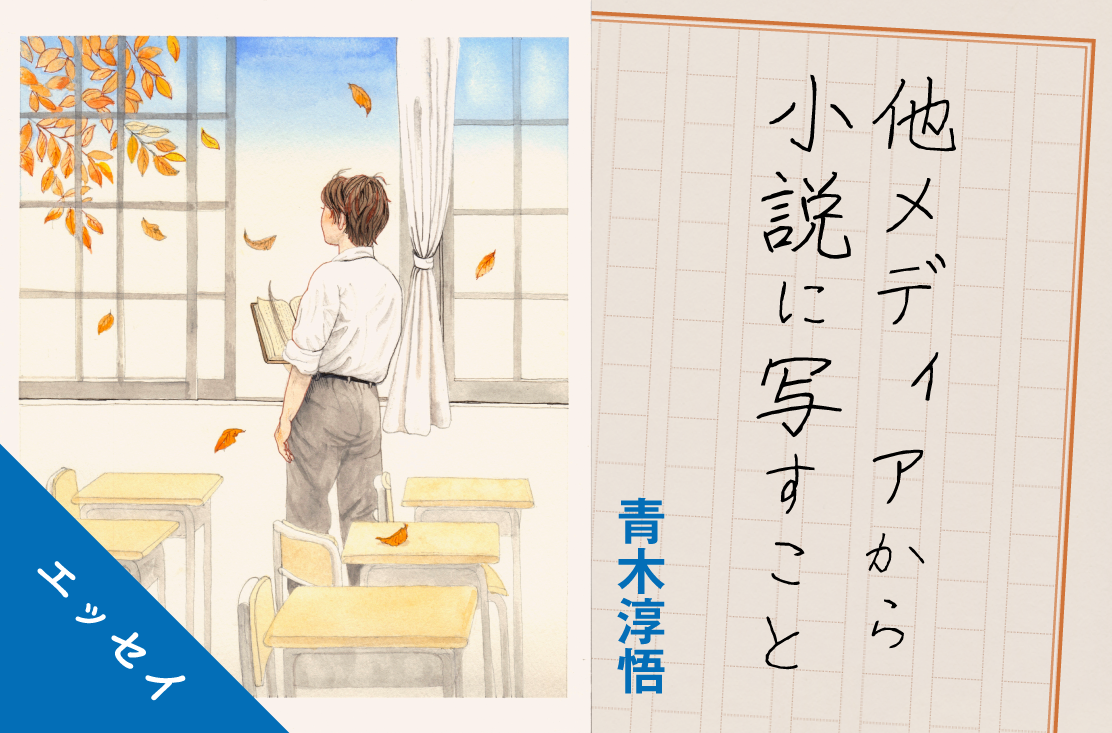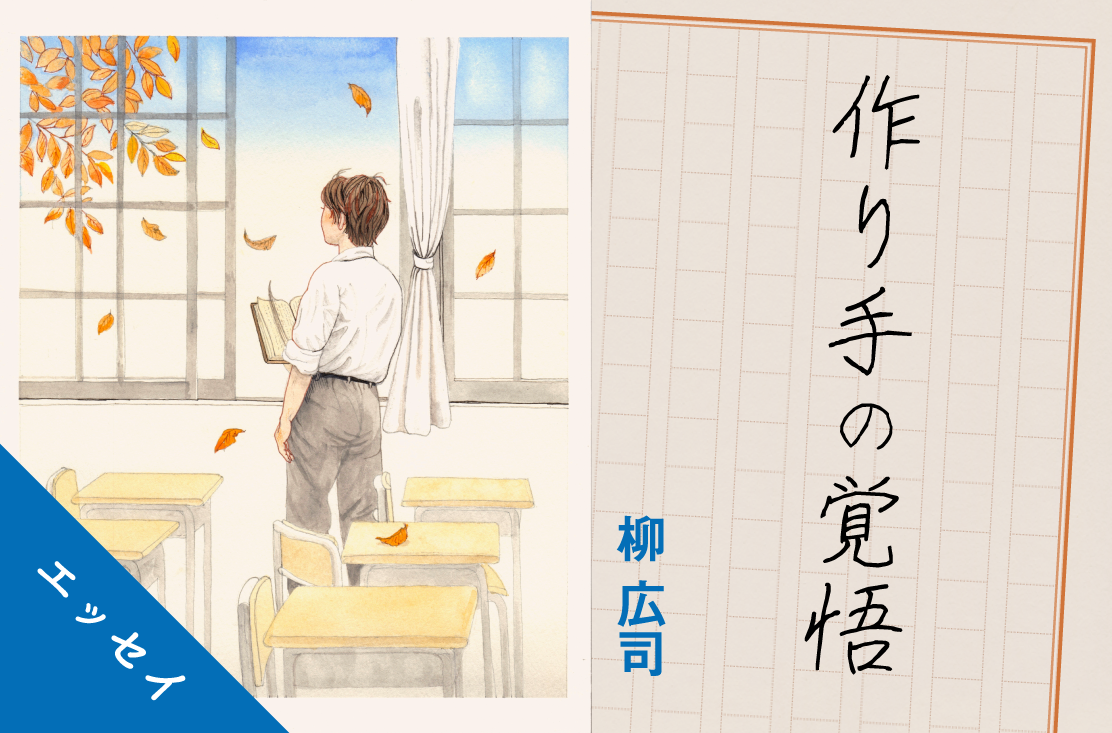文学エッセイ
とにかく面白くて、楽しくて
金原瑞人
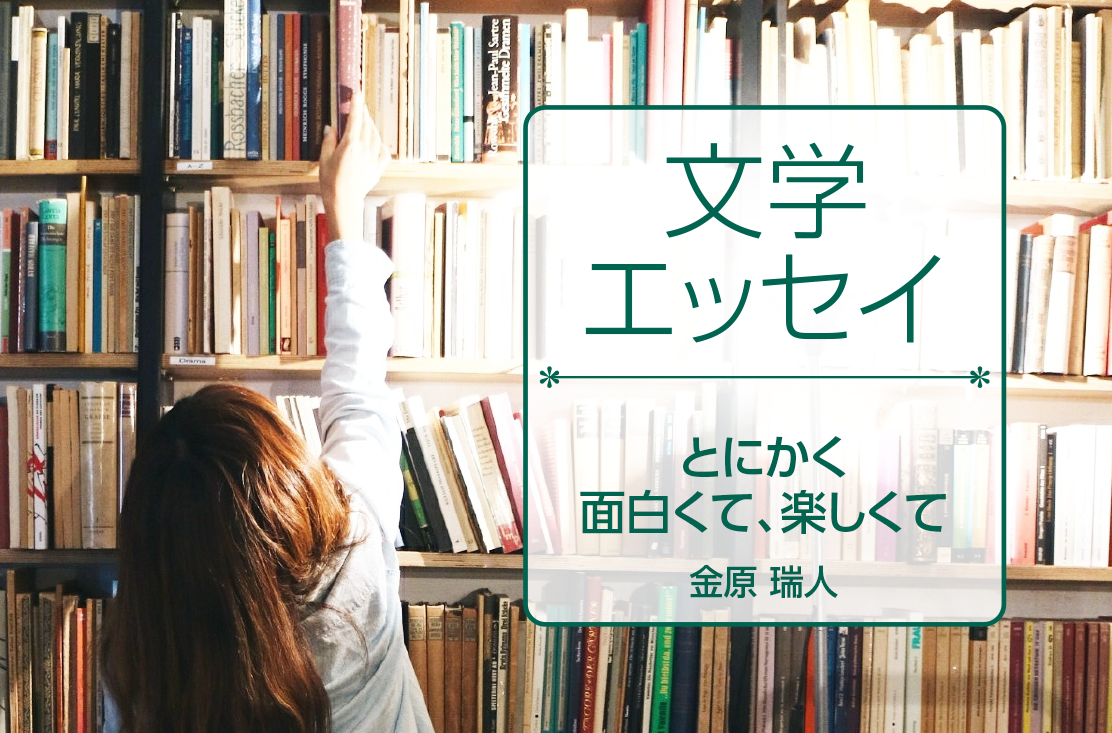
もう30年以上、翻訳をしている。訳書は550冊くらい。絵本も、共訳のものも、単行本が文庫本になったものもふくめてだ。翻訳という作業そのものはしんどくて、それほど好きではない。なのに、何が楽しくて、こんな辛気くさい作業をしているのだろう、肩は凝るし、目は悪くなるし、腰もあぶないし、などと不思議に思ったりする。
ひとついえるのは、本を読むのが好きということ、それからもうひとつ、自分が面白いと思う海外の作品をさがしてきて、それを訳して、「面白かった!」といわれるのが好きだということ。つまり、本が好きで、好きなものを紹介してほめられるのが好き、そこにつきる。
「文学」という言葉は気恥ずかしいので、ここでは「本」といっているのだが、つまるところ、いつもそばにあって、おそらく死ぬまでそばにあるのが本なのだと思う。ぼくにとっては、本も、音楽やアートやスポーツと同じものなのだが、最も親和性の高いのが本なのだろう。
じつは小学生の頃は、根っからのマンガ少年で、ほとんど本を読まなかった。というか、本の読み方がわからなかったのだ。曲がりくねった針金か折れ釘のような文字を音に変換し、その意味しているものを想像し、さらにそこから人物やストーリーを再現していくという作業が異様に難しかった。小学校にはそれがすんなりできる生徒とできない生徒がいて、自分はまるっきりできない生徒だった。幼い頃から本が楽に読めた人に、この気持ちはわからない。鉄棒の得意な生徒に、逆上がりのできない生徒の気持ちはわからないのと同じだ。
意外に思う人が多いかもしれないが、読み方がわからないというのはよくあることなのだ。たとえば、ぼくの母は本好きで、70を過ぎても時代小説なら1日で1冊くらいは平気で読んでいたが、マンガが読めなかった。読み方がわからないというのだ。もうひとつ、母は3Dの本(ごちゃごちゃした模様が見開きのページに印刷されていて、うまいこと目の焦点を合わせると、画像が浮き出て見える)の見方もわからなかった。読み方、見方、楽しみ方がわからないというのはそういうことだ。
ところがぼくの場合、中学生のある時期、ふと本の読み方がわかった。これか! と思ったときの驚きと喜びはいまでもよく覚えている。それからというもの、いきなり逆上がりができた男の子同様、まわりの人間があきれるほど逆上がりばかりし続けて、現在に至る。
自分の読書体験をまとめるとこんな感じだ。
中学生の頃は、海外のSF、ミステリーにはまり、本棚には古本屋で買ってきた、ブラッドベリ、ハインライン、アシモフ、クラーク、ウィリアム・アイリッシュ、ディクスン・カー、エラリー・クイーンなどといっしょに、筑摩書房の『世界文学大系』と河出書房のグリーン版が並んでいた。『現代日本文学大系』は第1巻を読んで、さっぱりわからなかったので、それきり開かなかった。坪内逍遥や二葉亭四迷の作品が入っていたのだからしょうがないのだが、その頃は、そんなことはわからなかった。
高校ではちょうど1年生のときに三島由紀夫の事件があって、「国語の授業なんか受けてるときじゃないだろう。三島の本を読もう」とかいっていたらしい(本人は覚えていないのだが、同級生からそんな話をきいた)。当時、三島、三島といいながらも、やはり澁澤龍彦や、フランスのマンディアルグといった幻想小説がむやみと面白く、じつに不健康な文学に夢中になっていた。そして大学は英文科に入って、今度は、思いのほか地平の開けた、見通しのいい本を読むようになり、さらに大学院に入ると児童書やヤングアダルトの本を好んで読むようになって……思いがけず、翻訳をするようになる。
という経歴なので、文学の魅力とかいわれてもよくわからない。とにかく面白くて、楽しくて、そばにないとさびしいというだけなのだ。
ただ、文学の魅力がわからないという人の気持ちはよくわかる。かつての自分がそうだったから。だから、そういう人は自分にしっくりくる音楽なりアートなりスポーツなりにそういうものを求めればいい。ただ、ぼくのように、本当は本が一番面白いはずの人が一生、その楽しさがわからないまま死んでいくのはもったいないと思うので、あちこちで講演をしたり、若者むけのブックガイドを作ったりしています。
『国語教室』第112号より転載
著者プロフィール
金原 瑞人(かねはら みずひと)
法政大学教授・翻訳家。児童文学、ヤングアダルト(YA)小説、一般書など幅広い翻訳を手がける。その他、YAのためのガイドブックの監修本なども多数。
一覧に戻る