青山あり! 中国祠墓紀行
第一回 唐玄宗泰陵(陝西省蒲城県)
平井 徹
- 2023.07.06

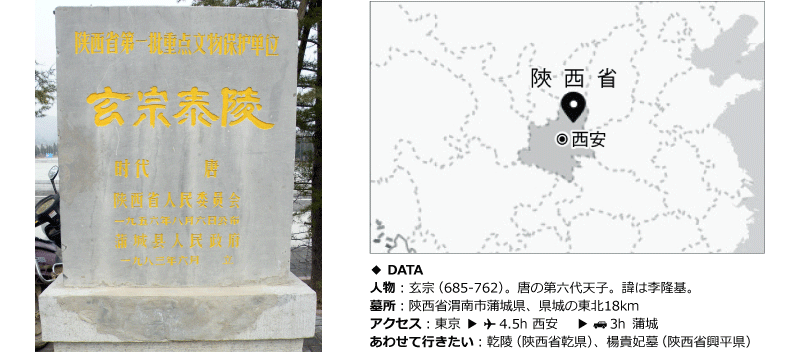
玄宗皇帝(六八五~七六二)。唐の第六代天子。姓は李、諱(いみな)は隆基(りゅうき)。王朝の内紛「武韋の禍」を収め、颯爽たる皇太子として史上に登場、即位後は「開元・天宝の治」を現出させたが、晩年、楊貴妃を寵愛し政務を怠ったことが「安史の乱」を引き起こし、憂悶のうちに世を去った。中国歴代皇帝の中でも、抜群の知名度を誇る人物である。
唐代に擁立された皇帝は二十一名おり、皇帝として崩じたのは十九名。うち一名を除く十八名の陵墓を総称して、「唐の十八陵」と呼ぶ。それらは、唐都長安(現在の陝西省西安市)を擁する関中平原の北に東西のラインを画す北山山脈の南麓にほぼ直線状に点々と分布しており、玄宗の「泰陵」はその最東端に位置している。一部の皇族、功臣の「陪葬墓」を除き、いずれもまだ発掘されていない。
泰陵は、省都西安市内中心部から約一三〇キロ、陝西省渭南市蒲城県、県城(県の中心街)の東北十八キロ、保南郷石道村にある。陵の周囲は三十六キロ、唐長安城とほぼ同じという。『旧唐書』玄宗紀によると、玄宗がかつて自ら「五陵」を拝し、父睿宗の「橋陵」に至った時、近くの金粟山が「龍が蹲り鳳が天翔ける」(龍盤鳳翥)地勢であるのを見て、左右の臣に「吾(われ)千秋(せんしゅう)の後(のち)、宜(よろ)しく此(こ)の地(ち)に葬(ほうむ)るべし、先陵(せんりょう)を奉(ほう)ずるを得(え)て、孝敬(こうけい)を忘(わす)れず」と言い置いたという。死の翌年、代宗皇帝(粛宗の子、玄宗の孫)の広徳元年三月に葬られた。

▲清の乾隆年間に立てられた石碑。「唐元宗泰陵」と刻まれている(2009年撮影)
西安を訪れる人は多いが、泰陵まで足を延ばす人は稀であろう。私はここに二〇〇九、二〇一七年と二回足跡を印している。前回はほぼ一日行程の強行軍であった。あともう少しというところで道が細くなり車が入れなくなって、現地の案内人が帰ろうというのを聞き入れず、ちょうど塀を建築中だった農家のレンガを道路に敷き詰めて道幅を確保し、車を進めたことが思い出深い。
泰陵は、多くの皇帝陵がそうであるように、山全体が墓という「山陵形式」である。後ろに金粟山、西南に敬母山、東に臥虎山が聳え、山ふところに抱かれている。二〇〇九年当時、陵へ続くアプローチ「神道」は工事用の車しか入れない砂利道で、左右の文官武官の石像も、半ば草に埋もれていた。中ほどまで行ったところに清の乾隆年間に立てられた石碑があり、ここだけ少々整地され開けていた。碑には「唐元宗泰陵」と刻まれているが、文字が違うのは、乾隆帝の祖父にあたる先々代康熙帝の諱を避けて、「玄」を「元」字に置き換えたことによる。
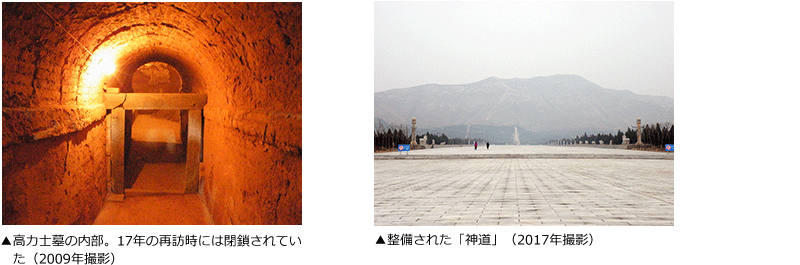
この時は、向かう途中で、玄宗の側近で、李白を讒言したことで名高い宦官高力士の墓(椿林郷山西村)を見つけ、地下の墓室まで入れてもらうというおまけもついた。彼が代宗によって玄宗陵に「陪葬」されたことは、新旧両『唐書』に記載がある。
再訪時は、西安から蒲城までの高速道路を利用して、二、三時間でスムーズに到着した。神道もすっかり舗装され観光地化していて、玄宗と楊貴妃の物語を講釈する商売をしている地元の老人の姿が印象的だった。この時は父睿宗の橋陵にも立ち寄ったが、雰囲気はほぼ同じだった。一方で、高力士の墓は閉鎖され、立ち入ることができなくなっていた。

▲芝居の神様となった「唐明皇」(2005年撮影)
前世紀末、私は留学先の天津に滞在していた。市の旧城内に、今から百年余り前に建てられた「広東会館」(「会館」は同郷者のコミュニティの意)という瀟洒な建物があり、現在は「天津戯曲博物館」として公開されている。内部には立派な「戯台」(芝居舞台)があり、一九一二年には孫文がこの場で演説を行っている。ここの職員と仲が良かった私は、自由に出入りさせてもらっていたのであったが、ふとある時、楽屋裏で何かを祀っているのでたずねてみたところ、それは「唐明皇(タンミンホワン)」だ、との答えが返ってきた。「明皇」とは玄宗の諡(おくりな)。長安の宮中に歌舞団「梨園」を抱えていた故事によって、また歴代天子の中で民衆の人気が最も高かったことから、彼は芝居の神様として、今なお信奉されているのである。ちなみに、廟号の「玄」字は、彼が道教を厚く尊崇していたことに由来している(南宋の陸游『入蜀記』に、道服をまとった玄宗の金銅の像が祀られていたとの記録がある)。「玄宗」の名を持つ皇帝は、中国史上、彼一人しか存在していない。
『国語教室』第112号(2020年2月)より

詳しくはこちら
一覧に戻る









