青山あり! 中国祠墓紀行
第三回 朱熹墓(福建省南平市建陽区)
平井 徹
- 2023.07.26

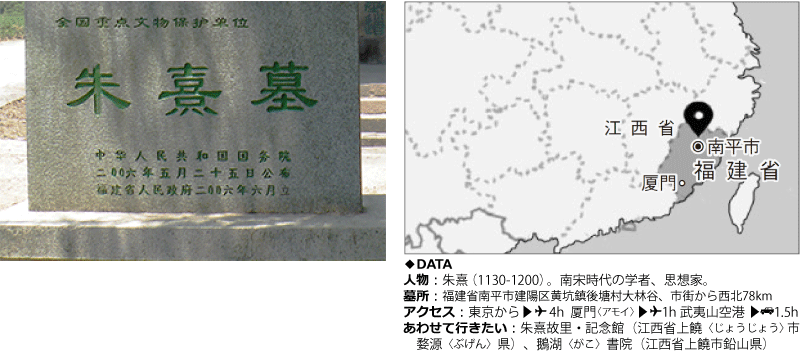
朱熹(しゅき)(一一三〇~一二〇〇)。南宋時代の学者、思想家。字(あざな)は元晦(げんかい)、のち仲晦(ちゅうかい)。号は晦菴(かいあん)など複数ある。儒学を組織的に体系化し、「宋学」を樹立した。朱子と尊称される。
福建省をめぐる旅の一環として、朱熹墓を訪ねようと企図したのは、二〇一二年の七月末のことだった。初日の夕刻に武夷山(ぶいさん)空港に着き、翌日から一帯を歩くこととした。

▲五夫鎮の荷花(2012年7月撮影)
まず市の東南部、五夫鎮府前(ごふちんふぜん)村にある「紫陽楼遺址」を訪れた。十代半ばの朱熹が母とともに移り住み、その後四十年間を過ごした旧居跡で、彼の祖籍(徽(き)州婺源(ぶげん)にある紫陽山から命名された。一九九八年に祠堂などを復元したが、ここはむしろ「荷花(ハス)の里」として有名で、日本の鄙びた農村を思わせる風情が心に残っている。同じ五夫鎮には、朱熹が講学した「興賢(こうけん)書院」(書院は、宋代以降多くあらわれた私塾の意)もあり、清(しん)代重修の古建築に興趣をそそられた。五夫鎮は、二〇一〇年に「中国歴史文化名鎮」に登録されている。
武夷山では、観光地区の一角にある「朱熹園」にも立ち寄った。敷地内には、「武夷書院」(もとの名は「武夷精舎(せいしゃ)」。ここも朱熹が講学した私塾)と、記念公園を備えている。公園内には、朱熹をはじめとする同時代の学者たちの塑像が並ぶ。
翌朝、一路南下して、建陽の朱熹墓に向かう。二〇一五年以降の行政区分では、建陽区として南平市の一部に編入されているが、私が訪問した時は独立した市だった。

▲建陽の朱熹墓。酷暑の中、訪れる人もなく、神さびたたたずまいで、沖縄に多く見られる亀甲墓を想起した。(2012年7月撮影)
墓は郊外の黄坑(こうこう)鎮後塘(こうとう)村大林谷(だいりんこく)、田圃の中の静寂な一角にある。墓地は二百平米ほどでこぢんまりしている。墓は東向きで、中国の墓には珍しく、卵型の栗石に覆われた円丘形で、いかにも「奥津城(おくつき)」といった風情に富んでいる。清の康煕(こうき)五十六年(一七一七)に建てられた墓碑に「宋先賢/朱子/夫人劉氏/墓」とあるとおり、夫婦の合葬墓である。 劉氏の歿年は朱熹より二十年以上も前であり、風水に恵まれた地であることから、朱熹は生前より、妻とともにここに葬られることを望んでいた。朱熹が建陽の「滄州(そうしゅう)精舎」(現在の「考亭書院」)で歿した当時、その学は「偽学」として弾圧されていたが、葬儀には、彼を慕う数千人が参列したという。朱子学が「官学」として認可され、権威を有するようになって以後、彼の墓に詣でる者は、手前の亭で、文官は轎(かご)より降り、武官は下馬する習わしとなった。
劉氏の歿年は朱熹より二十年以上も前であり、風水に恵まれた地であることから、朱熹は生前より、妻とともにここに葬られることを望んでいた。朱熹が建陽の「滄州(そうしゅう)精舎」(現在の「考亭書院」)で歿した当時、その学は「偽学」として弾圧されていたが、葬儀には、彼を慕う数千人が参列したという。朱子学が「官学」として認可され、権威を有するようになって以後、彼の墓に詣でる者は、手前の亭で、文官は轎(かご)より降り、武官は下馬する習わしとなった。
『国語教室』第114号(2020年10月)より
一覧に戻る











