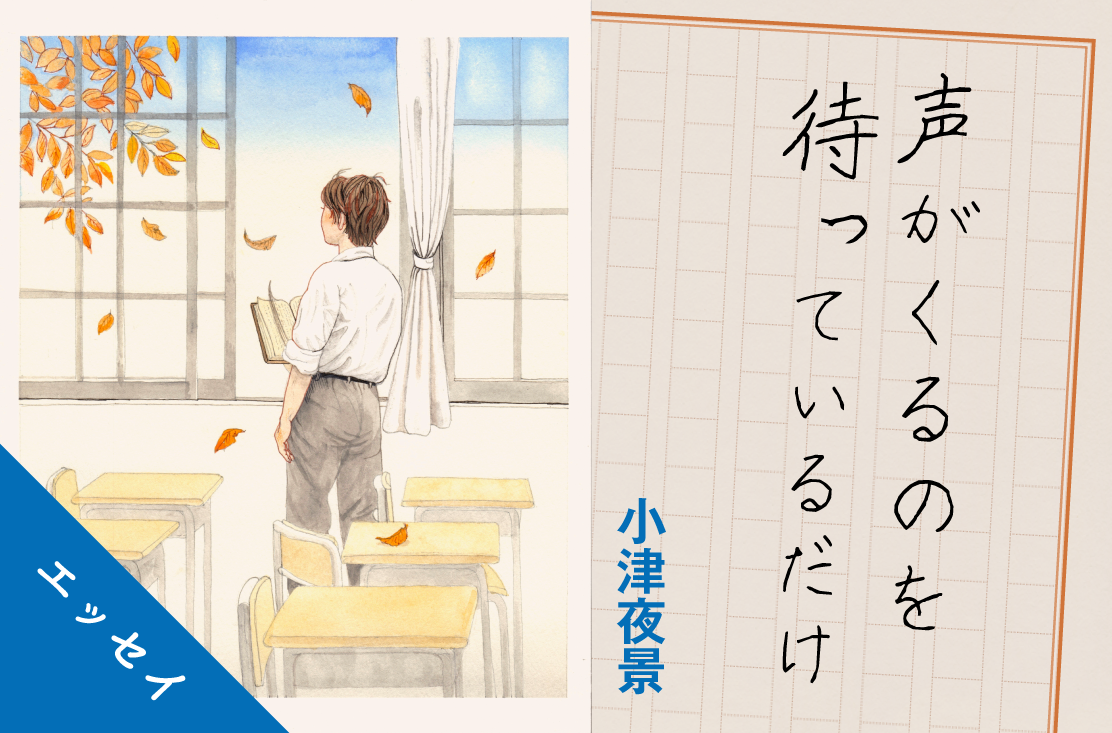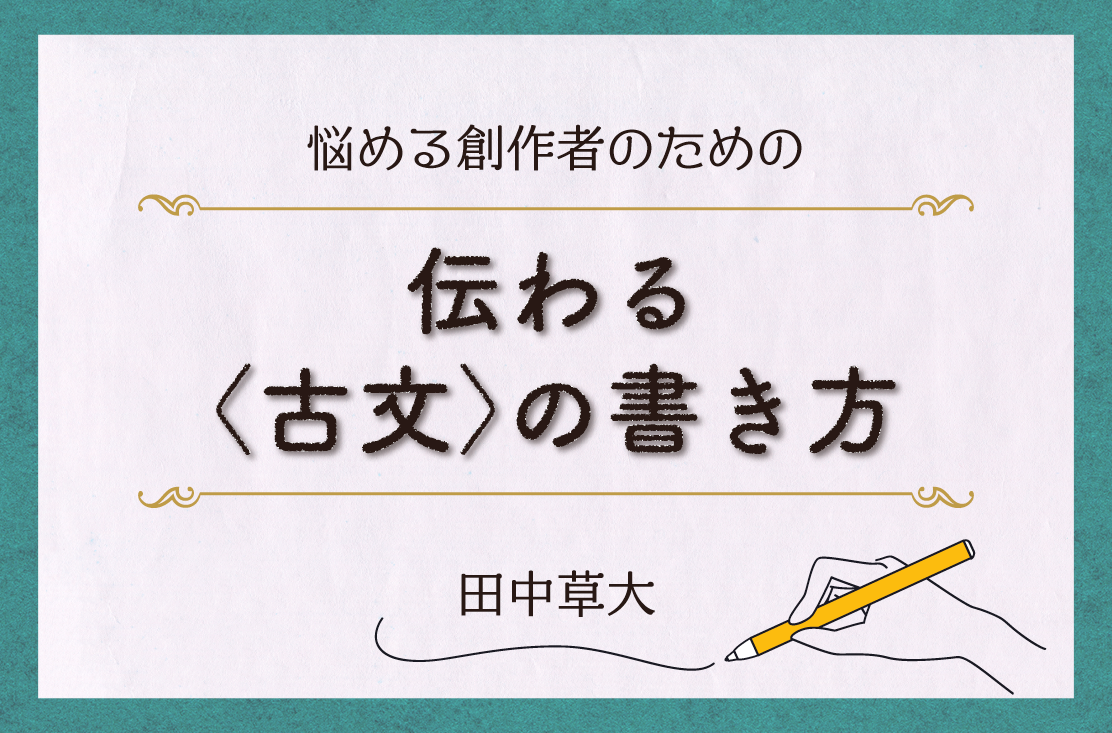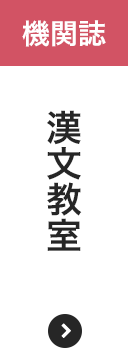エッセイ
他メディアから小説に写すこと
青木淳悟
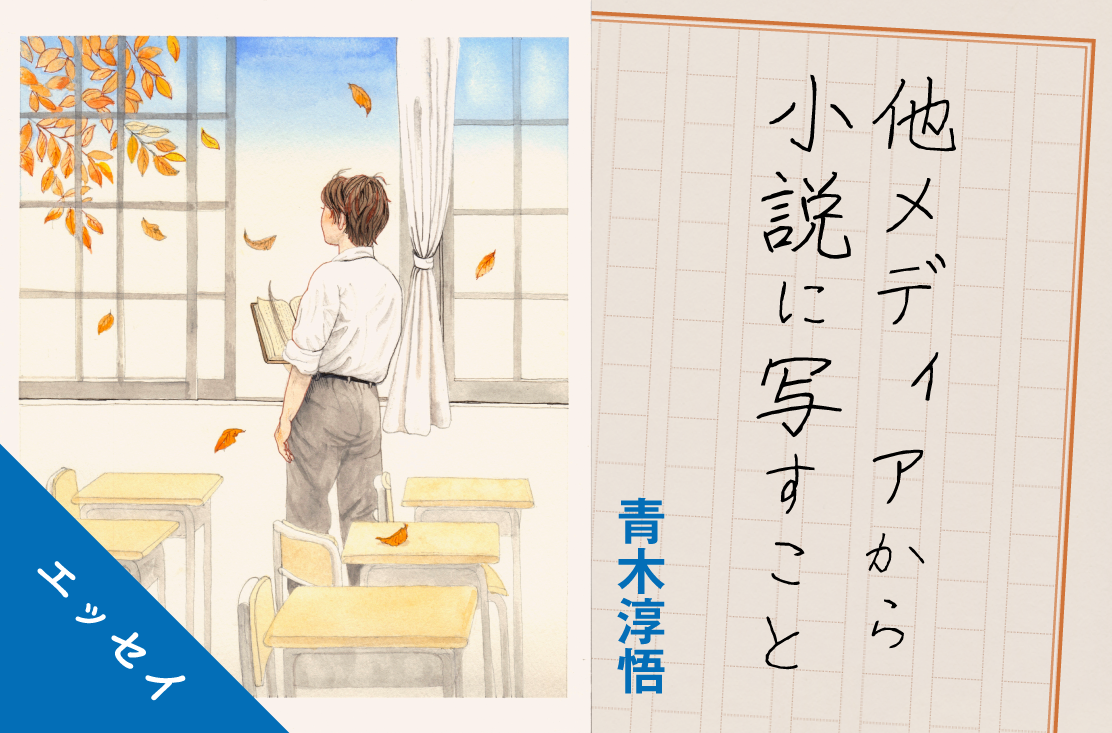
昨年末に刊行した作品集『憧れの世界』には「翻案小説を書く」という副題がついている。ジブリ映画『耳をすませば』を一度ならず二度までも「翻案」して2篇の小説を書き、またその取り組み全体を動機や創作過程の面からエッセイと自作解説に書いて1冊にまとめたのだった。
さて、こうして文芸書に「翻案小説」と銘打つこと、これがなかなかレアケースだというのはご存じだろうか――原作アニメと同様に作品舞台を東京・多摩に設定し団地や図書館を描いたこともあり、「東京都立図書館統合検索」でキーワード検索(「翻案小説」で実行)してみると、都内全体の区立と市町村立図書館を合わせても図書のヒット数がだいぶ少ない(……え、多摩市内の図書館全7館で所蔵数がゼロ?)ことがわかる。
ある程度は予測できた事態だった。少なくとも現行の文芸業界の価値基準(雰囲気)からすると、翻案色を明確に打ち出すスタイルはあまり好まれていない。一度目の翻案作の文芸誌掲載時、担当編集者の意見に従い誌面への原作クレジットなしを選択した。後日聞くと、当初は編集長にも詳しい事情を明かさずにいたこと、さらにその発行責任者たる編集長本人が『耳すま』未見だったと知り、何か肩透かしを食った気になったのだ。
「とあるアニメを原作とする翻案小説なんです!」
こんな主張が現場でアピール材料になるわけもない。もしどうしても何かを翻案したい心積もりなら、正しく「古典文学作品」を原作に仰いでこそ文芸の伝統に連なることができるだろう。筆者の場合はそこに加えて、原作アニメの舞台も時代も変えずに平成初期(およそ30年前)に東京で中学3年生だった彼らを小説に書こうとし、その方法自体が、大胆な設定アレンジや内容の現代的再解釈などを武器とする翻案の一般的な作法からも外れていたのだった。
それなのに同じ雑誌媒体で同一アニメの二度目の翻案を試みた(!)とは、思えば当時30代最後の焦慮と情熱のなせる暴挙だった。そこに介在する創作動機なるものをいえば、「青春時代まっ直中にあった『青春アニメ』に小説を介してもう一度近づきたい」という中年作家の未練たらしいノスタルジックな夢だ。
過去の何らかの思いや感情を「清算」する、あるいは「回復」「消化」「深化」させる手段を求めた結果、単純にそれが同じ過去と結びついた創作を促すことになるのではないか。そして小説であるからには、方法上の問題は「何をどう」書くかに収斂するのは当然として、筆者自身が小説の素材を求め作品化しようとしてきた事実を思うとき、古典にも人生経験にも拠らない創作上の「翻案的方法」とは、今回の件ばかりでなく別の機会にこれまで何度も行ってきたと気づくのである。(ここに「原作」を列挙すると……朝日新聞縮刷版、中学英語リーダー、不動産掲示板サイト、高校国語教師の業務日誌、ゲームソフト『プロ野球?殺人事件!』、テレビ時代劇『水戸黄門』ほか)
こう整理し一般化してみたらどうか。「小説創作の『翻案的方法』とは、古典文学作品の本式の翻案とは別に(映像作品等の)他メディア・別ジャンルのものに取材して小説を書く場合、これを『どう写すか』に積極的な価値と創造性を見出そうとするもので、純然たる創作物=小説というオリジナリティ至上主義を相対化する有力な方法の一つである」。
例えばジブリ作品の躍動感を「どう写すか」。とりわけ宮崎監督作となるとナウシカ以来ずっと空を志向してきたわけで、舞台のスケールといい冒険活劇といい、果たして文章でその片鱗に触れることはできるのか。近づくだけで大いに翻案的想像力が必要となるだろう。
筆者にとって「原作」をまるごと翻案しようとした別の試みに、今回のアニメ翻案と前後して書いていた『プロ野Qさつじん事件』(電子書籍のみ)という作品がある。原作は自力でのクリアがまず不可能な推理物のファミコンゲームだ。何しろ難解で、まともな推理推論常識が役に立たず各球団本拠地の都市を彷徨い歩くことになるが、特異な昭和末期の世界観やそのプレイ感に翻案の余地があると感じた。ここはぜひ動画投稿サイトの「ゲーム実況」等で実感してみてほしい。あちらの世界ではどれだけ無意味な市民や球界関係者や警察官との会話がなされるか、マップの広さと行動の自由さのわりに肝心のクエストが見出せずオープンワールド的行き先不明感を味わうか。ゲームそれ自体がまるで終わりなき日常世界の翻案ではないかとも感じるのである。
『国語教室』第124号より転載
著者プロフィール
青木淳悟(あおき じゅんご)
小説家。『私のいない高校』で三島由紀夫賞受賞。『憧れの世界――翻案小説を書く』では、ジブリアニメ「耳をすませば」に材をとる翻案小説2作品とエッセイ、自作解説を収録。
一覧に戻る