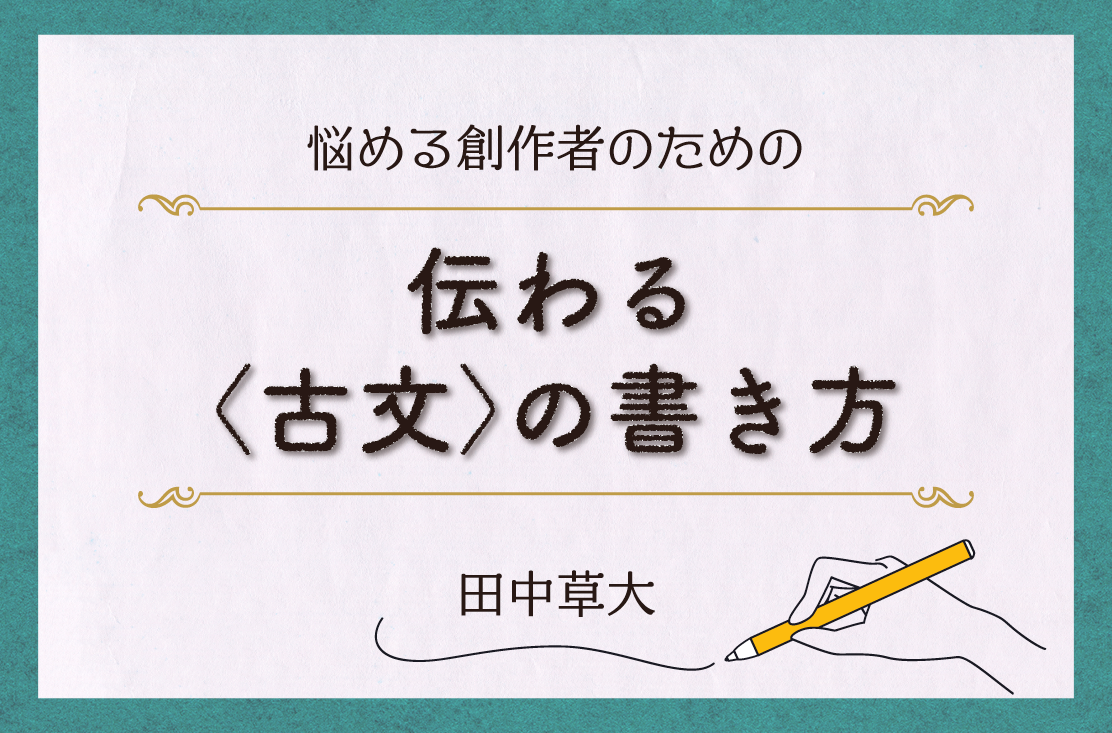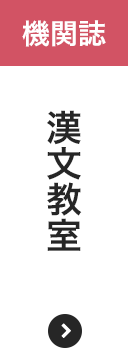いま、漱石を読む
第2回 男同士の争い――『こころ』②
石原千秋

漱石没後100年、生誕150年の節目に、漱石の現代性を探る本連載。第二回は、よく知られる「先生と遺書」の章に着目し、『こころ』を教室で読む意味を考えます。人の「心」の意外な動きとは……?
三角関係を書く作家
漱石は三角関係を書き続けた作家である。ざっとおさらいしておくと、以下のようになるだろうか。
『虞美人草』では宗近一と小野さんで藤尾をめぐってガチンコの対決が行われるが、藤尾の自死によって勝者はいない。前期三部作に進むと、『三四郎』では里見美禰子をめぐって小川三四郎と野々宮宗八がそれとなく意識し合うが、美禰子が兄の友人の法学士を結婚相手に選ぶことで、これはどちらも敗者と言えそうだ。『それから』では長井代助が友人の平岡常次郎に菅沼三千代を「斡旋」したものの、平岡から三千代を取り上げるが、三千代の体調の悪化で結末はわからない。『門』では野中宗助が友人の同棲相手(「内縁の妻」と呼んでいいかどうか)だったお米を奪うが、罪の意識に苛まれ続ける。
後期三部作に進むと『彼岸過迄』でははっきりした三角関係は書かれないが、須永市蔵が幼なじみの田口千代子が避暑地に招いた高木という男性に嫉妬する場面がある。『行人』では、大学教授の長野一郎が、妻のお直が弟の二郎に「惚れてる」のではないかと疑い抱く。『こころ』では〈先生〉とK。
晩年に進むと、漱石文学唯一の自伝的小説と言われる『道草』にははっきりした三角関係は書かれてはおらず、『明暗』では津田由雄が清子をめぐって新婚の妻お延と神経戦を繰り広げるので、これまでの一人の女と二人の男という構図ではなく、一人の男と二人の女という、漱石文学では新しい展開が期待できたが、残念ながら未完に終わった。
こうした三角関係の構図の中で激しい、あるいは微妙な神経戦が行われるのである。そこに漱石文学の登場人物に特有の心の動きがあった。こうした主人公に粘着した(?)心の書き方は同時代的には不評で、漱石文学を批判し続けた(亡くなってから批判したのではないから立派なものである)田山花袋などは、『それから』など〈自分なら描写式を用いるから半分の長さで書ける〉と豪語(!)している。しかし、人工知能に思考を奪われ、やがて心も奪われるかもしれないこの時代に『こころ』を教室で学ぶのなら、この心の動きに驚いておかなければならないのではないだろうか。
〈先生〉はKと戦争している
国語教科書に載録されている『こころ』は、「先生と遺書」(「先生の遺書」ではないので念のため)の章の、〈先生〉とKの下宿先で行われたお正月のカルタ取りの場面からが、教科書の『こころ』としては長い方だろう。交際範囲の狭い当時の中流から上流の階層にとって、カルタ取りは数少ない公の男女交際の機会だった。少し古いが明治30年代の尾崎紅葉『金色夜叉』の冒頭の場面を思い出してほしい。『金色夜叉』はカルタ取りから始まる物語なのである。
載録箇所の最後は、ほぼすべてKが自死したところになっているはずである。この範囲での山場は、上野での〈先生〉とKとの対決(?)の場面だろう。
Kにお嬢さん=静への恋を打ち明けられた〈先生〉は、なんとしてもそれを食い止めなければならなかった。Kが直接告白してしまうのではないかと焦っていた〈先生〉にはもうこの日しかなかった。そこで、かつてKが口にした「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」という言葉を二回Kに投げつける。二回目は「馬鹿だ」の前に一拍おいて、「精神的に向上心のないものは、馬鹿だ」と、いっそう「馬鹿だ」を強調したようだ。それを受けて、Kは「馬鹿だ」と二回繰り返す。Kはかつて自分が「馬鹿だ」と思っていた、そういう人間にいま自分がなっていると感じたからだ。
問題は、こうした場面を記述する〈先生〉の語彙と表現の偏りにある。
私は丁度他流試合でもする人のようにKを注意して見ていたのです。私は、私の眼、私の心、私の身体、すべて私という名の付くものを五分の隙間もないように用意して、Kに向かったのです。罪のないKは穴だらけというよりも寧ろ明け放しと評するのが適当な位に無用心でした。私は彼自身の手から、彼の保管している要塞の地図を受け取って、彼の目の前でゆっくりそれを眺める事が出来たも同じでした。(四十一、新潮文庫)
〈先生〉自身が「他流試合」と書いているように、「要塞」とか「地図」といった語彙によって、これが〈先生〉にとってはKとの「戦争」だったことを如実に表している。耐えきれなくなったKが「もうその話は止めよう」、「止めてくれ」と懇願するように言ったとき、〈先生〉は「狼が隙を見て羊の咽喉笛へ食い付くように」こう言ったのだった。「止めてくれって、僕が云いだした事じゃない、もともと君の方から持ち出した話じゃないか。(後略)」と。「狼が隙を見て羊の咽喉笛へ食い付くように」という表現の残酷さには注目しておく必要がある。
こうした〈先生〉の心の動き方を読んで、いったい何を学べばいいのだろうか。
一つは、前回説明したように、〈先生〉が信じられないのは、実はお嬢さん=静の心なのだということだろう。『こころ』の全体を、少なくとも〈先生〉の遺書の全体を知っている生徒なら、毎月受け取る利子の半分で十分生活ができるほどの財産を持っている〈先生〉は、日清戦争で夫を亡くして素人下宿をはじめなければならなかった「未亡人」の母娘にとって、学歴(将来性)も含めて最高の条件を備えていたということを指摘するだろう。特に経済的に見て、Kは〈先生〉のライバルにはなり得なかった。
このことは、教科書収録範囲でも十分にわかる。
〈先生〉は奥さん=静の母に静との結婚を申し込んだ。静に直接申し込まずその母親に申し出たことは、この時代のこの階層の人間にとっては自然なことというより、それがしきたりだった。それを奥さんは、すぐ承知して、自分が静が不承知のところへ行かせるわけがないと、静の気持ちまで保証する。つまり、二人の気持ちはもう固まっていたのだ。あとは、〈先生〉が言い出すのを待てばよかった。しかし、「恋」という一字に不慣れな〈先生〉は、こうした状況が見えなかったのである。
そして、〈先生〉はKと争った。〈先生〉とKとの争いは「戦争」だったということの意味を考えなければならない。
ホモソーシャルな二人

▲『男同士の絆』
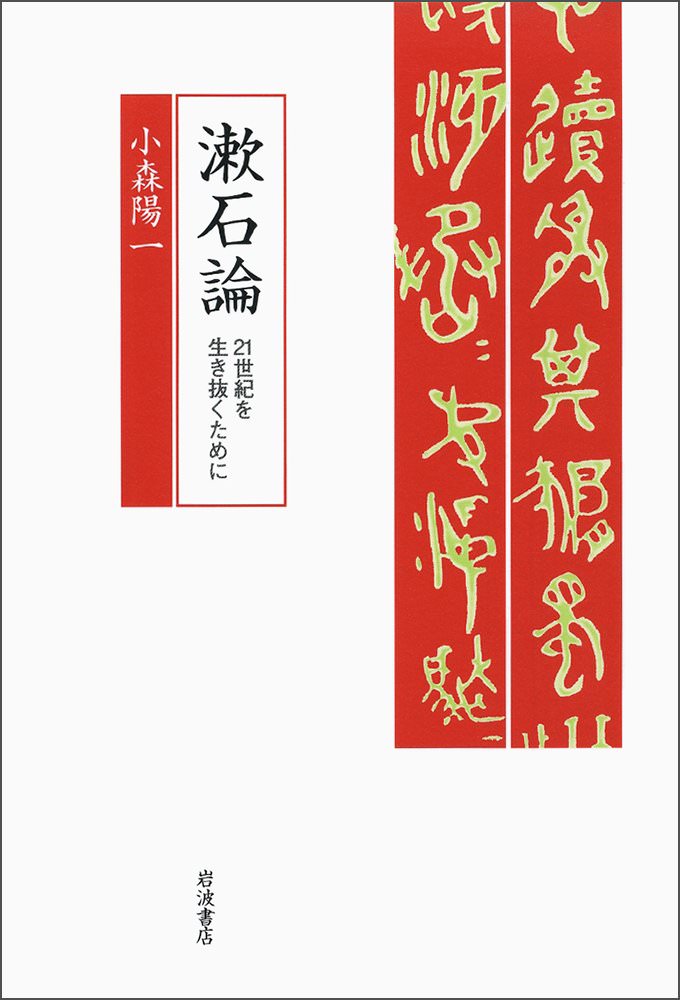
▲『漱石論』
漱石文学はホモソーシャルな文学である。この「ホモソーシャル」という概念は、英文学者のセジウィックが提案し(『男同士の絆』上原早苗・亀澤美由紀訳、名古屋大学出版会、2001・2)、いまではほぼ一般化しているが、漱石文学に即して説明しておこう。
ホモセクシャルとホモソーシャルは違う。ホモセクシャルはふつう「ホモ」と略されるもので、男性同士が肉体的な関係を持つことを言う。ホモソーシャルは「ホモ」と完全に無縁ではないが、それとは違った概念で、「ソーシャル」だから「社会構造」のレベルの問題なのである。簡単に言ってしまえば、男性中心社会のことである。現在のわれわれの「父権制資本主義社会」の性質はホモソーシャルと呼んでいい。ホモソーシャルな社会では男たちが社会を支配しているが、この男たちはあるやり方で男同士の絆を強めていく。それは「女のやりとり」である。これがホモソーシャルな社会を支えている。
漱石文学から分かりやすい例を挙げると、すでに指摘があるように(小森陽一「漱石の女たち――妹たちの系譜――」『漱石論』岩波書店、2010・5)、『それから』は典型的なホモソーシャル小説と言える。三千代は、代助の友人平岡との共通の知り合いで、おそらく代助と三千代は憎からず思い合ってるような雰囲気がある。しかし、それはお互い口にしない。そこへ、平岡が三千代を好きだと代助に告白する。そうすると、代助は三千代と平岡が結婚できるように取り計らって、三千代と平岡が結婚する。
実はこれが物語の発端になっていくので、いったん平岡に「斡旋」した三千代を代助が取り戻す物語が『それから』の実質なのである。これをまとめれば、代助と平岡という男同士の友達がいて、その男同士がお互いの絆、つまり友情を確認するために代助が三千代を平岡に譲る。ほとんど自分の手に入っていた女性を相手に「斡旋」することで、代助と平岡の「友情」は強固になるわけだ。ただし、そうして築いたホモソーシャルな「友情」を崩すところに、『それから』の「新しさ」がある。
『こころ』はこのバリエーションである。〈先生〉がいて、Kがいて、お嬢さん=静がいて、三角関係のようになる。発端は、〈先生〉がKの気持ちをほぐすためにと、お嬢さんとKをわざと近づけたところにある。実は、〈先生〉は結婚相手としてお嬢さんをもうほとんど手に入れているも同然の状態だった。そのお嬢さんをKに近づけることで、〈先生〉はKとの「友情」を再確認する形を取るわけだ。ところが、Kが先にお嬢さんへの「恋」を告白すると、慌ててお嬢さんを取り戻すことになる。『それから』と同じ構図だ。
こういうホモソーシャルの構図の中では、女性は男同士の絆を強めるためにやりとりされる存在になる。したがって、ホモソーシャルな社会では「女性蔑視」の思想がベースとしてある。なぜなら、女性を他者として「尊敬」していたらこのようには扱えないからだ。根底に「女性蔑視」の思想があるから、男同士は女性のやりとりができる。それがホモソーシャルな社会なのである。
ホモソーシャルな社会を個人レベルで見ると、もう一つの特徴が見えてくる。『それから』では、第一段階では女性を相手に渡す。ところが、第二段階では女性を奪い返していた。男は女性のやりとりを介して力比べをしているのである。『こころ』の〈先生〉も力比べでKに勝った。あるいは、Kに勝つことがわかっていて、あらかじめお嬢さんをKに近づけた。そのことでKは自殺した。なぜ〈先生〉がそんなことをしたかというと、自分より上のポジションにいた(と〈先生〉には思えた)Kを引きずり下ろすためだ。これは「象徴的なK殺し」だと言える。力比べに勝つことは、最終的に相手を「殺す」ことなのである。これもホモソーシャルな社会の一面である。
〈先生〉の心の動きが自然であるかどうかは問題ではない。むしろ、〈先生〉にとって自分の心の動きが「自然」に見えた方が、ホモソーシャルという思想にとっては都合がいいのだ。人びとが、自分の心が何かの思想に動かされていると思わなくてすむからだ。近代は個人の思想の主体性を大事にしてきたが、それは個人の心が個人にとってまったく自由で自然な働き方をすることを意味しない。
ミシェル・フーコーは、主体化とは自由を得ることではなく、社会の規範を内面化することだと主張した。心の自由を追究してきた西洋哲学への挑戦だった。大学生を教えていてつくづく思うが、ミシェル・フーコー以前と以後(学習以前と学習以後)とでは、議論の質がまったく違ってくる。ミシェル・フーコーは持ち出さなくても、人の心は決してその人の自由に働くものではないことは、『こころ』から学んでいいのではないだろうか。
2017年1月31日
著者プロフィール

石原 千秋 (いしはら ちあき)
1955年生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専攻は日本近代文学。夏目漱石から村上春樹までテクスト分析による斬新な読解を提供しつつ、国語教育への問題提起も果敢に行っている。著書に『漱石入門』(河出文庫)、『読者はどこにいるのか 書物の中の私たち』(河出ブックス)、『国語教科書の中の「日本」』(ちくま新書)など多数。
一覧に戻る