いま、漱石を読む
第6回「芸術」が生まれるとき―『夢十夜』「第六夜」
石原千秋

漱石のアイデンティティ
『夢十夜』が実際に漱石が見た夢を書いたものか、純然たる創作かどうかにかかわらず、この連作にはほかならぬ漱石のアイデンティティのあり方がよく現れている。それは、『夢十夜』の時間と空間に関する構造に現れているのである。
よく知られているように、アイデンティティは二つの性質によって成り立っている。一つは、自分自身によって自分が自分であると確信できていること。これは、かつてもいまも自分は自分であり続けているという時間的な性質によって支えられている。少し前の言葉を使うなら、実存的自己と言っていい。もう一つは、他人によって自分が自分であると認識されていると確信できていること。これは、Aさんに対する自分もBさんに対する自分も、あるいは、ここにいる自分もあそこにいる自分もやはり自分であるという空間的な性質によって支えられている。社会的自己と言っていい。
『夢十夜』の連作は、時間的な永遠は手に入るが空間的な永遠は手に入らないという実にシンプルな構造を持っている。解釈による揺れを度外視して簡単に挙げておくなら、時間的な永遠は「第一夜」の百年、「第三夜」の百年、「第八夜」の「高々百枚位」の紙幣、「第九夜」の「御百度」、「第十夜」の「無尽蔵」にやってくる豚が表象している。空間的な永遠は 「第二夜」の「無」、 「第四夜」の「臍の奥」、「第五夜」の「自分」と「女」との距離、「第六夜」の「自分」の家と「護国寺の山門」までの距離、「第七夜」の船の「甲板」から海面までの距離が表象している。これは、漱石がこの構造に意識的であったか無意識であったかにかかわらず、漱石の自己確信と他者不信の現れのように思える。そして、これは漱石文学の基本構造でもある。漱石の主人公たちは、ほんとうは自己に怯えているのに、他者に怯えているように思い込んでいるというように。
運慶・護国寺・仁王
「第六夜」はこういう話だった。護国寺の山門で運慶が黙々と仁王を彫っている。鎌倉時代のようでもあるが、見物人を見ると明治の現代のようでもある。見物人が運慶は木の中から仁王を掘り出すのだと言う。さっそくやったが、自分にはできなかった。明治の木には仁王は埋まっていなかったのだ。
少し注釈的なことを書いておこう。
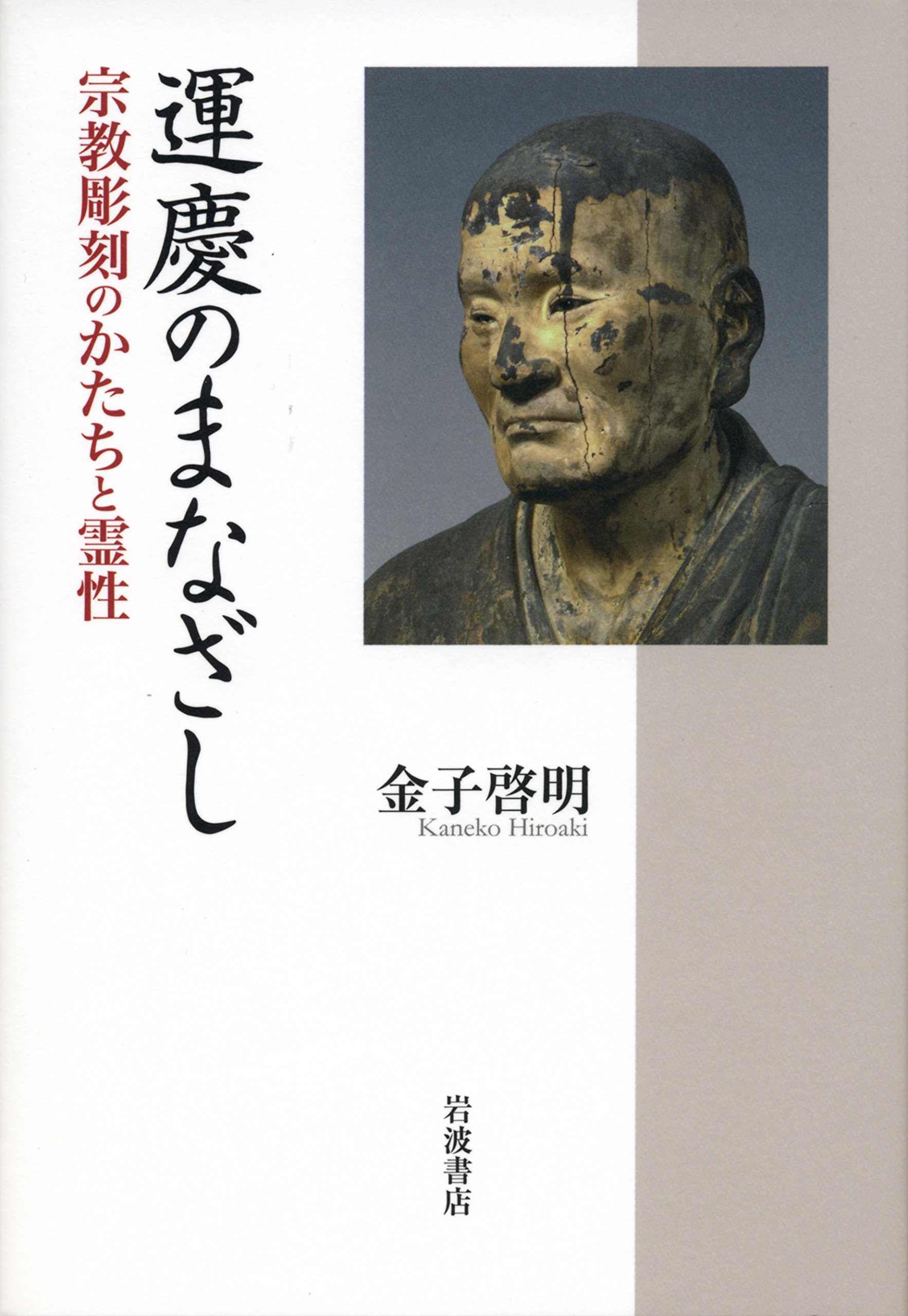
▲『運慶のまなざし』
運慶は、鎌倉時代の仏師であり、空海を開祖とする大乗仏教の真言宗の僧侶でもあり、『法華経』を写経もしている。『法華経』は平等な救いを説く。源頼朝が挙兵した1180年に、平重衡の襲撃によって奈良の寺が大きな被害を受けた(南都焼打ち)。運慶は東大寺や興福寺の復興に携わり、1203年には、いまに伝わる有名な東大寺南大門の金剛力士像(仁王)を中心となって造像し、興福寺の仁王像は運慶に近い定慶か運慶の子息の造像である可能性が高いと言う。絵画とはちがって、運慶の時代の宗教彫刻には、その質感から「永続性(永遠性)」や「霊験性」が期待されたと言う。また、運慶は鎌倉幕府と朝廷双方の中枢と関わりを持った唯一の仏師だった(金子啓明『運慶のまなざし 宗教彫刻のかたちと霊性』岩波書店)。言うまでもなく、護国寺は真言宗派だが、江戸時代に作られた比較的新しい寺である。
見物人は品がないようだ。運慶の彫っている仁王は日本で一番強いと評判する男は、こうだ。「この男は尻を端折って、帽子を被らずにいた。余程無教養な男と見える」と。戦後のある時期まで、成人男性は外出時には帽子を被るのが習慣だった。『道草』の冒頭に現れる主人公健三の養父島田は、帽子を被らないだけで不気味な感じを与えている。健三だけでなく読者もそれを感じるから、以後の島田のイメージが決まるのである。「第六夜」に戻れば、これより少し前の「人間を拵えるよりも余っ程骨が折れるだろう」という言葉には、性的なニュアンスがある。見物人は、運慶とは対照的な男たちなのである。
『夢十夜』の基本構造に従えば、仁王には「永遠性」があるのに、明治の木に仁王が埋まっていないのは、護国寺と「自分」の家までの距離(空間)が障害となっているからだと考えればすむ。「自分」が明治の見物人とうまくコミュニケーションが取れていない理由も、他者不信の一つの形だということになる。見物人をやや差別的な眼差しで見る「自分」が、『法華経』を写経した運慶と同じことができないのも当然なのだ。
しかし、教室での「第六夜」は近代批判の枠組みで読まれることが多いのではないだろうか。ごく平たく言ってしまえば、近代となった明治の世には、運慶の彫っている仁王のような立派なものはもうないのだと。「自分」が仁王を彫りだせなかったことだけでなく、やや品のない明治の見物人たちもその印象を強めているはずだ。教室での問いは、「では、どうして明治の現代には仁王が埋まっていないのか」となるだろうか。「第六夜」にその答えはない。ないから国語教材になるのだが、「第六夜」はこの問いを誘うような一種のオープンエンディングになっている。生徒たちはどのくらいの自由度でこの問いに答えるのだろうか。
たしかに、漱石は「近代」が嫌いだった。近代という時代も近代というシステムも嫌いだった。漱石には、近代は個性を生み出すようなシステムと個性を抑圧するようなシステムがなぜか矛盾なく併存しているように見えたらしい。個別化と均質化が同居しているわけだ。漱石の用語系では、前者は自意識で後者は道義であるはずだが、初期の漱石は、『虞美人草』の藤尾のように自意識を女性に与えて嫌い、道義を男たちに与えて称揚した。後期の漱石は、自意識も道義も男性知識人に与えて、その悩みを書いた。つまり、近代の矛盾を暴いたのである。ここで言いたいのは、学校空間がそうなってはいないかということなのである。個性を言いながら、その一方で「〜らしく」と言って古い道徳に押し込めてはいないだろうか。これが漱石的文脈から読んだ「第六夜」が批判する近代ではないだろうか。学校空間の説明であれば、よくわかるのではないだろうか。
では、運慶的文脈ではどういう答えになるだろうか。運慶の時代の宗教彫刻には「永続性(永遠性)」や「霊験性」が期待されたというのであれば、明治の現代で失われたのはこの二つのものということになる。これこそが、時間的な永遠は手に入るが空間的な永遠は手に入らないという『夢十夜』の文法通りの答えになる。これは「第六夜」に書いてあるのだろうか、それとも書いてないのだろうか。難しい問題だが、それが文学の面白さでもある。しかも文学にかぎらず、わかる人にしかわからないことはいくらでもあるのだから、これは個人というもののあり方の問題だと言える。
「第六夜」は、「第六夜」が誘発する問いに答えようとして、個人が試される実に高級な作品だと言えるだろう。
「わからない」という感覚
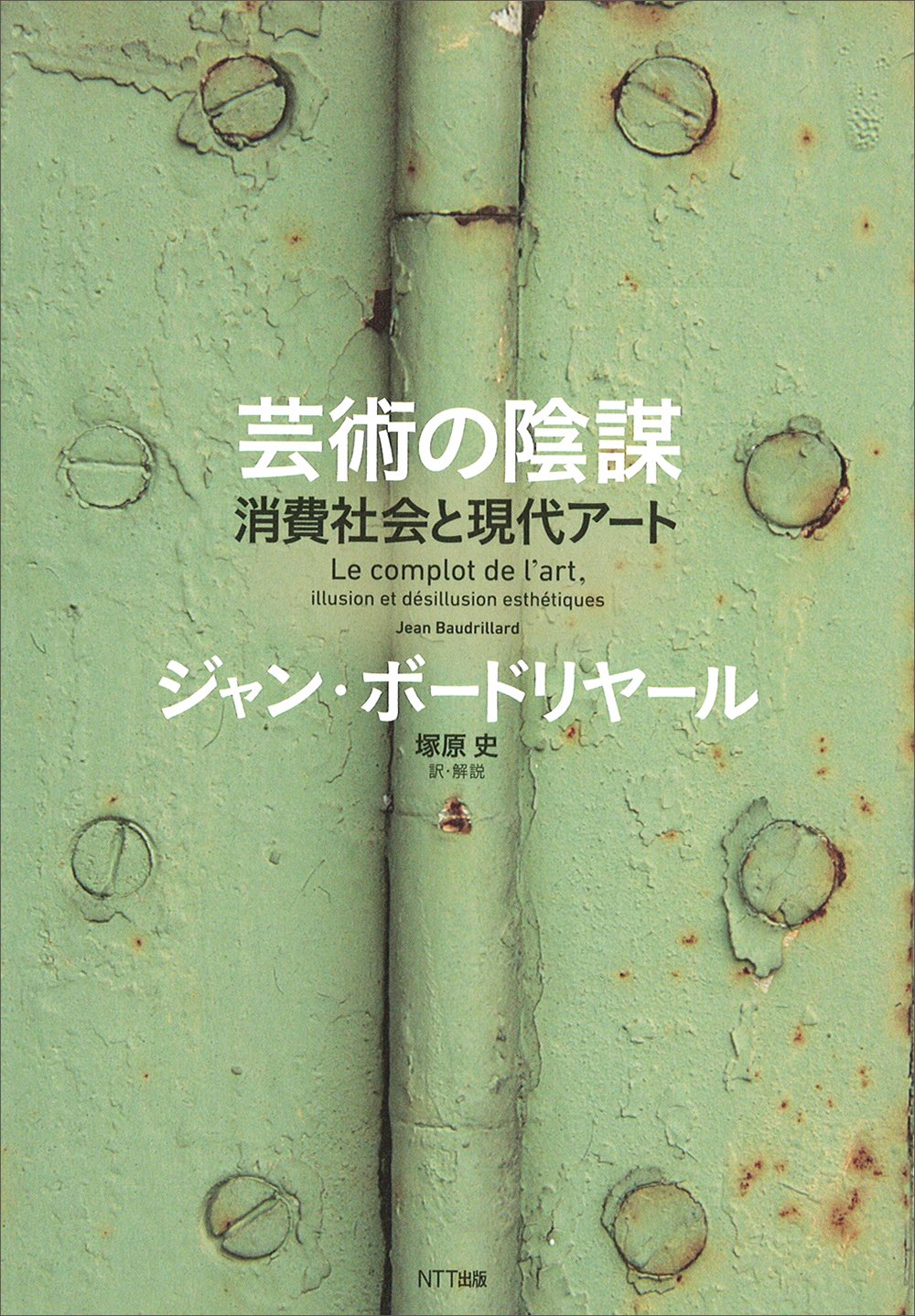
▲『芸術の陰謀』
しかし、「第六夜」が誘発する問いの答えは結局わからないのではないだろうか。それは、とりつく島のない運慶がわからないという感覚を含んではいないだろうか。そう感じたとき、私たち読者は「第六夜」の「陰謀」にはまったのだ。
フランスの思想家・ジャン=ボードリヤールに『芸術の陰謀 消費社会と現代アート』(塚原史訳、NTT出版)という刺激的な文章がある。現代アートは自らが「無価値・無内容」だと主張し続けるのだと言う。たしかに、ボコボコにされたブリキ缶にペンキをでたらめに吹きかけた「作品」を見せられれば、これは「無価値・無内容」だと思う。しかし、そのとき私たちは現代アートの「陰謀」の手に落ちたのだと、ボードリヤールは言うのだ。
それは、こういうことだ。その「陰謀」とは、「現代アートをまったく理解できない人びと、あるいはそこに理解すべきことなど何も存在してないことが理解できなかった人びと」に〈私には、もしかしたら現代アートがわからないのではないか〉という不安を呼び起こし、そのことで現代アートには自分だけがわからない何か特別な価値や内容があると思い込ませることができる仕掛けである。それによって、現代アートは簡単には理解できない、まさに解釈されるべき価値と内容を持つ「芸術」になる。繰り返す。現代アートを「芸術」にするのは、私たちの「わからない」という感覚なのだ。
これは現代アートに限らず、すべての芸術に言えることだろう。「第六夜」が誘発する問いの答えがわからないと思ったとき、運慶の作っている仁王が、明治の現代では「わからない」ような、解釈されるべき価値と内容を持つ「芸術」となっている。そして、「第六夜」の読者は、最後に「自分」が何を「わかった」かがわからない。そう、そのとき「第六夜」こそが解釈されるべき価値と内容を持つ「芸術」となっているのである。「第六夜」とは「芸術」が誕生する仕掛けそれ自体を書いた小説だった。ここに「第六夜」を学ぶ意義がある。
『国語教室』第108号(2018年10月)より
著者プロフィール

石原 千秋 (いしはら ちあき)
1955年生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専攻は日本近代文学。夏目漱石から村上春樹までテクスト分析による斬新な読解を提供しつつ、国語教育への問題提起も果敢に行っている。著書に『漱石入門』(河出文庫)、『読者はどこにいるのか 書物の中の私たち』(河出ブックス)、『国語教科書の中の「日本」』(ちくま新書)など多数。
一覧に戻る









