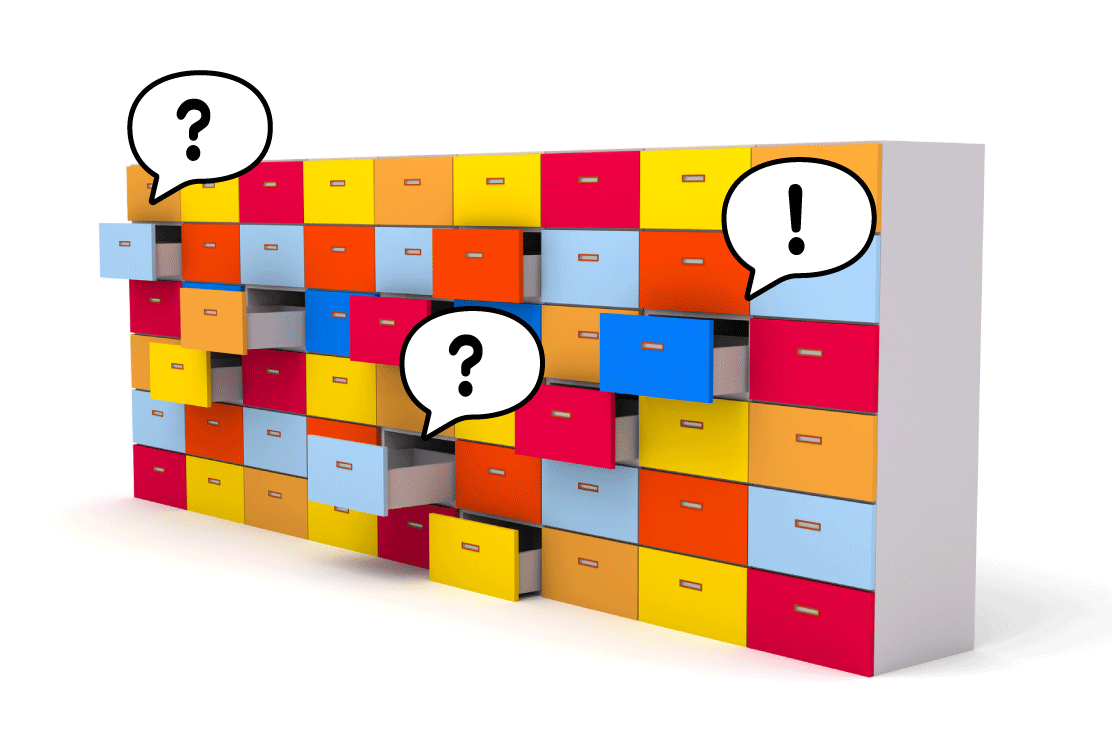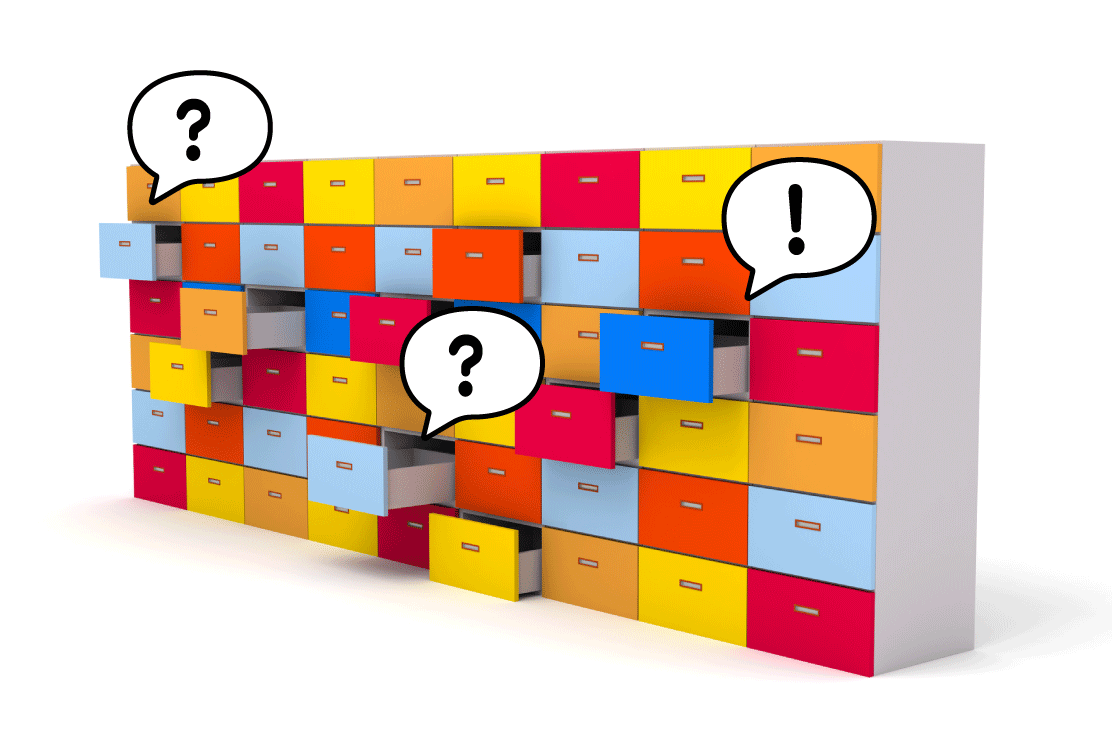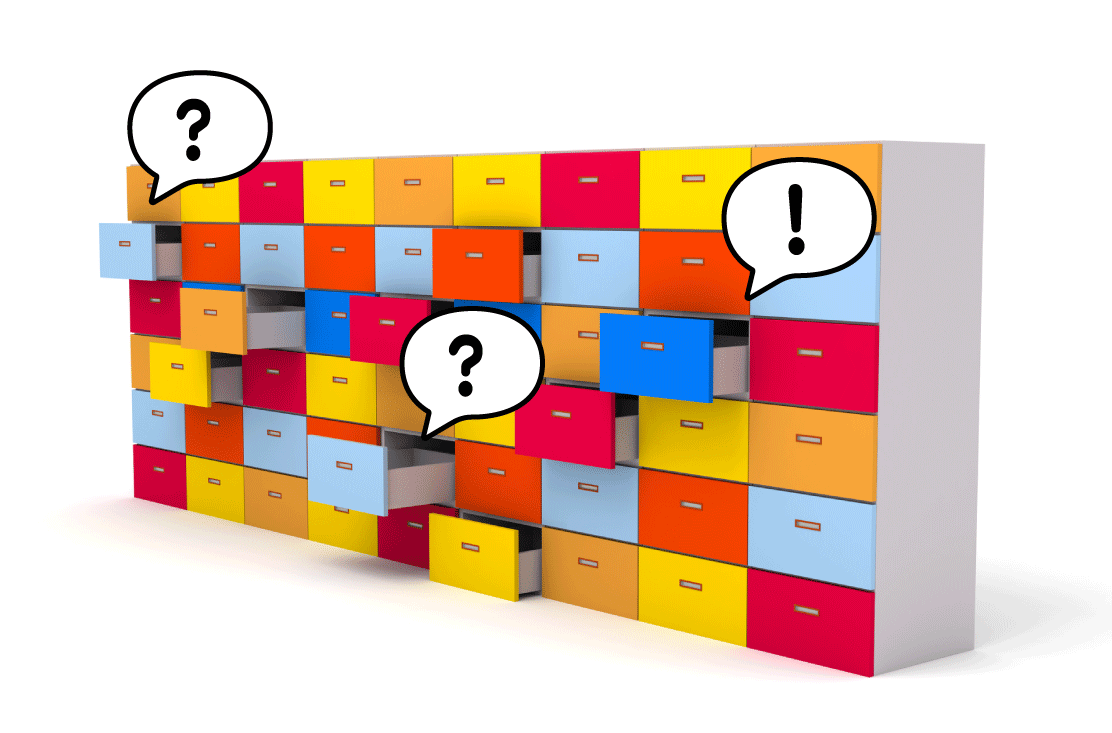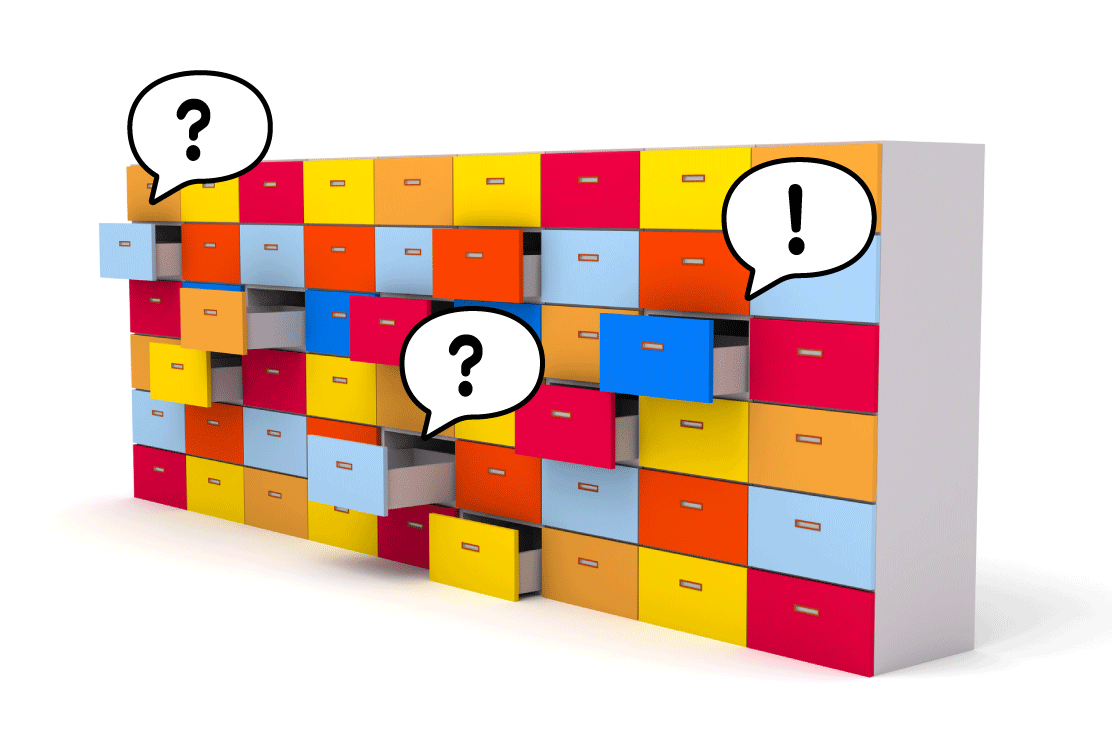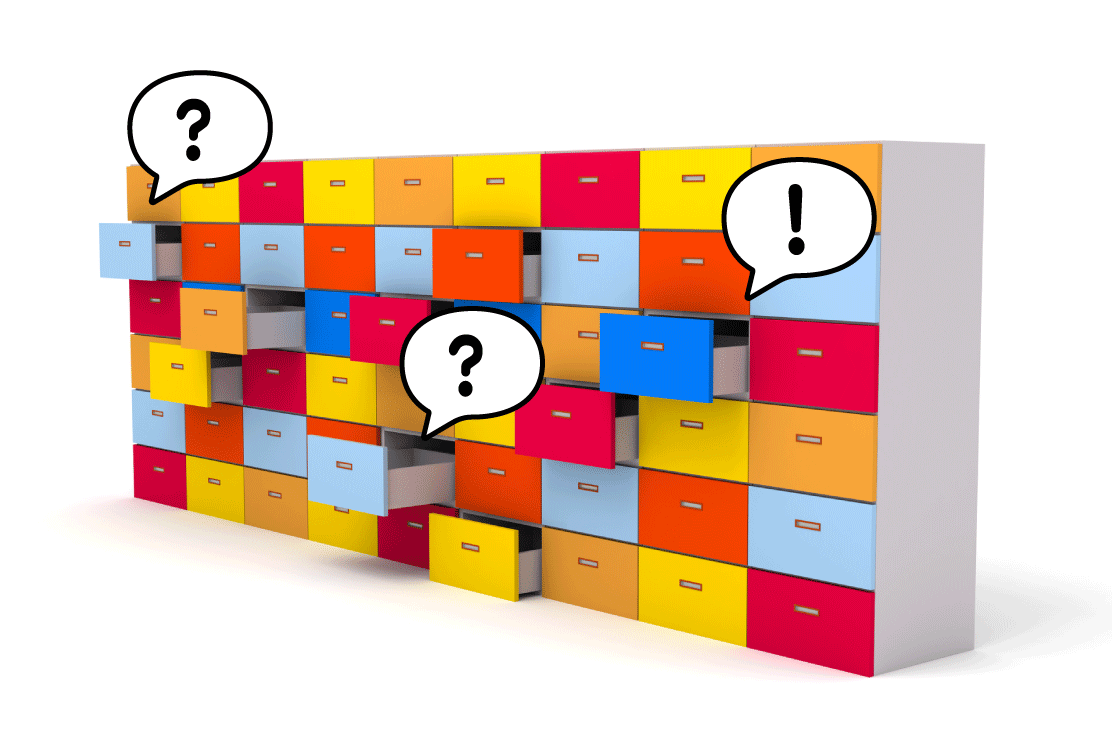コトバのひきだし ――ふさわしい日本語の選び方
第3回 眉をしかめて風潮を論じる
関根健一
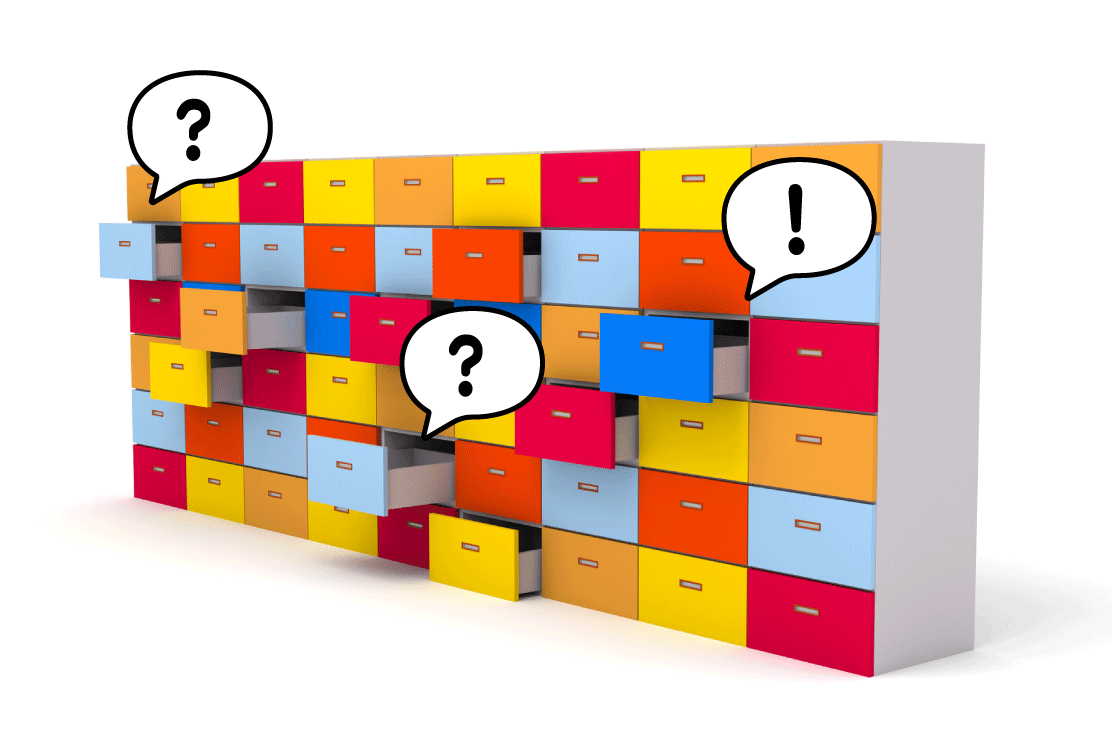
テレビをつけたら、ワイドショーの司会者が「こうした風潮について、どう考えますか」とコメンテーターに質問する声が聞こえてきました。どんな内容かは分かりませんが、批判的なコメントを期待しているような気がしました。
*****
「風潮」は、「時代とともに変わっていく世の中の傾向」(明鏡国語辞典 第二版)を言います。辞書の語釈には、「よくない方へ」といった条件は付けられてはいませんが、新聞では、「好戦的な風潮」「排外的な風潮」「軽視する風潮」「異端視する風潮」など、そう変わるのが望ましくないという場合に使われているのが目につきます。
文学作品では、「俗書が段々科学的の書に接近して来る風潮」(森鷗外)、「ああいう悪い風潮に染まないようにしてくれたまえ」(島崎藤村)、「奢侈及び淫靡なる風潮」(岸田國士)、「軍国主義的な風潮」(福永武彦)などの用例が見つかります。「教育を受けた若い婦人が進んでそれらの職業に就くという新しい風潮を祝福した」(与謝野晶子)のような(プラス方向に近い)中立的な使い方もありますが、数は多くありません。
*****
もともと「風潮」は、風と潮、もしくは、風に吹かれて生まれる潮の流れのことです。社会現象をたとえるときには、「風に流されていく」というイメージから、無責任さや、判断能力のなさが連想され、行ってはいけない方にふらふらと行ってしまう様子に結びつきやすいのでしょうか。また、『大漢和辞典』には「暴風と狂潮。台風」ともあり、そもそも災厄をもたらす現象を指しても使われたようです。
いずれにしても、「~を軽視する風潮」「~という誤った風潮」など、マイナス方向の価値観を持つ言葉と親和性が高いように思います。状況を客観的に述べるつもりで、「女性の社会進出の風潮」などと表現すると、それを批判、慨嘆しているように受け止められるおそれもあります。「女性の社会進出の風潮を歓迎する」だと、「一般には好ましくないとされているが自分はそうはとらない」とでもいった一ひねりしたレトリックなのか、もしくは皮肉や揶揄が潜んでいるのかなどと、読み手は一瞬戸惑いそうです。
*****
「時流」「時勢」も、世の中の移り変わりをいう言葉です。風向き次第、潮の流れ次第の「風潮」に比べると、ある方向に確実に向かう強いうねりのようなものが感じられます。
「風潮」と異なり、(マイナス方向の)連体修飾語を伴った「~の(~する)時流/時勢」の形では用いられません。乗るか乗れないかというところに注目して使われるのが「時流/時勢」です。うまく乗れれば、「~に投じる」「~を読む」「~を先取りする」、乗り損なえば「~に遅れる」です。といっても、「~におもねる」「~に迎合する」のは嫌われ、「~にあらがう」「~に逆らう」ことには、時として喝采が送られます。
*****
性質や状態が特定の方向で傾くのが「傾向」で、方向の良しあしによらず使われます。
ただ、「特定の方向」を指す「傾向」もないわけではありません。かつて「傾向文学」なるジャンルがありました。思想的に特定の方向、特に左翼的な方向にかたよった作品群を指します。芸術的文学が本道であるとすれば、好ましからざる方に向かうものという位置づけでした。
*****
移り変わっていく方向を手放しで認める場合は「トレンド」が好まれるようです。行く世の流れを見つめるとき、無常の思いが浮かびがちな日本的伝統とは、切れたところにある外来語の強みかもしれません。
『国語教室』第111号(2019年10月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。文化審議会国語分科会委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(以上、三省堂)、『ちびまる子ちゃんの似たもの漢字使い分け教室』『ちびまる子ちゃんの敬語教室』『ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室』(以上、集英社)、『上質な大人のための日本語』(PHP研究所)など。
一覧に戻る