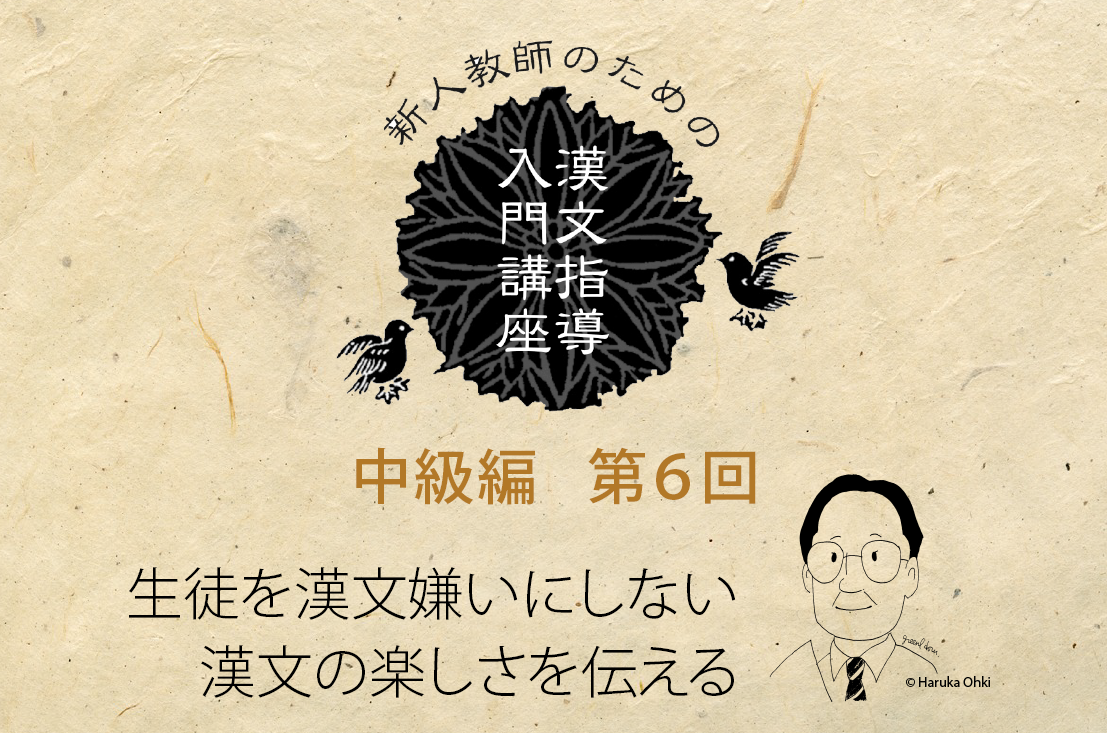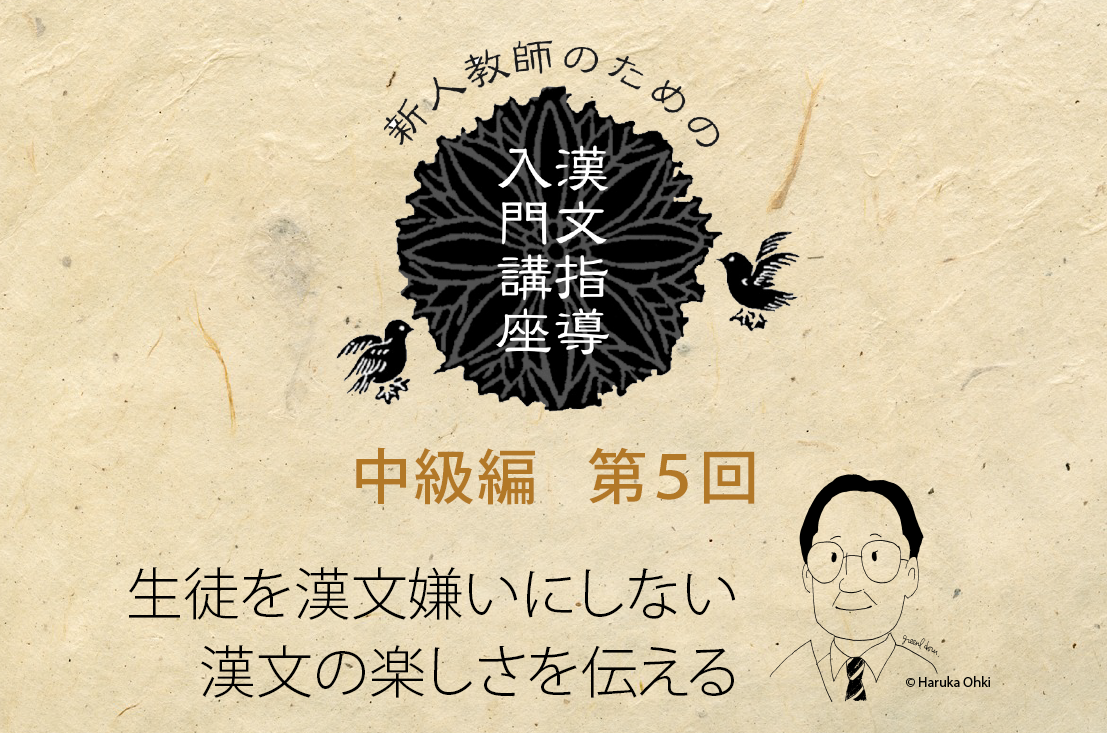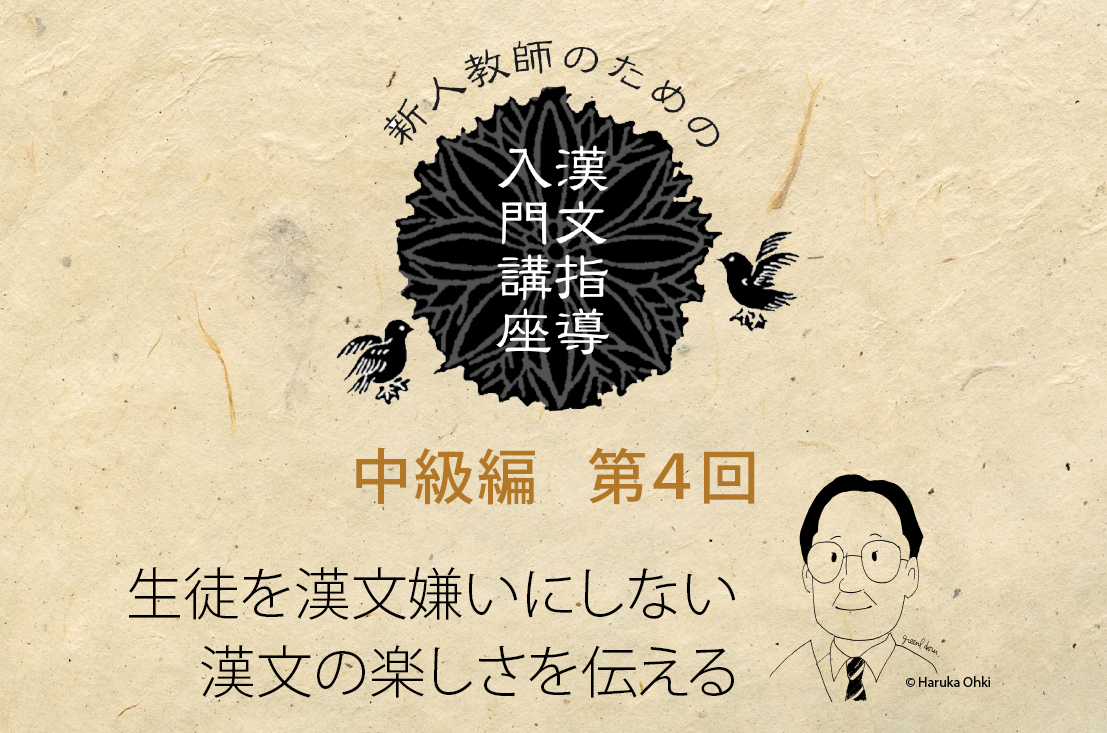新人教師のための漢文指導入門講座
中級編 第1回 「古典」の授業始め ―句法に偏らない豊かな授業を目指して―
塚田勝郎
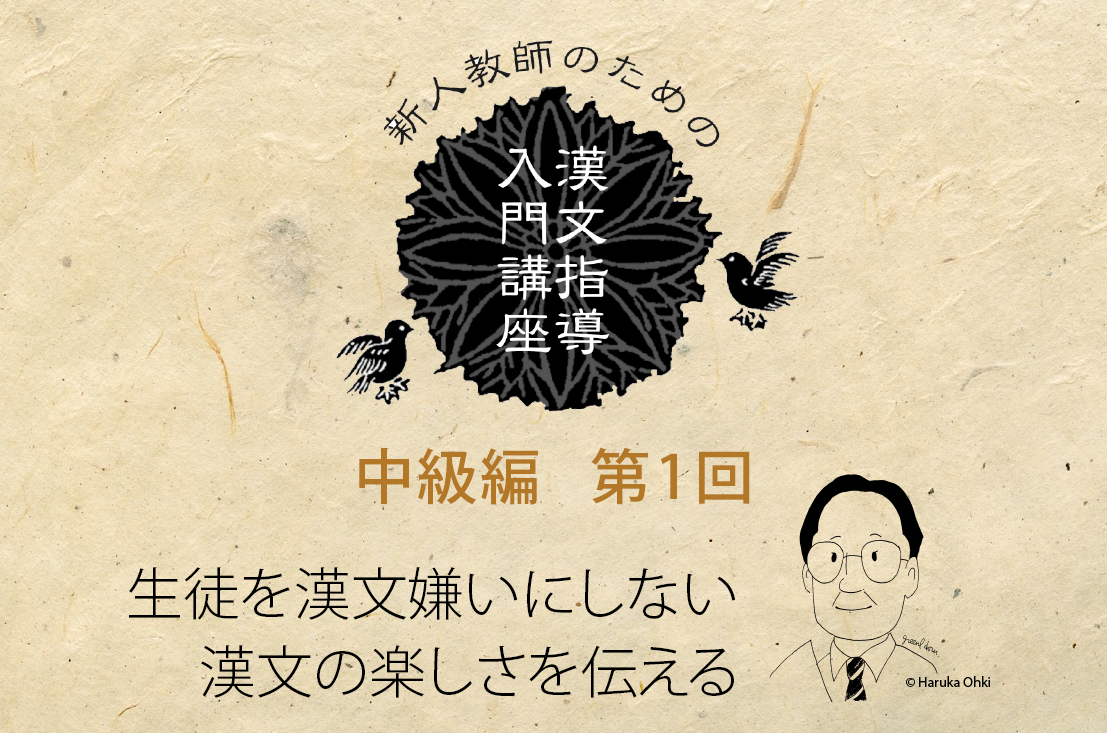
1 「国語総合」と「古典」の関係
年度が改まり、学校では新しい学期が始まりました。この連載の第一部では「国語総合」を教材としてきましたが、今回からは「古典A・古典B」の内容を扱います。本講座も、ようやく第二学年に進級できたといえましょう。
ところで、「国語総合」の漢文の授業と「古典A・古典B」のそれとのちがいは、どこにあるでしょうか。簡単にいえば、「国語総合」は入門段階、「古典」は応用・発展段階です。「国語総合」は漢文に親しむことを目標とし、「古典」では自分の力で読み、考え、味わうことに力点が置かれます。
このように述べると、「『古典』の授業では、句法に時間を割かなければならない」と早合点される方があるかもしれません。たしかに句法の指導を抜きにして、漢文教育は語れません。しかし残念なことに、句法指導の意義や、その範囲、内容、指導法については、議論が尽くされていると言い難いのが現状です。その結果、句法指導を最優先する授業が行われたり、生徒が「漢文の勉強は、句法がすべて」と即断したりする状況が生まれています。
ここでは、「句法に偏らない豊かな授業を」との立場から、「古典」段階の漢文の授業について考えていきます。
2 二年生「古典」最初の授業―「画竜点睛」の授業展開
「古典」が応用・発展段階とはいえ、いきなり重厚長大な作品を扱うのは逆効果です。その意味で、「国語総合」と同様に「古典」教科書が故事成語の単元から始まるのには、理由があるのです。今回は「国語総合」入門編にも採られることの多い「画竜点睛」を教材として、二年生「古典」の最初の授業を構想します。
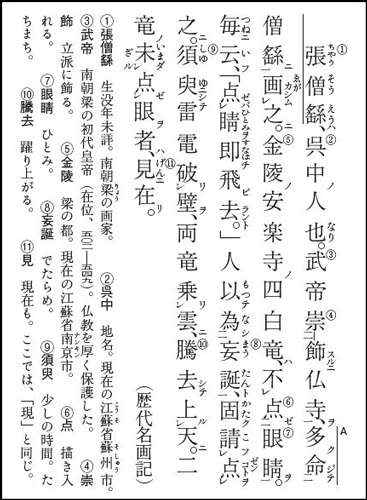
(1)固有名詞に傍線を付す
既に「国語総合」で指導が行われているかもしれませんが、漢文を読む時に、固有名詞とそれ以外を正確に区別することは、読解の出発点です。固有名詞に傍線を付す習慣は、入試や模試で初見の文章を読み進める際に武器になります。「画竜点睛」は短文でストーリーも複雑ではありませんから、傍線は人名だけに限ってもよいでしょう。
(2)語注を確認する
語注の確認の習慣づけも忘れてはなりません。センター試験の漢文で語注を参照せず、大失敗したという「悲劇」を例年耳にします。語注を抜きにしては読解が成り立たないことを、繰り返し説き、実感させたいものです。
語注には、いくつかのタイプがあることを知らせる必要もあるでしょう。この教材には、二つのタイプの語注が付けられています。
【ことがらを説明するもの】
①「張僧繇」②「呉中」③「武帝」⑤「金陵」の語注がこれにあたり、登場人物や時代背景に関する重要な情報が載っています。生徒の中には、次のタイプの語注と混同する慌て者がいますから、生徒の様子を注意深く見守る必要があります。
【現代語訳にそのまま使えるもの】
④「崇飾」⑥「点」⑦「眼睛」⑧「妄誕」⑨「須臾」⑩「騰去」⑪「見」の語注が該当します。「最近の教科書は語注が多すぎて、教師の説明する余地がない」と批判する向きもあるようですが、筆者は逆の立場です。語注を参照しながら文章のアウトラインを把握することは、漢文読解の重要な手段の一つだからです。 また、⑪「見」の「現在も。ここでは、『現』と同じ。」という語注も不可欠です。「見」のこの意味は、漢和辞典を引いてもすぐには見つかりません。この語注は、誤読を防ぐ大事な使命を帯びています。
語注にはこの他にも、句法や出典の解説などがあります。
(3)題名の「画竜点睛」を訓読する
授業の最後に行うことも考えられますが、ここではあえて初めの段階に設定しています。前項でも触れたように、正しい読解にはアウトラインの把握が欠かせません。この文章では、「画竜点睛」という題名を訓読することが、アウトラインの把握につながります。
「画竜点睛」の訓読の可能性を示しましょう。
a 画竜に点睛す
b 画竜に睛を点ず
c 竜を画きて睛を点ず
d 画きし竜に睛を点ず
a→b→c→dの順に、アウトラインの理解を伴ったよい訓読と評価できます。作品の題名がいつでも訓読できるとは限りませんが、取り入れたい手法の一つです。
(4)「睛」と「晴」の字体のちがいに注意する
「古典」の教材には、「国語総合」以上にふだん見慣れない文字が多く登場します。そのせいか、「睛」を「晴」と誤記する生徒が少なからずいます。機会を見て、誤りやすい文字の一覧を示し、注意を喚起したいものです。
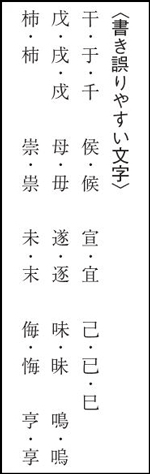
なかでも「鳴」と「嗚」の混同は後を絶たず、「ああ」を「鳴呼」と書いて平気な生徒は毎年多くいます。文字の構成部分の細部にまで眼を届かせることは、漢文読解の大きな助けになるだけでなく、社会人として言語生活を営む上で、貴重な財産となるでしょう。
(5)傍線部Aを使役に読む理由を考える
通常、「使・令・教・遣」などの使役の助字が用いられている場合は、「…をして…(せ)しむ」の形に訓読します。しかし、この文には使役の助字が見当たりません。では、なぜ使役に読むのか。その説明は、「意味上から使役に読む必要が生じるから」とか、「『命』は使役を暗示する動詞だから」と説明されることが多いのですが、筆者の経験では、これらの説明は生徒を納得させるには充分ではありません。そこで、次のように板書して、二つの動詞「命」と「画」の主語を考えさせます。

省略されている主語を補ってこのように整理すると、多くの生徒が一分の中に主語・述語の関係が二組あることに気づきます。「主語の異なる二つの動詞を含む文では、主語を一つにそろえて読む必要がある。そのため二つ目の動詞に使役の『しむ』を添えざるを得ない」と補足すると、納得が得られます。
(6)「以A為B」の形に習熟する
この形は、「国語総合」で学習済みであっても、復習を兼ねてもう一度取り上げるべき大事なものです。
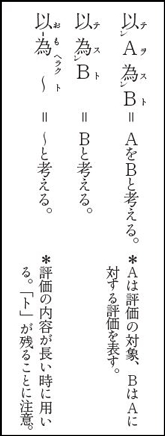
これは一種の慣用句で、句法集には出てきません。「請(フ) ~(セン・セヨ)」などとともに、一度は触れておきたいものです。
3 発展的な学習の契機に
漢文の学習に限らず、授業時間内にすべてを伝え、理解させることは不可能です。生徒の自発的な学習を促すべく、様々なヒントを与えることも、教師の使命です。発問の一例を示します。
① 「画竜」は読み方は、「ガリョウ」か「ガリュウ」か?
② 「妄誕」の「誕」に「でたらめ」の意味がある理由は?
③ 「雷電」の「雷」と「電」の字訓とその語源は?
漢和辞典を引き、漢字に興味を持たせることが目的です。「竜」の字音は「リョウ(リヨウ)」が漢音、「リュウ(リウ)」が呉音だと知ることは、訓読は原則として漢音によることの再確認にもつながります。「誕」は、漢和辞典の解字欄に注目させることがねらいです。「言葉をのばす→いつわる、のびる→生まれ育つ」という説明を興味深く読む生徒も多いでしょう。「雷・電」の字訓は、「かみなり」と「いなずま(いなづま)」です。国語辞典も併用して、このように訳した先人の発想に気づかせたいものです。
④ 「画竜点睛」を参考にして、次の文章に返り点と送り仮名を付してみよう。
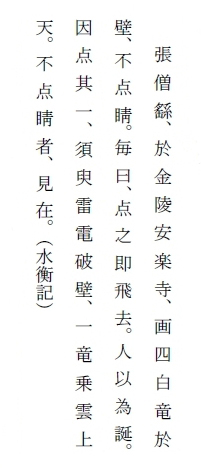
④は、一見して難しそうですが、「画竜点睛」の本文を参照すると、多くの生徒が正しい読み方にたどり着きます。「白文を読めた」という成就感は、生徒にとって大きな励みになるはずです。参考までに、 ④の文章の書き下し文を載せておきます。
張僧繇、金陵の安楽寺に於いて、四白竜を壁に画くに(画くも)、睛を点ぜず。毎に曰はく、「之に点ぜば即ち飛び去らん。」と。人 以て誕はりと為す。因りて其の一を点ずるに、須臾にして雷電 壁を破り、一竜 雲に乗りて天に上る。睛を点ぜざる者は、見に在り。
*次回以降は、句法指導の様々な側面を取り上げます。
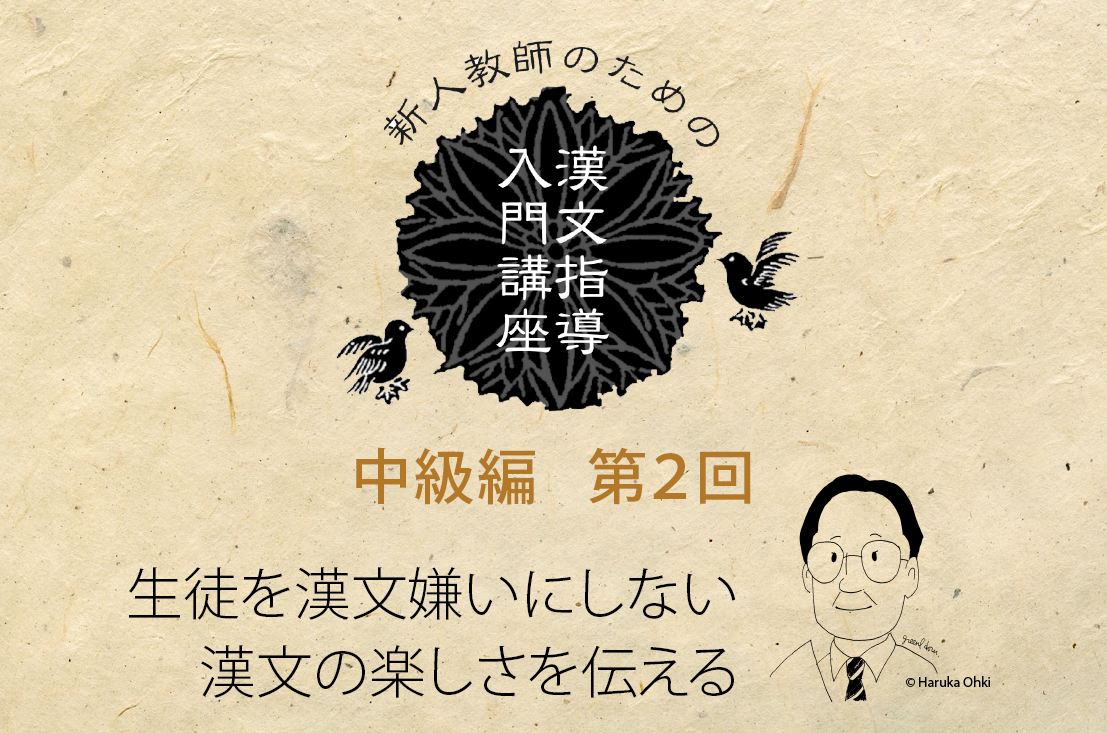
詳しくはこちら
一覧に戻る