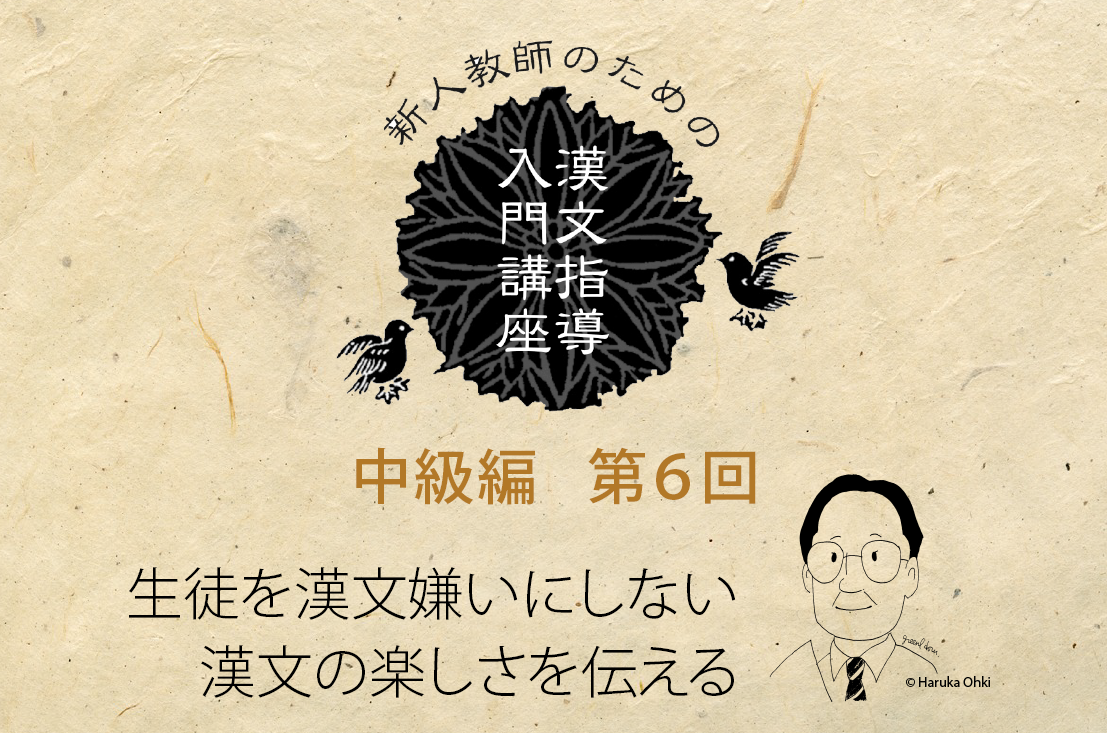新人教師のための漢文指導入門講座
中級編 第4回 句法指導の心得 ―四大句法② 受身―
塚田勝郎
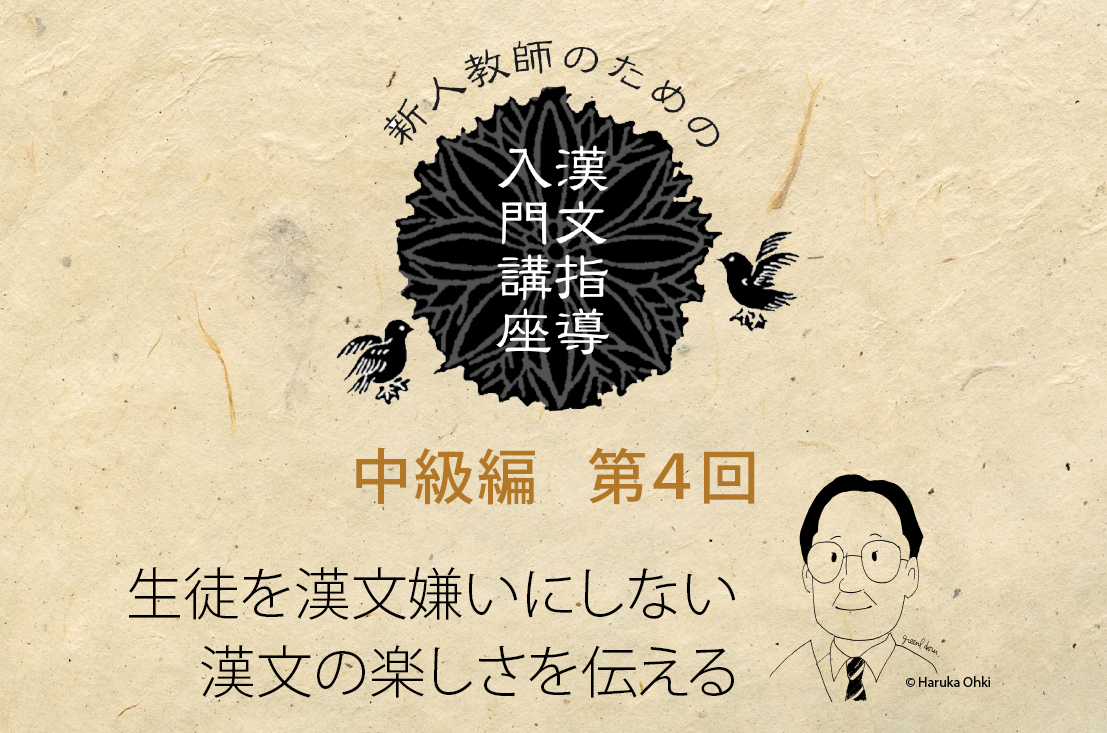
1 使役の形の再確認
前回扱った使役の形について、一点だけ補足しておきます。使役の形の訓読を誤って覚える生徒が、例年一定数います。具体例をあげると、「使人読。」を「人をして読ませしむ。」と読んだり、「令写。」を「写させしむ。」としてしまうのです。
使役の形は、一般に「使AB。〔AをしてB(せ)しむ。〕」とパターン化して説明します。助動詞の「しむ」は未然形接続であり、漢文訓読には「愛す」「論ず」のようなサ変動詞が多く出てくるところから、「B(せ)しむ」と表記するのですが、「動詞の未然形に『せしむ』を添えればよい」と早合点する生徒がいるようです。あるいは、近ごろはやりの「文書を読まさせていただく」のような、「サ入れ」表現の影響があるのかもしれません。
いずれにしても、「せ」を補う意図を丁寧に説明する必要があります。その際、次のような練習問題も有効でしょう。
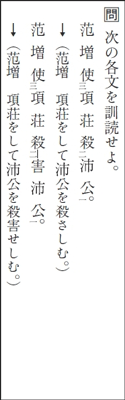
「殺す」は四段動詞ですから、「殺さしむ」と接続し、「殺害す」はサ変動詞ですから、「殺害せしむ」と接続します。「殺させしむ」とはならないことを、しっかり認識させたいものです。
2 受身の形を学ぶ意味
句法の学習の中で、受身の形が重視されるのはなぜでしょうか。「型」がいくつもあって、教えるのも覚えるのも大変だから、というのは一面的な理由でしかありません。説明のために、『史記』項羽本紀の「四面楚歌」の一節を抜粋してみます。

この部分を句法的な視点で観察すると、動詞「幸す」を、「見」「被」「為」などの受身の助字がないにもかかわらず、「幸せらる」と読んでいる点が目を引きます。では、「幸す」を受身に読む根拠は、どこにあるのでしょう。試みに「有美人、」以下の部分を、次のように図式化してみます。

項羽と、彼の最も身近な「従属物」であった「虞」「騅」との関係が、対句によって対比的に示されていることに気づかされます。
ここで、「幸す」の主語を考えてみます。この語と対の関係にある「騎る」の主語が項羽であることは明らかですから、「幸す」の主語も項羽と考えて間違いないはずです。項羽を主語と考えると、「常に幸して従はしむ。」と訓読できます。一方、伝統的な訓読では、「常幸」の主語を虞美人として、「虞美人はいつも寵愛されて、項羽のお供をしていた。」という解釈に立った読みが行われています。
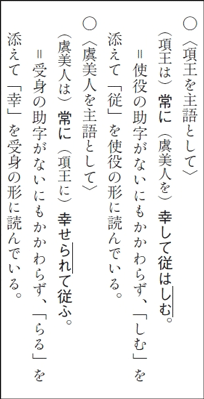
このことからわかるように、使役の形と受身の形とは表裏一体の関係にあり、どちらの形も主語の確定と深く関わるのです。「受身の形はなぜ大事なのか」という疑問に対しては、受身の形への習熟が動作の主体の確認につながるから、と答えることができます。
3 指導の実際
今回も高校三年生用の「受身の形の総まとめ」のプリントを用いて、能率的な指導法を考えてみます。指導時間は、一時間を想定しています。
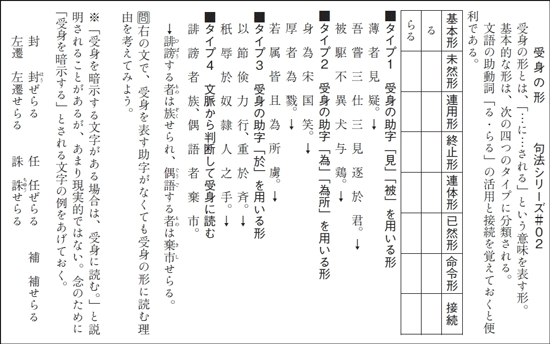
この種のプリントを作る際には、次の四点に注意する必要があります。
1 生徒が作業しながら知識を吸収できるようなワークシートのスタイルに仕上げる。
2 一時間の授業内で完結するように構想する。
3 文例はできるだけ既習の教材から選ぶ。初出の文を掲げる際は、書き下し文と現代語訳を添える。
4 参考書ではないので、瑣末な知識は省く。
プリントの内容に従って、受身の形の指導内容を見ていきましょう。
⑴ 助動詞「る・らる」の接続の違いを意識させます。
| る………四段・ナ変・ラ変の未然形に接続。 |
| らる……それ以外の活用の未然形に接続。 |
中には「古文の時間じゃないのに……。」とつぶやく生徒もいるかもしれませんが、漢文の訓読は文語訳であることを思い出させる絶好の機会です。
⑵ タイプ1では、「見」「被」の順にこだわりましょう。というのは、受身の助字というと真っ先に「被」を想起する生徒が多いのですが、実際には「被」を用いた受身の文は多くありません。ここでも「る・らる」の使い分けを思い出させます。「疑ふ」「逐ふ」「駆る」はいずれも四段に活用しますから、「疑はる(こと)」「逐はる(こと)」「駆らるる(こと)」と訓読することになります。ただし、「駆らるる」は「駆- らる- る」という錯覚を招きやすいようですから、丁寧な説明が必要でしょう。
⑶ タイプ2については、同じ「為」を用いながら、一文目と二文目では「為」の読み方が異なることに疑問を持つ生徒がいるはずです。この疑問に対しては、次のように説明するとよいでしょう。
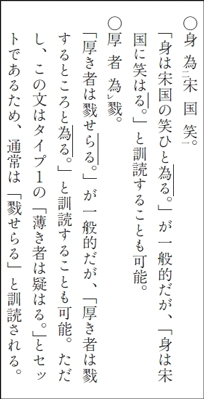
⑷ タイプ3でも、「る・らる」の使い分けを確認しましょう。「重んず」はサ変ですから「重んぜらる」と接続し、「辱かしむ」はマ行下二段ですから「辱かしめらる」と接続します。
⑸ タイプ4の例文には動詞が複数あり、それぞれの主語は二種類に分類できます。
民が皇帝を「誹謗す」。皇帝が民を「族す」。
民が(皇帝のことを)「偶語す」。皇帝が民を「棄市す」。
使役の項でも触れたように、一文に主語の異なる動詞が二つ存在するという漢文特有の現象が、ここにも見られます。この文では「誹謗者」「偶語者」という形で主格が明示されていますから、二つ目の動詞「族」「棄市」は「族せらる」「棄市せらる」と受身に読むことになります。
なお、プリントにも書いたように、「受身を暗示する文字」については、軽く触れる程度でよいでしょう。
*次回は疑問と反語の形を取りあげます。
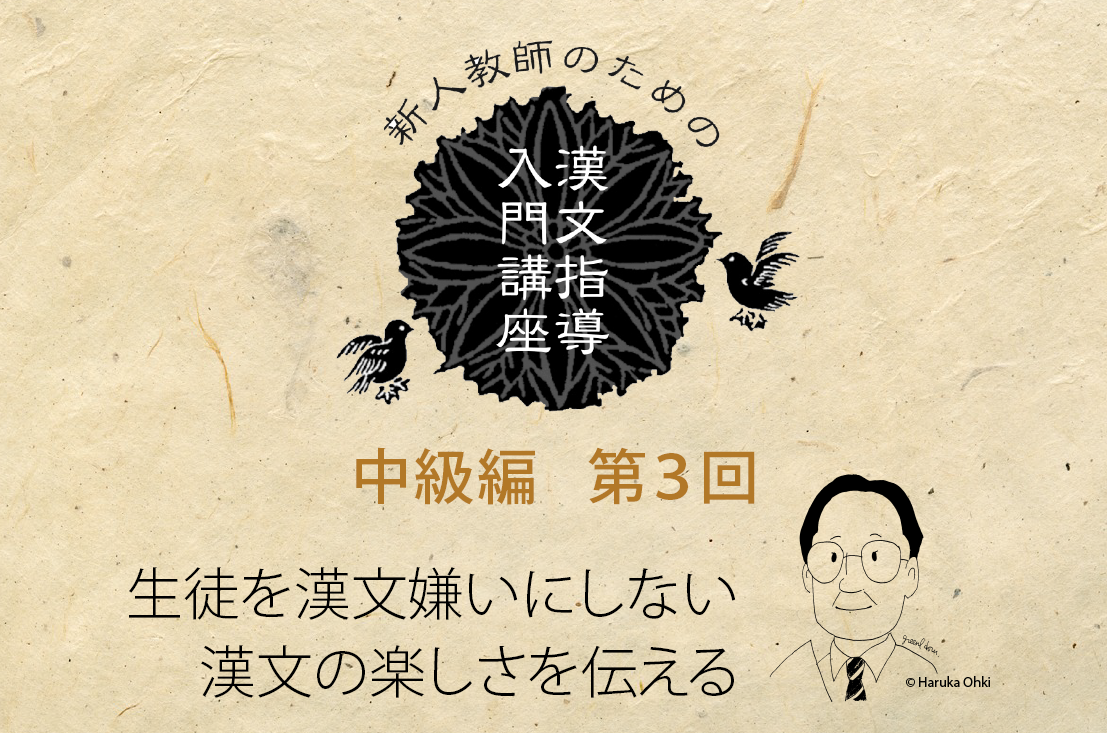
詳しくはこちら
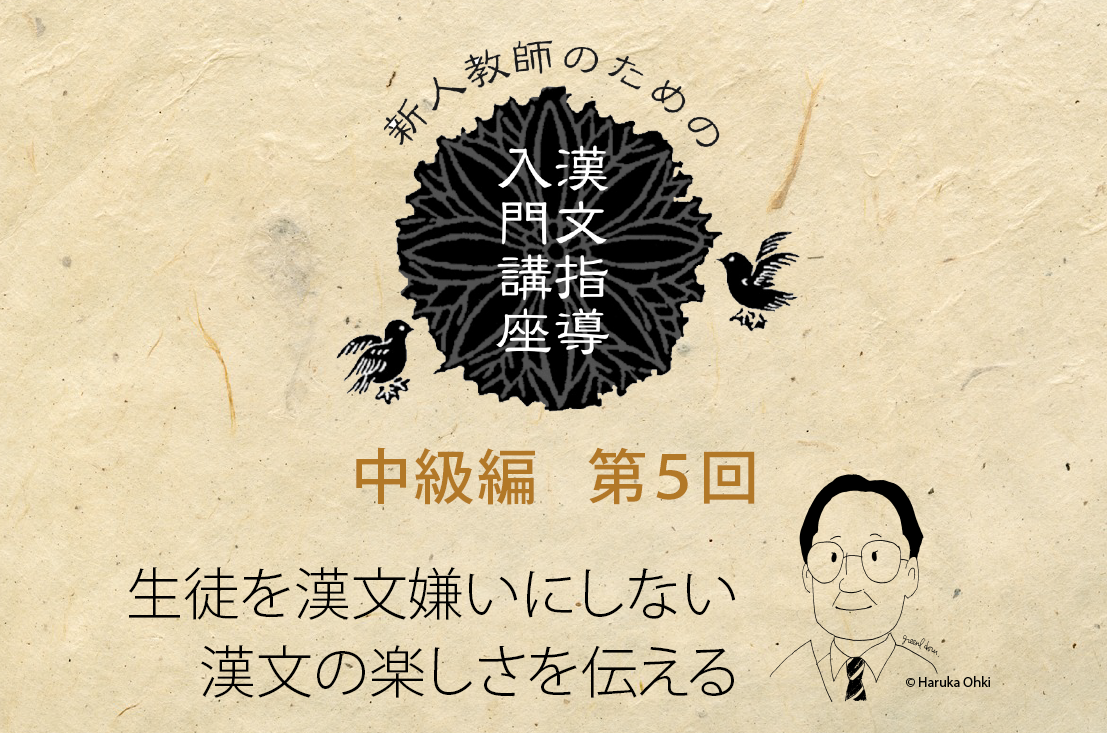
詳しくはこちら
一覧に戻る