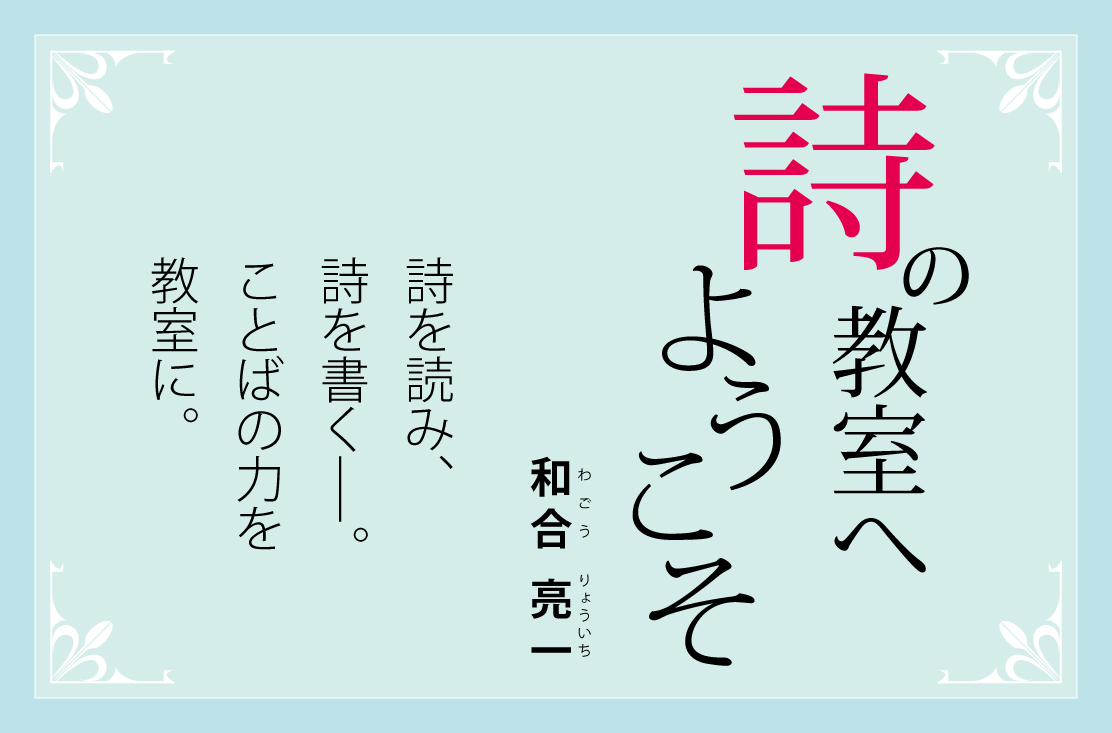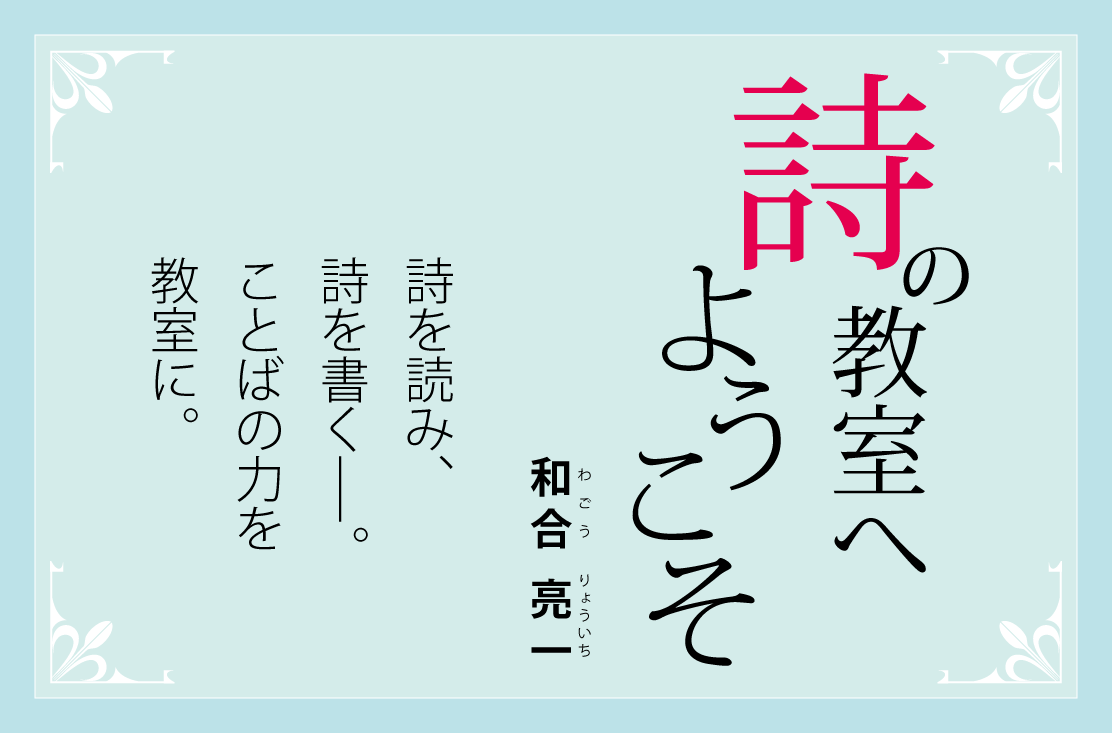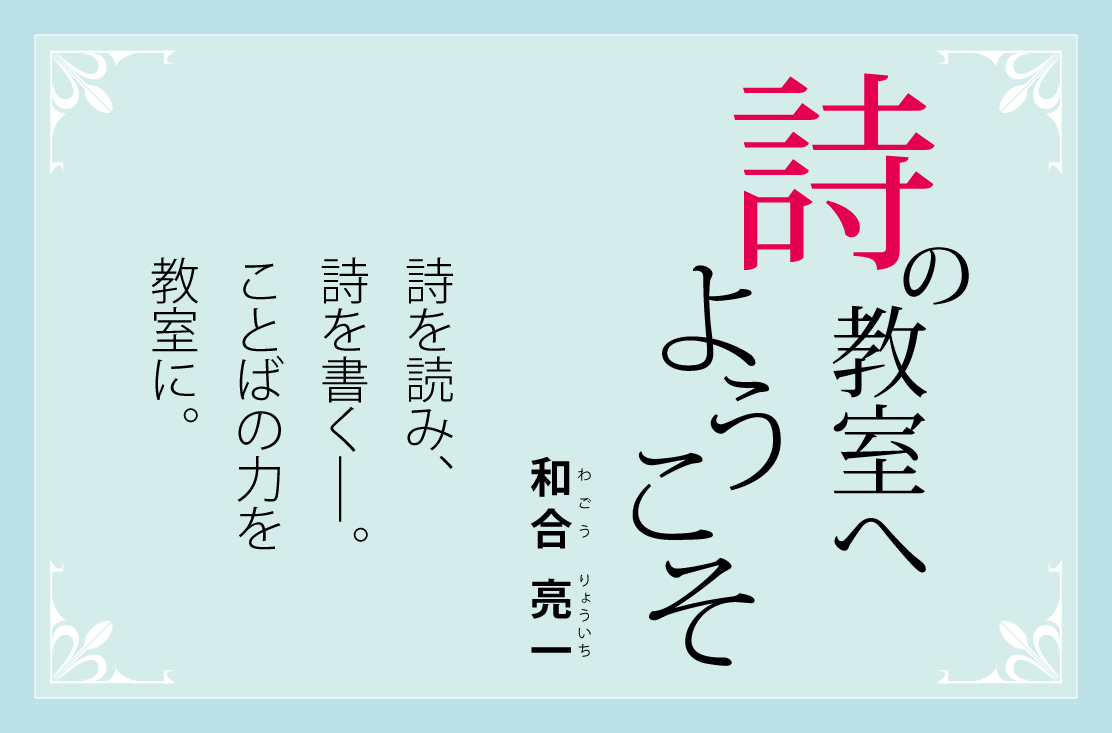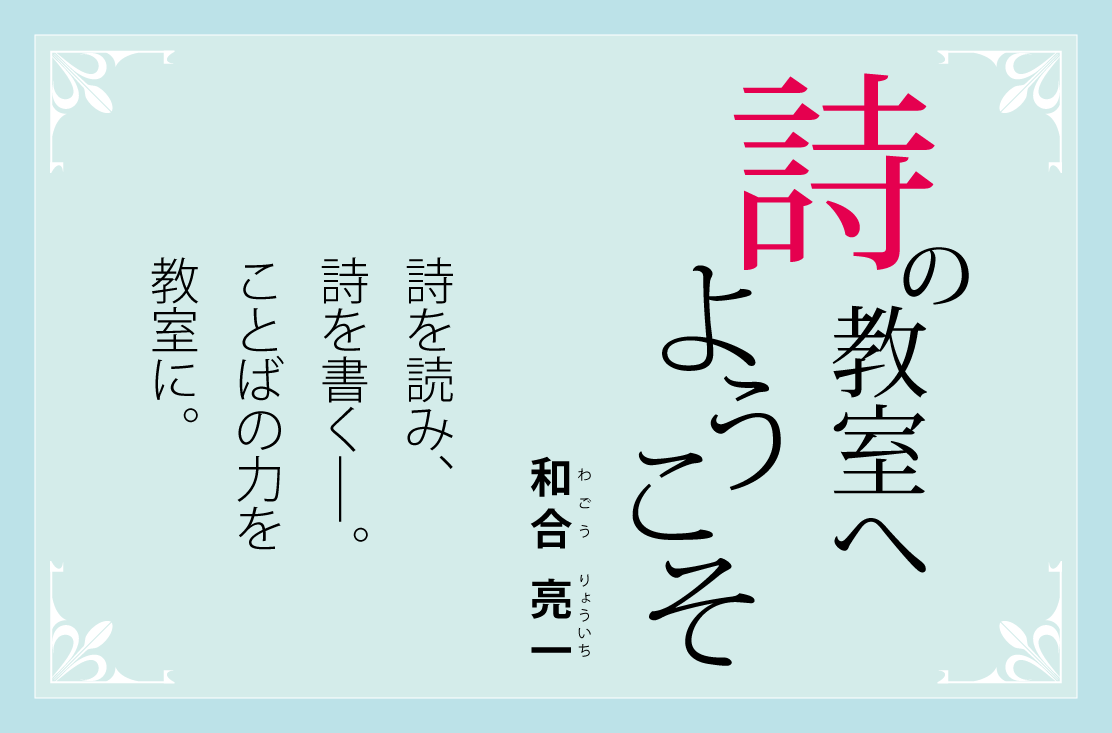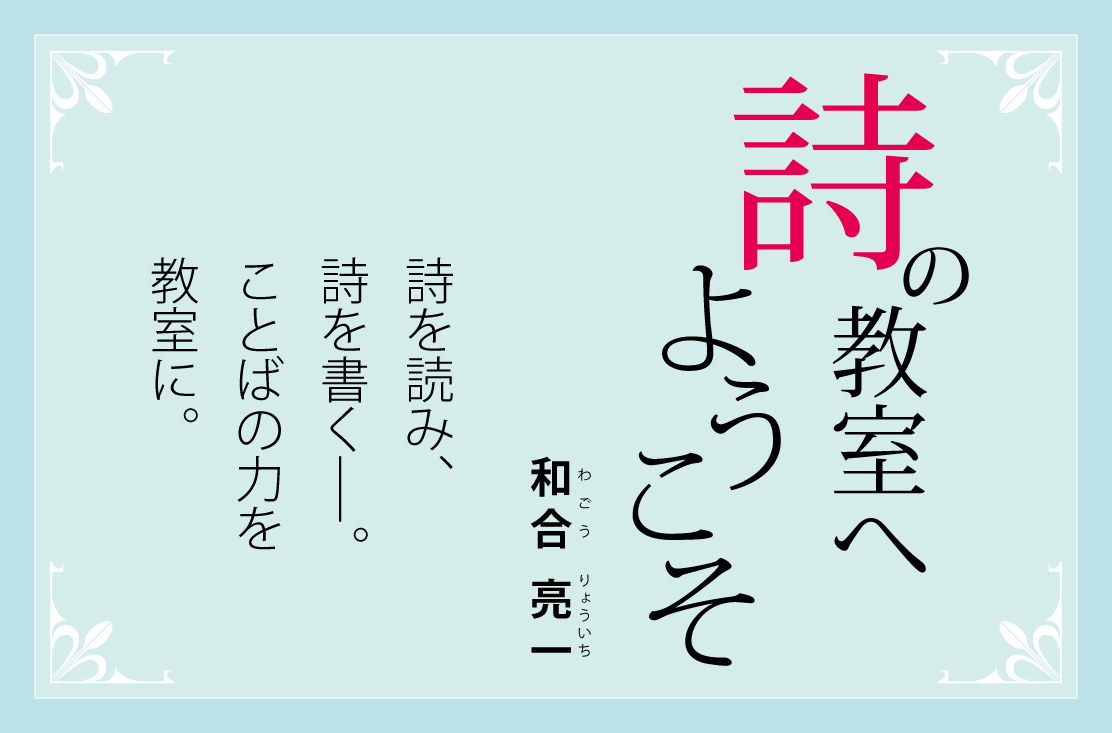詩の教室へようこそ
第4回 詩の時間を告げるチャイムを…
和合亮一
- 2022.04.08
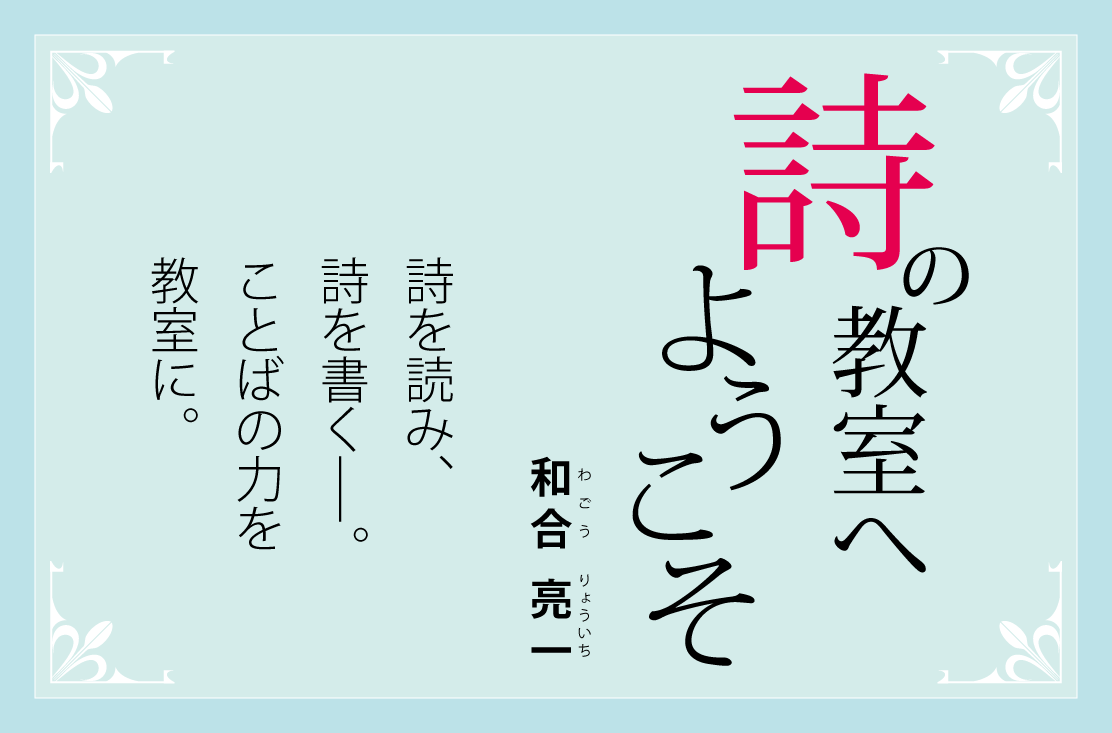
◆「読む」から「書く」へ
詩集の親しみ方について時々に、たずねられることがあります。
もちろん、あまり難しいことは考えずに好きな時に好きな詩を読むということで良いと思います。
ある方はカバンの中にいつも詩集(文庫本がサイズ感として良いそうです)を入れておいて、通勤や待ち時間などで少し暇を見つけた折に読むことにしていると話してくれたことがあります。とても素敵な親しみ方をしていらっしゃいますねと感心いたしました。
詩の種類も実に様々で、そのとらえ方も人によって色々、読み方も千差万別…。だから一概にこうだとは言えないと思います。私は詩を作る時のヒントを探すために詩集を開くという気持ちが、実作者として強くあります。でも詩を書いてみたいと思う前は、詩の世界を知りたいとか触れたいという素直な心持ちのほうがとても強かったと思い返します。そしてあれこれ読み耽っているうちに、次の扉を開きたくなったのです。それを開いてみて…。
親しみ方を語る前に、なぜだか実作をおススメしてしまっていますね。
◆真似ることから始める
私は何かを書いてみようかなあという生徒さんには、まずは詩集を読むことから勧めます。読み終えてから、好きだと思った詩を尋ねてみます。そして、コピーして手渡したり、短いものなら書き写すことも勧めたりしてみます。それをホチキスで綴じたり、ファイリングしてみたり…、言わば自分だけの手作りアンソロジー詩集を作ってみることをアドバイスします。世界に一冊しかないコレクションブックを、繰り返し読んでみることを伝えます。
するとしだいに何か書きたくなってくる…。ここがチャンスです。何事もまずは真似ることから始まるという考え方があります。その通りです。書かれている詩を真似て書いてみることを強く勧めます。
なるべく、そっくりに…と。
私は詩を書き始めた時に、真似をしたい=盗み出したいという気持ちで眺めているのだと気づいたことがありました。少し邪な気もして自己嫌悪のようなものに陥った時もありました。しかし室生犀星の記した文章にこのようなものがあったことを発見して、とても励まされたのです。
「詩というものは先ずまねをしなければ伸びない、まねをしていても、まねの屑を棄てなければならない」。
なるほど。このようにして近代詩人たちはこつこつ読むことと書くことに励んだのだと思わせてくれる一節です。特に「屑を棄てる」とは面白い言い方です。誰それの真似をしたのだと思わせないことが、さらに重要なのだとも気づかせてくれます。でもここはかなり創作熱の入った人へ向けている内容であって、初めての生徒さんには伝えなくて良いと思います。あれこれ真似てみようとすることが、書き始める第一歩としてとても大事…、まずは詩人のモノマネに徹してみよう、と。それが出来るのもまずは、しっかりと生徒さんが時間をかけて、繰り返し詩を読み耽ってみるということが前提としてあるから出来るのです。読むことと書くことの両輪の始まりです。
震災直後、私は被災地の福島で起きている出来事を、「詩の礫」と題し、無我夢中になって毎日、現状の報告のような心持ちでツイッターに詩の発信をし続けました。
メディアなどで谷川俊太郎さんの「生きる」、宮沢賢治の「雨ニモ負ケズ」という詩が数多く取り上げられて紹介されていて、私自身もとても励まされました。この時に詩が多くの方々に求められたという事実は、皆が正に言葉の力を欲していた証であったのだと思います。
生きているということ
いま生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ
くしゃみすること
あなたと手をつなぐこと
激しい余震にさいなまれながら新聞やネット記事などであらためてこの詩を目にした折に、子どもさん向けのワークショップの思い出…、参加者の小さな表情の一つ一つが浮かび、懐かしく、切ない心持ちになったことを、あれから歳月が過ぎましたが、今でも時折に思い出すことがあります。
まずは谷川さんの真似をしてみるような気持ちで最初の部分の続きを書いてみようということから、そのワークショップは始まったのでした。谷川さんになり切って、どんなふうに続くのか、それをみんなに考えてもらいました(本当の続きの部分は隠します)。たくさんの「生きる」が飛び出しました。例えば「失恋」や「ねぼう」など名解答・珍解答が出ました。
続きはどうなるだろうという想像の時間を終えてから、正解の谷川作品をみんなで声に出して読んでみました。あがったのは「おお」とか「そうか」とか「こう書かれているんだなあ」という、楽しんだり、感心したりしている声でした。クリエイティブな雰囲気を感じました。
なり切って作ってみたことにより、子どもたちがとても能動的になっていることを目の輝きや呼吸で実感できたのです。
悪ノリは続きました。例えばその詩をまた隠して、もう少し続きを書いてみようと勧めたり、「生きる」というタイトルが無かったら、何になるかということをみんなで話し合わせたりしました。例えば「夢」「好きなこと」「成長」など、別のタイトルが生まれました。
ワークショップの最後には、スペシャルゲストとして招いた谷川俊太郎さん…、ご本人に登場していただきました。子どもたちからここまで挑戦してみた内容を一つ一つ発表してもらいました。
その前に、作品を好き勝手にしてしまい(ひとえに私という講師の責任なのですが)、失礼なことをしてしまいましたとお詫びいたしました。自分の書いた一つの作品でみんなにあれこれと楽しんでもらえて、とても嬉しいですとにこにこと話して下さった姿が印象的でした。
この時に、詩人の真似をはっきりとやってみようということは効果的なのだ…と、勝手ながら指導する側として確信したのでした。時には創作者の気持ちでオリジナルの作品にコミットメントしていくということが、読むことをより親しいものにして、広がるイメージも豊かで具体的なものになっていくのだと思いました。
読むと書きたくなる、じゃ、書いてみる、するとまた読みたくなる…という具合に。両輪は回り続けていくのです。
◆詩集と語り合うこと。
吉田兼好が記した「徒然草」の第13段に書物を読むことの楽しみを語った一節があります。「ひとり、燈のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とする」(灯のもとで書物を広げ、かつて筆を執った遠い昔の世の人を友として…)。
彼は中国の南北朝時代や春秋時代などの詩文集や論文をこよなく愛し、読み耽っていました。書物を広げて、その向こうに見える人の影を友として…、兼好法師に読書の極意を教えられたように思います。
しかしここであえてまたまた勝手ながらの提言ですが、例えば「見ぬ」ではなくて「見る世の人」という考え方もあてはめてみては…と思うことがあります。
私はこれまで、中原中也の妹さんや弟さん、室生犀星のお孫さん、萩原朔太郎のお孫さん、晩年に花巻で暮らした高村光太郎と親しくしていた近所の子どもさん、土井晩翠の教え子さん…etc、の方々に会いに行き、直接にその詩人本人の逸話はもちろん、その人物と交流のあった人々の話などを伺うことをしています。
不思議とその後で、彼らの詩を読む意識がすっかりと変わることをいつも実感します。ゆかりのある方々と出会うことで、姿が見える気がするのです。言わば「見ぬ」から「見る」に変わる瞬間なのかもしれませんね。彼らの人物像や人生にもっと触れたくなるし、全ての作品を読破してみたいと強く思うようになります。
好きな詩人をしっかりと見つけられた折には、その人生を追いかけてみるのを生徒さんたちに勧めてみるのはいかがでしょうか。例えば近代詩人が好きなのであれば、数々の書き手たちが、詩人たちの伝記を手がけていることは私が言うまでもないでしょう。それに触れながら、制作時期と作品とを照らし合わせてみるような読み方を生徒たちに紹介してみると、言わば詩人論の入口に立つことにもなると言えるでしょう。
私の母校の先輩の詩人長田弘さんの、読書について書かれたエッセイで、兼好法師の境地と似たメッセージが伝わってくるような、印象深い一節があります。
「灯りの下に自由ありき。灯りの下の自由は言葉なりき。最初に手に入れた、首の曲がる、じぶんだけの電気スタンドの下で見つけてからずっと、いまも胸中にあるわが箴言です。」(『幼年の色、人生の色』)。
長田さんもまた、「灯り」=「燈」のもとで、静かで深い読書の時間をこよなく愛し、人生の中でずっとそれを大事にしてきた姿が、ここの部分から良く分かってきます。積極的に何かを書物へと求め続けていくことの自由…。
光の下の本の頁に広がる限りない言葉の世界の味わいを生徒さんたちへ伝えていくことが出来たらと願っています。
*****
素敵な投稿作品が届きました。
校舎
都立大江戸高校1年 藍原
響く あなたの声がきこえる
遠い 天井で響く
ガラス張りの空気 透けた先のあなた
響く あなたの声がきこえる
近づく 少しでも同じ場所にいたくて
ここは冷たい
ガラス張りの空気 透けない足元
遠く あなたの声がきこえる
近づいたって 定規一本ぶん 遠く
響く あなたの声はいつも私のそばで
遠い 天井で響く
ガラス張りの空気 融かしてしまいそう
言葉を絞って 言葉を磨いて
そしてやっと あなたに声をわたす
近づく 少しでも早くわたしたくて
響く 私の声をあなたに
ここは冷たい
ガラス張りの空気 透ける心
近く もっとずっと
ガラス張りの空気 あなたの熱を映す
透ける心さえ あなたと交わっていく
響く あなたの声をきく
そばで 私の声をわたす
灰と白で縁取られた私は
灰と白で縁取られたあなたの
響く あなたの声を探す
時間を告げるチャイムすら
ガラス張りの空気 さえぎってしまうから
空気を震わせている何かをキャッチする鋭い感覚があります。
今という瞬間の一つひとつを心に刻んでいる姿が見えてきます。誰かと何かを伝え合い、響き合うことの新鮮さが、見事に言葉に託されていると感じました。
そうですね。時間を告げるチャイムは、何かを終わらせて、何かを始めさせてくれます。私たちは学校という場所で、その連続を生きているんですね。
かけがえのない青春のありかを。
『国語教室』第117号より転載
筆者プロフィール
福島県立本宮高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。
一覧に戻る