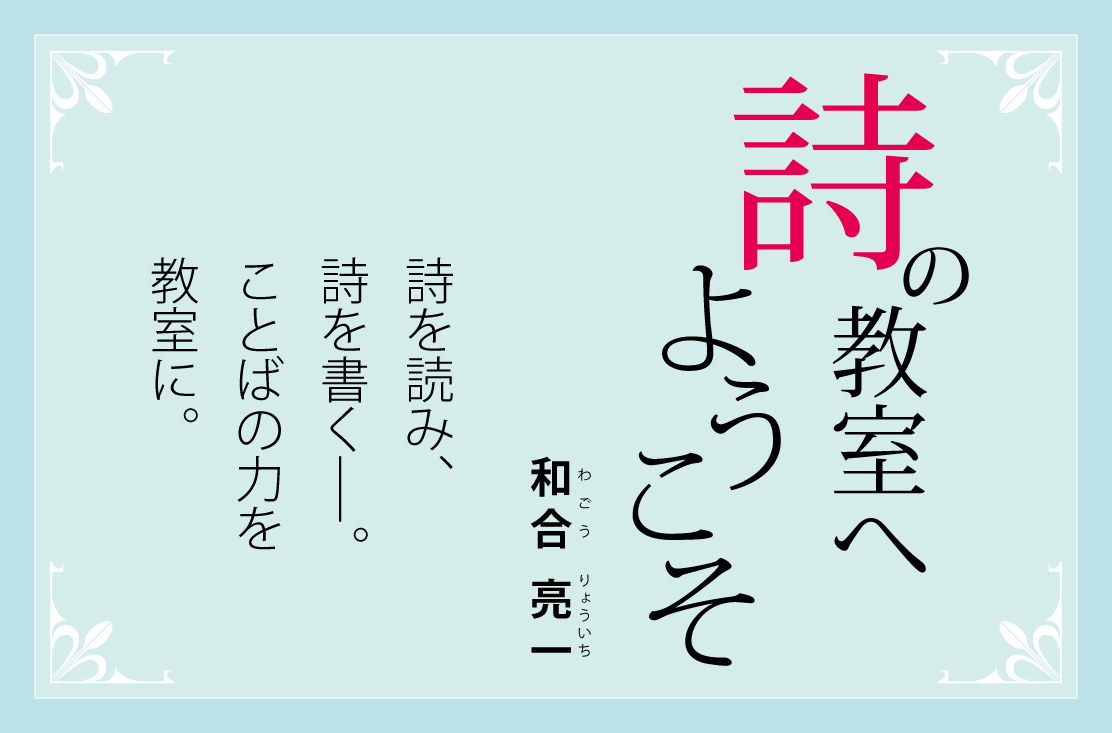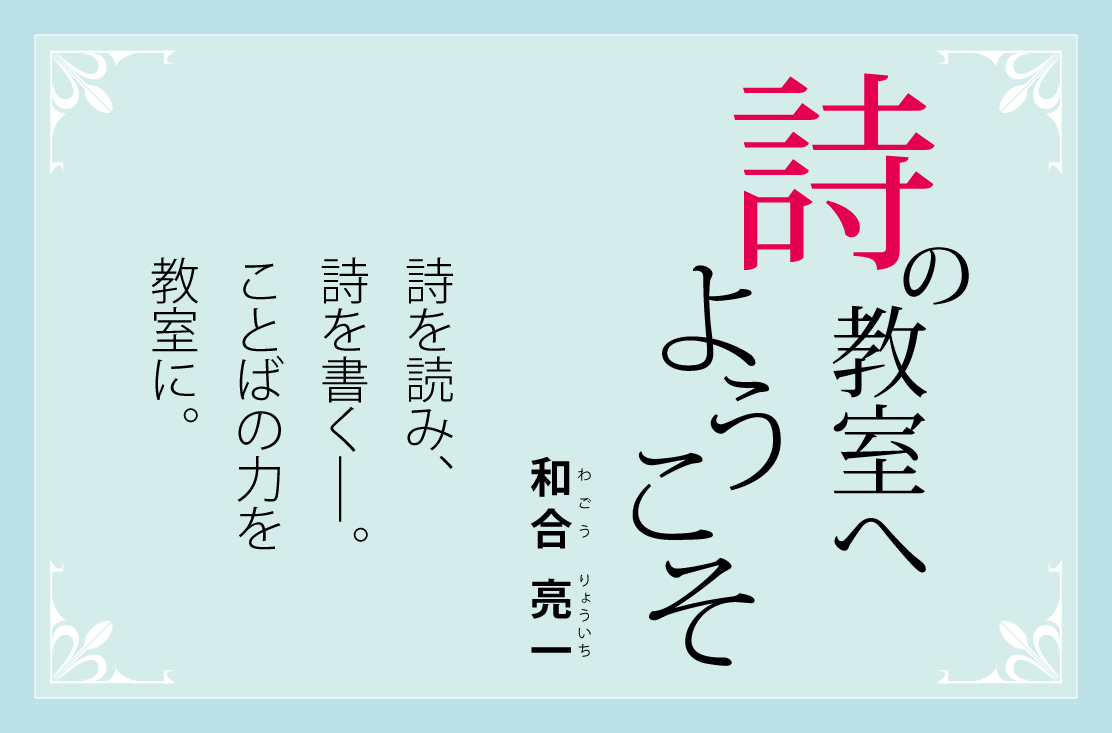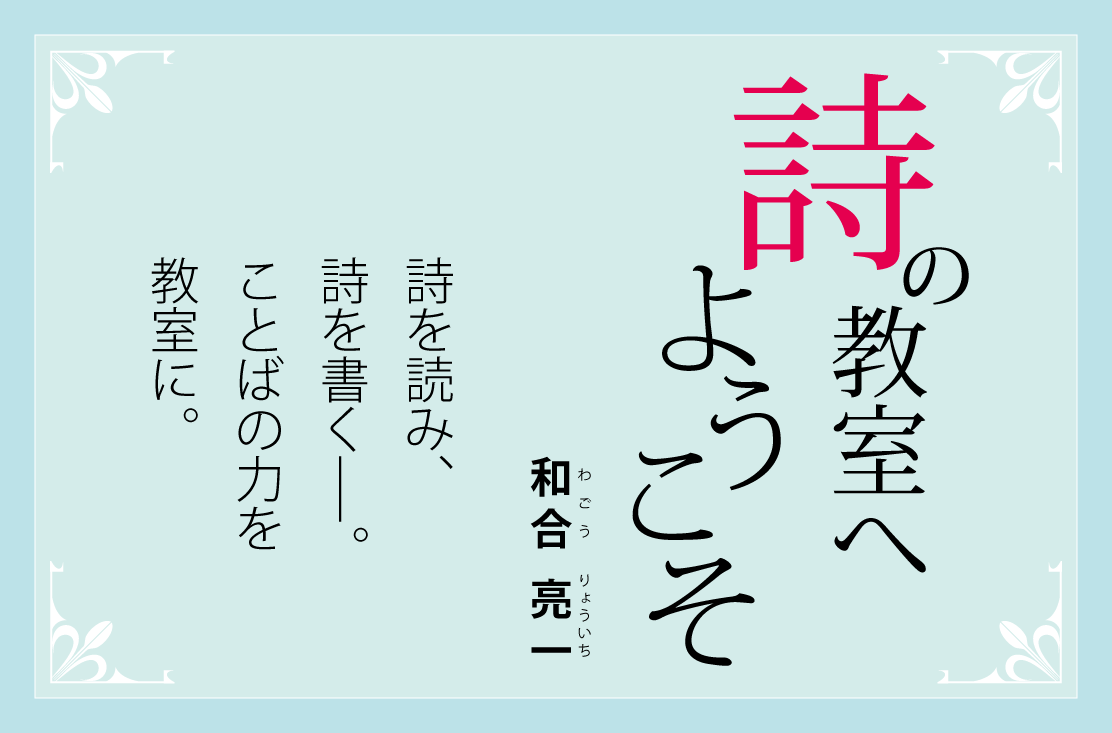詩の教室へようこそ
第10回 微細な繊細な力を信じて
和合亮一
- 2025.07.04
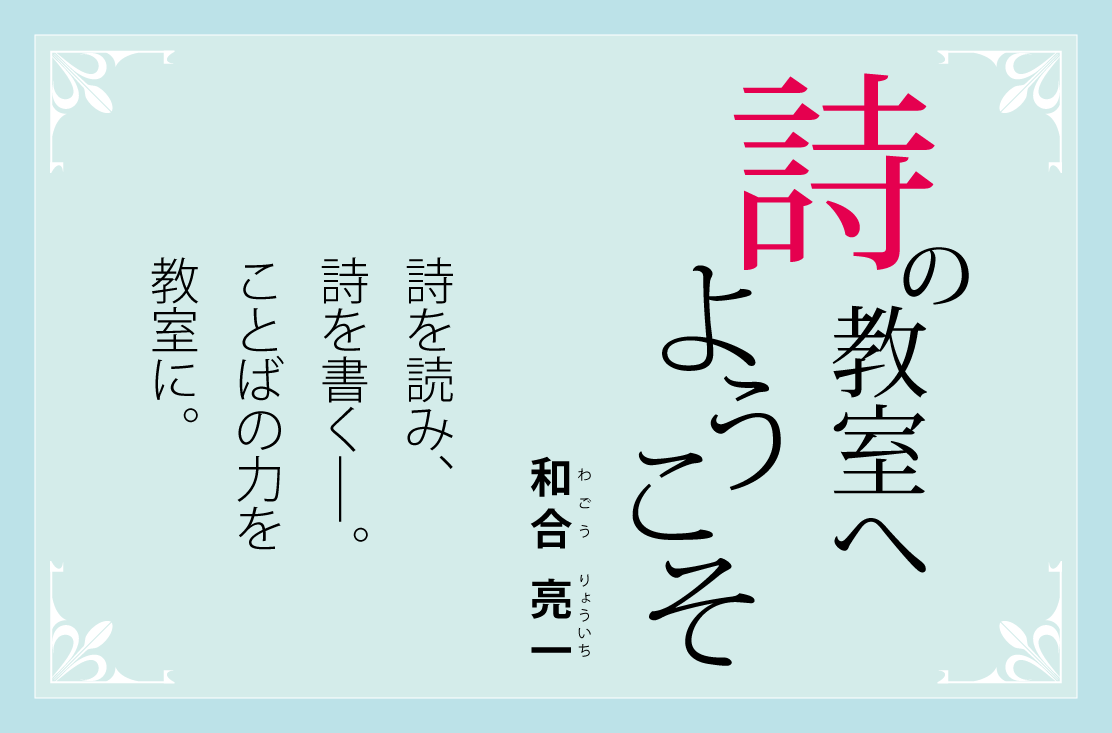
谷川俊太郎さんの訃報を知ったのは2024年11月19日、早朝の6時前でした。親しくしている新聞記者の方から、その事実を確かめる電話がありました。
私が朝早くに執筆をしていることをよく知っているからこその連絡でしたが、昨日の仕事の疲れから起きることができなくて寝床に居り、寝ぼけ眼のままで電話に出ました。驚きのあまり私の方が聞き直してしまいました。
7時を過ぎて別の新聞社からも電話が入りました。気持ちの整理ができないままにコメントの取材などに対応しました。
翌日の新聞は各紙で1面に記事が大きく載っていました。これほど国民に愛されていたのだとあらためて知りました。それぞれの記事といくつかの自分のコメントをたどりながら、やはり旅立たれてしまったのだと、深く実感した次第でした。
◆嵐の前夜にあたる時期に
谷川さんとの共著に、15年前の3月に刊行された、谷川俊太郎さんとの対談集『にほんごの話』(青土社)があります。2006年の雑誌『ユリイカ』での対談を第1回目として、2009年までの3年間のうちの、全6回分の対談が、この一冊にまとめられています。
当時の私は30代後半から40代の始めにさしかかるところであり、谷川さんは元気な70代。谷川さんの掌で転がされていたり、それでも若手の勢いで頑張って迫っていったり、お互いに大笑いしたり…。対談集を開いてみると、いろいろな思い出がめぐります。
対談集は、2010年3月の刊行です。その1年後に東日本大震災が起きて、「詩の礫」というシリーズを皮きりに、私は憑かれたように詩を書き続けるようになります。
言わば嵐の前夜にあたる時期に、谷川さんから数多くのことを教わり、示唆を受け、時には厳しく鍛えられたのです。当時と、震災を経てからでは、考え方がずいぶん変わってきていると自覚できます。
◆長年の「美」への希求
谷川さんはこの対談の中で、このように述べています。「僕は詩にはメッセージはないという立場です。日本語を、いい職人が作った美しい細工のように、ある存在としてそこに置けるのが詩だと思っているんです。だから、まず美なんです、真・善よりも。」
谷川さんは、92歳で旅立たれるまで詩を書き続け、66冊の詩集を作りあげられました。20歳の折に最初の詩集『二十億光年の孤独』を出されていますから、70年あまりも詩を書き続ける人生を送られたことになります。これは並大抵の詩業ではありません。
詩人というよりは「職人」でありたいということを、この時も含めてよく話されていたことを思い出します。脇目もふらずに、こつこつと完成へ向けてこしらえ続けていく意志と持続力が、谷川さんの心にずっと満ちていたことをあらためて想像いたします。
先ほどの言葉に続けて、谷川さんはこう述べています。「日常では『美』ということはあまり問題にならないですよね。本当か噓かのほうが問題になります。しかし詩の言語は美が問題であり、真実か噓かというのは全く問題にならないと思っています。」
長年の詩作のなかで追い求めてきたものは、こうした「美」への希求であったことがあらためてわかります。
◆詩集『二十億光年の孤独』
先ほども述べましたが、新聞各紙は1面で訃報記事を大きく載せて谷川さんの死を悼みました。『二十億光年の孤独』を代表作にあげている内容がかなり多く見受けられました。18歳から19歳の時の詩集が70年ほど後になっても代表作として紹介されることを、当時の彼は予想しなかっただろうと思います。
万有引力とは
ひき合う孤独の力である
宇宙はひずんでいる
それ故みんなはもとめ合う
宇宙はどんどん膨んでゆく
それ故みんなは不安である
二十億光年の孤独に
僕は思わずくしゃみをした
(「二十億光年の孤独」より)
例えば、日本の社会をめぐる何かというよりも、自然科学や天体などの分野に若い頃から興味があり、それは詩を書き始めた頃から一貫しているとよく語っていらっしゃったことが思い出されます。人間や社会への批評というよりも、宇宙や自然の摂理に向けてアンテナを立てるようにして、様々な事実よりも原始的な心の真実へまなざしを注ごうとしている、若々しい姿が伝わってくるかのようです。
科学の力が加速度的に進み、今や宇宙の果ては一三八億光年と言われているから、「一三八億光年の孤独」にいつか書き直さなくちゃ、と笑いながら、楽しそうに話されていたお姿が浮かびます。科学の進行も、社会や経済の有り様と同じく日々更新されていくものであり、いつもそうした分野の変化のめざましさに、深い関心を寄せていらっしゃったことが、お話しの中でよく伝わってまいりました。
この詩集には新鮮な感性がとらえた様々な自然の表情が描かれており、特に空への視点が多く見受けられます。
「飛行機雲/それは芸術/無限のキャンバスに描く/はかない讃美歌の一節/(この瞬間 何という空の深さ)」。「空の深さ」にはっとして、立ち止まっている印象があります。
この詩や他作品から伝わってくるのは、自然界が抱える深さへの敬意であり、美への希求であるのかもしれません。
◆意識よりさらに深いところから
「詩のフレーズはいったいどこから?」と、青年の私は尋ねています。「意識よりさらに深いところから出てくる何か」と谷川さんは答えています。深いところ…。あらためて対談集を読み返してみるとこうした「摂理」と「深さ」と「美」とが結びついた時に詩人は、等身大でありながら感覚と宇宙のまるごととが瞬時に結びつくかのような、懐の広い言葉を次々に生み出していったのではないかと感じられます。
さらに、こうしたお話も続きました。「文字ではないですね。声になった言語という感じでしょうか。口に出さなくても、頭の中に声が出てくる、ということはあります」と。
これも思い返してみると興味深い内容だと思います。例えば、文章のように考え抜いて書くのとはまるで違う次元で紡がれている、直の声が宿っている詩語と言えばよいのでしょうか。それが芯となって心に直接に届けられるからこそ、老若男女の心をつかむ作品が生まれていったのでしょう。
私が詩を書き始めた頃に衝撃を受けたのは『世間知ラズ』(1993)という詩集でした。これまで親しんできた作品とは違う味わいを受けました。還暦を迎えた時に作られた詩集でしたが、不惑そして天命を知る年代を過ぎて、自分へと向けられた視線の厳しさが伝わってくる印象を覚えました。外界へと向けられてきたまなざしが自分の内側へ、人間と社会の方へ、そして詩人という存在へと強く向けられているイメージを感じました。
私はただかっこいい言葉の蝶々を追っかけただけの
世間知らずの子ども
その三つ児の魂は
人を傷つけたことにも気づかぬほど無邪気なまま
百へとむかう
詩は
滑稽だ
(「世間知ラズ」より)
新しい出発をしようとしている…。客観的なまなざしを自分自身へ向けながら、新鮮に息を吹き返そうとしている印象を覚えました。その後に出された『minimal』(2002)という詩集からも再出発のたたずまいが伝わってきました。「夜明け前に/詩が/来た/むさくるしい/言葉を/まとって」。谷川さんは、この後にまた旺盛な創作活動を続けていき、詩集を次々に刊行していきます。
心境の変化なども踏まえつつ、対談集の刊行後も、いくつかの語り合いの場を重ねさせていただきながら、その都度、詩作とは何かについて何度も尋ねてしまう私の姿がありました。谷川さんから、少しでも創作のヒントをいただきたいという一心からです。谷川さんはいつも真摯に向き合ってくださいました。
親しみを覚えるお人柄で、常におだやかな語り口でしたが、詩作に関しては妥協を許さないところがあり、それを語ろうとするまなざしも顔つきも、ぐっと引き締まる感じがありました。だから、詩作について問いかけるとき、こちらはいつも緊張しました。
◆微細な繊細な力
このような話をしてくださったこともあります。「非常に微細なエネルギーが人にある程度影響を与えるということを信ずる」。「どういうことでしょうか」と聞き返そうとしている私に、続けてこう詳しく語ってくださいました。
「権力にしろ財力にしろすごい強い力ですけど、それに対して文学の力というのは、もっと微細な繊細な力なんですよね。その微細な繊細な力というものを信じるようにならないと駄目なんじゃないか。」
「知らない間にその人にちょこっとでも何らかの作用を与えるかもしれない言葉を紡いでいく、その微細な力を信ずる、信じさせるということじゃないでしょうか。」
こうした「微細な繊細な」何かを大切に詩に込めていくことと、「摂理」「深さ」「美」を求めていくこととは同義だったのではないかとあらためて思い返しております。
生きているということ
いま生きているということ
それはのどがかわくということ
木もれ陽がまぶしいということ
ふっと或るメロディを思い出すということ
くしゃみをすること
(「生きる」より)
喪失感は大変に大きいものですが、谷川さんの詩の中にこうした「微細な繊細な」ものを自分なりに探すようになりました。その時に、ふっと呼吸が聞こえてくる感じがいたします。
谷川さんの詩を生徒たちと読み深めていくのは、これからが始まりなのかもしれないと思い始めるようになりました。詩の中に微細に繊細に息づくものを国語の教師として少しでも伝えていきたいとあらためて願っています。
教室の窓に映る雲の姿に、美しい讃美歌を耳にしたような思いを抱きながら。
『国語教室』第123号より転載
プロフィール
和合亮一(わごう りょういち)
福島県立福島北高等学校教諭。第一詩集にて、中原中也賞、第四詩集にて晩翠賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitter(現「X」)で「詩の礫」を発表し話題に。詩集となり、フランスにて詩集賞受賞(日本人初)。2019年、詩集『QQQ』で萩原朔太郎賞受賞。校歌、合唱曲作詞多数。
一覧に戻る