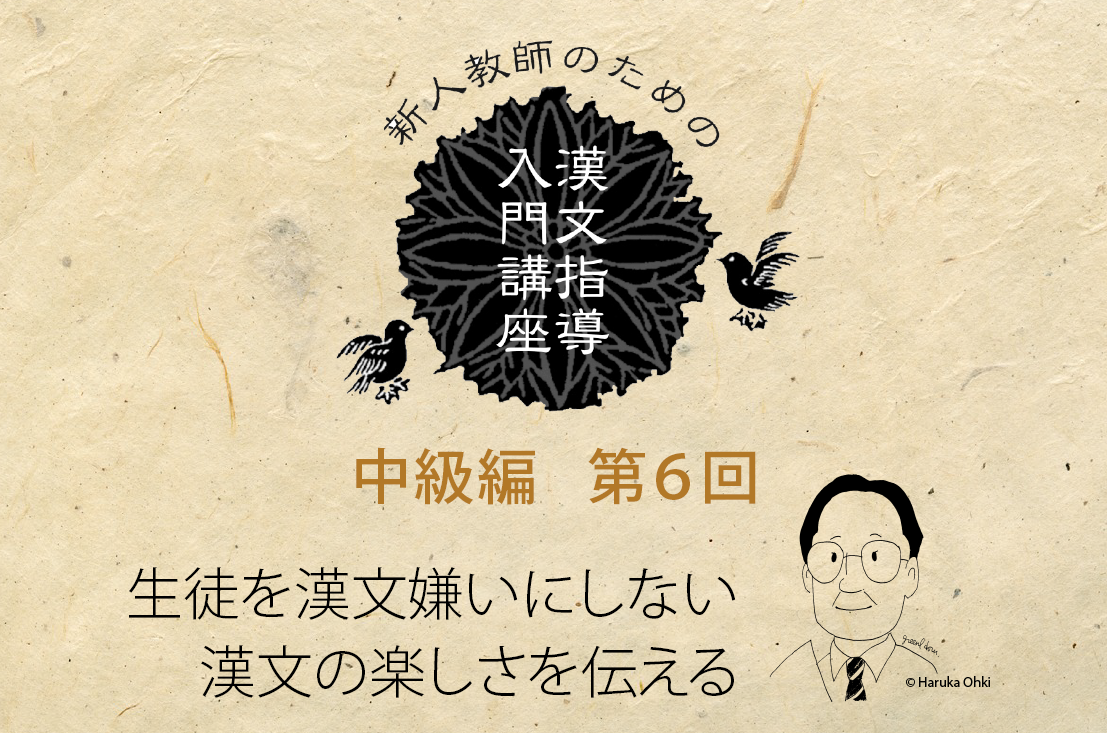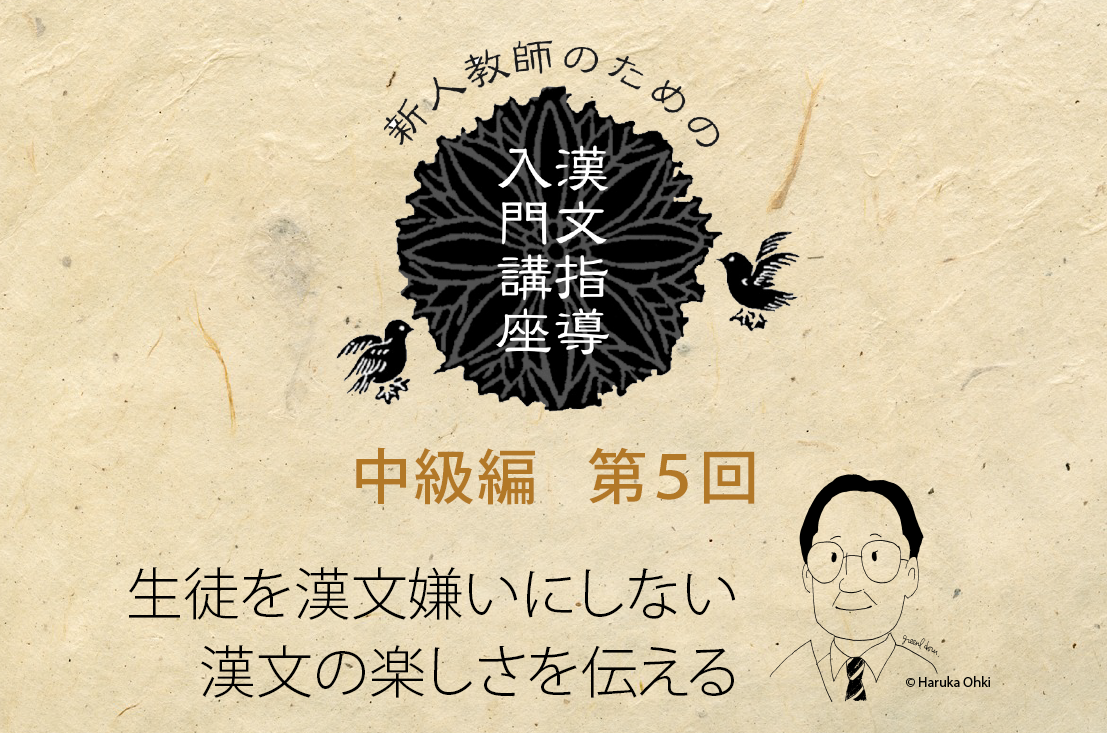新人教師のための漢文指導入門講座
中級編 第3回 句法指導の心得―四大句法① 使役―
塚田勝郎
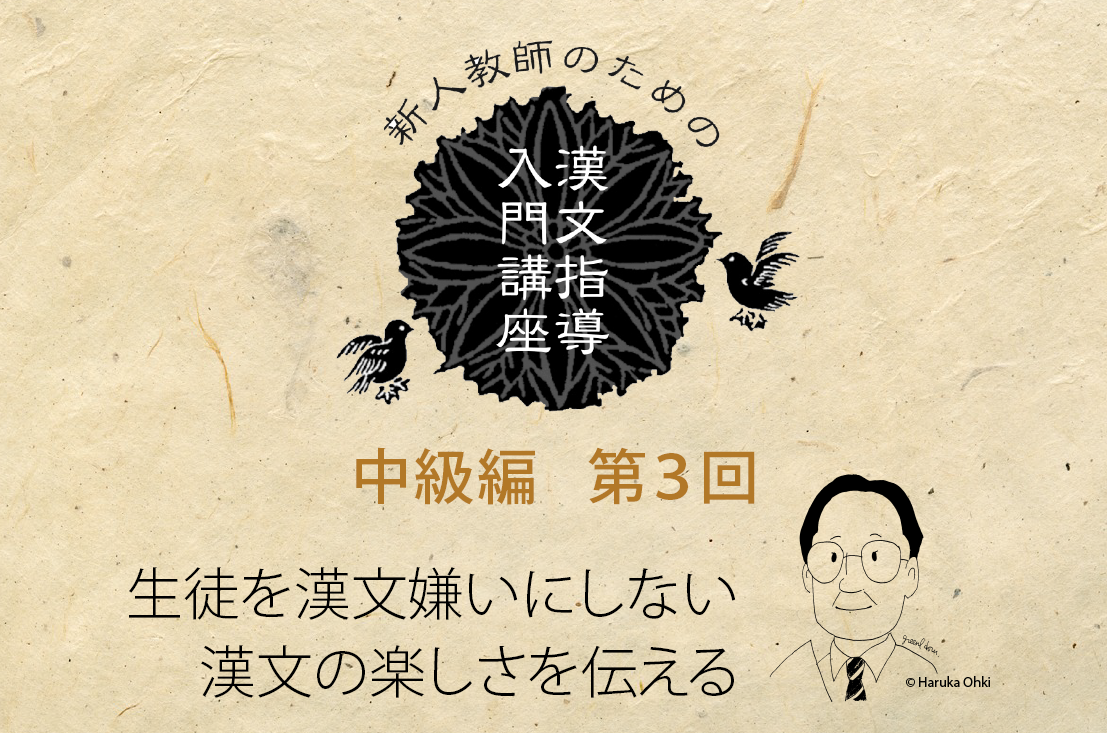
1 句法との適切な距離とは
筆者の高校時代には、二年生の文系クラスに古典文法の時間がありました。当時を振り返ってみると、退屈と我慢という言葉しか浮かんできません。古典文法のテキストを一年かけて一冊こなしたものの、筆者自身の意欲不足も手伝って、古文の力がついたという実感はありませんでした。
漢文の句法だけを扱う時間があったらどうでしょうか。時間数不足が悩みの種になっている昨今では、あまり現実的ではありませんが、筆者と同様に、つまらない時間と感じる生徒が多く出現するでしょう。
句法の重要性を否定するわけでは、まったくありません。むしろ「句法は大事」というスタンスを取りつつも、「漢文を攻略するためには、句法がすべて」とか、「まず句法を全部頭に入れる」という受験界の一部の「常識」に抵抗したいのです。
では、漢文の授業では、句法とどのように向き合えばよいのでしょうか。筆者の考えは、次の五点に集約できます。
1 句法は大事である。しかし、句法だけですべてが解決するわけではない。
2 句法を指導する際は、その句法が大事である理由を生徒に明確に説明する必要がある。
3 句法の中でとりわけ大事なのは、疑問と反語、使役と受身の四つ。この四つの形は、教材に出てくるたびに簡単に触れる。
4 句法は、必ず教材と関連させて扱う。句法集の短文の羅列を覚えさせても、効果は期待できない。
5 句法は「型」であることをしっかり認識させる。訓読では「型無し」や「型破り」は認められない。
2 句法指導の実際
前段に掲げた五項の補足説明も兼ねて、句法指導の実際的な場面を考えてみます。
漢文の読解には、様々な力が要求されます。漢字の意味、語順、文体、詩の形式、作者、時代背景など、多岐にわたる知識に加えて、前回取り上げた古典文法も、訓読には不可欠です。句法だけで解ける問題がないわけではありませんが、句法は読解のためのツールの一部に過ぎず、漢文読解は「総力戦」であることを強く意識させなければなりません。
また、句法指導は単調で無味乾燥なものになりがちです。そこで、数ある句法を最低限必要なものに絞り、生徒に安心感を与えることにします。筆者は最重要句法を、疑問と反語、使役と受身の四つに絞り込み、それぞれ組み合わせて指導しています。その理由を簡潔に整理してみましょう。
【疑問と反語】 特殊な例を除き、疑問と反語は見かけでは区別がつかない。区別は文脈からで、疑問は相手からの返答を期待するが、反語はそうではない。反語は、「…でない」「…である」という発言者の主張や意志を強く発信するためのレトリックであるから、解釈の上でも重要な部分になる。
【使役と受身】 この二者は、「型」を知らないと訓読できない。いずれも古文で学習した助動詞を当てて訓読する「型」である。使役の基本型「…をして…(せ)しむ」の「…をして」を、勝手に「…を」とか「…に」に変えてしまう生徒が多くいるが、「型破り」は困る。受身は、使役とちがって「型」が何種類もある点が生徒をとまどわせる原因になっている。
これ以外の句法、たとえば詠嘆や限定の形は、あえて時間をかけて指導する必要性は感じられません。「ああ」で始まったり、「かな」で結んだりすれば、詠嘆の形であることは一目瞭然です。「ただ…(のみ)」と来れば、限定の形と命名するまでもないでしょう。ただし、「ああ」という感嘆詞や、「ただ」と読む限定の助字にはどのようなものがあるかは、必ず漢和辞典の音訓索引などを使って調べさせておきたいものです。
指導する側が、句法との距離を適切に保つことが求められるのです。
3 使役の形の指導例
今回は、筆者が行っている使役の形の指導例をご紹介します。
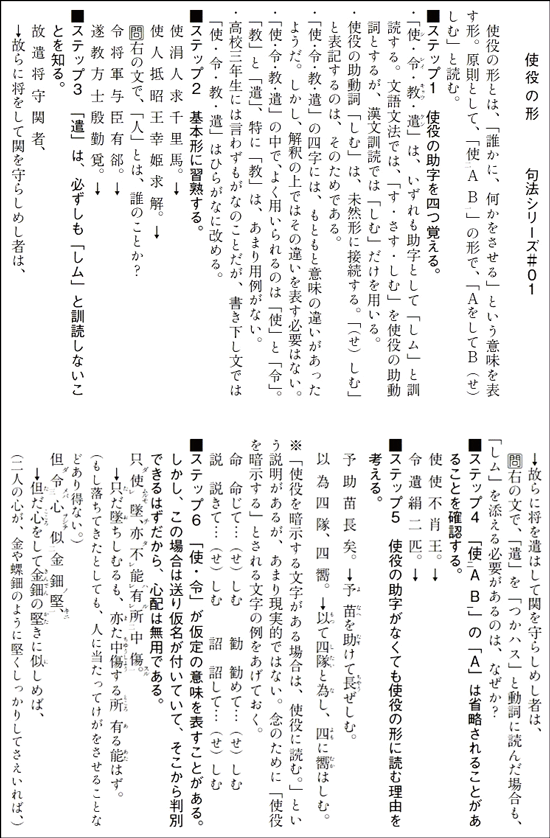
筆者の勤務校では、古典文法のテキストと便覧(図説)は採用していますが、漢文専用の副教材は生徒に持たせていません。そのため、句法の指導には、自作のプリントを用いています。右に掲げたのは、高校三年生が使うものです。使役の形は教材に出てくるたびに取り上げて説明していますから、これは「使役の形の総まとめ」ともいえましょう。指導時間は、一時間を想定しています。
くり返しますが、このプリントは、三年生が一時間で使役の形の総まとめができるように工夫したものです。一・二年生で、使役の形が出てくるたびに簡単に触れていることを前提としていますので、このプリントだけで使役の形をマスターさせることには、無理があります。
授業は、プリントの項目に従って進めていきます。〔ステップ2〕以降の白文の部分は、筆者が読みを提示し、生徒が返り点と送り仮名を書き取ります。矢印の下が空欄になっている箇所は、生徒が各自で書き下し文を記入します。
〔ステップ3〕の発問はかなり高度ですから、段階を踏んで考えさせましょう。まず「『遣』と『守』の主語は何か。」と問いかけます。「遣」は沛公、「守」は「将」が主語であると確認した上で、「一文に主語の異なる動詞が二つある場合、訓読する際には、どちらかの動詞を使役か受身に読む必要が生じる。この文は『沛公』を主語としているため、『守』を『守らしむ』と読むことになる。『遣』を使役の助字に読んだ場合も、動詞として扱った場合も、事情は変わらない。」と説明すると理解が得られるでしょう。
最も実戦に役立つのは、〔ステップ4〕でしょう。生徒の多くは「AをしてB(せ)しむ」と丸暗記していて、使役の対象であるAが省略されるケースがあることに気づかないのです。「不肖の王に使ひせしむ。」も「絹二匹を遺(おく)らしむ。」も、「人をして」を省略した形であることを知ると、〔ステップ2〕で「『人』とは誰のことか。」と発問した意図を容易に理解できるはずです。「人をして」の「人」は、あえてその名を書き記すほどではない家臣や下僕をさしています。したがって、使役の対象の「人」を「家臣」「下僕」などと訳すことも可能ですし、「人」を無視して現代語訳することも許されるでしょう。
句法の指導にあたっては、効果的で無理のない方法を追究したいものです。
*次回は、受身の形を扱います。
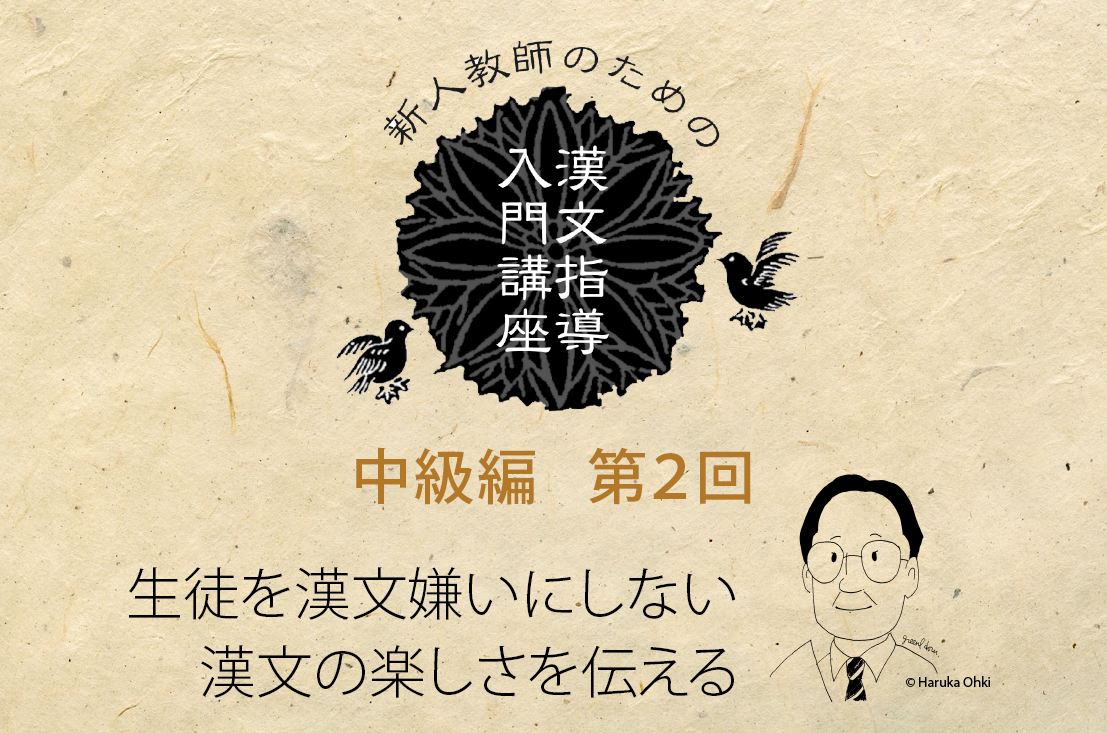
詳しくはこちら
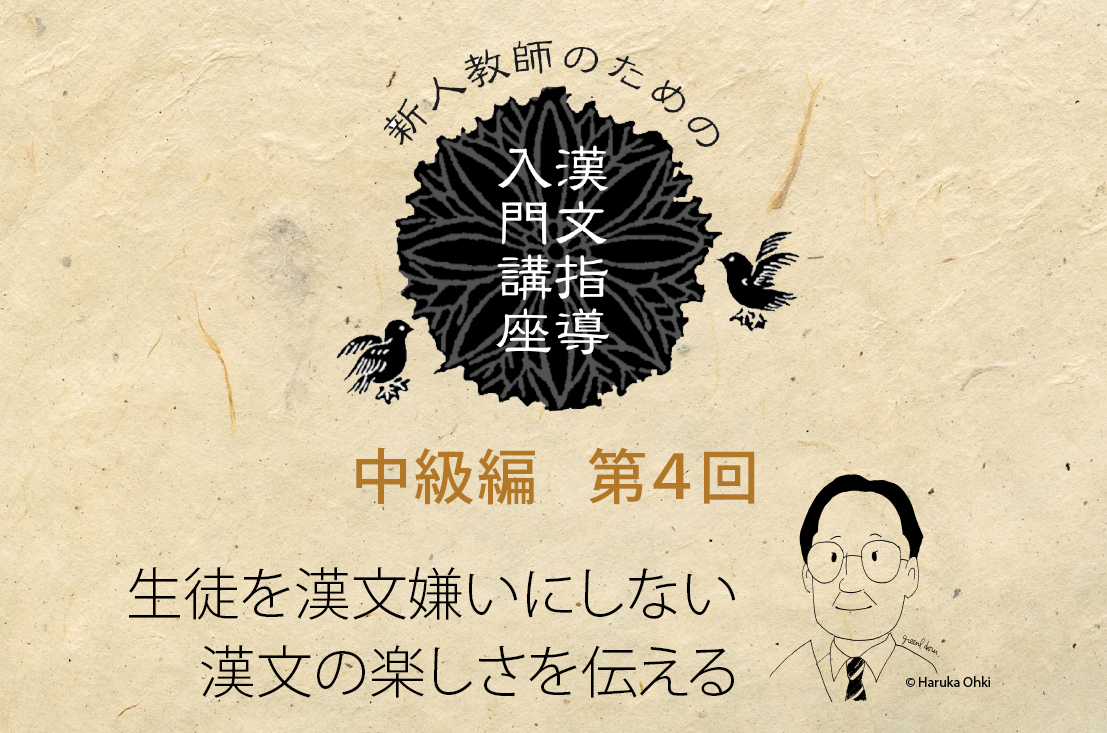
詳しくはこちら
一覧に戻る