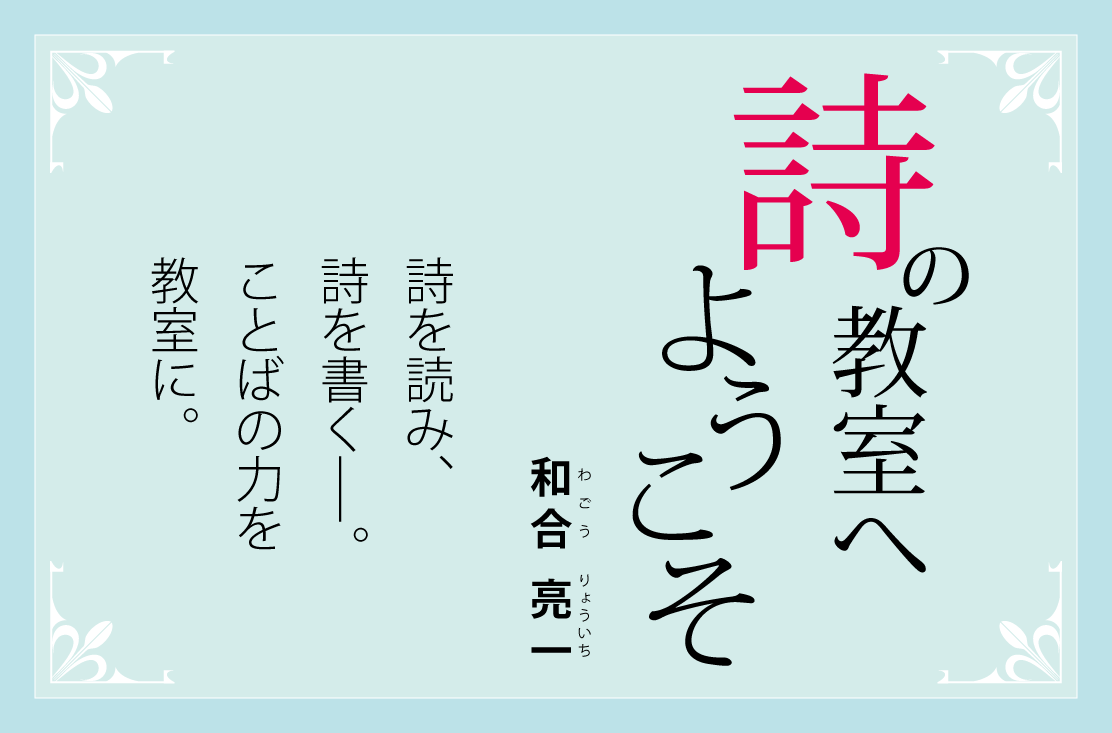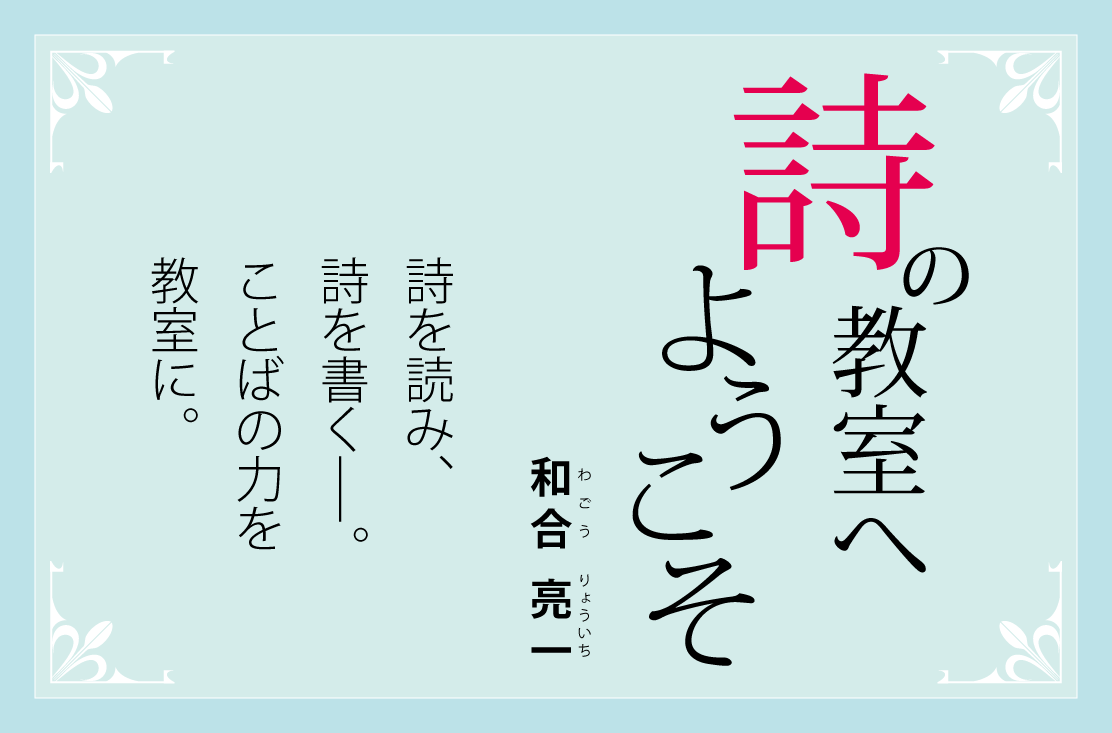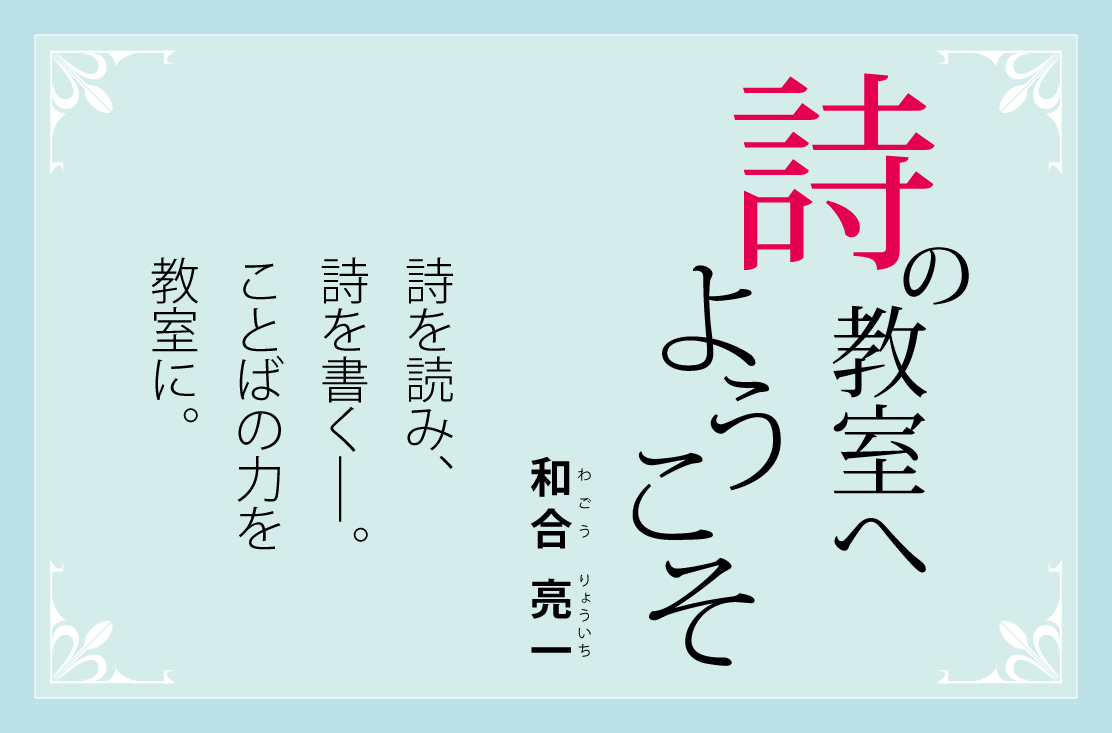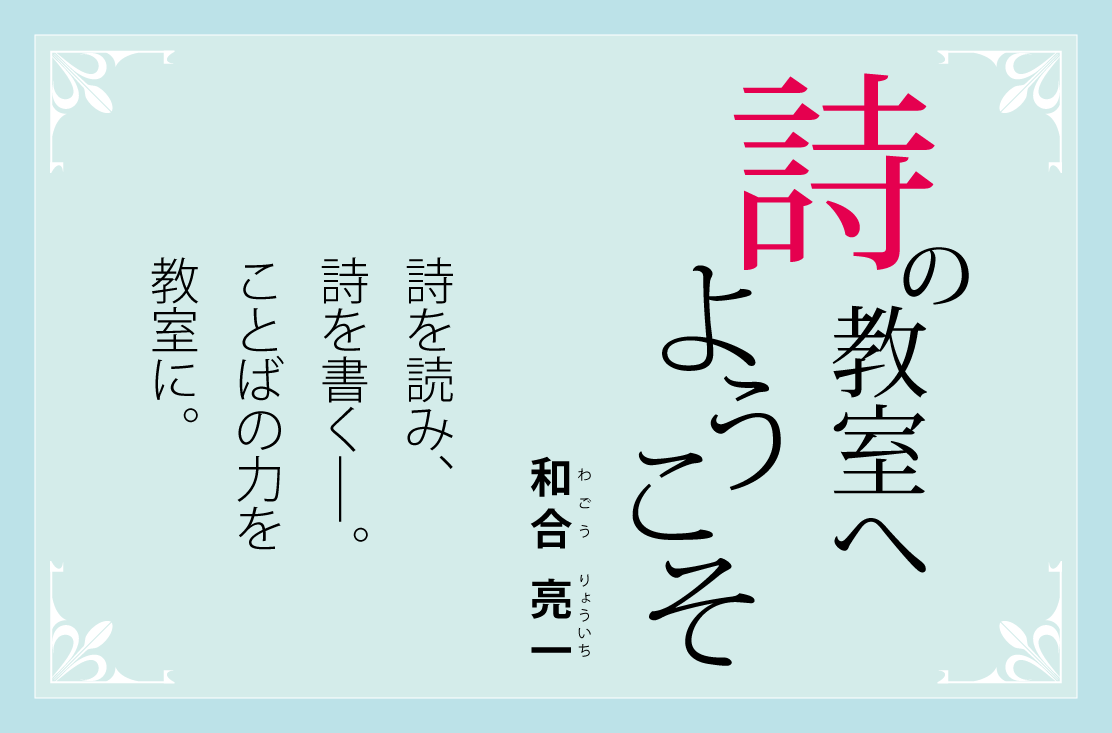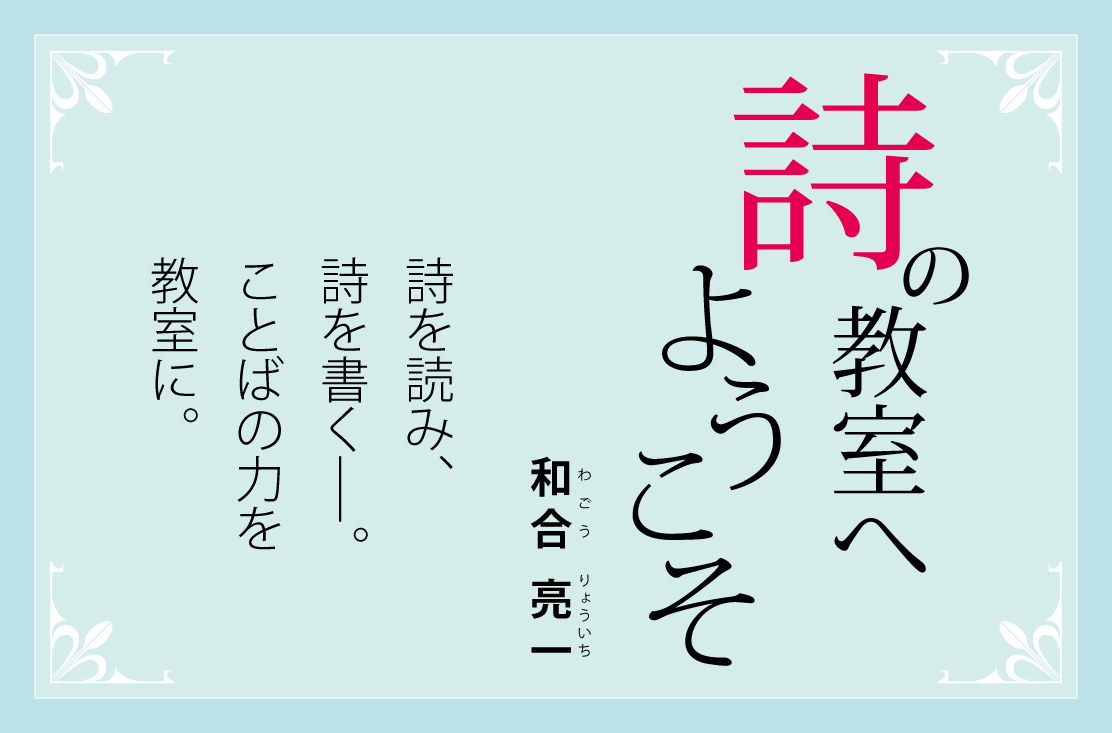詩の教室へようこそ
第5回 呼吸をするように
〈対談〉若松英輔×和合亮一
- 2023.03.09
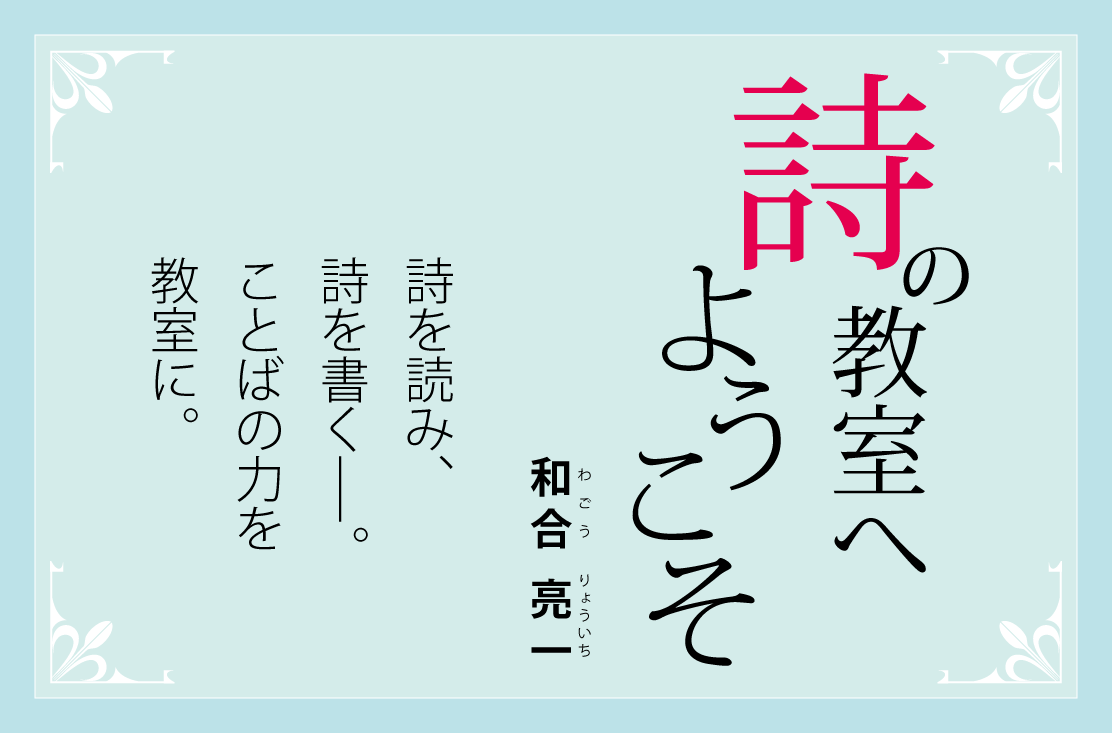
詩を読むことと書くこと。この二つの往還をテーマとしてきた、詩人和合亮一先生の本連載。今回はゲストとして若松英輔先生をお迎えし、「読む」と「書く」との向き合い方について語り合っていただきました。
◆正解がないことを考え続ける
和合:4月から使われている教科書『言語文化』(大修館書店)に若松さんの「文字の深秘」が掲載されています。率直なところ、書き手としてどのようにお考えですか。
若松:現在、自分の書いた文章が4〜5冊の国語の教科書に採録されているほか、大学の入試問題などにも採用されています。実は私は、ともかく国語が苦手で、授業は嫌いではなかったのですが、点数がすごく悪かったんです。自分が書いた文章で、入試の合否が決まると思うと、なんだか気分が重たいですね(笑)。入試問題などを見ると、書き手として「正解なんてそう簡単に言えないのではないか」と感じることや、「答えがない」「正解が複数ある」と思うことがあります。そのような、選択肢の中から正解と思われるものを選ぶという思考法は、若者にとって本当によいことなのかを危惧しています。正解がないものを考え続けることは、とても大事なことです。正解を人よりも早く言い当てるのは、社会生活でも有用ではありません。あまり「こういうふうに読みましょう」と言わずに、固定しないで読んでいただけると、私としては幸いなんです。
和合:私は現在、教師として高校生を教えています。教科書を一つの仲立ちとして生徒と向き合うことで、常に新しい発見があります。文章は、答えがないものや言葉にできないものに向かって書かれるもの。一つに明確な答えが導き出せないものほど、生徒や教師の心に残る気がしています。若松さんの文章にはそれがあると感じます。
若松:文章は書かれたときではなく、読まれたときに完成します。若い人たちに読まれたときに完成されていく言葉が、自分の中に生まれてきていたことはありがたいことですね。国語は苦手でしたが、本を読むことは嫌いではなかった。ちょっと変わった子どもだったんです。芥川龍之介や夏目漱石、小林秀雄の文章を自分なりに読んで、1冊の本や作家との出会いを楽しんでいました。「読む」とは、その人しか切り拓くことができない地平を切り拓いてゆくことです。勉強は苦手だけど、「読む」ことを楽しんで、学ぶことを愛している。ただ答えがうまく見つけられない。そんな子どもたちを大切にしてほしいと願っています。
和合:とても大事なことだと感じます。授業は生徒のリアクションによって作られるので、生徒の目の動きや溜息など一つ一つが教師にとっては大切です。大学生のとき、大学の教授に「『力動する授業』を目指してください」と言われました。決して、一つの方向に向かわなくてもよい。でも、先生と生徒の両方が歯車となって動いていることが大切だ、と。
若松:そうですね。「わかる」「わからない」と関心の有無は別です。わからないことは関心や探究心につながります。でも、わかっていることは探究しません。子どもの探究心が飛躍的に伸びることがあります。その種子は学校で植えられますが、必ずしも、学校の3年間で開花するとは限らない。そういう若者たちを、見捨てずに見守ってほしいと思います。桃栗三年柿八年。柿の木は、8年後に柿にしかつけられない実をつけます。「勉強」と「学び」は違う。「勉強」は目的と期限がありますが、「学び」は目的が定かではなく、期限もありません。学校は、勉強の場でありますが、「学び舎」でもあってほしい。その方向で若者たちに開かれるとよいですね。
◆文学経験はどのように開花するか
和合:若松さんが創作活動をしたいと思ったのはいつ頃ですか。
若松:けっこう早くて、本を読み始めてすぐの頃、17歳くらいのとき、「物書きになりたい」と思いました。その時期に、日本ペンクラブの大会に参加し、作家の加賀乙彦さんと出会い、1時間ほどお話をさせていただく機会を得ました。加賀さんは「書きたいけれど、どうしたらよいかわからない」という私の思いを受け止め、深く話をしてくださいました。本を読んだり書いたりするのはもちろん大切ですが、本物の書き手に生で会うことも大切です。
和合:私も成人するまでは、自分が詩を創作するなんて考えたこともありませんでした。高校時代も、自分から何かをするよりもみんなとはしゃいでいるほうが自分らしいと思っていましたし、考えることも、人にどうウケるかばかり……。20歳を過ぎて萩原朔太郎の『月に吠える』と『青猫』に出会ったとき、「生まれたときからこれを求めていた」と感じました。読むことと書くことの衝動は同じです。それから詩を書くようになり、自分がどんどん変わっていきました。ちょうどその頃、井上光晴さんの文学講座を聞きに行く機会がありました。若松さんと同じで、それが、本物の作家との生の出会いです。その講座には、真剣に文学と向き合う人たちがいて、そこでの濃密な時間はかけがえのないものでした。
若松:文学と真剣に向き合う、言葉を深く体験するという経験が、表現者という形ではなく、別様に開花することがあります。創作というと、絵を書く、音楽を作る、文章を書く……ということを思い浮かべがちですが、仕事を立ち上げることなども、とてもクリエイティブです。国語の授業で学んだことも、まったく違う形で開花することのほうが多いのではないでしょうか。
◆真似をして、真似を脱する
和合:今年の4月から、新しい国語の授業が始まりました。新しい教科書には創作が取り入れられていますが、現場ではなかなか実践できていないと個人的に感じます。
若松:創作によって、自分の詩や作品を作ることができればとてもよいですが、まずは「引用」から初めるのはどうでしょうか。たとえば、1冊の本を読んで、大事だと思うところを10箇所引用するとします。すると、生徒によって引用する箇所は見事に違います。短く引用することはとても難しい。引用によって浮かび上がった世界はすごく創造的なものです。次に、引用した文章に表題をつけるということをしてもらいます。引用した文章を一つの絵画のように見立てて、それにタイトルをつける。このタイトルは、形を変えた一行詩で、詩の精神=ポエジーが表れます。引用が的確にできるようになると、必ず文章が書けるようになるんです。
和合:面白いですね。私も創作の敷居を低く考えていけたらよいといつも感じています。
若松:引用をするのは、1冊の本だけでなく、教科書の教材でもかまいません。引用することで、「読む」ことがとても創造的だということに気づきます。そして、「読む」という創造性を鍛えることが「書く」という創造性につながっていきます。
和合:知らず知らずのうちに、「書くこと」を教師が特別なものとしてしまっているのかもしれません。「鍛錬を積んだ人しかよいものは書けない」「内容が深くなければならない」というような思いに無意識のうちに縛られているのかも。ゼロから始めることに力点を置き過ぎず、まずは真似てみる。子どものもつ真似をする力、そこから学び取る力を生かしてもよいのではないでしょうか。
若松:そうですね。本当に学び取ることが上手になると、真似するのをやめるようになります。本当に学び取ることができると、学び取ったものと自分の中にあるものが違うことに気づきます。人は、あこがれると真似をしてしまうものですが、「やっぱり真似はできない」ということに気づくところから、本当の面白さが始まります。
和合:室生犀星は詩作にまつわる本の中で「詩というものは先ず真似をしなければ伸びない。そしてその後に、きれいに真似の屑を棄てなければならない」と言っています。まず真似をして、本当に自分らしいものができたら、屑を棄てる。私はこの言葉を知って、気が楽になったことがあります。
若松:屑を棄てるまでの人間は、屑こそが大事なものだと思っています。「あなたが大事だと思っているものは、あなたが本当に大事にしなければいけないものに比べたら大事ではない」ということを、教師が伝えてあげられるとよいですね。
◆独りになることの「学び」
和合:現在は、インターネットを通して、凄まじい速さで情報を得ることができます。国語の教科書でも、QRコードをかざして動画を見て、すぐに情報を得ることができますね。そのような中で、物を書いたり、調べたりすることの本当の難しさ、それを乗り越えた後の静けさや時間の重みを感じることが、どこかできなくなっているのではないでしょうか。
若松:本当の意味で「読むこと」と「書くこと」を行うとき、私たちは必然的に独りになることを強いられます。一方、「話すこと」と「聞くこと」は他者がいないと成り立ちません。この両方が本当に豊かに行われるとき、「勉強」から「学び」へと移り変わって、意味あるものになると思います。授業は50分ですが、数日後、1週間後の次の授業までの間、会っていない時間に起きる学びが大切です。独りになって読んだり書いたりする。そこで見えるものには、言葉にならないものが多くあります。言葉にならない大切なことを深く認識しているとき、沈黙せざるを得ないことは珍しいことではありません。そのことを、「黙っていてもわかっているんだ」と生徒同士が尊重し合えるといいですね。
◆「書くこと」は手放すこと
和合:若松さんは、「読む」「書く」ということをテーマに数々のご執筆をされていますね。
若松:「書く」ということについて、私は二つのことを大切にしています。一つ目は、「書く」ということは、手放すことだということ。一見、書くことは、自分の中に経験を定着させることのように感じますが、高村光太郎は「自分は彫刻家だ。詩を作るということは、自分の彫刻を純化するために、自分の中にあるものを手放して彫刻を作る準備をすることだ」と言っています。書くことは、一人の人間として何かをつかむために、今までにあるものを手放すことなんです。
二つ目は、自分のために書くということです。私たちは、言葉にならないものに向かって、書くことと向き合っています。自分の知らない誰かが、自分の書いたものに何かを見つけてくれたら……という願いはありますが、それは淡い期待であって、結局、自分の人生を照らすために書いている。言い換えれば、書くことによって人は自分の人生を照らしうるのです。
和合:私は、詩がつまりは日記だと感じています。読み返すとそのときの自分が鏡のように見えてくる。自分の人生が比喩化され、生きてきた時間がその内側へと深く溶け込んでいる感じがある。それが、いま・ここの瞬間を照らし出してくれているのかもしれませんね。暮らしの日々に自分の姿を鏡で眺めることと同じようにとらえているから、詩を書くのは日常的で、とても当たり前のものになる。そのような暮らし方を生徒たちに伝えていきたいです。
◆詩の誕生、詩集の誕生
和合:私は詩を書きながら教師として教壇に立つ中で、どうやって詩を教えたらよいか聞かれることがあります。若松さんも詩を書かれていますが、どのようにお考えでしょうか。
若松:詩人が詩を書くのではなく、真剣に詩を書いた人が詩人であると考えています。その意味で、詩は万人に開かれています。そして、万人の中に眠れる一冊の詩集がある。一人一人の中に言葉の姿をしていないエネルギーのようなものがあって、詩を書くことは、それを掘り起こすことにすぎません。どう取り出すかによって言葉が結実する、いかようにもなりうる詩集です。だからこそ、詩が書けないなんてありえません。あるとき、詩人が誕生する、眠れる詩人が掘り起こされる瞬間があるんです。同じように、詩集が生れる瞬間もあります。ただ、詩人の誕生を告げ知らせる作品と、詩集の誕生を告げ知らせる作品は別のものです。多く作品を書く詩人でも、詩集がまとまらないことはあります。でも、詩集の誕生を告げ知らせる作品が生まれたら、とにかくその一冊の詩集を書くことにエネルギーを使ってほしい。そのとき、全部の詩を自分で書けないのであれば、引用をするのもよいでしょう。何を引用するかに、その人自身が表れます。詩人と詩集の誕生が起きると、詩はその人にとって永遠のものになります。
和合:すごくよくわかるお話です。生徒たちの日常生活、何気なく書いたもの、話していること、感じていることの中に、詩はすでに宿っている。それを、気づいていないだけなんだと思います。そして、私たちはお互いに「それは詩だよ」「詩集になるんだよ」と照らし合うことができるということが重要なんですね。
◆呼吸のように「読む」「書く」
若松:「読む」と「書く」は、自分に出会うための最も確実な道です。もしも自分がわからなくなったり、信じられなくなったりしたら、「読む」か「書く」のどちらかを真剣にやってみることをおすすめします。「読む」と「書く」は呼吸のような関係なので、どちらかを真剣に行えば、自ずともう一方も行うようになる。だから、まずはどちらかでよい。私たちは、自分に本当に必要なものを、誰かに与えられるのではなくて、自分で生み出すことができます。若い人たちには、そのことを知っておいてほしいですし、先生方には、それを支えてほしいですね。
和合:「読む」が「吸う」で「書く」が「吐く」だとすると、その呼吸がとても大事ということですね。高校教師をしながら創作活動を行うことについて、よく「大変ですね」と言われます。でも、私にとって、「読む」と「書く」は呼吸と同じ。先ほど姿見の鏡を引き合いにして述べたように、暮らしの中で見ずにはいられないもの、日常的で身近なもの、そしてとても敷居の低いものだということですね。そのことを、教育の現場でも話をするべきですし、創作者同士でも言葉を交わしていきたいと思います。
今日は長い時間ありがとうございました。
『国語教室』第118号より転載
プロフィール
若松英輔(わかまつ えいすけ)
批評家・随筆家。文芸評論から哲学、宗教、詩作に至るまで幅広い分野で著作活動を続けている。主な著書に『イエス伝』『小林秀雄 美しい花』、詩集『見えない涙』『愛について』など。
和合亮一(わごう りょういち)
福島県立福島北高等学校教諭。中原中也賞、晩翠賞受賞、萩原朔太郎賞受賞。2011年の東日本大震災で被災した際、twitterで「詩の礫」を発表し話題に。校歌、合唱曲作詞多数。
一覧に戻る