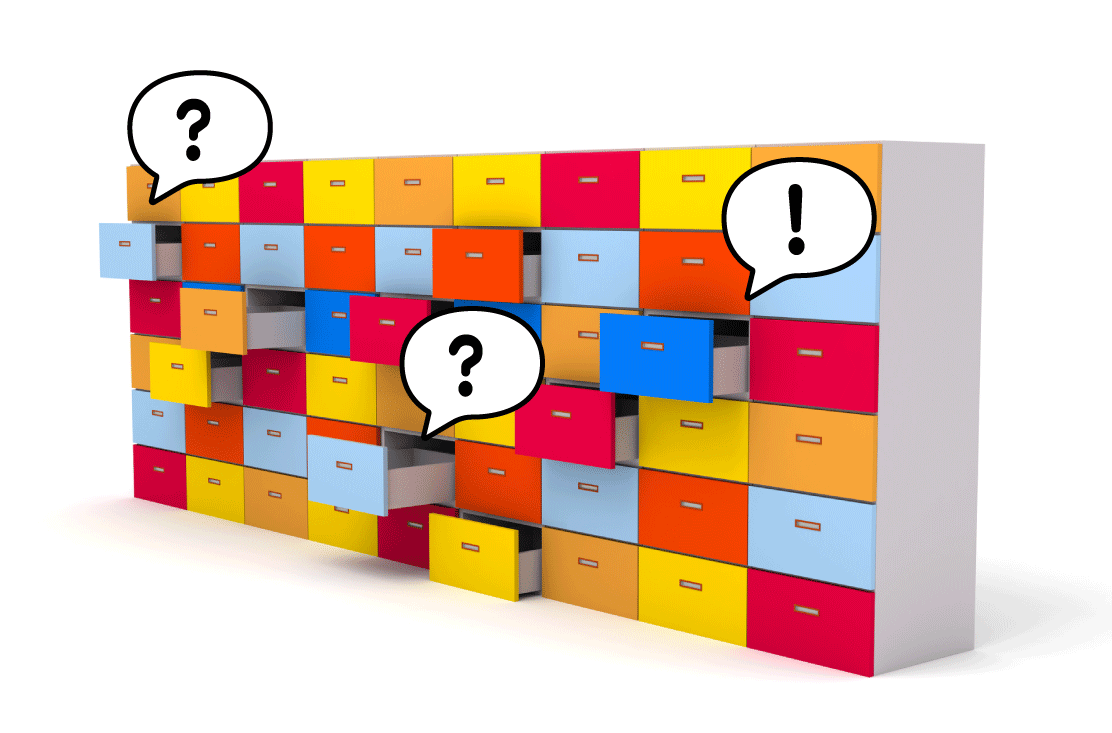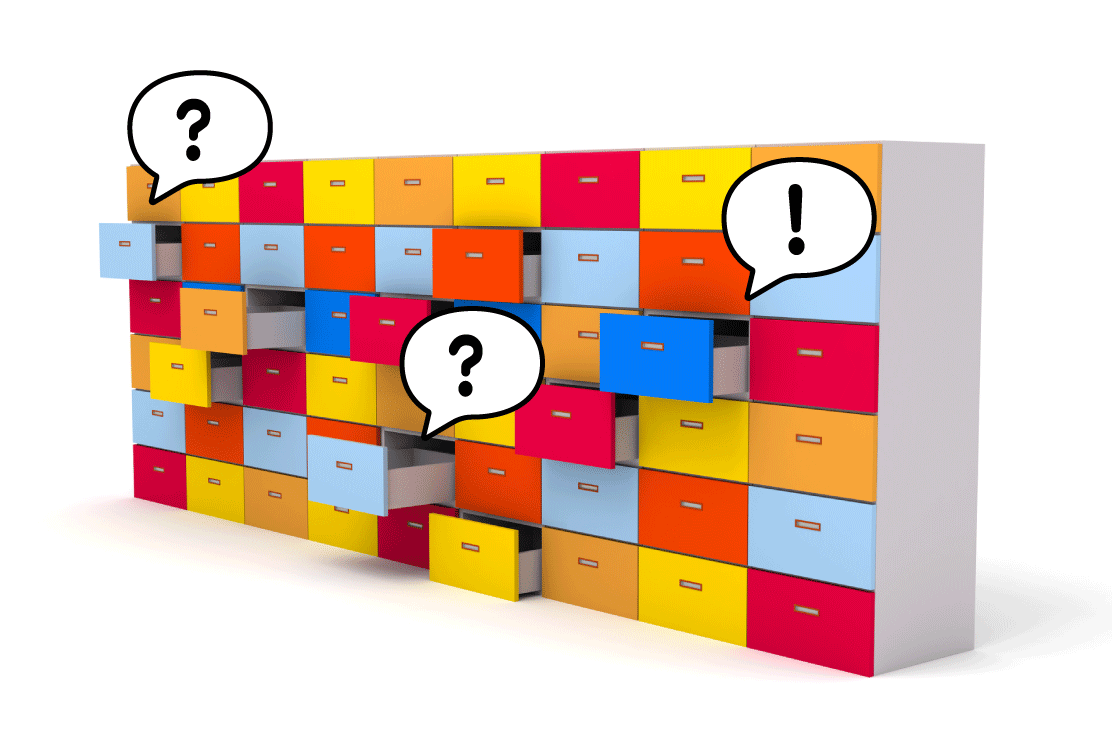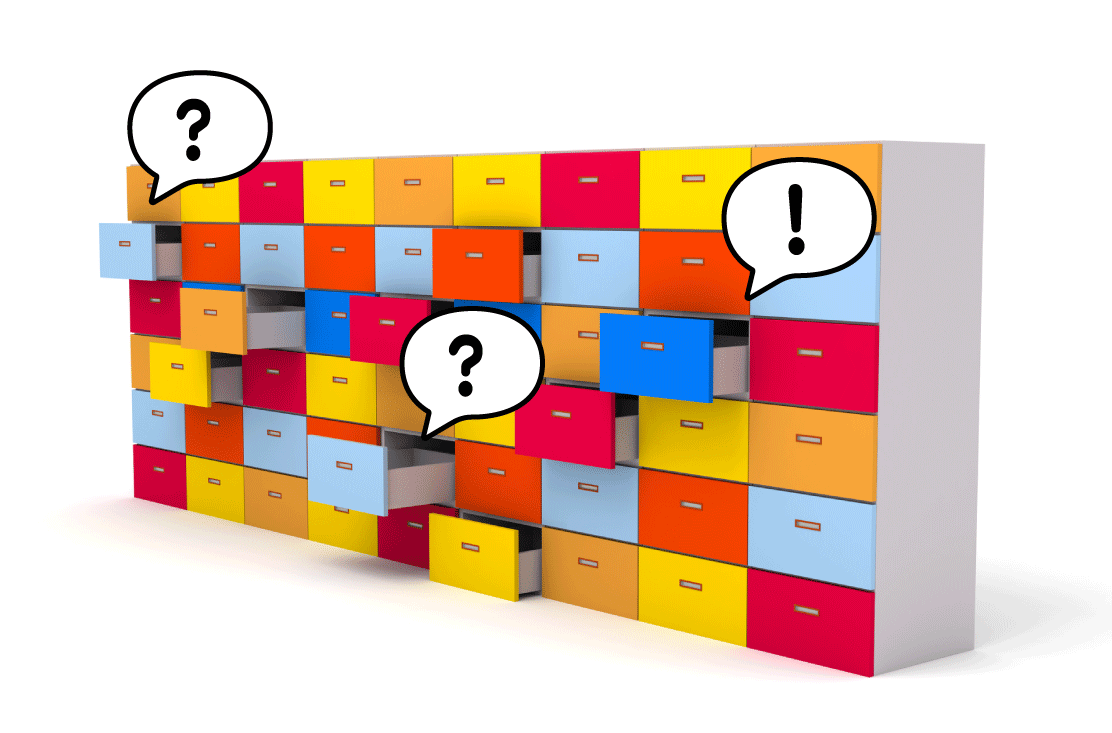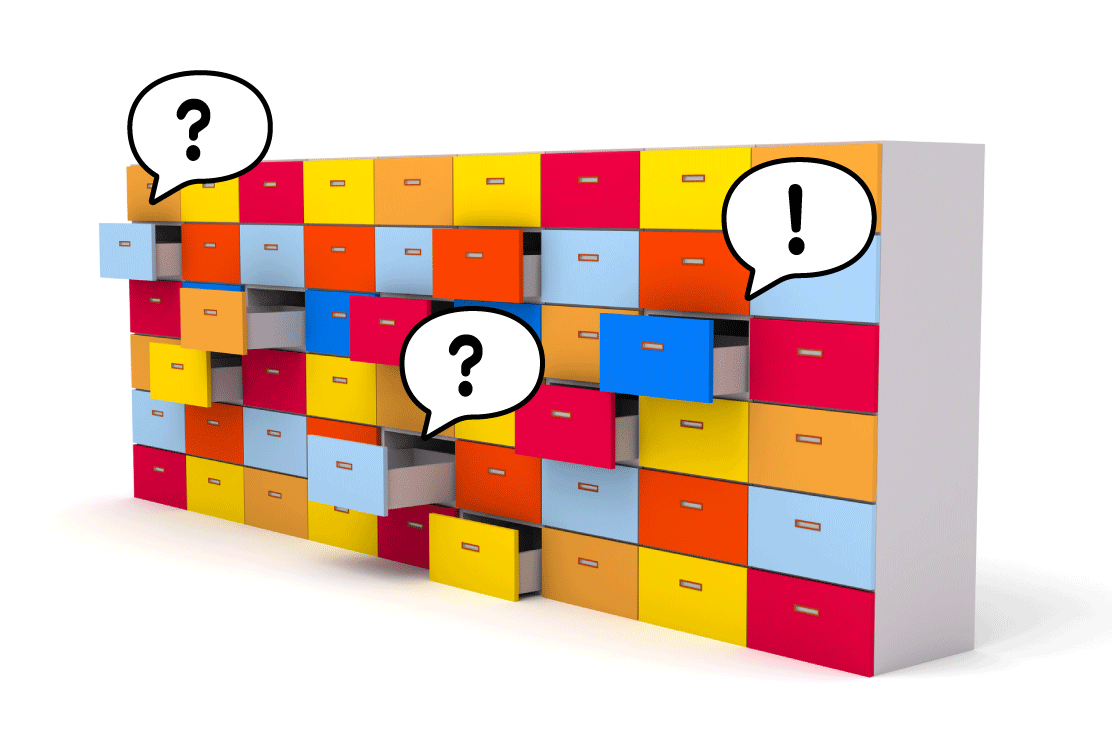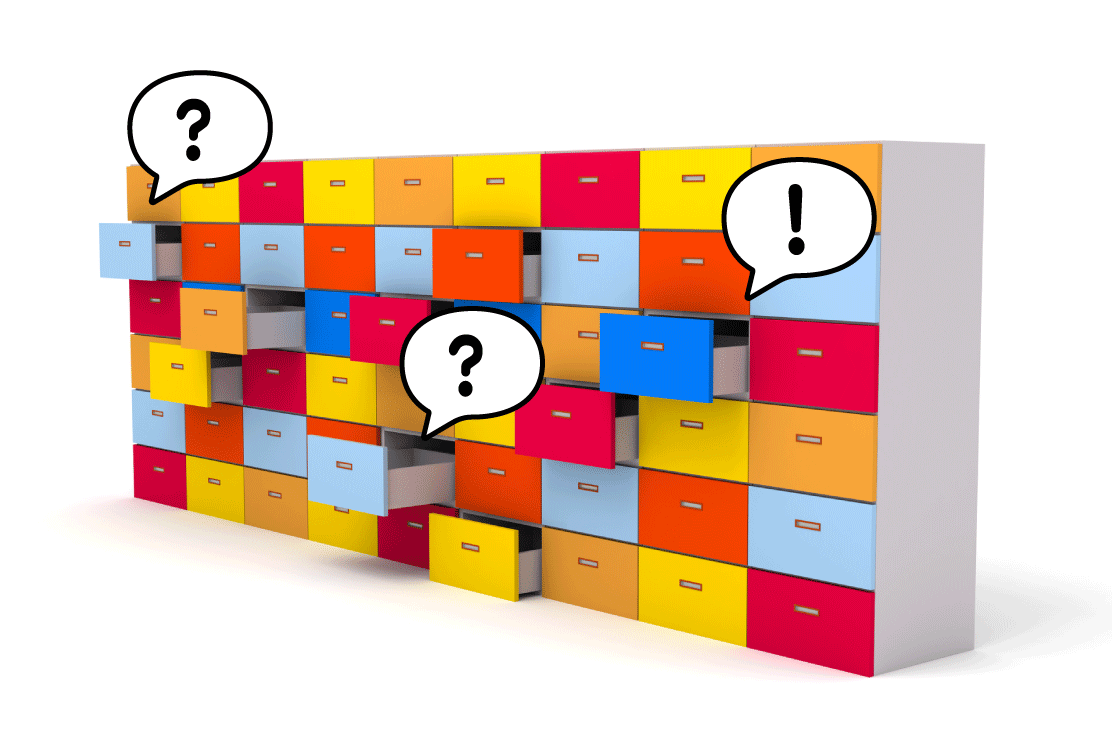コトバのひきだし ──ふさわしい日本語の選び方
第8回 あふれる「人流」、活用する「人財」
関根健一
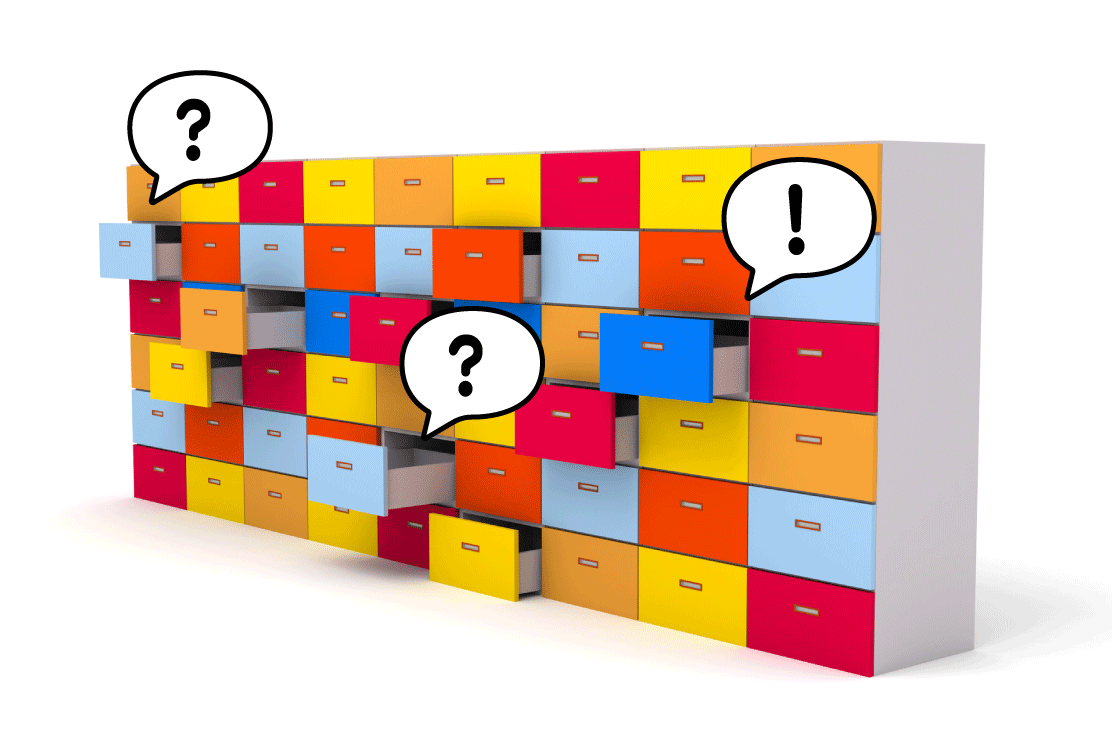
「いかに人流を抑えるか」「人流データを解析する」──新型コロナウイルス感染症防止に関して「人流」という言葉をよく見聞きするようになりました。最初「ジンリュウ」と耳にして、一瞬何のことか理解できず、「人流」の表記を見て意味は推測できたものの、違和感は残りました。
*****
政治家が会見などで使うのを引用する形で、新聞や放送でも頻繁に使われるようになっています。行政や観光の分野ではこれまでも用いられていたようです。物の流れが「物流」なら、人の流れは「人流」となるのでしょう。しかし、国民に広く注意を促すべき事柄について、行政用語・専門用語をそのまま発信するのでは、伝えるべきものが伝わらないおそれがあります。
「人出」と言った方が分かりやすい場合もあるはずです。ただ、特定の場所に集まっている人の数を指す「人出」に対し、「人流」はどのくらいの人が移動していくかに注目した言葉なので、単純に置き換えると正確さを欠くこともあるかもしれません。ニュースでは、「人の流れ」「人の動き」と言い換える工夫もしています。とはいえ、「~抑制」「~解析」「~動向」などに続けるには、漢語の「人流」がぴったりはまります。便利に使われているゆえんでしょう。
*****
安易に使ってほしくないという思いは残りますが、一方で、異常な事態であることを喚起させるには、むしろなじみがなく、抵抗を感じるくらいの表現の方がふさわしいともいえます。「いったい何のことだろう?」と立ち止まらせ、そこに注意を向けさせる効果があるからです。
平常時であれば増えることが発展や隆盛につながる「人流」ですが、パンデミックの記憶を呼び起こす言葉として残っていくのかもしれません。
また、「人流」という言い方に、「人」を「物」と同列に扱う感じがする、と反発を覚える人もいるようです。「物流」のアナロジーと捉えると、そうした感覚にもうなずけるところがあります。
*****
「人材」という言葉についても、人間を「材料」や「材木」のように扱っているのではという見方があるようです。しかしこれは誤解で、「適材適所」「逸材」と使われるように、「材」は「資質・才能」の意です。役に立つ人を指すのが「人材」で、「木材」に見立てているわけではありません。
それでも気になるのでしょうか、従業員募集や会社経営の理念を述べた文章で、「材」の字を「財」に換えた「人財」の表記を用いているのをしばしば目にします。かけがえのない「財産」であると強調したいのでしょう。しかし、人間的・精神的価値を「財産」と表す使い方もあるとはいえ、金銭や経済的価値をまず連想する場合が多いのではないでしょうか。そうした直接的な利益を生み出さなければ「人財」ではない、と誤解されては本末転倒です。また、「材」と「財」は本来は通じる意があり、あえて入れ替える必要はないともいえます。思い込みや早合点で、長年使われてきた表記をいじることには慎重でありたいものです。
*****
ところで、少ない人材をやり繰りするというとき、「人繰りが難しい」「人繰りがつかない」といった表現をしているのを見かけます。金のやり繰りを「金繰り」と略するなら、人のやり繰りは「人繰り」といえそうですが、こちらは辞書には見当たりません。
調べてみると、世界記憶遺産に登録された炭鉱画家の山本作兵衛(やまもとさくべえ)が酔うと歌うというゴットン節に「嫌な人繰り邪険の勘場(かんば)」とありました。人を人とも思わない封建的な人事管理に由来する用語なのかもしれず、これこそ人を物扱いした言い方ではないでしょうか。
『国語教室』第116号(2021年10月)より
著者プロフィール

関根健一 (せきね けんいち)
日本新聞協会用語専門委員。元読売新聞東京本社編集委員。大東文化大学非常勤講師。著書に『なぜなに日本語』『なぜなに日本語 もっと』(三省堂)、『ちびまる子ちゃんの敬語教室』(集英社)、『文章がフツーにうまくなる とっておきのことば術』『品格語辞典』(大修館書店)など。『明鏡国語辞典 第三版』編集・執筆協力者。
一覧に戻る