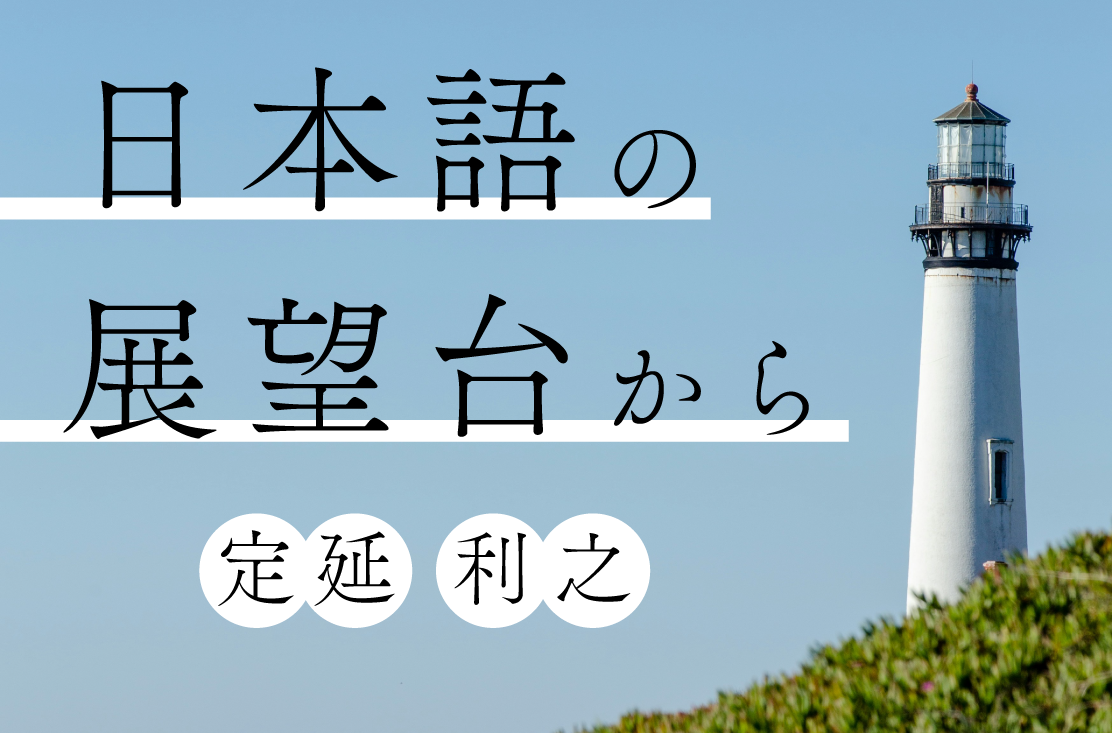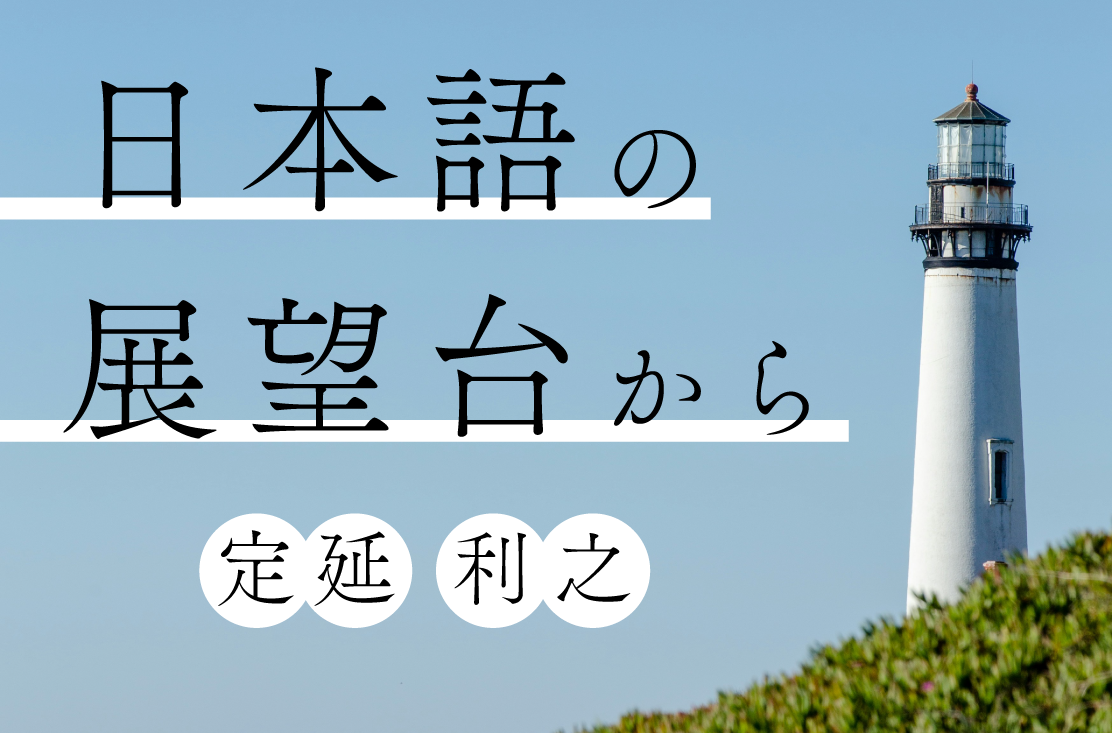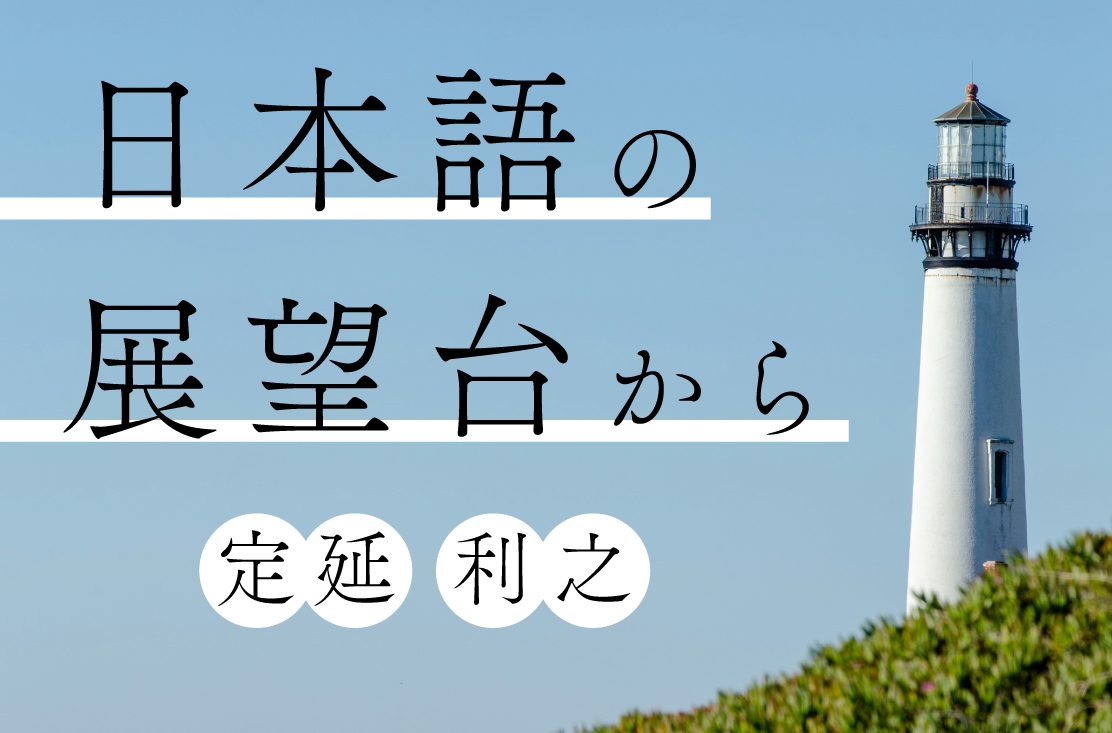日本語の展望台から
第8回 煙を立たせて火を起こす
定延利之
- 2025.06.27
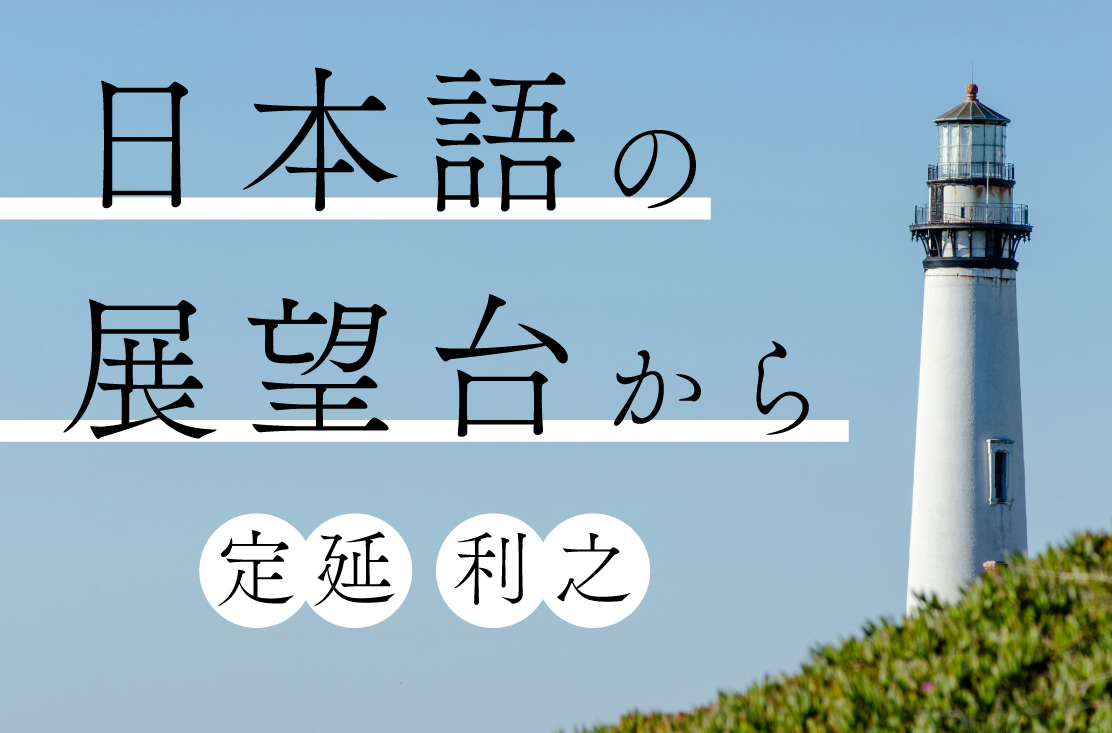
1.オノマトペとは?
「ワンワン」「ニャーニャー」「よちよち」「はらはら」「どしん」「ばたん」「ポッキリ」「シーン」といったことばは広く,「オノマトペ」(mimetics, ideophone)と呼ばれる。
いま挙げた例からも感じられるように,オノマトペの意味は,多分にイメージ的で,感覚モードの違いに敏感で,態度や感情を含むと考えられている。また,その意味を表すオノマトペの音韻は,「この音韻なら,どこの誰でも,この意味を思い浮かべる」というのはさすがに言い過ぎとしても,かなり必然的な形で意味と結びついている。そして,このことは,ソシュール以来の伝統的な言語観(音韻と意味は当該社会の歴史的経緯で結びついているだけで,それ以上の理由などない)に対する反例としてよく持ち出される。
これらのことに反対するつもりはない。だが,ここではオノマトペを,少し違った角度から見てみたい。
2.オノマトペは完全反復型が多い
オノマトペは,和語,漢語,外来語と並んで,日本語の語種(語彙のタイプ)の一つとされることがある。和語,漢語,外来語と異なり,オノマトペは形態的なパターンとして,「ガタガタ」のような完全反復型が最も多いことが知られている。オノマトペ辞典(Kakehi et al. 1996)の見出し語の形態を調査した角岡(2007: 6, 71-72)は,これを,語基そのもの(例:「ふ」)・音素交替形(「がさごそ」)・語基交替形(「すってんころり」)・完全反復型(「がさがさ」)・不規則反復型(「ぶるるっ」)・「り」延長強勢擬容語(「あっさり」)・「り」接辞(「きらり」)・N(「ことん」)・Q(「にゅっ」)・R(「きー」)・R+N(「ばーん」)・R+Q(「にゅーっ」)・その他(「ぺたんこ」)のように分類した上で,「数的には反復型が圧倒的に多い。完全反復型だけでも696語と,全体1,652語の42.13%を占める」と述べている。
3.オノマトペの意味的な特徴は本当にオノマトペの特徴か?
この形態的な特徴は,オノマトペ以外の語種の語にも持たせてみることができる。すると,どうなるだろうか?
完全反復型の形態をとると,オノマトペでない和語・漢語・外来語も,語によってはオノマトペと似た意味的特徴を持つようになる。この意味的特徴とは,冒頭に述べた通り,「多分にイメージ的」で「感覚モードの違いに敏感」,そして「態度や感情を含んでいる」ということである。
「多分にイメージ的」とは,たとえば和語動詞「獲れる」の連用形「獲れ」の完全反復型「とれとれ」が,獲れたばかりであること,つまり[獲れる]というイメージと強く結びついていることを意味する,ということである。いつ獲れた魚も,捕れたことに変わりがないが,「獲れた」というイメージが強いのは,獲れたばかりの魚である。
「感覚モードの違いに敏感」とは,たとえば,形容詞「あつい」の語幹「あつ」の完全反復型「あつあつ」が,夏の高気温や,熱せられた高温の金属などに対する皮膚感覚を意味せず,もっぱら食品に対する舌の感覚(や転じて熱愛関係)を意味するように,皮膚の感覚モードと舌の感覚モードを区別する,ということである。
そして「態度や感情を含んでいる」とは,いま例に挙げた「とれとれ」「あつあつ」がいずれも単なる捕獲直後・高温を表すにとどまらず,肯定的で嬉しいイメージを意味する,ということである。
オノマトペがよく持ちがちな形態的な特徴(完全反復型の構造)を,他の語種の語にも持たせることができ,その結果,それらの語についても,オノマトペの意味的な特徴と同じ意味的特徴が観察されたとしたら,オノマトペの意味的な特徴とは,本当にオノマトペの特徴と言えるのだろうか? そしてオノマトペの特徴は,他のところにもあるのではないだろうか?
4.遂行性と疑似遂行性
オノマトペは,スピーチアクト(言語行為)という語用論的な面において,他の語種の語にはなかなか真似できない特徴を持っている。このことを説明するために,「遂行的」と「疑似遂行的」という2つの概念を紹介しておこう。
ここで言う「遂行的」(performative)とは,言語哲学者オースティン(John L. Austin)の術語で,これはたとえば人間が「(私は)約束します」という言葉を発することで約束が成立し,かつ,「約束します」と言わなければ約束が成立しないように,「それを発することで行為が遂行される」かつ「それを発しなければ行為が遂行されない」という発話の性質を指す。たとえば「マットの上にネコがいる」と言ってもマットの上にネコは現れず,ただ述べられた命題[マットの上にネコがいる]が真であるか偽であるかに過ぎないが,「約束します」は真偽値を持たず,それを発することで行為(約束)が遂行される。もっとも,本当に約束が成立するかどうかは,聞き手がそれをちゃんと聞いてまともに理解するかどうかにかかっているが,ここではそれは措いておく。
「約束します」と似た効力を持つのが,物語のことばである。「昔々,あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました」と言えば,昔々あるところに,年老いた男女が住んでいたことになる。言わなければ,あるところもなく,男女も存在しない。話し手が言ったことが,言った端から,何でも次々に成立していく。ただこの場合,成立する舞台は,現実世界ではなく,語られる世界である。その意味で「疑似」を付けたのが,私の造語「疑似遂行的」である。
物語のことばは疑似遂行的である。これは話す・聞くの音声言語に限ったことではなく,書く・読むの文字言語にもほぼ当てはまる。小説のことばは,書けば,物語世界にその事態状景が作り出されるという意味で疑似遂行的である。
5.オノマトペの疑似遂行性
オノマトペは,この疑似遂行性を持つことがある。「ゴーン。鐘が鳴った」は自然だが,「ゴーン。鐘が鳴らなかった」は不自然である。「ゴーン」と言った以上,物語世界で鐘は鳴っている。後からこれをキャンセルすることはできない。
オノマトペ以外の語種の語が,このような疑似遂行性を持つことも,ないわけではない。が,それは「男が寝ている。鐘。男は飛び起きる」のような,物語のことばの中でも異彩を放つ,芝居の台本のようなものに限られるようである。
オノマトペの特質は,このような疑似遂行性にあるのではないだろうか。
6.発話末オノマトペ
「ゴーン。鐘が鳴った」に見られるオノマトペの疑似遂行性は,結局のところ,こうしたオノマトペが物語のことばであることを示している。
いや,すべてのオノマトペが物語のことばというわけではない。オノマトペが物語のことばらしさを持つか否かは,オノマトペの出現位置や形態と関係している。
上で疑似遂行性の紹介に用いた「ゴーン。」は,伝統的にはオノマトペの「文外独立用法」と言われてきたものである。この用法名は,文から独立して発せられるという意味で名付けられたものだろう。ただし,「あっちでもゴーン。こっちでもゴーン。あたりじゅうで鐘が鳴りだした」のように,修飾語句(「あっちでも」や「こっちでも」)が前に付いても,オノマトペの疑似遂行性は失われない。そこで従来の「文外独立」を「発話末」と呼び替えておきたい。オノマトペが疑似遂行性を持つのは,発話末のオノマトペに限られる。以下これを仮に「発話末オノマトペ」と呼ぶ。
発話末オノマトペは,形態は自由である。日本語(共通語)の普通の語音にない音「ぐぉ」を取り入れて,鐘の音を「ぐぉーん」としてもよい。「ぐぉーん。鐘が鳴った」と言っても,まったく問題ないだろう。なぜ「ぐぉーん」と言ったのか? それは,鐘がそう鳴ったからである。同様に,「ssssshh。書類が風で飛んでいった」「rrrrrr。誰かがスクーターに乗ってきた」など,自由自在である。
発話末オノマトペは,語音だけではなく,モーラやアクセントからも自由である。「ぐぉーん」はたまたま3モーラっぽいかもしれないが,「ssssshh」の長さは何モーラかと問うことはできないし,「rrrrrr」のアクセントは何型かと問うこともできない。まさに,言いたい放題のワイルドなオノマトペが,発話末オノマトペである。
7.引用オノマトペ
オノマトペが,引用という形であれ,文の中に取り込まれると,疑似遂行性は失われてしまう。「(今度は)ゴーンと鐘が鳴らなかった」は,問題なく自然であって,不自然な「ゴーン。鐘が鳴らなかった」とは大きく違う。このように文中に引用されたオノマトペを仮に「引用オノマトペ」と呼ぶことにする。発話末オノマトペが持っていた疑似遂行性という特質を,引用オノマトペは持っていない。
ただし形態的には,引用オノマトペは発話末オノマトペと同様のワイルドさを保ち,語音,モーラ長,アクセントからは自由である。「ぐぉーんと鐘が鳴った」「ssssshhっと,書類が風で飛んでいった」「rrrrrrって,誰かがスクーターに乗ってきた」など,問題はない。
8.名詞類オノマトペ
引用という囲いも外れて,文の世界にいよいよ取り込まれ,文中の「一般」のことばと直接結びつくようになると,オノマトペは形態的なワイルドさも失ってしまう。おまけに,「一般」のことば並みに,品詞も担ってしまう。疑似遂行性がないことを示すため,念のため例を否定文にするが,「この服はヒラヒラがない」「カチカチな状態ではない」の「ヒラヒラ」「カチカチ」は,日本語(共通語)の語音で構成され,4モーラ,平板型アクセントで,名詞類(名詞や形容名詞)である。このように,文中に名詞類として現れるオノマトペを仮に「名詞類オノマトペ」と呼ぶことにする。
名詞類オノマトペの多くは4モーラである。そして一般に,4モーラの語が平板型アクセントを持ちやすいことは,以前から指摘されている通りである。和語・漢語については,代表的なアクセント辞典(NHK放送文化研究所1998編)所収の4モーラ語の中で平板型の語が最多であること(坂本1999),それが和語については改訂版(NHK放送文化研究所2016編)でさらに増えており(塩田2017),漢語についても平板型の発音が(頭高型の発音と共に)NHKアナウンサーによく受容されがちであること(塩田2016b。調査は2009年)が報告されている。また,外来語については,一般的には平板型は少ないものの,4モーラ語は複合的な条件下で平板型になりやすいこと(Kubozono 1996・Kawahara 2015: 457-459),NHKアナウンサーの受容度調査(2009)を通して見られる平板化の中に,長音を持つ4モーラ語がまとまって見られること(塩田2016a)が述べられている。
9.動詞語幹・副詞オノマトペ
外来語の品詞は,名詞類がほとんどである。「ディスる」の「ディス」(正確には「ディスr」だが)のような動詞語幹は少数である。(ここでは「テストする」の「テスト」などは名詞と考えている。)
副詞はさらに少ない。「食事中なう」と,今時も書き込むのかどうか知らないが,書き込むとすればその「なう」,あとは「ワンチャンスがあれば」を意味する「ワンチャン」ぐらいだろうか。
何が言いたいのかというと,名詞類という品詞は,日本語の文の世界の,いわば玄関口であり,動詞語幹や副詞は奥座敷だということである。オノマトペの馴化も,ここが終着点である。このオノマトペを,動詞語幹・副詞オノマトペと仮に呼んでおく。
動詞語幹・副詞オノマトペは,「(今度は)頭がクラクラしない」「(今度は)野菜をコトコト煮込まない」と,否定文が問題ないように,疑似遂行性は持たない。これらは日本語(共通語)の語音でできており,(「すばり答えた」の「すばり」など例外はあるが)4モーラが多く,そして頭高型アクセントが多い。
なぜ頭高型なのか? 文外で,アクセントもなくワイルドに過ごしていたオノマトペが,文の,それも奥座敷に入ってきた。アクセントを付けないといけない。どうしよう。困ったら頭高型ということで(本連載第6回),頭高型になったのではないか。私が思いつけるのは,そんなことぐらいである。
10.発話末オノマトペを発する人々1
以上に述べたように,オノマトペのうち,最もオノマトペらしいのは,「ゴーン。鐘が鳴った」のような疑似遂行性を持つ発話末オノマトペである。物語のことばであるから,日常会話の中で発話末オノマトペを発することは,小さい子供に絵本を読んでやっていて,といった機会を除けば,ほとんどないだろう。
しかしながら例外はある。少なくとも昔の大阪には,タクシーに乗っても,飲み屋に行っても,「ガッシャーン。ガラス割れた。どないしよ。もうみんな真っ青ですわ。そしたら,棒を持ってた奴が…」などと面白おかしく体験談を披露して,その場の一同を惹きつける手練れの話術師たちがいた。尾上圭介氏の論文「「ボチャーンねこ池落ちよってん」:表現の断続と文音調」は,それを扱ったものである。
11.発話末オノマトペを発する人々2
そこまでの話術はないけれども発話末オノマトペを口にする人々がいる。それは,発話オノマトペを,疑似遂行的にではなく,遂行的に発しようとする,つまり「ゴーン」と言うことで鐘を鳴らせようとする話し手たちである。ここには,マンガのフキダシ外の描き込みが関係している。
その場がシーンと静まり返って,マンガなら背景に「シーン」と描き込まれそうな状況で「シーン!」と言う。ショックを受けて,マンガなら「ガーン」と描き込まれそうな状況で「ガーン!」と言う。相手の言葉が心に突き刺さり,マンガなら「グサッ」と描き込まれそうな状況で「グサッ!」と言う,そうやって自らを戯画化し,会話をショーアップして遊んでいるのだろう。「火のないところに煙は立たない」という諺があるが,この遊びは,いわば「煙!」と叫んで火があるように仕立てる遊びである。
12.発話末オノマトペを発する人々3
発話末オノマトペを遂行的に発しようとする,もう一群の人々がいる。それは,他人に指示を与える人々である。
私の会話資料の中には,こんなシーンが映っているビデオがある。床に寝ている幼児に向かって,お母さんが「はい,ころーんとして。こ,ろーん」と言う。すると幼児が最後の「ろーん」に合わせて体を回転させる。こういうことは,母子の遊びに限らず,ベッドのシーツを交換しようとする介護者と被介護者など,いろいろな状況で起こるだろう。これは「煙」と言って本当に火を起こそうとする人たちである。
※角岡賢一 2007 『日本語オノマトペ語彙における形態的・音韻的体系性について』東京:くろしお出版
Kakehi, Hisao, Ikuhiro Tamori, and Lawrence Schourup. 1996. Dictionary of Iconic Expressions in Japanese. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
Kawahara, Shigeto. 2015. “The phonology of Japanese accent.” In Haruo Kubozono (ed.), The Handbook of Japanese Language and Linguistics: Phonetics and Phonology, pp. 445-492. Berlin; New York: Mouton de Gruyter.
Kubozono, Haruo. 1996. “Syllable and accent in Japanese: Evidence from loanword accentuation.” 『音声学会会報』211, p. 71-82.
NHK放送文化研究所(編) 1998 『NHK日本語発音アクセント辞典』東京:日本放送出版協会
NHK放送文化研究所(編) 2016 『NHK日本語発音アクセント新辞典』東京:日本放送出版協会
尾上圭介 2011 「「ボチャーンねこ池落ちよってん」:表現の断続と文音調」『文法と意味I』pp. 159-166, 東京:くろしお出版
定延利之 2015 「遂行的特質に基づく日本語オノマトペの利活用」『人工知能学会論文誌』第30巻第1号, pp. 353-363
定延利之 2017 「発話が生み出すアクセント」楊凱栄教授還暦記念論文集刊行会(編)『楊凱栄教授還暦記念論文集 中日言語研究論叢』pp. 333-354, 東京:朝日出版社
定延利之 2018 「オノマトペと感動詞に見られる「馴化」」小林隆(編)『感性の方言学』pp.45-64,東京:ひつじ書房
坂本 充 1999 「アクセント辞典にみる拍数別,語種別のアクセント分布」(最上勝也・坂本充・塩田雄大・大西勝也「『日本語アクセント辞典』:改訂の系譜と音韻構造の考察」第3節)『NHK放送文化調査研究年報』第44号, pp. 123-137.
塩田雄大 2016a 「NHKアクセント辞典“新辞典”への大改訂④ 外来語のアクセントの現況:在来語化する外来語」『放送研究と調査』第66巻第10号, pp. 84-102.
塩田雄大 2016b 「NHKアクセント辞典“新辞典”への大改訂⑥ 漢語のアクセントの現況:変化の「背景」を探る」『放送研究と調査』第66巻第12号, pp. 64-85.
塩田雄大 2017 「和語のアクセントの現況:~キ\ズナは消えてもキズナ ̄は強い」『放送研究と調査』第67巻第3号, pp. 72-87.
著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)
京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。
一覧に戻る