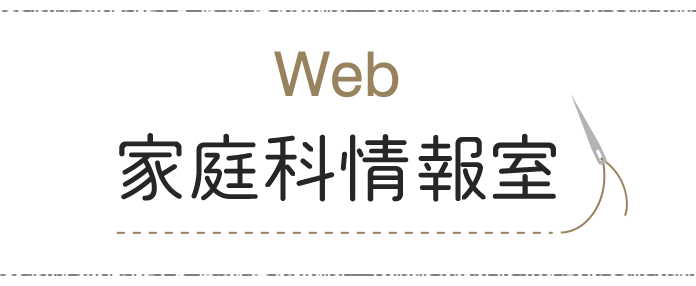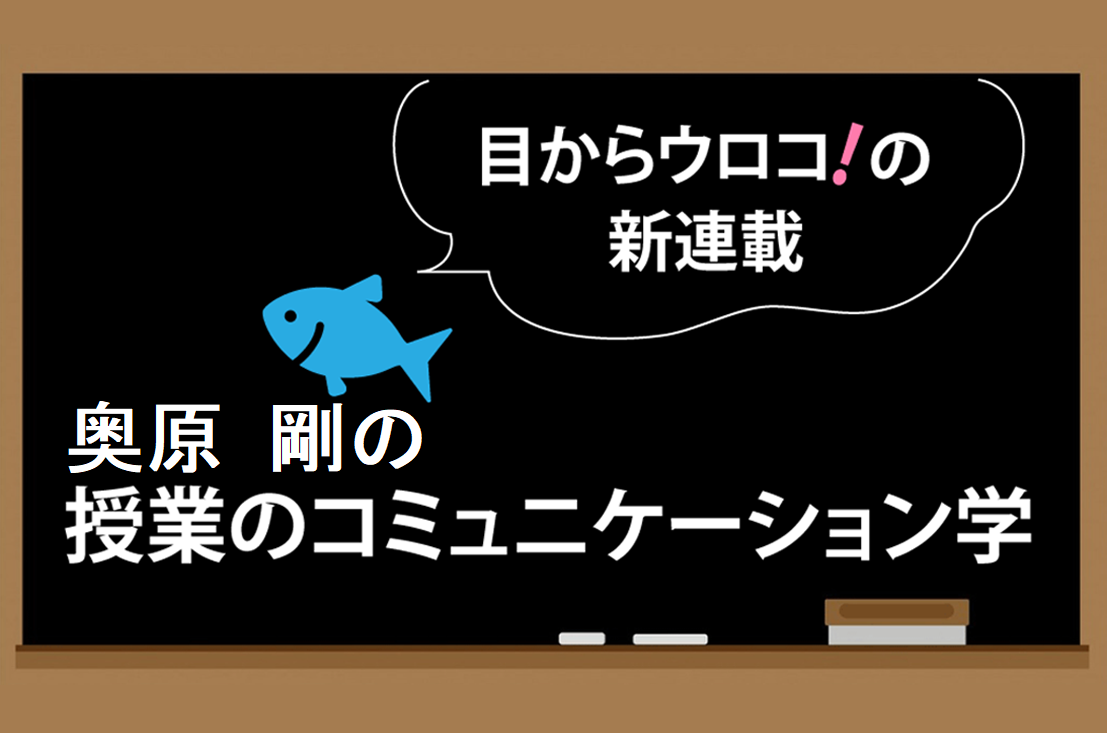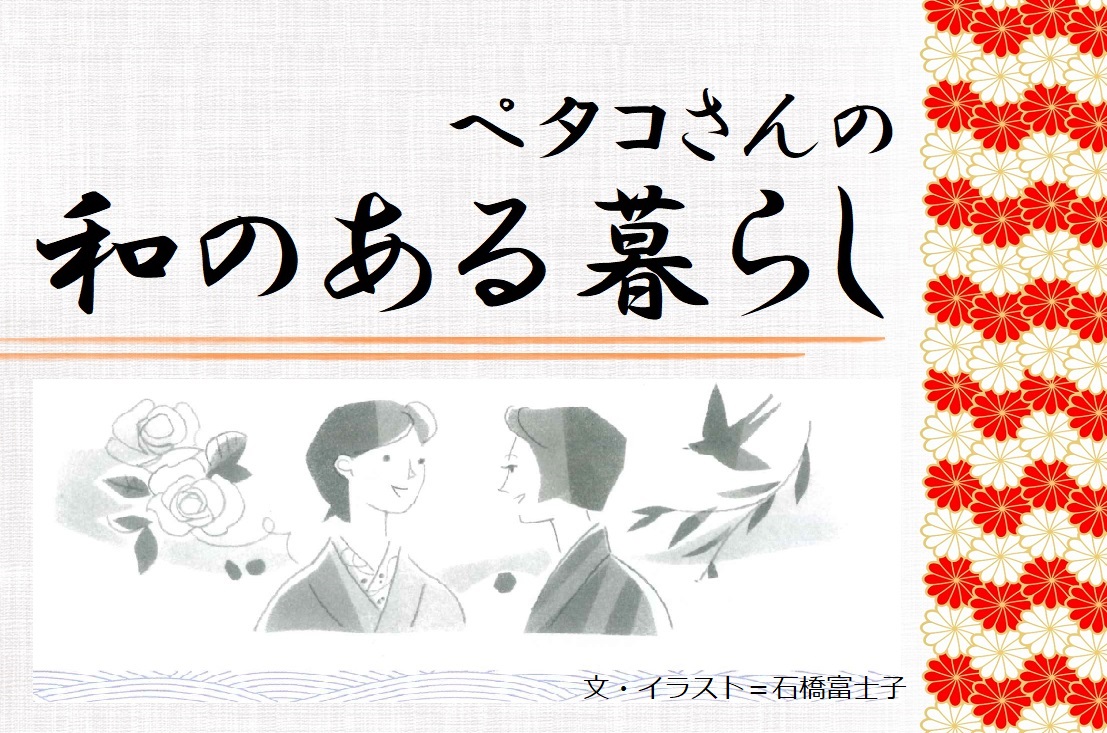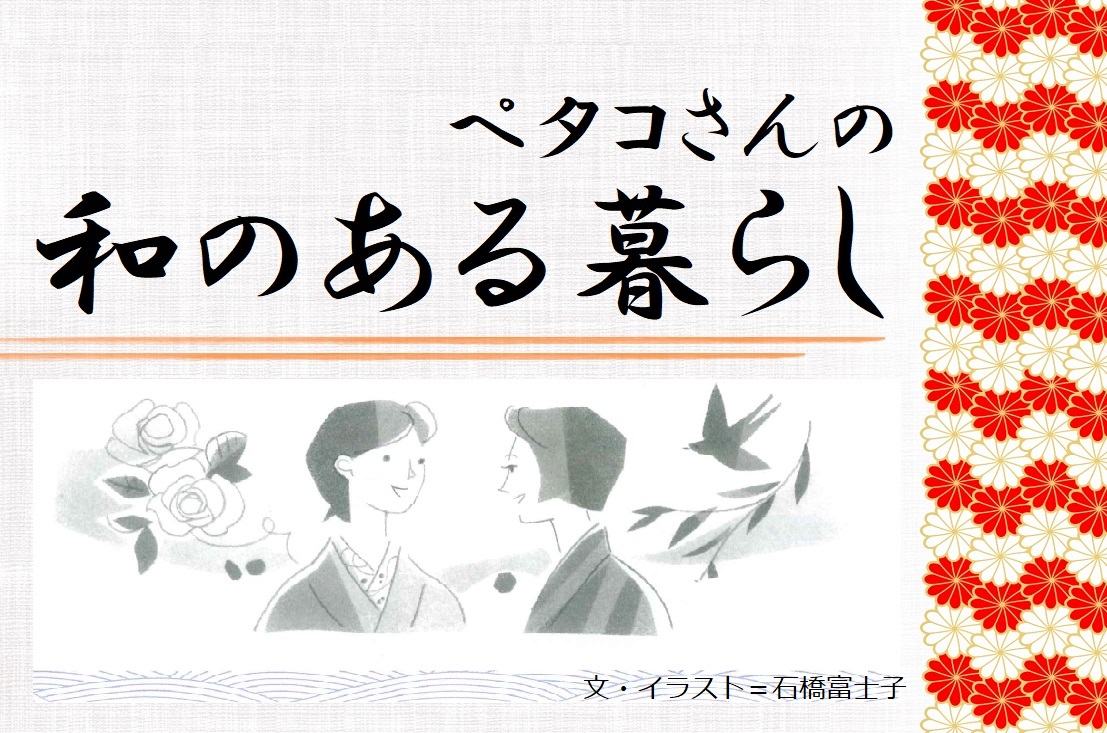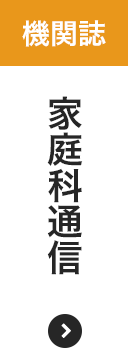レビー小体型認知症
3大認知症(アルツハイマー型,レビー小体型,脳血管性)の一つで,アルツハイマー型に次いで2番目に多く,認知症の約2割がレビー小体型認知症とされる。アルツハイマー型が女性に多いのに対し,レビー小体型は男性に多い傾向がある。レビー小体型認知症は,1976年に,小阪憲司医師(横浜市立大学名誉教授)により発見された。最近では,漫画家・蛭子能収さんが,アルツハイマー型とレビー小体型を併発している軽度の認知症であることを公表した。
レビー小体は「αシヌクレイン」という特殊なタンパク質のかたまりで,大脳や中脳にたまると神経細胞を徐々に減少させていく。レビー小体型認知症のおもな症状として,注意力の低下や視覚認知の障害,記憶障害などの認知機能障害がみられるが,初期から中期にかけては記憶障害がめだたない場合も多く,一般的な認知症だとは認識されにくい面がある。
また,レビー小体型認知症の特有の症状として,実際には見えないものが見える(幻視),その時々による理解や感情の変化(認知機能の変動),歩行など動作の障害(パーキンソン症状),大声での寝言や行動化(レム睡眠行動障害)などがある。
レビー小体は「パーキンソン病」の発症原因でもあり,レビー小体型認知症とはきょうだいのような関係といえる。初めにパーキンソン症状が現れて「パーキンソン病」と診断された後に,記憶障害が出てきてレビー小体型認知症とわかったり,パーキンソン病から10年,20年経てレビー小体型認知症を発症したり,もの忘れでアルツハイマー型認知症だと思われた後にパーキンソン症状が現れてレビー小体型認知症と診断されるケースもあったりするなど,正確な診断が難しい認知症である。
朝日新聞社運営Webサイト「なかまぁる」https://nakamaaru.asahi.com/article/13781599
エーザイ株式会社運営webサイト「相談e-65.net」https://sodan.e-65.net/basic/ninchisho/hayawakari_lewy.html